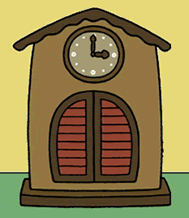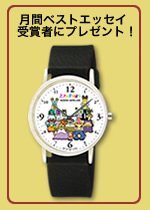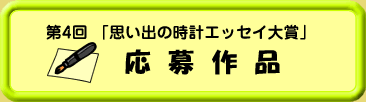 応募期間 2004年1月10日〜2004年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
2004年の作品
1月-2月 3月 4月 5月 6月-7月 8月-9月 10月-11月 12月
![]() 10月-11月の作品(23作品)
10月-11月の作品(23作品)
10月度のベストエッセイ審査に当たって、応募作品数が少なかったため、事務局で協議の結果、11月度応募作品と合わせて審査させていただくことにいたしました。よろしくお願いいたします。
「流行?の時計」金谷 慎吾さんのエッセイ
「不思議な目覚まし」岡村 豊さんのエッセイ
「ラブラブクロック」なあこさんのエッセイ
「無限の中の有限」なあこさんのエッセイ
「ガンコ時計」後藤 順さんのエッセイ
「時計のない生活」小林 絵美子さんのエッセイ
「記憶に残る時計たち」笠原 康永さんのエッセイ
「贈られた時間」小林 麻里絵さんのエッセイ (10-11月のベストエッセイ)
「両親がくれた腕時計」大田 明弘さんのエッセイ
「おやすみ、目覚まし時計」静久 記章さんのエッセイ
「幸せの時間」コマキさんのエッセイ
「おもちゃの時計、大きな想い」山平 友恵さんのエッセイ (10-11月のベストエッセイ)
「おばあちゃんの腕時計」如月さんのエッセイ
「家族の思い出とともに」辻沢 賢信さんのエッセイ
「奇跡的に動いた腕時計の秒針」高橋 聖子さんのエッセイ
「私の時計」サニーサイドさんのエッセイ
「時を語りゆく時計」上坂 幸大さんのエッセイ
「時の始まり。」えぐち かずこさんのエッセイ
「止まった針と思い出」人部 さおりさんのエッセイ
「母と時計」田辺 隆次さんのエッセイ
「父の腕時計」たかの むつみさんのエッセイ
「僕と彼女の時間」近藤 正則さんのエッセイ
「相方について」手塚 優さんのエッセイ
その腕時計は中学2年生の誕生日に両親に買ってもらったものだ。近所の時計屋に、今流行っていますよ!と店員に薦められた布製のバンドの腕時計だ。もっとも、未だかつて同じ時計をしている人間に出会ったことはないのだが。
時計を身につける習慣のない私にとって、その腕時計は大して興味をそそる対象ではなかった。高校生時代に一度持って出かけたきり、そのままカバンの脇の小さなポケットにいれたままだった。
さてそれなりに無事に成長し、私は大学受験という人生において結構重要だろうと思われる初めての大舞台にたどり着いた。試験前日、入念にチェック表まで用意して、持ち物は完璧にそろえた。カバンの中に受験票も入れた。地図も入れた。よし!そのおかげもあって私は、若干の緊張はあるものの、なんら普段と変わらない自然体で試験当日を迎えることができた。そう、普段と全く変わらず時計を持たずに・・・。
試験会場に着いて、初めて時計を持ってきていなかったことに気がついた私は、慌ててカバンの中をあさり始めた。あせる、あせる、あせる。自分でもないことは分かっていた。しかしなぜかあった。あの時計が入ったままだった。しかも動いていた。約2年間も誰の目に触れるわけでもなく、それでもその腕時計は動いていた。
私は今念願の大学でまさにキャンパスライフを満喫している。入学してすぐに新しい腕時計を買ったとたん、あの時計は止まってしまった。電池を替える気もしない。今流行っていますよ!例えあの時計が流行って無くても、絶対に捨てることはできない。
もう随分と前の話だが、僕には忘れられない目覚ましの思い出がある。僕が仕事でソウルに出張した時のことだ。そこでの仕事を終え明日は帰国するという前夜、いや正確には当日の明け方にその現象は起こった。
もう帰国するだけだったので僕はホテルに備え付けの目覚ましをオフにして翌朝はゆっくり起きるつもりだった。ところが明け方に目覚ましのアラームが突然鳴り出した。驚いて目覚めた僕は時計を見るとまだ4時だった。
”勘弁してくれよ”と思いながらオフにしてまた眠りについた。
すると3分位してまたアラームが鳴り出した。”何なの、この目覚まし”とぶつぶつ言いながら僕はまた目覚ましをオフにした。
もう一度眠ろうと思い再びベッドに入りライトをオフにした。
5分ほど経過した頃、またまたアラームが鳴り出した。 "一体、何なのだよ”と独り言を言いながら僕は起きだし三度(みたび)目覚ましをオフにした。次に鳴ったらホテルに文句を言おうと思いながらベッドに入った。その後は目覚ましが鳴ることなく朝方まで眠ることが出来たが、成田空港に着いて妻に電話を入れて驚いてしまった。彼女は泣き声で義理の弟が今朝の4時に亡くなったと言うのだ。
まだ40歳だったのにどうしてそんなことになったのか理不尽でならなかった。妻はこれから奈良に行くので息子たちを連れて明日連れて来て欲しいと言って電話を切った。
僕は成田空港から自宅へ向かう間、今朝の目覚ましは彼が僕に最後の別れを言いたかったのではなかったと思い、元気だった頃の彼の姿を思い浮かべていた。
私の実家には今でもゼンマイ式の掛け時計がある。今ではすっかりインテリアになってしまったが、子供の頃は活躍していた。
どうしてなのか置き所が寝室にあったので、夜中までコチコチという音が響いて、寝るタイミングを逃すとかなり耳障りだった。しかも、昼夜をとわず定時になると、ボンボンとなりだすので、寝入りばなを起こされることもしばしばあった。
それでも子供の頃は、ねじを巻くのが楽しかったり、時計を三十分も早めていたずらしたりと遊びにする余裕があった。けれど中学生になるとそうもいっていられなくなった。
時間はアバウト、音はうるさい、、まめにねじを巻かないと勝手に止まるなど、機能性を考えるとどこまでも不便であり、不快なのだ。しかし父も母も一向にこの時計を日陰ものにはしなかった。
ある時「いいかげん 別の部屋に置いて!じゃなきゃ捨てて」
と母に噛み付いたら、かなり照れくさそうに
「これね、新婚の時 一緒に気に入って買ったの」
と返事がきた。私にはそれ以上論議を続ける気持ちがなくなっていた。
私が嫁にいくまで時計はそのままの場所に居座りつづけ、未だに場所を明け渡す気配はない。
今からもう十五年も前のことである。高校に入学を控えた私に、祖父が合格祝いをくれると言ってくれた。予算は二万円以内。あれやこれやと悩んだが、母のアドバイスもあって、プレゼントは時計に決まった。
しかし祖父は「今流行りのものは解らない」と言い、
結局私と母と父でデパートの時計売り場に行って、選ぶことになった。私にとって時計を身につけるということは、大人に近づけるような憧れがあり緊張していた。高価なものは望めないが、絶対条件に正確な時を刻んでくれるものがほしかった。
金属のバンドは通学に不適切だとか、なるべくシンプルなものでという注文を出した結果、店員が勧めてくれたのは、
『SEIKO Avenue』
という新しく売り出されたものだった。文字盤で飾り気がなく、ちょっとクリーム色が強い地に、くっきりした数字が十二個並んでいる。金の縁取りにこげ茶色のバンドがユニセックスの上品なものに感じた。
「いいね」
三人の気持ちが一致した。男女用あって、婦人物は紳士物より一回り円形が小さい。父の「文字盤は大きい方が見やすくていい」という、押し通しで紳士物を手にすることになった。
早速、その足で祖父の家に時計を披露しにいった。照れながらも「いいじゃないか」と仕切りに時計を眺めていた。
時計は、私が三十路を向かえ、祖父が亡くなったいまでも、愛用の品だ。バンドは二回変えているが、あの時の気持ちでいられるよう、茶色を受け継いでいる。そして今でも正確に時を刻んでいてくれている。
たとえこの先、壊れてしまう日が来ても私は必ず大事に持ち続けることだろう。それは家族の温かく懐かしい思い出が、昨日のことのように鮮明に刻まれているからだ。
僕が小学生の頃、祖父は軍隊から支給された腕時計をはめていた。機械式で、暇さえあれば、ネジを巻いていた祖父がいた。
父がボーナスで自動巻きの腕時計を買った。それは祖父のより正確に動いた。僕は父に「今何時」と聞いた。自慢げに腕を差出す。それを見て、祖父は嫉妬したのか、「俺の方が正確だ。何たって、命を預けて時計だ」。祖父の厳しい言葉に、父は押し黙った。ガンコな性格を知っていたからだ。「進め、前進」と時計を見ながら指揮を取った祖父の姿があったのか。
祖父は僕が中学のときに亡くなった。形見としては、その時計があった。父は譲り受けるのを拒否した。「ガンコな性格が乗り移る」と笑った。兄とのジャンケンで僕のものになった。心から欲しいとは思わなかった。すでに父から新型の時計を買ってもらっていた。後生大事にしないモノは、なくなっても気にならない。祖父の時計は、どこに行ったのか不明になった。一応探したが見つからなかった。
四十年過ぎて、五年前亡くなった父の書斎にあるのを発見した。本当は、父がガンコ時計を欲しがっていたのだ。
我が家の居間には、もう10年以上使ってきた壁掛け時計がある。近頃は、家電製品に時計がついていて、中には自分で正しい時刻に修正をするものまである。しかし、長年愛用の時計は、真っ直ぐ掛かっていないと遅れ、電池のご機嫌によっても、進んだり遅れたり。しかも、家には「あまのじゃく」と呼ばれる母がいて、時計を家族に内緒で5分進めてしまったりする。一日もしないうちに、「あの時計は進んでいる」という認識が家族の間に定着して、その時計にだまされるのは母だけになってしまうのだが。
そんなこんなで、最近その時計はすっかり信用をなくしていたが、どの時計よりもはっきりと大きく時を示してくれるので、大まかな時間を把握するには便利で、そのまま使っていた。だが、時計というのは、ただ淡々と時刻を示し続けるので、時には、「へ?こんな時間だったのぉ」なんて驚かされることにしばしばあった。そんなことの繰り返しの中で、私は、自分が時や時計に縛られていると感じることも多く、「時計のないところへ行きたい」と、漠然と頭の隅で思っていたのかもしれない。
そんな私のわがままを、時計はどこかで聞いていたのか?ある日時計は、長針を動かすことをやめてしまった。それでも私は気づかずに、横目で時計を見て「もうこんな時間」などと言っては、家事をしたり、夕飯の買い物に出かけたりした。
その日の夕方、夫が、時計が動いていないことに気づき、直そうとしたが直らず、時計ははずすしてしまった。しかし、つい元時計があった場所を見て時刻を確認しようとしてしまう。今日も何回も、チラッと見ては。「そうだ。」とつぶやいた。
時や時計に縛られて暮らしているのだと、思い込んでいたが。本当は、時計に頼って暮らしを進めていたのかもしれない。10年近く、家族と一緒に時を刻み、引越しをしてきた時計は、私の心の奥のわがままで小さな願いを、そっと叶えようとしてくれたのかもしれない。
中学の入学とともに父親から初めて時計をもらった。その時の感動はすごいものだ。得てして、その時計は残っていないが、記憶には、すごく残っている。次に感動したのは、デジタル時計が出た時だ、その時のインパクトもすごい。それから、太陽電池のものが出てきた。
時計のことを思い起こすうちに、もっと前に、感動した時計があった。それは、子供の頃に親戚の家で見つけたハト時計だ。
いやあ、子供心に、あれには感動した。
今は、駅ビルにカラクリ時計などがおいてあるが、あの時の感動はすごかった。
子供には、そういうカラクリ時計を買ってやりたい。
そういえば、まだあった。実家の時計の思いでもある。実家の時計は、振り子時計だった。イスに上ってその時計のぜんまいを巻くのが私の役目だった。懐かしい。
こうやって、時計を通して思い出が蘇るのもいいものです。
もう、なくなった祖母と近所のデパートに行ってお子様ランチやそばを食べた思い出や母に剥いてもらったりんごや梨を縁側で食べたり誰かが持ってきた鯉を父がさばいたのを見ていた思い出が思い出される・・・みなさんも、心に刻まれた思い出を思い起こすのもいいのではないでしょうか?また、よい思い出を家族と育んでいってください。では・・・
「贈られた時間」小林 麻里絵さんのエッセイ (10-11月のベストエッセイ)
初めての家族四人での海外旅行。楽しかったこの旅行中、私にはずっと、気になっていた事があった。それは妹の時計が刻んでいる時間だ。
茶色の革ベルトがそろそろ痛んできたこの時計は、数年前、祖父が妹にプレゼントした物だ。大好きだった祖父はちょうどこの旅行の数ヶ月前に他界してしまっていた。今では形見となってしまったこの時計が、この旅行中、ずっと妹の腕で日本時間をさし続けていたのだ。
度々家族で時差の説明をしたのだが、妹はいっこうに時間を変えようとしない。時差について理解していないわけではなさそうなのだが、いつになく頑固に時間を変えようとしなかった。結局この時計は旅行中ずっと日本時間を刻み続け、家族の体内時計をおおいに惑わせた。
帰りの飛行機の中、自分の時計の時間を日本時刻に戻しながら、私はふっとこの事を思い出し、妹に、理由を聞いてみた。返事はあまり期待していなかったのだが、妹はにこりと笑い、誇らしげにこう言った。
「だってこの時計のこの時間は、おじいちゃまが合わせてくれたんだもん」
とっさには何を言っているのかわからなかった。しかしやがて私は、亡き祖父が、包みを開けた妹の前で竜頭を回して時間を合わせてやっていた光景を思い出した。
妹は言う。
「あの時合わせてもらった時間がおじいちゃまがいなくなっちゃった後でもずっと私の腕で動いてるんだよ。それってすごい事だと思わない?」
妹が時計の時間を変えたがらなかった理由。それは腕時計だけでなく、それに流れる時間も祖父から贈られた物だったから。祖父のくれた愛が今も時を刻んでいたから。
彼女の腕で今日もあの腕時計は時を刻み続ける。これから先この時計のベルトが擦り切れ、文字盤が傷ついてしまっても、そしてやがて止まってしまう日がきても、妹が祖父のことを忘れない限り、彼女の周りを流れる時間はあの祖父の時間なのだと私は確信する。
それはかれこれ17年も前のこと。高校の入学祝にと両親から腕時計をプレゼントしてもらったことがある。アナログ式で秒針がコツコツ小さな音を立てて時を刻み、茶色の本皮ベルトだった。それを初めて腕に捲いた時少しだけ大人の仲間入りをしたような気になった。登校時、始業に間に合うかどうか、又、バスの時刻表を腕時計と見比べながらと、身体の一部になったようについつい腕時計を眺めてしまう。両親がこの腕時計をプレゼントしてくれた時に私にこう言ってくれた。
「お前も腕時計をして行動する年齢になったんだな、だから思い切って奮発した。一生もんだぞ!大事にな」
その時は高価なモノを私に購入してくれたんだ、とにかく大事に扱おう、そう心に誓ったもんです。それ以降、私は学生時代を終え、社会人になっても使い続けた。干支がひと回りしても電池の交換はしたものの使い続けた。文字盤のガラスはキズだらけ、職場で飛んだ溶接の火の粉で竜頭は黒く焦げて変形していたが時間だけはキッカリ狂うことなく動き続けていた。そんな時、当時付き合っていた彼女(今の妻)から腕時計をプレゼントしてもらった。それは今流行のダイバーズウォッチだった。私のしている腕時計を見かねて誕生日にくれたものだ。嬉しかったけど、とうとう両親からプレゼントしてもらった腕時計に「さようなら」しなければならなかった。両親には話さずにいられなくなって話をすると「腕時計も人間と一緒で節目がある、学校を卒業するようにお前から卒業するんだ、12年も使ったんだろ?十分だ。これからは妻となる一生の伴侶の気持ちを大事にするんだ」と言われた時、少し心にジーンと来るものがあった。
時計にもその人に使われる人生があるんだな〜と使い古したボロボロ腕時計を眺めた。お世話になりました。
長い長い浪人生活の挙句。やっと入れた大学は、実家から300キロ以上も離れていた。
同年代で同郷の顔見知りは、当然皆無。おまけに僕ときたら人一倍、いや十倍人見知りだ。下宿にも大学にも町にも。一人の友人も知人も出来なかった。一日中会話というものがない。一年目の京都は寂しかった。一年目が終えて春休みで帰省した時。どっかの結婚式に出た両親がちょっとしゃれた目覚まし時計を引き出物としてもらってきた。
しゃべる時計である。目覚ましをセットしておくと「時間です。起きて下さい。」という声で予定時間に起こしてくれる。僕は、早速こいつを京都へ持ち帰った。
以来目覚ましだけが唯一の友人となった。下宿にも大学にも町にも。
人は、いつも満ち溢れていた。けれど僕に向かって話しかけてくれるのは、この目覚まし時計だけだった。いつまでも寝ていていい休みの日でさえ、ただ声が聞きたい。それだけの理由で目覚まし時計をセットした。寂しくて、人恋しくてたまらぬ時は、その日あった出来事とか今考えている事などを、目覚まし時計に向かって話したりした。二年目にやっと親友ができた。「俺にもやっと友だちができたよ」真っ先に目覚まし時計に報告した。「よかったね」そう言って目覚ましが、ほほえんだようにみえた。今、役目を終えた目覚ましは、部屋の片隅でホコリをかぶって眠っている。もう二度と起こすまい、と思っている。
小さな頃から憧れていたウェディングドレスを着て、お互いの両親が見守る中、私達は結婚式をしました。今年の1月のことです。
場所はグアム。暖かな風と、挙式30分前まで降っていたスコールがやんだあとの小さな虹。あの風景は今も鮮やかに私の心に残っています。
帰国の日、グアムの思い出に私達はひとつの時計を買いました。小さな置き時計です。
いつも仕事で忙しく時間に追われることの多い私達は、せめて家では時間を気にせずのんびりしたい、と目覚まし時計以外はあまり見える位置に時計を置かないようにしているのですが、とても可愛らしくて新居に飾りたいと思って衝動買いをしてしまいました。
帰国後、私達はその時計を新居に飾りました。グアムと日本は1時間の時差がありますが、敢えてその時差を戻しませんでした。とても感動的なあの日のことをいつも鮮明に覚えていられるように。時間に追われる毎日にこそ、日々に忙殺されないように、幸せの時間のまま今日もその時計は時を刻んでいます。時計としては意味をなしていないのでもったいない使い方かもしれません。でも、私達にとっては幸せな時間を刻み続ける貴重な思い出がたっぷりと詰め込まれています。
「おもちゃの時計、大きな想い」山平 友恵さんのエッセイ (10-11月のベストエッセイ)
私は母の腕時計が嫌いだった。おもちゃの様な作りでいかにも安っぽいその時計を電池を替えながら何年も使う母の行動が理解できず、恥かしいとさえ思っていた。誕生日や母の日の度に「時計をプレゼントする」と言っても「今はこの時計で充分」と返す母に呆れる私。
そんなある日、たまたま床に置いていたその時計を私は知らずに踏んで壊してしまったのだ。壊れた時計を手に母が取りあまりにも寂しそうな顔をするので「そんなおもちゃみたいな時計何年も使う自体おかしいよ。何でなの?」と聞くと、母はその時計は父が会社を辞め事業を始める時にプレゼントしてくれた物であること、普段恥ずかしがり屋の父が選んできてくれた気持ちがとても嬉しかったことなどを初めて話してくれた。私は今まで値段が安いことやブランド品でないことを理由に馬鹿にしていた自分を恥かしく思うと同時に、それらに捕らわれることなく気持ちを受け止めた母の一途な想いに感動すら覚えた。
今、母の腕には新たな時計がはめられている。父は今度は一体どんな想いを込めたのだろうか。
高校を卒業し、会社勤めを始めてからの初めてのおばあちゃんの誕生日。私は姉と二人で大好きなおばあちゃんに何かをプレゼントしようと思い、さんざん迷って腕時計を買った。
さっそくおばあちゃんにプレゼントすると、とても喜んでくれたのを今でも覚えている。
けれど、その日から何日経ってもおばあちゃんがその腕時計を使っているのを見ることはなく、姉と二人、気に入らなかったのかな?と少しがっかりしたりしていました。
結局、その日から数年後、おばあちゃんが突然の病でこの世を去ってしまうまで、私たちはその腕時計が使われているのを見ることはありませんでした。
おばあちゃんの葬儀が終わり、家族で後片づけをしていたある日、私たちは、おばあちゃんのタンスの奥に、こっそりとしまわれているその腕時計を発見した。一度も使われずに、渡したときのまま箱にしまわれている時計。それを手に取り不思議に思っていると、隣で見ていた母が言ったのです。
「せっかくだから使ったら?」と何度も言ったのだけど「孫がくれた時計はもったいなくて使えない」とずっと大切にしまっていたのだと。
そのとき私は思ったのです。この腕時計は、確かに時計としては使われることは無かったけれど、でもそれ以上に大切にされてきたんだなあと。若い私たちが買ったものですから、そんなに高価なものではありません。けれど、それをそんなにも大切にしてくれたおばあちゃんの気持ちが嬉しくてたまらなかったのです。できることなら棺に入れて、天国で使ってもらいたかったけれど、それも叶わぬまま、今でもタンスの奥にあの日のままの姿でこっそりとしまわれたままです。
「ボーン、ボーン、ボーン」
ゆっくりと時を告げる、重くしっかりした響きが、今も耳に残っている。それは母の胎内にいたときから聞いていたせいだろうか。
私が生まれた家は、かつて松尾芭蕉が奥の細道で歩いた北陸街道沿いにあった。
ほうきやざるなど、荒物を売っていた店の横にある玄関を入ると、黒くて太い梁がむき出しの部屋があった。屋根の明かり取りから光が差し込む不思議な空間。今でいえば、二階までの吹き抜けである。
その部屋の大黒柱に、古びた時計が掛けてあった。塗装も分からないほど灰色に変色しているが、きちんと時を告げていた。
小学生だった私に、祖父は「時計が止まっているから、ぜんまいを巻いてくれ」とよく言った。私は、喜んで踏み台を取ってきて、時計のふたを開ける。中にある蝶々のような形をした器具を取り出し、針を動かすぜんまいと、時報を鳴らすぜんまいの二カ所の穴に差し込み、それぞれ内側の方向に巻いた。
「巻きすぎたら、ぜんまいが切れるよ」。そんな祖父の言葉に、力を加減して巻いた。
時刻合わせで長針を回すたび、「ボーン、ボーン」と鳴った。おもちゃのような感覚だったかもしれない。しかし、子供心にも仕事を与えられた喜びの方が大きかった。
私が東京に出て大学に行っている間に、家は人手に渡った。新築し、引っ越したからである。古い柱時計がどこにいったのかは分からない。真新しい家にはふさわしくないと捨てられたのかもしれない。
あれから、三十年あまり。なぜか、何度となく古い家を思い出す。小さな中庭の柿の木、五右衛門風呂、かまど、土蔵―。すべてが無声映画の一こまのようによみがえる。
その中で、柱時計だけは音を伴って記憶のかなたからやってくる。「ボーン、ボーン、ボーン」。優しい響きは、亡くなった祖父の声、若かった家族の声も連れてくる。
2年前の夏、最愛の祖母が亡くなりました。おばあちゃんっ子だった私は、暫くショックで涙が止まらず、二ヶ月くらい自室に引き籠って泣く毎日を過ごしました。祖母が亡くなってから一年が経った昨年の夏、ようやく少し落ち着きを取り戻した私は、生前祖母が暮らしていた家に行き、祖母の部屋の整理をしていました。すると、祖母のタンスの引き出しの奥の方から、見覚えのある時計が出てきたのです。それは、祖母が生前、まだ元気だった頃、毎日のように腕にはめていた祖母の腕時計でした。金色に輝くその祖母の腕時計が、小さい頃の私は大好きでした。
しかし、昨年の夏に、祖母のタンスの引き出しの奥から出てきたその腕時計は、もう輝きを失っていました。綺麗な金色はもうさびていました。でも裏返すと、銀色にまだちゃんと輝いていました。しかし、時間は止まったままでした。重いネジをまわせば、短針と長針ならいつでも簡単に動かすことができるのですが、秒針だけがどうしても動きません。私は、祖母の長男である叔父に頼み込み、その腕時計を自宅に持ち帰りました。以来、悲しいことや辛いことがあった時、祖母に話しかけるつもり?で、その祖母の腕時計にそっと話しかけています。たまに、自分の腕時計の上に、その祖母の腕時計をのせてみたりします。そんなある日、いつものようにネジをまわして短針と長針をめちゃくちゃに動かしたりしていたら、なんと、奇跡的に、11から4のところに秒針が動いたのです。びっくりして、「すごいぞ、頑張れ!」と褒めたら、又ほんの少しだけ秒針が動いたのです。
まるで眠りから覚めたかのようでした。それ以来、その祖母の腕時計の秒針は、なでたりふったり褒めたり、腕にはめたりネジを動かしたりすると、たまに少し動きます。調子のいい時は暫く動いています。まるで祖母が生き返ったようなのです。この不思議な現象に感激した私は、以来ずっと、ベッドのところにおいてある祖母の写真の前にその祖母の腕時計を置き、寝る前にいつも話しかけています。私もこの祖母の腕時計のように、何があっても諦めずに、残りの人生を祖母の分まで精一杯、悔いのないように生きたいと思います。
私には自慢できる腕時計がある。値段が高いわけでもなく、現代風なわけでもない。でも人に自慢できる代物である。それは、私の父が成人式に買ってくれた腕時計である。その時以来、いやその腕時計をして以来、一度も故障したことがないのである。私が就職したときも、結婚したときも、子供たちが生まれた時もずっと私と共に時を刻んできてくれた時計。つい先日までその時計を持っている事さえ意識させなかった、私の時計。ふっとその事に気づくと、愛着を通り越して、何か自分の分身のようにさえ思えてきた。この40年もの間、頑固一徹、健康で勤勉だけがとりえの人生。ふっと自分に笑みがこぼれた。「親父はわかっていて、俺の人生の門出にこの時計を送ってくれたのかな。」これが私の自慢できる私の時計である。
中学校の入学後、私は、初めて自分専用の腕時計を持つことになった。当時はまだ、私と仲が良かった両親から、入学祝いとして贈られたものだ。
価格以上に、高級感が漂う漆黒の色、一秒たりとも誤差が発生しないデジタル式、腕に装着するときの斬新な感覚。私は、そのいずれの特徴においても、非常に満足し、大いにこの時計のことを気に入っていた。入学祝いを予想していた段階では、他に欲しいものが多くあり、腕時計はその候補にすらあがっていなかった。だが、実際に腕時計を受け取ってみると、「初めての時計」ということもあってか、他のものを圧倒的に凌駕する嬉しさがあった。
きっとこの贈られた時計には、様々な意味が込められていたのだろう。
「時間を守りなさい、大切にしなさい、有意義に使いなさい。」
そのいずれもが、思春期の青年にとっては、耳障りな内容であるが、同時に、一人の社会人として非常に大切なことでもある。
未だに幼かった私は、そのことをどれだけ理解していただろうか。今思えば、私は何一つその真意を理解することなく、単にファッションの一部として、その時計を使用していただけであった。その頑固なまでに、大人の言うことに拒絶反応を示し、時計のストップウォッチ機能で、いつまでも楽しそうに遊んでいた。
思い出というものは、よほど強い印象がない限り、大抵は時とともに風化してしまうものだ。しかし、何か一つでも当時を偲ばせるものがあれば、それは水を得た砂漠がオアシスに変化するように、再び潤いを取り戻す。
この時計は、もう既に動かない。だが、現在でも、私の手元に大切に保管されている。
時を刻まず、時を語る時計として。
父から送られた丸型の腕時計は、それまで時を取るということを知らなかったわたしへの戒めだったと思います。学生の頃、アルパイトをしてはふらり一人旅に出て、旅先から絵葉書を両親宛てに送っていた。都会の真ん中にいて田舎のような近所付き合いもなく、田舎のような自然もなくただ狭く昼から電気を付けなければ暗いアパート暮らしに嫌気がさすとすぐに夜行列車に乗っていた。行き先も止まるところも出たこと勝負の気楽な娘から送られてきた絵葉書に両親は気に病んだことだろう。
旧中仙道の山の中をひとり歩いたり、バスが止まったところが山の中腹で民家もなく、しかも日はどっぷりと暮れている山道を歩いている運良く通りがかった人に事情を話して泊めてもらったことがあった。その時は決して死ぬこともなく、時間を取ることもないと思っていた。二十歳になって父から貰った腕時計は、人はだれでも年を取る。年は自分の命の数だと教えてくれた。時は命の重さと同じだと。来年はわたしの一人娘が二十歳になる。この子もわたしに似たところがあって、アメリカには一人で旅立った。まだ、娘の中に時間は無限大にある。でも、それは思い過ごし。時と命は同じもの。どちらも二度と帰らない。
5年前まで住んでいた家の扉を開けると目の前に、薄暗く天井の低い部屋が見える。その部屋の壁には、大きな掛け時計があり、時計の針は12時45分を指したまま止っている。
5年前、この家を引っ越すとき母が「この家の時間はこのまま。今のこの時をそのままにしたい。」と言って、この掛け時計の針を止めてしまった。父と結婚し、2人の子どもを産み育てたこの家を離れ難かった母は「せめて時間だけでも・・・」との思いだったようです。
今でもの時計を見ると、この家で過ごしていた時間蘇ってきます。まるで、新しい家で過ごした5年間が実は夢で今、夢から覚めたように。
その時計の12時45分。それは私達がこの家で迎えた最後の時間であり、その家と私達の変わることの無い永遠の時間です。
90歳の時、母が脳梗塞で倒れた。薬が発達し、点滴だけで脳梗塞は治る。1週間もすると、病院のベットに座っておしゃべりができるほどになった。元気になると、夜は長く、退屈なようであった。「夜中に時間が分からないのが困る」と、母はこぼした。病院には消灯時間があり、夜明けまで薄暗い中、ベッドで過ごさなければならなかったからである。
私は、母のために目覚まし時計を買った。暗い所でも見えるようにと、ボタンを押すと灯りのつく電池式置き時計にした。
3週間で退院した。退院後、散歩が母の日課となった。散歩時、母が転ばぬよう、私は母の腕を掴んで歩いた。
5年後、散歩中に母の呂律が一時的におかしくなった。一過性の脳梗塞であったらしく、その後、症状は出なかった。それ以来、散歩は母の日課から消えた。看護人は、被看護人に異変が起こるたびに、だんだんと臆病になるものだ。
母もベットで過ごす時間が多くなり、寝ては起きての繰り返しとなった。寝起き時、「いま何時?」、「きょうは何日?」と質問するようになった。時の観念がなくなったとき、人は惚けるという。時を意識している間は、まだ惚けてはいない。
母のために、新たに置き時計を買った。しかし文字盤が小さいく、場所によっては見えないために、相変わらず時間を聞いてきた。そこで、文字盤の大きな電池式掛け時計と日めくりカレンダーを買い、部屋のどこからでも見えるようにした。それからは、目を覚ますたびに時計を見ては、「もうこんな時間か。今は昼か、夜か?」と、質問するようになった。そんなとき、昼と夜を知らせる時計があったら、と思ったものだ。
「110まで生きる」と言っていた母は、99歳の若さで他界した。死ぬまで惚けることはなかった。時に対する意識が、母の脳を活性化していたのだ。その手助けをした掛け時計は、今も同じ場所で時を刻み続けている。
八時間の手術に耐えた父は、集中治療室のベッドに横たわっていた。
母とわたしに気づいた父が、ひょいと手を上げると、父の手首の腕時計はスルスルと肘まで下がった。
父の腕は、悲しいほどやせ細っていた。
「おとうさん。手術が無事に終わって良かったね」
母が声をかけると、父はホッとしたようにうなづいた。
父の表情には、いつもと変わらない頑固さと明るさがあった。
退院してから、やりたい仕事が、父には山ほどあった。
たくさんの医療機器に囲まれながら、父は回復の時を待っていた。
それから一ヶ月後、電話の音が鳴り響いた。
「おとうさんが、危篤なの!すぐ来て!」
妹の言葉にわたしは耳を疑った。
車を走らせながら身体が震えるのを感じた。
病院に着いた時、父はすでに息を引き取っていた。
まだ温もりが残っているのに、呼びかけても揺すっても、父の身体は動かなかった。
「・・・おとうさん、家に帰ろう」
無言の父を乗せて、車は走り出した。
車の窓からまぶしい日ざしを受けて、涙が、あとから、あとからあふれ出た。
青い空の向こうには、父の愛した雪の山々が、銀色に輝いていた。
あれから七年の歳月が流れた。
父の腕時計は、何事もなかったかのように、わたしの腕で規則正しく時を知らせている。
山や川の自然は、四季折々の美しさを、くり返し、くり返し見せてくれている。
そして、残された家族は皆、これからも、ずっと心の中に生き続ける父と一緒に、しあわせな時を刻んでいきたいと願っている。
僕はカリブ海に浮かぶ島、クラサオ島で約半年間のインターンシップを行った。日本との時差は13時間。彼女との時差も13時間。非常に辛い時間の距離。
今日は非常に君が恋しい。時差13時間。ということは、君は今地球の反対側で朝色に包まれて、9時38分を過ごしている。
元気にしてる?なんか最近、カップルがキスしてるのをよく見るんだ。なんかいいよね。ああ、キスしたくて、仕方なくて、こんなところでしたんだ、みたいな。君といろんなところでキスしたなあ。
体に触れる、それだけで気持ちが、何万もの言葉が伝わるんだからすごいね。唇は唇に。手は手に。今は言葉で伝えるしかない距離にいる。
今すぐ、幽体離脱して、飛んで行きたいよ。
僕はクラサオ島にアナログとデジタル両方使える腕時計を持っていった。アナログはクラサオ島時間、つまり僕の時間。デジタルは日本時間、彼女の時間を刻む。2つの時間が僕に彼女との距離を実感させ、僕を憂鬱にした。アナログ時計の針が刻む音が聞こえてくるようで、そのカチカチという小気味良いリズムが、僕を悠長に構えさえてくれる。一方、デジタル表示は「そんなスピードじゃだめだよ。もっと急がなきゃ。彼女には追いつけないよ。」と僕を急き立て、さらに憂鬱にさせた。
そして、時間の距離は僕に数々の疑問符を投げかけた、「君は今何をしているんだろう?」と。是が非でもアナログは13時間前を走っている彼女の時間に追いつきたいが、追いつけない。時計が刻む同じ時間軸の上で一緒に過ごしたかったが、僕の腕時計は13時間の差をついに詰めることはできなかった。アナログはデジタルとの競争に負けたんだ。僕は彼女を捕まえきれなかったんだ。
高くもなければ、安くもない。私の腕時計はそんな代物だ。
この時計とはじめてであったのは、高校二年のクリスマス・イブだった。いい加減サンタクロースを信じる歳でもないので、プレゼントは直接父からもらった。
この時計は結構便利である。ネイビーブルーの文字盤は、太陽の光を吸収して、時計の原動力に変えてくれる。しかし、日に当ててないとすぐに力尽きてしまう、根性のない時計でもある。また、海やプールの中は無理だろうが、雨粒くらいの水なら耐えることができる。そして、アナログ式なので、時間の経過が分かりやすい。おかげで大学のテストのときにこの時計は重宝している。
この時計は、私の手元に来たときから、さまざまな体験をすることになった。私が部活に間に合うよう、開始時間を指し示してくれた。高校最後の年、いくつもの模擬テストで、苦手な数学を後何分で解くべきか教えてくれた。一人で暮らし始めて図書館にいるとき、スーパーのタイムサービスに間に合うようにここを出ることを私に促してくれた。
移り変わる私の生活のなかで、この時計は変わらないまま、時を刻み続けてきた。
父は、私にこれをくれるとき、この時計は大人になっても使えると言った。きっとそうだろう。社会に出て働き、家族を持ち、やがて老いていくときまで、私はできるだけこの時計と一緒にいようと思う。
(事前のご同意)
「思い出の時計エッセイ募集」に送っていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツル株式会社に帰属します。
また、みなさまのエッセイと氏名(ペンネームを記載いただいた場合はペンネーム)を、当ホームページ上に掲載させて頂きますことを、
予めご了承ください。