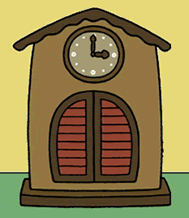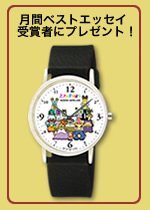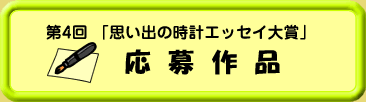 応募期間 2004年1月10日〜2004年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
2004年の作品
1月-2月 3月 4月 5月 6月-7月 8月-9月 10月-11月 12月
![]() 5月の作品(13作品)
5月の作品(13作品)
「海」小夏さんのエッセイ
「プーさんの時計」美鈴さんのエッセイ
「マイパートナー」平増 有子さんのエッセイ
「20年後の約束」yukariさんのエッセイ
「自己防衛の盾」そらさんのエッセイ
「霞の中の置時計」山下 昭蔵さんのエッセイ
「ふたつの時計」風間 和子さんのエッセイ
「水に浸かっても。」古川 美穂子さんのエッセイ
「曾おばあちゃんと時計」酒井 陽子さんのエッセイ
「医者と腕時計」田中 邦雄さんのエッセイ
「腕時計と父の臭い」小木曽 祐子さんのエッセイ (5月のベストエッセイ)
「はじめての腕時計」新田 三佐雄さんのエッセイ
「再出発」三浦 由美さんのエッセイ (5月のベストエッセイ)
小学校6年生の夏、私は漁師の父と潜りに行った。
その日は、水温が低く、海水がとても透き通っていた。深い底の砂がはっきりと見えた。岩かげに光るものを見つけて近づいてみると、がっちりした腕時計だった。
私はそのダイバーズウォッチを持ち帰った。小さな傷はあったが、しっかり動いていて、K.S.という刻印があった。少し重かったけれど、なんとなく私の腕にもおさまる感じがした。そして私はいつしか昔から自分のもののように思い始めた。
しかし、何日かして不思議なことに気がついた。その時計をして海に行くと、いつも同じ男の人に出会うのである。地元の人ならだいたい顔を知っているはずだから、きっと都会から来ている観光客であろう。私はその人を見かけると、なんとなく自分の腕にしている腕時計を隠すようになっていた。もしかしたら、「K.S.」さんはあの人かも知れない。
・・・夏が終わり、もうあの人の姿を見かけなくなった。その後も何回か桟橋に行ってみたが、結局二度と彼の姿を見ることはなかった。私は自分があの人に多少の好意を抱いていたことに気づいた。いったいあの人は何者だったのだろう。この時計はやっぱりあの人の時計だったのだろうか。聞いてみればよかった。でもその機会はもう二度と来ないだろうと思った。
私は時計を拾った海に戻すことにした。秋の海はもうすっかり表情を変えていて、三角波が立っている海の上をカモメがやたらとたくさん飛んでいた。私は、腕にしていたあの時計を海に投げた。
月日が経ち、あれから何も変わったことはない。もちろんあの人の姿を見ることもなかった。でもときどき海に行くと、あの人の姿を探す習慣だけが残っている。
母に起こされて、時間を確かめようとすると、ベッドの上のいつもの場所にプーさんがいなかった。4年生の誕生日に父が買ってくれたプーさんのおなかに文字盤がある目覚まし時計である。そして部屋を出ようとしたとき、ドアのノブに手をかけながら、私は変わり果てたプーさんの姿を見つけた。バラバラに壊れ、小さな部品が散らばっていた。片方の耳のかけらは、部屋の隅っこに落ちている。私はあわてて耳を拾って、付くはずもないのにプーの耳を直そうとしていた。
誰がこんなひどいことを!
壊れた時計を抱きしめて泣きながら、犯人は姉に違いないと思った。私は三人姉妹で、高校生の姉と小学生の妹がいる。姉と私は一つの部屋を与えられていた。プーさんの時計は私のベッドの棚に置いてあるが、高校生になって急に部活に燃えだした姉が、朝練に行くため、私はしぶしぶ姉の使用も認めたのである。
その日の夜、私は姉を問いつめた。
「朝、うるさいからムカついて思いっきり投げちゃった。」
姉はケロケロ笑って反省の色もない。私はもう絶対に姉としゃべらないことにした。
・・・・そして半年ほどして、姉は友だちとディズニーランドに行ったとき、プーさんの目覚まし時計を買ってきてくれた。でも前のプーの方が可愛いかった。もう怒ってはいなかったが、やっぱりあのプーさんの代わりはいないと思った。
さて、私が高校生になって、今度は妹と同じ部屋になり、部活や勉強に明け暮れる毎日が始まった。
ある朝、テスト中でいらついた私は妹の目覚まし時計を壁に向かって投げつけていた。バラバラになった時計を見て、妹は泣いて抗議した。姉妹でケンカをしながら、私は心の中でつぶやいた。やっぱり姉妹ってすごい!同じ事を繰り返している。
そして現在、私は妹への償いのために、夏までに新しい目覚まし時計を買おうとアルバイトをしている。スーパーのバイトをしながら、きっと姉も同じことをしたんだろうな、と思った。
コツ、コツ、コツ、コツ……。枕元にある時計の秒針の進みが恐ろしく遅く感じられた。「もう一分たっただろう」と時計を見ても、まだたったの三十秒。「まったく、この時計、おかしいんじゃないの!」怒りと共に徐々に痛みも込み上げてくる。初めての出産のとき、病室に持ち込んだのは、普段から使い慣れている秒針付の目覚まし時計だった。神経質な私が枕元に置けるのは、秒針の音が静かで小さな時計に限る。この時計もなかなか気に入った品がなく、何店もの店をハシゴしてやっと見つけた貴重な品だった。
「陣痛のときは、時計を側においてその間隔を測るべし」と、どの本にも書かれている。そして私は迷わずそれに従った。しかし、陣痛が増すにつれすぐに後悔した。時計なんて持ってくるんじゃなかった! なぜなら、痛みと戦っていると、とにかく時間がたたないのだ。
夜中に病室に入り、周りは皆寝ていたため、迂闊に声を出すことができず、ただただ傷みを堪え、時計とにらめっこをするしかなかった。たった一人で陣痛に耐える時間は心細く本当に長く感じられた。今思えば、あの時計だけが陣痛を一緒に戦ってくれた戦友であり、出産を最初から最後まで見守ってくれていた唯一の証人である。
時の流れいうものは、自分の都合で早く感じるときもあれば、ノロノロ感じるときもある。陣痛のとき、あんなに早く進んで欲しいと思った時間だが、三歳の娘と一緒にいると、あまり焦らず、子どもとともにゆっくりゆっくりと時を刻んでいきたいと思い始めている。
あの日の時計は、今も枕元で動き続けている。七月には第二子出産予定である。そのときには、もちろん持っていくつもりだ。そして、今後も私のパートナーとして子育てを見守りながら時を刻み続けて欲しい。
私の祖父はとても無口な人でした。そんな祖父とは会いにいっても当然あまり話をすることはありませんでした。
その祖父が突然亡くなりました。 突然の出来事で、誰もが驚きました。
そして、母からおもいもよらない話を聞きました。祖父の遺品は母が片付けていたのですが、その中の箱から、私の七五三、小学校入学、中学入学、・・・と写真がでてきたそうです。そして、その中に、腕時計がはいってたそうです。
なぜ腕時計?とおもって祖母に聞くと、私が小さいころに欲しい、といっていた時計だったようなのです。どうやら、私が社会人になったときにプレゼントしようと思っていた、とのことでした。
ずっと私のことを見守ってくれていた祖父の気持ちとその結晶の腕時計は今、私の腕にあります。ネジ式の腕時計は、一度も途切れることなく、私と祖父の時間を案内してくれています。
自分を変えたいと気持ちばかり でも全然変わらない。
時が経てば変わっていくもの沢山あるけど 自分自身は変わらない。
本当は変わらないんじゃなくて 変わろうと努力してないだけ。
自ら変わるんじゃなくて 周りが変わるのを待ってるだけ。
何の努力も無しに変わりたいなんて ただの我侭
どうしたらいいのか解らない ただの言い訳
そんな人が多いんだよね。
求めるだけで何もしない「依存症」そんな人が多すぎる
「うつ病」なんて誰にでもなる素質はあるだろうけど なるか、ならないかは自分次第。
うつ病だからという言い訳する人も結構居たり
病気だと言って盾にして自己防衛してるのってどうなのかな
誰しも強さ・弱さどっちもあっていいと思うけど それを盾にはしたくないと私は思う。
ずっしり重い大理石の分厚い板で囲まれた置時計。その冷たい質感と量感が、六十年という時空を超えて、今この手によみがえる。
個人の歴史でいえば霞の彼方の記憶のはずだのに、不思議とリアルなのはなぜだろう。
当時十五歳だった少年がなんの技術も持たないくせ、傲慢な自信で修理しようと試みた結果、跳ね飛んだぜんまいの勢いで、部屋中に部品をばら撒いてしまった情景が、昨日のことのように再現されたのは、あの歌を聴いた時だった。
歌……。隣の部屋から流れてくるテレビの音。霞に包まれた禁断の世界に踏み込むような不思議な雰囲気の歌だった。〈題名を控えておかなくちゃ〉
その時、もう潜在意識の中でCDを買いに走ることを考えていたにちがいない。
…大きな古時計…
応接間に置かれていたその時計が故障して
止まってしまったのをいいことに、父は新しい時計を買った。ウェストミンスターの山型で綺麗な鐘の音を響かせた。
わがままだった父の道楽は、いいものに目がくらむくせ、すぐに目移りして新しいものを買い込む。およそ貯金とか備蓄には縁のない生活がある日、瞬時に灰燼に帰した。無差別に夜空からばら撒かれた焼夷弾のためだった。
かろうじて故郷の九州に逃げ延びた年に怪我と食料不足の栄養失調で父母も兄もあっけなく逝ってしまった。一人図々しく生き残り、今〈大きな古時計〉のCDを買ったその少年、つまり私は七十五歳を迎えた。
その歌を聴くとあの大理石の時計への想いがよみがえる。せっかく買ったCDだったけれど、数回聴いただけでやめてしまった。
あれを聴くと、心が過去に向いてしまって、
「明日だけを見つめて生きる」という突っ張った心が萎えてしまいそうだからなのだ。
二女家族は、この春から外国の地へ移住することになり、希望に胸膨らませ成田から発って行った。幼い孫娘は今から行く地がどこか知るはずもなく、無邪気にバイバイと可愛い手を振り搭乗口に消えて行き、見送る私たちは、しばらく会えない寂しさや異国で暮らす家族へのいろいろな不安が胸から離れず、これが今生の別れでもないのについ涙がにじむ始末であった。
空の彼方に、飛行機が米粒になるくらいまで見送り、しばしの別れに寂しさを隠しきれないまま帰宅した。
つい先日まで仮住まいして賑やかにすごしていた様子が一変した部屋を見渡していると、なぜか心に穴がぽっかりと開いたような気分で、どうも気が落ち着かない。今ごろ、あちらは何時だろう、何してるかしら、困ってることはないかしらと、それからそれへと考えてみる、転居先のイタリアを思い、時差を読み、計算するのにまごつく。そこで、はたと考えて時計をふたつ側に置き、ひとつはイタリア、もうひとつは日本時間をそれぞれに合わせた。これで指折り数えなくても済む。住むことになったイタリアの時を刻む時計には、イタリアと書いたシールを貼り、いつでも分るようにした。日本時間では今は夜中だが、あちらはそろそろ夕方だから、もしかしたら幼稚園から帰った頃かな、電話をしてみようかな、でも電話代がちょっと高いからなどと躊躇しながらも、指はダイヤルを回している。
こうして一日に何回となく覗きこむこのふたつの時計である。
家ではこれで不便はないが、外出時はワールド時計が欲しい気もする。
時計店で探すがなかなか気に入ったデザインの時計が見つからない。ときには腕時計をふたつも腕に外出したが慣れない腕がまた落ち着かない。
ふたつの時計を用意したことで、いつでもイタリアを想い、こちらの時間と比べて見ていると時差を越えて心は通じているのだという思いにかられ心もなぜか落ちつきを取り戻せる。
初めて時計売り場で腕時計を買ってもらったのは十歳ぐらいだっただろうか。
その時の私にとって腕時計は大人のシンボルだった。学校の先生や、親や、街行く大人の腕にはまっている時計を見るたびに、また彼らが何かの拍子に腕時計をちらりと見る度に私もいつか自分の時計をもってそれを見て自分でなんでもやりたいと思った。私にとって腕時計は自立の象徴でもあった。
そんな私の気持ちを知ってか知らずか、ある日母は時計を買いに連れて行くと言い出した。私は嬉しくて嬉しくてどきどきしながら時計を選んでいた。すると母が「水に何度も浸ってもいいものにしなさい」と言った。母の仕事は看護師で、一日に数え切れないほど手を洗う。だから時計も何度もの激しい手洗いに耐えられるものでなければならない。その事が自然になっていた母は私に何気なく言ったのだろう。しかし私はそのとき初めて母の手は日に何回も水にさらされていたのだということに気がついた。消毒液に荒れた母の手にもその時初めて気がついた。
その時買った十気圧の時計はいつのまにかなくなってしまったが、腕時計のはめられた荒れた母の手は、私の心からなくなることは決してない。私はそれを持って本当の大人への道を歩いていくのだろう。
私には大好きな曾おばあちゃんがいました。とても元気で、朝起きると着物に着替え一日中背筋をピンと伸ばしている明治生まれの素敵な女性でした。
高校入学の時お祝いに時計をプレゼントしてくれました。オシャレとは言えず地味であまり高価でない時計でした。高校3年間使用し、就職した頃止まってしまったので大事にしまっておきました。
ある日ふと思い出し、時計の電池を変えてもらおうと時計屋さんに持ち込みました。「替えるより買った方が安いよ」と言われたので「いいです。替えてください。」と言うと不思議な顔をされました。「大事な人からもらったのです。」と言おうかと思いましたがやめました。
無事時計が動き出し毎日身に付けていました。それからすぐ曾おばあちゃんが亡くなったと連絡がありました。私は(時計を動かしたからだ!)と思い時計をしまいました。
看護婦見習だった私は仕事を休めずお葬式にも出れませんでした。それから数年して看護婦として働いていた時ふと思い出し、また時計をつけました。その後はその時計をして患者さんのお世話をしました。
あれから10年近く経ち今は一児の母です。今はまた止まっている時計を動かすのは娘に譲る時です。
「先生、いい腕時計をしてますね。100万くらいはするんでしょう?」と、脈を診ているとき患者さんから質問された。
「そうですね」と返事し、(インターネットで探した1万円くらいのですけどね)と内心ニヤニヤしてしまう。
“医者=金持ち=高い物を身につけているはず”という三段論法が成立しているようだ。人間は、相手の身につけている物の値踏みを職業からする傾向があるらしい。私自身、時計は正確な時を刻んでもらえば十分と考えているので時計に金をかけるつもりなどさらさらない。世の中には何十万、何百万もする腕時計があるが、その良さも存在価値すら分からない。時計は数年に一つは買うが二万も出すつもりはない。高価な時計をしていると見てもらえるのは職業上の役得だと思っている。
もっとも脈を診るときに必要なので診察に腕時計は欠かせない。普通は10秒から15秒の脈拍数を測りそれに6か4を掛けて1分間の脈拍にする。故に腕時計に秒針は必須である。また書類を書く時に日付を度忘れすることがあるので日付の標記はあったほうがよい。つまり医者が仕事で使う腕時計は秒針が動くアナログ仕上げで日付が付いていれば十分だと思う。
「腕時計と父の臭い」小木曽 祐子さんのエッセイ (5月のベストエッセイ)
私が小学生だった頃、営業マンだった父は毎日腕時計をして出勤していた。車であちこち走り回っていた父にとって、腕時計は欠かせないものだった。
そんな父が、ある日、愛用の腕時計をはずして
「祐ちゃん、時計のベルトの臭いをかいでごらん。メロンの臭いがするよ。」
と私に差し出した。使い古された黒い皮のベルト部分はしわしわで、マスクメロンの網目模様のようにも見えて、私は、
「メロンの臭い?どこどこ。」
と父に飛びつきながら腕時計に顔を近づけた。そして、大きく息を吸ったその瞬間
「くさ−い。」
と逃げ出した。父の汗がしみこんだ皮は、メロンの臭いとはほど遠く、何とも言えない臭いがした。
父はにやにやと笑いながら
「メロンの臭いがしただろう。もっとかいでみていいぞ。」
と腕時計を持って追いかけてきた。いたずらっ子のように、父は子供の私をからかって楽しんでいたのだ。
「もう。お父さんったら。」
それ以来、父は時々
「今度こそメロンの臭いだよ。」
と腕時計をはずして見せてくれたが、そのたびに私は
「やだやだ。うそでしょう。」
と逃げ回っていたことを今でも覚えている。
今年は父の三回忌。仏壇に飾られている父の写真と腕時計。昔のことを思い出しながら、そっと腕時計の臭いをかいでみた。もしも今、父が「メロンの臭いがするだろう。」
と声をかけてきたら、私はこう答えよう。
「ううん。お父さんの臭いがするよ。」
と。
高校生の進路相談の時、母が担任に「今の成績では合格できる大学はない」と言いきられた事がある。あまりの悔しさに母はメッタな事では、父にチクッたりしないのであるが、たまらずに直訴したのである。父の前では、口答え、言い訳など一切通用しない。その日は如何言う訳か怒られなかった。でも約束させられたことがあった。まず第一に現役で合格する事。二つ目は工学系である事。そして落ちたら直ぐ働く事。以上の三つである。友達の多くは無駄な抵抗せずに、予備校行きを決めていた。元々勉強と言えば一夜漬けしかした事がない。担任を見返すには、合格しかなかったのである。そして作戦を立てた。いまさら勉強しても無理である。入試まであと二ヶ月。作戦とは、勉強した事は絶対間違えないで覚える。理解が出来ないとか、解らない所の勉強は時間がないのでやらない。と決めたのである。
その後運良く合格できた。父は黙って合格祝いに腕時計をくれた。よく見ると外国製のそれである。時計を持つのも初めてであった。それは秒針がなく、その代わりに小さな飛行機が秒針の変わりにグルグルまわっいた。その後なんとか卒業できた。そして就職もした。卒業した事を何故か黙っていた。今度は弟がチクッたらしい。その時は母に怒られた。無理もない。私は半年の間、小遣いを搾取していたのである。その時も父は怒らなかった。彼は私が恐る恐る差し出した卒業証書を黙って見つめていた。しかし卒業して3年後、父は胃がんで無念にも、その生涯を閉じたのである。葬儀の時、父に貰った時計を、旅立ちの祈念としてその腕に巻きつけた。享年55才であった。奇しくも来年私はその年齢に達する。その後その時計は弟が何故か持っていた。聞くと父に貰ったと言う。おそらく彼はドサクサに搾取したのである。でもマッいいか。
「再出発」三浦 由美さんのエッセイ (5月のベストエッセイ)
実家を目の前にして、足がすくんだ。この地元の高校を出てから、僕は東京の大学へ進んだ。そして11年。その間ここに帰ったのは、6年前の母の葬式の時だけだ。2度目の帰省。5年も経ってしまった。
「ただいま」
変わっていない、家の引き戸。
「ああ、お帰り」
聞こえてきた父の声。昔とは違ってどこかやわらかく、優しい。そして少し、弱々しくも感じた。
父は黙ってお茶をいれてくれた。「僕がやるよ」。痩せた父の手が切なくて、その一言も出てこない。沈黙の中、父のお茶を啜る音が気まずさを増す。
父の腕が、きらっと一瞬、光った。腕時計だ。僕の憧れだった、父の腕時計。今もしているのか。小さい頃、夜中に棚からこっそり持ち出した父の腕時計は、ずっしりと重かった。そしてそれは、僕にとって、父の重みだった。
「その時計、見せて」
父は黙って腕時計を差し出した。それは軽くて、まるでおもちゃのようだった。ただ、しっかりと時を刻んでいた。父の時間、そして僕の時間。秒針は狂いなく進んで、まるで「戻らない時間」というものを、僕に気付かせようとしているようだ。自分の愚かさを悔やんだ。
11年前は家の玄関までさえ見送らなかった父が、列車のホームまで来てくれた。
「着いたら電話するよ」
僕は自分の腕にした父の腕時計に目をやった。
「がんばれよ、人生は短くもない、長くもない。時間を大切にしなさい」
僕は黙ってうなずいた。時刻丁度。僕は東京行きの列車に乗り込んだ。
(事前のご同意)
「思い出の時計エッセイ募集」に送っていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツル株式会社に帰属します。
また、みなさまのエッセイと氏名(ペンネームを記載いただいた場合はペンネーム)を、当ホームページ上に掲載させて頂きますことを、
予めご了承ください。