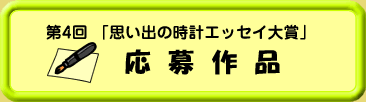 応募期間 2004年1月10日〜2004年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
2004年の作品
1月-2月 3月 4月 5月 6月-7月 8月-9月 10月-11月 12月
![]() 4月の作品(17作品)
4月の作品(17作品)
「100年休まずに」宮島 和騎さんのエッセイ
「チーズを食べられないねずみくん。」ともひさんのエッセイ
「骨ばった手に」稲垣 マユミさんのエッセイ
「父からもらった時計」内田なOさんのエッセイ
「時計余話」新玉 義男さんのエッセイ
「左利きでもないのに」武藤 喜明さんのエッセイ
「大人になりたい」小野 亮さんのエッセイ (4月のベストエッセイ)
「親の色々」福ちゃんのエッセイ
「想像ゲーム」増田 真奈美さんのエッセイ
「娘のファースト・ウォッチ」岩城 えりさんのエッセイ (4月のベストエッセイ)
「先生と私」さくら 葉子さんのエッセイ
「腕時計の交換」後藤 順さんのエッセイ
「相棒」keiさんのエッセイ
「時間が流れる音を」由紀夫さんのエッセイ
「春の時計」日高 大輝さんのエッセイ
「あの時の腕時計」揚葉久さんのエッセイ
「ピヨピヨと鳴く時計のお話し」薩摩 亜矢さんのエッセイ
僕の持っている腕時計は中学受験の当日に父から貰った。
それはそれは古い時計で、いたるところに錆が浮いていて手に巻きつけるバンドはボロボロで今にもちぎれ落ちそうだった。
父が僕の左手にその腕時計をつけながら言った言葉を覚えている。
「お前もここまで大きくなったか。」
とても、感慨深げで嬉しそうだった。
僕は腕時計なんかしたトコがなかったけれど、少し大人になったみたいで嬉しかった。
あれから10年近くたった今も未だに時を刻み続けている。
最近、祖父と父が写った古い写真をアルバムから見つけた。
若い祖父の左手には、今、僕がつけている時計があった。
そっか、これは祖父が父に受け渡した時計なんだ。
あと数年すれば、この時計は3代目から4代目に受け継がれることになるだろう。その日がどんな日なのか、想像しながら毎日ねじを巻いている。
中学校に入学する時、叔父に赤い革のベルトの腕時計を
プレゼントしてもらった。
秒針がチーズで、12時の所にはフォークとナイフを持った
ねずみの絵が描かれていた。
腕時計なんて、ちょっと大人になったようで、すごくうれしく
て。チーズも好きな私はじーっとその時計を眺めてた。
ある日、中学校のクラスの隣の席のK君が私に言った。
「あいつが、かわいいねだって。」
「あいつ」って、誰のことがわかってた。
K君の前の席の、H君。
私の右斜め前の席の色白のH君は、すごく照れてて赤くなってた。
でも、とっさに私は「ああっ、この腕時計?かわいいでしょ?
でもあげないよー。」なんて言ってしまった。
今でも時々想い出す。
世の中の難しいいろんなことなんて全く分からず、
でもそのときの私たちなりにいろんなことに悩んで、
いろんなことに一生懸命で、
だいすきな友だちと朝から夕方までずっとくだらないことで
笑いあってた中学生時代のこと。
H君、元気ですか?私は元気です。あの赤い腕時計は、
3時3分で止まったままです。
ねずみ君は、チーズを食べられなくてちょっと残念そうです。
あの時は、知らない振りしてごめんね。ごめんね。
父の骨ばった手に納まった重厚な時計。糖尿病が悪化し、父はどんどん痩せていく。子どものころ、父のお膝が私の特等席だった。背中にあたるお腹のぷにょぷにょのお肉が、たまらなく気持ちのいいクッションだったが今は見る影もない。
60歳の定年を迎えるにあたって、妹夫婦と一緒に送ったのが、この時計。プレゼント用にきらびやかに包まれた小箱を開いたとき、
「お父さんの手には重たすぎるよ」
と何度も照れ笑いしながら父は言った。
私たち娘二人は中学から私学に通い、何不自由なく大きくしてもらったが、ごくごく普通のサラリーマンだった父のお給料では、きっと大変なことだったに違いない。擦り切れた父の時計バンドを度々母と一緒に交換に行った思い出がある。あのころは、きっと自分にお金をかける余裕もなく、あまり上等とはいえない時計を繰り返し使っていたのだと思う。出勤間際にテレビ台の上に置いてあった時計を最後にはめて出かけるのが、父の習慣だった。その細かい仕草のひとつひとつを鮮明に覚えている。左手にしっくり時計が馴染んだ瞬間から、父の温厚な顔つきが、厳しい表情に変っていったことも。
「お父さんにプレゼントするなら時計がいいわ」
と最初に言い出したのは母だった。典型的な団塊世代の仕事中毒だった人が、60歳を機に躊躇うことなく仕事をやめる。これからは父の思うように人生を謳歌して欲しい、と選んだのが、職人魂宿るグランドセイコーだった。深い皺を刻んだ横顔に最も似合うと思ったからだ。残念ながら、退職後間もなく、病魔が父の生活を大きく制限するようになった。でも、庭仕事に精を出し穏やかな笑顔は増えた。インシュリンの注射を打つ細い腕には、いつも私たちの気持ちが光っている。
不器用で愛情表現が苦手な父。
ずっと嫌われていると思っていた。
小さい頃に会話をした記憶はほとんどない。
中学生になった時に父が買ってくれた腕時計。
アナログの小さな太陽と月が交互に登ってくる時計。
私はそのアクのないデザインが妙に気に入り、13歳から26歳まで13年間も愛用した。
高校時代、恋こがれていた人が、同じデザインの時計をしていた。妙な縁を勝手に感じた。でも遠くでみているだけで終わった。まるで父に対する態度そのままに。
時が流れ、私はもう32歳。家をでて大事な彼と出会い、今は二人で暮らしている。
5年前に脳血栓で生死をさまよった父は、ハタ目には分からないが、言葉がでにくいという。
姪の誕生日に久しぶりに実家に帰り、レストランへ食事にいった。たまたま席がなく、私が父と二人で座ることになった。言葉が発しづらいながらも話そうとしてくれる父。
「彼とはどうなんだ?」「サキ(姪)、すげー食べるんだよ」もしくは、笑うだけの返事。
もともと無口な父。子供だった私にはわからなかった家族に対する深い愛情を今は痛いほど感じる。
帰って彼に話そう。コルクボードにずっと飾ってあるあの時計は、父からもらってから13年間愛用し、今だ捨てられずにいるものだと。
私より両親の方に年が近い私の大事な人は、雰囲気が父に似ている。そして、愛情表現が苦手でいつもその人を困らせる私は父にそっくりだ。
父にもらった時計はもう動かないけれど、チクタクと時は刻まれ、それぞれの心を寄り添わせてくれる。チクタクチクタクと、色々なことを語りかけてくれる。
時計余話
人はその生涯の内に幾つの時計を身に付けるのだろうかと、ふと思うことがある。
10指に余る人も満たない人も手にした時計全てに満足しているかどうかは疑問の残るところである。
人生の節目、節目に贈られたり、買い求めたりそのプロセスは様々あるがその中には必ずこだわりの一品がある筈である。
買い物帰りに書店に立ち寄ると世界の有名ブランド時計が掲載された雑誌が目に止まった。
ページをめくって見ると超豪華な宝飾時計やスポーツ時計に混じって懐かしい時計が載っていた。
それは「君の若さがネジを巻く」といった軽快なCMソングにのって当時大流行したスポーツタイプの自動巻き時計であった。
高校生になったばかりの私にとってこの時計のデザインや機能性は憧れの的であったが
結局手にする事ができなかった。
今でもそのときの悔しさを忘れる事が出来ないでいる。
その反動からか社会人になって数年後、十数万円もするS社のKクオーツ時計を何のためらいもなく購入し、日々時計を眺めてはほくそえんでいた。
この時計とはその後十年以上の長い付き合いとなったが寄る年並には勝てずとうとうお蔵入りする羽目となった。
五十台半ばを過ぎた今、数えて6個目の時計を身につけているがkクオーツに勝る満足感の得られる時計にはめぐり合っていない。
この先、残りの人生を加味しても私が身に付ける時計の数は十指にも満たないであろう。
この数が人と比べて多いか少ないかは知る由もないがこだわりの一品に巡り合うことが出来た喜びは忘れることがないであろう。
『爺ちゃん、左利きなの?』『違うよ』『じゃ、なんで 腕時計を右手にしているの?』孫に聞かれて、何十年も昔の事を思い出した。
私が好きだった映画俳優の映画を観た時に、その主役が人との待ち合わせ場所へ先に着き、なぜか右腕に付けた腕時計を覗きながら『時間にルーズな奴は信用できねえ』と言って立ち去るシーンがとても恰好良く見えた。
それが きっかけで私は左利きでもないのにずっと右腕に腕時計を付けている。
昔はいちいち外してゼンマイを巻いたり、時間を合わせたりしたが今、腕時計の性能が 驚く程良くなっているので、何も問題なく極自然に右手に腕時計を付けている。左利きでもないのに・・・・
「大人になりたい」小野 亮さんのエッセイ (4月のベストエッセイ)
そうあれは今から20年前、私は小学校を無事卒業しようとしていた。
私の家庭は貧乏そのもので毎日の食べ物さえ子供たちが心配するくらいだった。兄弟は育ち盛りの5人兄弟、しかも母子家庭の中、育った。
母は毎日、子供たちに少しでも何かを食べさしてやりたい、、と必死だったと思う。昼間の仕事に夜の仕事、寝る時間なんてあったのだろうか?しかしそのころはそんなことを理解できる子供ではなく”なんで家はこんなに貧乏なのだろう?なんでお腹いっぱいごはん食べれないんだろう?”そんなことばかり考えていた。
卒業間近、中学校の制服やかばん、教科書・体操着、いろいろ準備をする時期になった。学校が遠いので自転車も必要だ、、。
新品など買える余裕などあるはずもない、制服はお下がり、教科書や体操着もお下がり、自転車は何とか近くの自転車屋さんで1000円の中古車を買えた。
ただ私は当時、中学生は大人に見えていた。制服からチラッっと見える腕時計、、。中学生になったら大人だから腕時計が欲しい!そう思っていた。しかし家にはそんな高価な腕時計など買えるはずもない。
そして卒業式も無事に終わり、家で普段と変わらぬ夕食をとっていた時だった、、母が”はい、入学祝、、”と私にけして綺麗ではない包装紙に包まれたプレゼントを差し出した。
私はごはんを口に頬張りながら涙が溢れてきた、、
年頃のせいか、うまく表現できず心の中でありがとう、ありがとうと叫んでいた。腕時計を握り締めながら、、、。
三歳の娘がキラリと光るものを発見した。
雨上がりのよく晴れた日で、場所は家の庭である。
掘り出してみると、それは腕時計であった。
金属製のバンドで、なんともいえない圧力感のあるつくり。とても安物には見えない。多分、男物だろうと思われた。
「じいちゃんのかもしれんけん、夜、確かめてみよう。持ち主が分からんかったら貰っていいぞ」
そう言うと娘は笑顔で頷いた。遠くに見える阿蘇の山々を背景に、娘は愛しそうに時計をなでていた。
夜…。
親父が帰ってきてから、その時計を食卓に出し、
「これ、誰のか分かるね?」
と、問うた。
時計はピカピカに磨かれている。娘が磨いたのであろう。
親父はそれを見るや、
「あ!」
皆がビックリするような声を上げ、
「お、お母さん!」
と、おふくろを呼んだ。
「こ、これ!」
「あっ、これは!」
二人は私や妻、それに孫がいるのに二人だけで盛り上がり、
「どこにあった?」
と、私に問うてきた。
庭に埋まっていたのを娘が見つけた事を説明すると、
「でかした!」
親父は孫を抱き締め、この時計の事を語り始めた。
この時計は結婚十年目に「互いにプレゼントをしよう」という事で、おふくろが親父に渡したもので、当時、親父は肌身外さず付けていたものらしい。が…、庭で草むしりをしている時にどこかへ落とし、いくら探しても見付からなかったのだという。
「そりゃ良かった」
家族皆で、その事を喜んだものであるが、一人だけ納得のゆかない女がいた。娘である。貰えると思っていたものが貰えないようになり、暴れ始めた。
「とけー! 私のとけー!」
私は親父にこの始末を押し付けた。
「親父がどうにかしろよ、見付けてもらったんだけん」
「うー、そうは言っても」
親父と娘の問答は永延と続き、結局、一万円二千円もする滑り台を買ってあげる事で落着した。
「ま…、金で買えんものを見付けてもらったけん…」
そう呟く親父の顔は、何ともいえない味わいがあった。
我が家では夜,布団に入ってから想像ゲームをするのが日課だ。
一人がある物を想像し,他の人が「それはどんな形?」などと質問して,当てるゲーム。
その夜,私は「時計」を想像した。娘が「何色?」「いろいろな色があるよ」。「どんな形?」息子の質問に「いろいろな形がある」。「どこにある?」「家にも,外にもあるよ」。「どこの部屋にある?」「う〜ん,全部の部屋にある」。主人が時計好きで,トイレや風呂場にもあるのだ。
「わかったぞ」今まで黙っていた主人が叫んだ。「電気だ」。「残念でした」「えー,じゃあ誰がよく使う?」「みんなよく使うよ,ないと困る物」「お金だ!」「違う違う,では大ヒント。お父さんが好きな物」「あーわかった。時計!!」とさわぐ子供たち。
「俺そんなに時計好きか?」首を傾げる主人。こんな楽しい時を,我が家の時計たちは刻んでくれている。
「娘のファースト・ウォッチ」岩城 えりさんのエッセイ (4月のベストエッセイ)
娘を出産した記念に、夫とペアーウォッチを購入しました。
何軒も、何軒も、時間をかけてお互いが気に入るものを探したので、購入した時、すでに娘は1歳の誕生日を迎えていました。
娘は、すくすくと成長し、今年で3歳になりました。
活発で、何にでも興味があり、我がままいっぱいの娘の最近の「マイブーム」は数字。
きっかけは、あの出産記念の「腕時計」。
「お外で遊びたい!」「長い針が上まで来たら10時だから、そしたら出かけようね」
「おやつ食べたい!」「長い針が上まで来たら3時だから、そうしたら食べようね」
娘の底なしの要求を、腕時計を見せながらかわすうちに、彼女は数字に興味を持ち始めたのです。
先日、夫が出張に行きました。
「お父ちゃんっ子」の娘は、毎晩お父さんを思い出しではシクシク泣いていました。
「何時になったら、お父ちゃん、帰ってくるの?」
本当に悲しそうな泣きはらした顔で聞く娘に、
「あした、あさっての8時だよ」
と、腕時計を見せて言い聞かせました。
娘は一日に何度も、私の右腕を引っ張り「そろそろ、じゃない?」と腕時計を確認していました。
出張から帰ってきた夫に、娘は駆け寄り抱きつき、しばらく離れませんでした。
夫から娘へのお土産は、シンデレラの絵が描いてある腕時計でした。
まだ細い娘の腕には、ぶかぶかなのに、娘は大喜びで寝ている時も腕につけています。
そして、毎日「ほら!長い針が上まで来たから、もう3時だよ!」と、1時間おきにおやつをねだるようになってしまいました。
私が先生に初めてあったのは桜の花が水面に浮かぶ頃。場所は古都金沢であった。お互いに受話器からの声を頼りに想像し会って、会うまでに半年以上の時を経て、。
出会いから1年後、先生は上京され、再び逢ったときは旧知の友のような懐かしい感覚を感じた。そのとき、先生は「ぼくは君に、プレゼントしたいんだ」と唐突におっしゃられた。私は「先生にお会いできるだけで幸せです。また、これからもあってくださるだけで充分です」と。実際、これは本音であった。先生は「いや〜、私の思い出をあげたいんだよ。どうだい、今からデパートへ行こう」
先生がプレゼントしてくださったのは今私の腕にしがみついている「銀色に輝く腕時計」だった。
先生の言葉は「私の人生の時計はあとわずか。でも、あなたの人生はこれからだ。いい‘とき’を刻みなさい」
そして私はいま、いい‘とき’を刻んでいるだろうか?自分に問いかけながら古都金沢を一人思う今日この頃である。
そして、もう一つの先生の言葉。「もし、来世があるならば、今度は私の娘として生まれてきて欲しい」。
この時計が来世までも時を刻み続け、私と先生を結びつけてくれることを願うばかりである。
二十五年前になる。妻との結婚が決まった。お互いにの家族には内緒にして、自分たちだけの「結婚式」をしようと思った。二人とも金がない。親たちに頼るのも嫌だった。
そこで、結婚指輪の交換ではなく、現在使っている時計の交換にした。女性のものは細いが、当時の僕はひどく痩せていた。限度まで開くとすっぽりはまった。僕のは彼女の腕にもフイットした。
とても簡素な結婚の儀式に、そこに参列した友人たちは驚いたらしい。会費だけの「茶和会」程度のもに、僕たちは胸を張った。何もないところからの出発でいい。今まで使い慣れた腕時計を相手に渡し、お互いの手と手を取り合ってのに、この儀式はベストだったのではないか。
親たちにはひどく怒られた。結婚式という門出を大きな式場で披露したかったのだろう。その代わりに、僕たちはペアウオッチを親たちからプレゼントされた。交換した腕時計は、記念として桐箱に入れて保管した。指輪ではなく、時計でもいい。長針が刻む間も、二人して生きる時間を感じる腕時計。
今度、子供たちが結婚するとき、僕たちのような「腕時計交換」という儀式を提案したい。
相棒へ
もうすぐ、この腕時計くんとの付き合いも1年になろうとしている。社会人になり、2ヶ月目に買ったこの時計。思えば、たくさんの時間を君と共に過ごしてきた、ということに改めて気づいたよ。
あれを、君はまだ憶えているだろうか?
会社で、上司に怒鳴られ、怒られているときにも、君は文句1つ言わずに、僕の腕で、時を刻み続けてくれた。君は悪くないのに、一緒に怒られてくたね。
他にも、初めて行った遊園地で、これまた初めての絶叫マシンに乗ったときにも、君はついてきてくれた。嫌なら、「いやだ」といえば良いのに。僕と共に、君は、地上数100メートル(実際には、数十メートル?)
の高さに持ち上げられ、一瞬にして、地上に舞い戻された。
はっきり言って、もうだめかと思ったよ、僕は。でも、君は、時間を刻み続けていたね。ジェットコースターに3回連続で乗っても、君は元気だった。僕は、ボロボロだったけど。
というわけで、いつも君は、僕をしっかりと支えてくれていたようだ。感謝しないとね。
ぜひ、これからも、末永く、僕と共に同じ時間を過ごして欲しいと願うよ。
よろしく。
高校入学の祝いに親父から腕時計を貰った。
約20年前のこと。
銀色の金属ベルトのゴツイ、自動巻きの時計だった。
腕を振るたびに、中のゼンマイが巻かれる小さな音がする。
腕時計に耳を近づけると、その外観からは想像もつかないような繊細な秒針の音がする。
自動巻時計特有の秒針の音だ。
その時まで、腕時計など持ったことは無かったうえに、初めて手にした時計が自動巻時計だったこともあって、非常に嬉しかったことを憶えている。
その腕時計は、2日間放置しておくと、止まってしまう。
自動巻の腕時計だから当たり前なのだが、止まるのが嫌で、いつも左手首にはめていた。
暇があると、左手首を細かく振って、ゼンマイが巻かれる小さな音を楽しんだ。
そして、耳を近づけて秒針が動く心地良い音を聞いた。
時間が流れる音を聞いた。
親父は、この音を聞かせたかったのかなぁ、などと最近になって考える。
面と向かって、聞くのも気恥ずかしいので、今更親父にそんな質問をしようとも思わないが、なんとなくそんな気がする。
あれから約20年間、自動巻時計を左腕に巻き付けて、時間の流れる音を聞いてきた。
25歳で結婚した時も、27歳で長男を授かった時も、29歳で次男を授かった時も。
長男が小学校3年生になり、次男が小学校に入学する今年になっても。
時間の流れる音は、変らない。
私も息子達が高校生になる頃、自動巻腕時計をプレゼントしようと考えている。
私が、親父に貰った自動巻腕時計と同じような、ゴツくて、重量感のあるやつを。
そして彼らの、まだ成長途中で、腕時計など似合わない左手首にはめてやり、一緒に手首を振って、時計に耳を近づけてみよう。
3人で自動巻腕時計の秒針の音を聞く。同じ時間の流れる音を聞く。
そして、左手首を細かく振って、耳を近づける彼らの姿はきっと、私に時間の流れを見せてくれるだろう。
親父にも見せてやるとしよう。
高校に入学して親元を離れた。高校生は腕時計をする、すなわち少し大人に近づいた気がする。別に時間さえ分かればいい、と思っていた。また私の好きな女性芸能人がアナログの時計にこだわっていたので自分もアナログの時計にこだわろうと思った。自分で安物の腕時計を買って着けていた。
五月の連休に初めて実家に帰った。母親は息子が帰ってきたことにものすごく喜んで
「いい時計を買ってあげる」
と言って一万六千円のベージュに輝く腕時計を買ってくれた。
自分の家はずっと貧乏だと思っていた私は、そんな高価なものをオレなんかのために買わなくていいのに、と思うと同時にやはり今まで着けていた安物とは違う高級感にうっとりとした。一生使い続けていこう、と思った。
それからというものどこに行くにしてもその時計は私の傍らで時を刻み続けた。遠く離れた故郷にいる母親が奮発して買ってくれたもの。勉強に明け暮れ、孤独を感じながらも頑張り続けた暗い部屋、炎天下の下部活のテニスをしている時も着けていた。ラケットがあたってバンドがちぎれたり、汗で臭くなったりもした。
故郷をさらに離れた大学時代、まじめだった高校生活のリバウンドで遊びに遊びまくった日々。時々腕時計を見ては母親が買ってくれた日の晴れた故郷を思い出した。
就職して仕事に熱中していた日々。いくら睡眠時間が少なくてもこの腕時計と共に起きていた。
仕事を辞め、先の見えない不安を抱えて過ごしていた日々。あまり時計を気にすることは少なかったが確かに私の左腕には私の思春期の戦友がいた。
新しく踏み出そうとした春、時計の中が錆び付いて針が止まってしまった。ちょうど十年が経ったときだった。第二ステージが始まった気がした。
小生が生まれて始めて腕時計を持ったのは高校入学時に親から買ってもらったやや薄めの自動巻きの物で文字盤は、コバルトブルーがっかったお気に入りのものだったバンドは黒いナイロンの編みこみのものだった。重宝していたのだが、2年ほどたったある日ラッシュの電車の中でバンドが緩んだらしくてなくしてしまった。そのときは足元に時計のようなものが落ちているなとは気付いていたがまさか自分のものだとは思わなくて乗換駅でドアから押し出されてしばらくしてから気付いたが電車は行った後でもう後の祭りだった後ほど落し物コーナーに行ってみたけれど見つからなかった。もうあれから30年以上たっているのだが小生の胸の中では、まだあの時計がときを刻んでいるようでまだ目を閉じると秒針がときを刻んでいるように思われます時はたったけれど思い出のスクリーンはストップモーションがかかった様です。
私は低血圧で朝が弱く自分自身の力で眼が覚めることはまず皆無です。自慢ではありませんが遅刻欠席は日常茶飯事。したがって目覚まし時計は手放せません。でもその目覚まし時計も私にはあまり役に立たないのです。なぜかと言うと鳴っても鳴ってもすぐに止めてまた寝てしまうからです。今までいくつ目覚まし時計を買ったか知れません。ある日、ぴょぴょと鳴くひよこの目覚まし時計を見つけました。これだったら機嫌よく起きれるかもしれない。
その晩からその目覚まし時計をかけて寝ました。その目覚まし時計は時間になるとぴょぴょと鳴き始めます。ぴょぴょと鳴くのです。
夢うつつの中で私は「ああーひよこが鳴いてる」という錯覚の中で寝ていました。私の脳細胞は起きなければいけないと理解はしているのですが身体が起きてくれません。目覚まし時計は律儀に命令どうりぴょぴょといつ間でも泣いています。私はいつの間にかベットの下に何十匹のひよこがうろうろとうろついてぴょぴょと鳴いている錯覚にとらわれながらも相変わらず夢の中でした。そのうち段々腹が立ってきてベットの下のひよこをひとつ残らず捕まえて首根っこを締め上げてやるぞと思いながら睡魔と闘っていました。そしてなんとかいやいやおきるなんとも機嫌の悪い目覚めなんです。それは毎朝、毎朝ひよことの戦いのようでした。毎朝セットした時間になると目覚まし時計は律儀にぴょぴょと鳴き始めます。その頃から私の脳細胞の中には何十匹という数に膨らんだひよこがペツトの下で点でばらばらに好き勝手にぴょぴょぴょぴょと鳴きながらうろついているのです。私はひよこに対して憎悪の何者でもない感情がわいてきてまた一匹づつ捕まえては首根っこをひねりつぶしてやるぞと思いながら繰り返し押し寄せてくる睡魔と戦う朝でした。
(事前のご同意)
「思い出の時計エッセイ募集」に送っていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツル株式会社に帰属します。
また、みなさまのエッセイと氏名(ペンネームを記載いただいた場合はペンネーム)を、当ホームページ上に掲載させて頂きますことを、
予めご了承ください。

