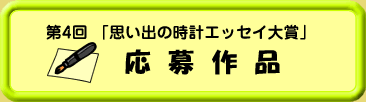 応募期間 2004年1月10日〜2004年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
2004年の作品
1月-2月 3月 4月 5月 6月-7月 8月-9月 10月-11月 12月
![]() 3月の作品(19作品)
3月の作品(19作品)
「朝一番のニワトリの声」トモヒロさんのエッセイ
「気になる時計」金井 綾子さんのエッセイ
「時計から時計を。時計からぬくもりを。」畑辺 なな実さんのエッセイ (3月のベストエッセイ)
「思い出の柱時計」牛島 典子さんのエッセイ
「「お姉ちゃん」の時計」舘野 なおさんのエッセイ (3月のベストエッセイ)
「夫からの時計」青木 桃子さんのエッセイ
「母の腕時計」福島 亜希子さんのエッセイ
「祖父が好きだった“ゆっきの時計”」藤橋 裕紀子さんのエッセイ
「おばあちゃんのくれた時計」ナゴ ミツグさんのエッセイ
「祖母にもらった腕時計」久司 若菜さんのエッセイ
「ま、待て!」福ちゃんのエッセイ
「親父のシルバーウェーブ」藤原 健伸さんのエッセイ
「戦利品」榎本 昭さんのエッセイ
「追っかけっこ」たなか しんじさんのエッセイ
「祖母との思い出」尾和 大介さんのエッセイ
「小さなふるい時計屋さん」松林 厚子さんのエッセイ
「やっさんの腹時計」後藤 順さんのエッセイ
「止まらない時計」anjelicaさんのエッセイ
「冷たい腕時計」清水 利恵子さんのエッセイ
「コケコッコー!コケッコッコー!」
耳元で鳴り響くニワトリの声。
眠気と格闘する私にはおかまいなしに彼は鳴き続ける。
その声によってまた今日一日がはじまる。
小学一年生のとき、祖母が私に一人で起きれるようにと買ってくれたニワトリの目覚まし時計。それから11年間、決して休むことなく私を起こし続けてくれている。この時計には私の11年間がつまっている。
時計を買ってもらった当時の私はいつも祖母や両親に起してもらわなければ一人で起きることができなかった。おまけに私の家は小学校からかなり遠かったため、普通の小学生よりもかなり早起きしなければならなかった。自分の身の回りのことから少しずつ自分でできるようにと、祖母はそんな思いでこの目覚まし時計を買ってくれたのだろう。よく「ばあちゃんがいつまでもそばにいてやれるわけじゃないんだからね。」と言われたのを今でも覚えている。
そんな私も小学校高学年から中学にかけて一人で起きれるようになった。その後、高校に入って下宿をして周囲の環境すべてが変わってしまった。しかし、朝一番のニワトリの声で目を覚ます習慣は今も変わらない。そしてこれからさきも。
私と主人は共通の知人を介して知り合った。初めて待ち合わせて会ったときに気になったのがなぜか主人の腕時計。どこにでも売っているシルバー色の普通のブランドの時計なのであるが気になる時計だった。主人と付き合うことになってからもなぜか自然と時計に目がいってしまう。主人には悪いが主人よりも主人の腕時計を見つめている時間のほうが長かったかもしれないっていっても過言でないくらい気になる時計だった。しばらく後に結婚し赤ちゃんを授かった。赤ちゃんが生まれるときにその時計は秒針の調子が悪くなり、産婦人科の病棟の中で2人の話題は生まれた赤ちゃんのことと時計をどこで修理するかだったのを覚えている。それから後は子育てに追われて時計を気になる暇もなくなってしまったが、そのとき生まれた赤ちゃんももう2歳になり今度は2歳の娘がその時計が気になっていつもパパから自分の腕に巻いてもらうのを楽しみにしている。他の腕時計を巻いてあげたりしてごまかそうとしてもぜんぜん効果がなく、主人のこの時計でないとだめらしい。この時計がこれからも私たちにとってどんな気になる存在であり続け私たち家族の歴史を刻んでいってくれるのかとても楽しみです。
「時計から時計を。時計からぬくもりを。」畑辺 なな実さんのエッセイ (3月のベストエッセイ)
もうあれから10年経っただろうか。
私は中学生になった。小学生には許されていなかった腕時計。これで一歩大人の仲間入りができると思うと何だかとても嬉しかった。
私の思い出の時計・・・。それは実際には私だけのものではない。どういうことか。。。それを今からお話しよう。
私の通っていた中学校は男女共学、但し別クラス、別校舎という、特殊なスタイルの学校だった。委員会以外では異性との出会いは一切なく、渡り廊下は先生が見回り、とても話のできる状態ではなかった。
そんな状態で、誰が考えたのか今となってはわからないが、時計の交換。中学生、自分たちから見たら大人の仲間入りの証とも言える自分の腕時計を、意中の人と一日だけ交換するのだ。果たして、私もその仲間入りをする時が来た。同じ委員会の2組の子。委員会の時に時計の交換を恥ずかしながら申し出ると快く応じてくれた。しかしそこで私は固まってしまった。彼の時計はぴかぴか光る金属ベルトの腕時計。私の時計は母のお古のぼろぼろになった革ベルト。後悔した。もっとよく考えてから申し出るべきであったと。光り輝く金属が今は冷たく重たいもののようだ。
彼は既に腕時計をはずし、先生がこないかきょろきょろと頭を動かしている。腹をくくって自分の時計と彼の時計を交換した。
1分後、先ほどの後悔はどこへいってしまったものか。私はまだ彼の体温の残る腕時計をしっかりと身につけ女子校舎へと駆け戻っていた。自分のものでないものを身に付けているという緊張、彼と私2人だけの秘密を共有しているというどきどき感。今思い出したらかわいらしい。
家に持ち帰っても宿題もせずじっとその文字盤を見つめ、バスを待っているわけでもないのに登校中もずっと時計を見ては周りを見回す。バカらしいと思いながら、そんな自分に満足していた。
明くる朝、彼に時計を返す時が来た。渡り廊下の隅っこで再交換。今まで持っていた立派な時計からまた薄汚い時計が私に戻ってくる。しかし次の瞬間、薄汚い時計がたちまち素適な時計に変わる。彼の魔法の言葉で。「時計、すっごいやわらかいね、手になじむね。」
「ありがとう」と言って受け取った私は自分の顔が熱いのを感じる。私はそのまま「じゃぁまた委員会でね。」と彼の時計を返す。「うん。」と言って彼は微笑み、最後に一言。「この時計、まだあったかいね。」
その言葉を背中に受けながら、私は女子校舎へと戻っていった。彼の手になじんでいた私の宝物を抱いて。
十六歳の頃に住んでいた英国の家にはアンティークがたくさんあった。例えば大きなベルが置いてあった。昔使用人を呼ぶ時に鳴らしたという説や食事が出来ましたよと家族を呼ぶ時に鳴らしたという説があった。他にも薪をくべる暖炉と煙突、玄関には百年は動いていると思われる柱時計があった。私の母が毎週一回ネジを巻いていた。当時私にはボーイフレンドがいた。家に電話は一つしかなく、会話を聞かれるのが恥ずかしいので週末の夜中に電話で話したことがあった。家族は二階で眠っていて、私は一階の玄関近くの電話で小声で話していた。十一時になり柱時計はボーン、ボーンと時を告げる鐘を鳴らし始めた。その間会話は自然と止まった。私は無意識に時計の音を数えていた。柱時計が十一回を鳴らし終えると静寂が訪れた。そして会話が再開された。幸せな時間はあっという間に過ぎ、一時間後に柱時計は再びボーン、ボーンと時を知らせた。また会話は止まり私は鐘の音を数えた。夜中の十二時にその柱時計は十三回鳴った。英国では十三という数字は不吉とされている。何となく不気味な感じがして私はボーイフレンドに「そろそろ寝るから。」と言い電話を切った。甘い時間とミステリが交差した不思議な夜だった。
「「お姉ちゃん」の時計」舘野 なおさんのエッセイ (3月のベストエッセイ)
2つ上の姉は小学校2年生の時から自分の腕時計を持っていた。二人だけで初めて祖母の家に泊まりに行く時に母が買ってくれたものだ。5才の私には赤いウサコちゃんの時計は大人の象徴のように思えた。羨ましいという感情はなかった。姉は大人であり、私はまだ小さい―負けん気の強い私が、その時は素直にそう思った。
私は乗り物に酔う質で、祖母の家に行く特急電車でも具合が悪くなった。上野で母と別れ二人きりになった電車の中で、心細がって泣く私を前に、姉こそ泣きたかったことだろう。勝気で口の回る次女の私と違って、姉は口の達者な子供ではなかった。引っ込み思案の姉が、普段の気の強さも忘れたようにメソメソ泣いている私をなんと言って慰めてくれたかは覚えていない。覚えているのは駅に着いて電車を降りる時、姉が私の荷物を持ってくれたこと、その手に赤い腕時計がはめられていたこと、それを見て私が不安ななりに何か安心したことだ。ここにお姉ちゃんがいる、お姉ちゃんは大人だ、と。
祖母の家で過ごした長い夏、私はホームシックでお腹が痛くなり、泣いてばかりいた。そんな時、姉が急にしっかり者になって私を支えた、ということはない。けんかもした。それでも、姉は「お姉ちゃん」だった。その前もその後も、いつだって彼女は2つしか違わない妹を何かあったら面倒見なくてはいけない姉だった。私が感じる以上にそうっだたのだろう。それが幼い私の目にわかる時、腕時計という形だったのかもしれない。
ずっと後になって赤い腕時計は姉の小抽斗にしまわれた。動かなくなったからかデザインが子供っぽくなったからだろう。私はそこにその時計があることを(おそらく)姉よりもしっかり覚えていた。抽斗自体処分された今も、中にある時計をはっきりとイメージすることができる。もうどこにあるかわからない時計。「冬の日のウサコちゃん」の絵のついた赤い子供用の腕時計。それは、大好きな「お姉ちゃん」の時計だ。
夫に時計を婚約の際にプレゼントされました。その時計は自動まきの時計で今までわたしが持ってないものでした。結婚指輪は一度もはめたことはないけれどその時計ははずしたらとまってしまうので必ずつけています。夫からはこれといってプレゼントをもらったことがないのでこれが一番のプレゼントです。
この時計をめぐってはいろいろなことがありました。私の住む町は電車が20分に一本しかないので時計が1分遅れたために電車に乗り遅れてしまい、20分駅で待ったこと、自動巻きは壊れやすいのか時計の針がしょっちゅう止まり、修理のために時計を保障期間中なので何回も交換してもらったことやついには時計の担当者が退職してしまい、なおすのに転々といろいろなところに時計をまわしてなおすところをさがしたりとてんやわんやでした。こんなかんじで私たちの夫婦生活も時計が壊れるたびに不吉な思いが頭をよぎりました。けれど今でも仲良くけんかしたながらもやっております。時計のようにいろいろあるの夫婦なのかと思っております。そして昨年待望の赤ちゃん喪授かることができました。本当に夫からの時計はてんやわんやの人生をはこんできたようです。
私は農業を営む両親の元に生まれました。父は公務員でしたが、仕事の日でも朝早く畑に出かけ、一仕事してから仕事へ行き、夏の日が長い時期は帰宅後も畑へ向かいました。そんな父を支えながら母は父の仕事の時は毎日、一人畑仕事に精を出していました。
しかし母の凄い所は「ただの農家では終わらない!」所でした。家事、畑仕事、全てを完璧にやりこなし「さぁ、これからはお母さんの時間よ」と言うかのように時間を見つけてはカラオケや趣味に出かけて行くのです。何でもきちんとこなしているので、父ももちろん文句は言えません。私は母のパワーに驚きながらも「仕事も遊びもなんて、体に無理だけはして欲しくないな」と感じていました。
母がいつも身に着けていた金色の腕時計。「気に入っているだけだけに高そうだな…」といつも思っていました。その時計が一番の母のお気に入りだったのです。
私が22歳の時、母は就寝中のクモ膜下出血により突然意識不明となり、そのまま意識を戻す事なく1週間後に帰らぬ人となりました。
遺品の整理の中、その金の腕時計を手に取り間近で見た私は、腕時計に母の働きを改めて納得しました。母の腕に着けられていた輝く金の腕時計は、本当はメッキも剥がれ隙間には垢が付着していたのです。「時計もお母さんと一緒にがんばったんだ…」と思うと悲しくて仕方ありませんでした。主亡き後の時計は輝きも全くなくなっていたのです。
あの時計の輝きは、きっと母自身の輝きであったのだと、今私は思います。
「祖父が好きだった“ゆっきの時計”」藤橋 裕紀子さんのエッセイ
カチカチカチカチ…『ゆっきの時計は鳴ってっか?』
ベッドの上の祖父が祖母に茶色いボックス形の時計を持って来させ、耳元に置いてくれる様に言ったという。“ゆっきの時計”、それは私が生まれた記念に買った時計である。カチカチカチカチ…私にしてみれば、耳ざわりとも思えるほどの音をたて時を刻む時計であるが、祖父にしてみればそれが良かったらしいのだ。『ゆっきと話をしているようだ』とまるで私を可愛がるように、その時計を大切にしてくれていた。祖父にとっては私が何か楽しいおしゃべりでもしていた様に感じていたのであろう。
そんな祖父が癌で入院したのはその直後であった。その悪者が脳にまで達していたのだ。だから、うるさいほどの時計の音も祖父には聞こえていなかったのかもしれない。そんな祖父が亡くなってもう五年。今でも何かにつけて思い出すのは祖父との楽しかった思い出。二才の息子の手を引いて遊びに行く公園。そんな時も、祖父が遊んでくれたことを思い出し、何となくつぶやく。『じっちは空から見てっかな…?』
じっち!ゆっきは毎日楽しくやってるよ!四苦八苦しながらも、子育てをゆっきなりに頑張っているよ!
そして…じっちが大切にしてくれていた“ゆっきの時計”もいつも元気に鳴ってるよ!
カチカチカチカチ…うるさいほどに鳴ってるよ!!
高校の入学祝に、おばあちゃんが買ってくれた腕時計。
おばあちゃんは僕が東京に出てきた年の4月に亡くなり初任給で香典を送った。働いたばかりで葬式にも顔を出せなかった。
船大工の妻として気性の荒い漁師達をうまくあしらい無口な職人のおじいちゃんを立てていたおばあちゃん。いろんな人たちが毎日出入りしてたっけ・・孫の僕達には旅行に行けばお土産、会いに行けばおこずかいと何かしらもらうという記憶が強い。
気配り上手で人が集まる人格者だったんだと今になってつくづく感じる。その時計は、二十歳の時ケンカして人を殴ったら止まってしまった。違う腕時計を3度してみたけれど、全てすぐに止まってしまったりベルトまで切れたり水を使う仕事の影響もあって、いつしか腕時計をしなくなってしまった。
時計を着けない時を十数年過ごした。
離婚して部屋を整理していると、引き出しの奥からおばあちゃんの時計が出てきた。二十歳のケンカした時間で止まっていた。すぐに電気屋さんで直しに出し待つこと数週間、時計はまた時を刻み始めた。いろんな時間は過ぎていってしまったけれど、今僕の左腕で生きている。物に執着はさほどない方だが、この時計は無くしたくないものになった。
いつも左腕から僕の心の振り子を揺らして「一歩踏み込んだ優しさを持ちなさい」と、さとすように時をいっしょに歩んでくれている。
姉の左手首に光っていた腕時計。それは、姉が中学校に入学する時に祖母に買ってもらったものだった。腕時計をした姉の姿は誇らしげで、私はそんな姉を尊敬していた。姉とは五つ年が離れていて、私には姉がすごく大人に見えた。だからかもしれない。腕時計をすることが、とても格好良く思えた。中学生なって初めて祖母が買ってくれる腕時計。それで私は腕時計は大人の証なのだと思うようになった。早く大人の仲間入りがしたくて腕時計に憧れるようになったのもその頃だった。中学生になって腕時計をつけている自分はどんな感じだろうと考えると、なんだか変な感じがした。姉みたいに大人っぽく振舞っている自分なんか想像できなかった。
それでも気付けば、あっという間に中学生になっていた。小学校を卒業して、期待と不安が入り混じりながらも、大人への一歩ということをなんとなく意識していた春休み。まだ小学生も卒業しきれていないような気がして、中学生になる自信がもてなかった。新品の腕時計をしていた姉はすごく大人に見えたのに、自分がこの歳になっても全然子どものままだと思った。自信を持てずに、なんだか不安だった私は、あんなに憧れて楽しみにしていた腕時計のことを忘れていた。祖母と買い物に行き、時計屋に連れてこられて初めて思い出した。「もう中学生になるんだものね。自分で好きな腕時計を選びなさい。お前はしっかりしているから、これからも頑張るんだよ。」
祖母からの入学祝の腕時計は、私の一生の宝物になった。この時やっと、自信が持てた。祖母の気持ちがとても嬉しくて、頑張ろうと思った。その腕時計は、今でもその時の大切な気持ちを思い出させてくれる。そして、やっぱり私は腕時計が「大人の証」のような気がしている。いや、私にとっては「大人になれた証」と言った方がいいのかもしれない。
腕時計の針が17時をさしていた。
バスがくるのは時刻表によると17時10分で、俺は今、そのバスをのんびりと待っている。
と…。
道を挟んで反対側に、付き合っているHが見えた。笑いながら隣の友達と何やら話をしている。
(奇遇やなぁ)
そう思い、手を振ってHの名を呼んだ。
Hは俺を捕らえると仰け反るようにして驚き、何かを隣の友人に囁いた。そして、全速力で走り出した。
「何だ?」
Hの異常な行動に違和感を覚えた俺は、
(Hの身に何か起こったんだ!)
と、すぐに追いかけた。
バスが来るまで10分はある。追いかけて事情を聞き、それから戻っても間に合うであろう。
全力で走った。
車道を突っ切り、細路地に入ったところでHの背が見えた。
Hが走り出した瞬間、その友人が別の方向に走り出した事も気になったが、まずはHであろう。
Hは足元がヒールで遅い。数百メートル先で捕まえた。
「何で逃げるんや?」
息を切らしながら聞くと、Hは、
「ごめん!」
そう言って頭を下げ、
「悪いのは私だけん」
そう繰り返した。
時間がなかったので、
「要点を説明しろ」
そう言ったところ、男といたところを俺に見られた、ただの友達だ、悪気はない、Hはしどろもどろにそう言った。
「隣にいた女みたいなやつ…、あれが男か?」
Hは頷いた。そして俺を涙目で見、「ごめん」を繰り返した。
腕時計を見ると、17時10分をさしていた。
バスは大抵が遅れてくるものなので、今から走れば間に合うだろう。家が田舎にあるため、これを逃すと後がない。
頭にはきていたが、
「後で電話する」
そう言ってバス停へ走った。
と…。
その俺の前を悠々とバスが通り過ぎていった。
「くそっ!」
舌打ちをし、振り返ると、Hの姿がなかった。多分、俺の背が見えた瞬間に逃げたのだろう。
「ふ…」
その情けなさに笑うしかなかった。
ふと、違和感を感じ、足元を見た。なんと犬のウンコを踏んでいた。
「ははは…」
更に笑うしかなかった俺は、その夜、野宿する事となった。
私の左腕に光る銀色の時計、セイコーシルバーウェーブ。取り立てて目立ったデザインでもなく、アンティークでもすごく高そうなわけでもない。当時、ブームであったでだろう薄型のデザインで、もう私の腕で20年以上も時を刻んでいる。
この時計は私が初めてアルバイトをして買った物である。高校を卒業する春、大学に入学する前の僅かな時間の中で肉体労働の末に得た品で、その頃、働いた分の対価はすべて物に換えようと思っていたから、勤労1週間の成果が二万二千円の時計だったのだ。
時計は親父と買いに行った事をよく覚えている。東北の田舎町で気がきくお店もなかったので、たった一軒の知合いの時計屋で親父に選んでもらったデザインだった。その頃、私のつけていた時計はお下がりのミッキーマウスだったり、貰い物のダイヤカットだったので、そのシンプルな銀面の表情には驚きを覚えた。これが永遠というものだろうか、半面、じじくさい印象もあったが、動き続ける限りずっと身につけられそうな気はしていた。
20代の頃はどんな時でもこのシルバーウェーブだった。勉強もスポーツも仕事も恋愛も失敗も、そして30代になると舶来品やスポーツウォッチ、手巻きとあらゆる種類を使い分けるようになったが、今でも生活の中心にあるのは親父の選んでくれた時計である。
選んでくれた親父は十数年前、脳梗塞で倒れ、今も寝たきりの生活を送っている。親父には悪いが、いつの間にか親父に選んでもらったこの時計が、このまま父の想い出になっていくような気がしている。親父は何も知らずに眠っている。母にもこの気持ちは伝えていないが、私は家族のために一所懸命、働いてきた親父に何よりも感謝している。時計が止まる気配はない。親父が目を覚ます様子はない。けれどその思いは私の中で永遠に生き続けている。
30年間使い続けていた腕時計が止まってしまった。一度も壊れず休むこともなく、時を刻んできた丈夫な時計。思い出の詰まった愛着のある時計の修理代は、1万5千円であった。
「そんなにお金がかかるなら、もっと安くて新しいデザインのクオーツでも買ったほうがいい」と、妻に言われた。女には宝物の価値はわからない。議論をしても無駄である。
リフトを降りて最初の急斜面でスキーヤーはよく転ぶ。みんなでゲレンデの端に立って、人がこけるのを待つ。急斜面での転び方は半端ではない。斜面に派手に叩きつけられたり、顔面から雪に突っ込んでいく。見ていて痛々しい。転んだ拍子に腕時計が飛ばされる。
上着を着込んでいるので気がつかない。私たちの視線を気にして、サアッと立ち上がり、体についた雪を手で払いのけ、何事もなかったようにその場を素早く滑り去っていく。
こけた場所に目を凝らし、陽に照らされてキラッと輝く物を見つけるのだ。ひかり物を見た瞬間、全員がわれ先に殺到する。先輩・後輩も関係ない。早いもの勝ちである。
せしめた腕時計は後輩や旅館の主人に売りつける。合宿の納会の酒代になる。
しかし、なぜかこの時計だけは今でも手元にある。
そりゃあ、人によって違うだろうけど、毎日何らかの形で、時を告げてくれるモノを身に付けて生活してるんじゃない?
最近は携帯電話だったりするみたいだけど、私はやっぱり腕時計がいいな。
しかもアナログの、短針と長針と秒針と文字盤だけのシンプルなやつ。
腹時計は、私の場合、ずっと鳴りっぱなしだから、うるさくて嫌いだし、だいたい場所を選んでくれないことが一番許せない。どんな状況であっても、いつも間の抜けた音を出して、恥ずかしい思いをさせる。
携帯電話で時間を確認するのも好きじゃない。静かな場所でカシャカシャとせわしなく開けたり閉じたりしている人を見ると、時間に追われているようでかわいそうだ。
デジタルの数字で表される時間は、時が決められたように過ぎて行くようで、冷たい感じがするから、そんな時計を自分から買おうとは思わない。
そして、数字で表される時間を見ても、私はわざわざ頭の中で短針と長針と丸い文字盤に置き換えて考えてしまう。午前11時0分でも59分でも、11時と表されることがピンとこない。
短針が長針を一生懸命に追いかけてこそ、時間を理解できる。
そんな理由もあって、アナログだったら、一秒一秒を大切に使いたくなる。針の一歩一歩が時間を紡ぎ出してくれてる気がする。
私にとって、今では少なくなってきたアナログの腕時計は大切なモノだから、その気持ちは変わらないんじゃないかな。
今から20年ほど前の話です。僕は小学校入学のお祝いに、祖母から時計を買ってもらいました。僕にとっては、生まれて初めての時計でした。僕はうれしくてたまらず、寝るときもつけていました。
それは、人気漫画のキャラクター(パーマン)の絵が描かれていて、とてもかっこよかったです。
僕は大はしゃぎでした。それをつけて、良く友達やら近所の人たちに見せびらかしたものです。
その時計は、今は亡き祖母との、いい思い出となりました。時計を見るたびに、亡き祖母を思い出します。
高校進学が決まり、私は電車通学するようになった。「これからは、腕時計がいるな」父の言葉に私は小躍りした。デパートの時計売り場に、きらきら光る時計がずらっと並んだショーケース。
わたしは、どんな時計にしようかとうきうきした。
数日後、黄土色のカーディガンを着た、顔見知りのおじさんがやってきた。おじさんは、黒いかばんから5種類の時計を出した。「さあ、お前の好きなものを選びなさい」父は、にこにこ笑って言った。この人、時計屋さんだったの? 私は、この中から自分の時計を選ばなくちゃならないんだ。ショーケースが遠ざかった。値札を見ると、どれも5万円以上の高級品だった。高校生にこんな高いものを。私は、手に取った時計を畳の上に置いた。「どれも、品質は確かなものばかりですよ」おじさんは、私が怯んだのに気がついて、自分が作ったように胸を張った。「ずっと使うものだから、好きなものを買いなさい」普段倹約家の父も、おじさんに義理があるのか私をせかした。赤い皮のベルトは、好みじゃない。細い黒皮も好みじゃない。私は、セイコーのロゴが入ったシルバーの腕時計を選んだ。「これは、いい品ですよ」おじさんは、時計をプラスチックのケースに入れた。
数日後、おじさんの店を父に教えられて見に行った。古いしもた屋風の店で、間口は狭かった。ショーウィンドウにも、ぽつんぽつんとしか時計は飾られていなかった。
何年かたって、おじさんは体調を崩し店を閉めた。「こどもに時計を買うっていうのに、あんな高いものばかり持ってきるんだもの。よく今まで店をやってきたよ」父が母に話しているのを聞いた。その時、買ってもらった腕時計は、二十年以上も故障することはなかった。
大工棟梁のやっさんは腕時計を持たない。時計が気になって仕事に熱中できないという。ところが、昼食時間の十二時になると、何で知るのか、仕事をきっかりと中止する。
「俺には生まれつきの腹時計があるからさ」
そう言いながら、愛妻弁当を美味しそうに食べる。
あるとき、やっさんが何かを落としたらしく、木屑や木片の中を埃まみれになりながら探していた。
「腹時計さ」
「腹時計?」
実は、やっさんは腕時計ではなく、懐中時計を持っていたらしいのだ。それを「腹時計」として隠していた。それは、結婚三十年記念品で、奥さんとのペアであった。命の次に大切な腹時計であった。現場では見つからず、落胆して帰宅した。
翌日、やっさんの元気そうな声がした。腹時計は風呂場に忘れていたのを奥さんが見つけたらしい。
その時計をパパが貴方に贈った本当の意味を、気付いたかしら?あの時、なぜパパが貴方にその時計を贈ったか?その時計は、そんなに高いものではないけれど、パパは一目惚れして買った時計なの。アメリカ米軍が使っていたものと、同じタイプのものらしく、太陽で動く、ソーラー時計だった。パパはすごく気に入って、いつもその時計をしていたのは貴方も知っているね?貴方が高校を辞めて、新しい高校でも上手くいかず、悩んでた頃、パパもすごく悩んでいたのよ?それでも、時間は静かに流れていって、どうすることもできずにいたパパは、大事にしていた時計を、貴方にあげたの。パパはね?怒ってなんかいないんだよ?貴方がもう一度、高校入試を決めて、自分と戦う道を選んだことも、貴方の人生だから自分の納得するように、すればいいと思っているはず。ただ、止まってほしくないんだと思うの、時が止められないように、その時計も止まることはまずないでしょう
パパにも貴方にも、そして私にも止められない時間。結果じゃなく、止まらずに前を見てやり続ける意味を、ほんとは伝えたかったんでしょうね?貴方は今は気が付かないかもしれないけれど、何年も動き続けるその時計を見て、その意味を知る日がくるかもしれないね?長い人生だもの、いろんな事がまってるよ。泣きたいくらい悔しいことや、悲しくて涙が出ない時も、あるでしょう。でも、止まらずに歩いていってね?そんなパパの切ない思いがその時計には詰まってる。いっぱい、いっぱい詰まってるんだよ?
男の人の時計って、大きいんだなぁ。と思った。
私の両手でやっと隠れるくらい。
大学生になってすぐの1年間。いつもいつも一緒だった人。
その人が、卒業と同時に遠くの会社に就職することになった。
行くなと言えるほど、私たちの過ごした時間は長くなかった。
一緒に行くには、私の学生の残り時間が長すぎた。
離れてしまうと、だめになる。私たちはだめになる。
そう感じながらも、何もできなかった。
あの人は、ただ大丈夫だよと笑っているばかりで。
飛行機の搭乗口の前に、2人で長いこと座っていた。
ずっと黙ってる私。
乗り遅れないようにと、時計ばかり見るあの人。
時計が憎らしかった。
そろそろだね。と、また時計を見る姿を見て、思わず手がのびた。
その、大きくて確実に時をきざむ腕時計を、両手で隠して
ただただ泣くしかなかった。
あの人の時計の冷たさを今でも覚えている。
そして、二度と会えなくなった今、
私の腕時計は、忘れなさい。忘れなさいと、時をきざみ続けています。
(事前のご同意)
「思い出の時計エッセイ募集」に送っていただいたエッセイの著作権は、セイコーインスツル株式会社に帰属します。
また、みなさまのエッセイと氏名(ペンネームを記載いただいた場合はペンネーム)を、当ホームページ上に掲載させて頂きますことを、
予めご了承ください。

