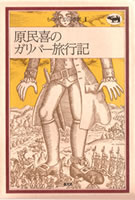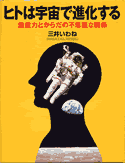(あいうえお順) あ〜さ行 た行〜な行 は行 ま行 や行 ら行
「原民喜のガリバー旅行記」(はらたみきのガリバーりょこうき)
ジョナサン・スウィフト:原作(げんさく)
原民喜:再話(はらたみき:さいわ)
晶文社:出版(しょうぶんしゃ:しゅっぱん)アイルランドの作家(さっか)ジョナサン・スウィフトが1726年に書いた(かいた)「ガリバー旅行記」を小説家(しょうせつか)、原民喜さんが再話(さいわ)というカタチで作品(さくひん)にした、言って(いって)みれば原民喜版(ばん)の「ガリバー旅行記」である。
原民喜さんは1905年11月15日広島市(ひろしまし)生まれ、詩人(しじん)、小説家としていくつかの作品を書いていたが、40歳の時に広島に落とされた原爆(げんばく)によって被爆(ひばく)したんだ。その体験(たいけん)を書き1947年に発表(はっぴょう)された「夏の花(なつのはな)」が注目(ちゅうもく)され、有名(ゆうめい)になったのであるが、わずか4年後の1951年には残念(ざんねん)なことに自ら(みずから)命(いのち)を絶ち(たち)亡くなって(なくなって)しまったのである。この「原民喜のガリバー旅行記」は亡くなる直前(ちょくぜん)に書かれたもので、原さん独自(どくじ)の語り口(かたりくち)によるすばらしい「ガリバー旅行記」になっているのである。翻訳本(ほんやくぼん)だけでもじつに多く(おおく)の「ガリバー旅行記」がこの世(よ)に存在(そんざい)するが、この「原民喜のガリバー旅行記」は、その中でも特に(とくに)優れた(すぐれた)「ガリバー旅行記」であると私は思う(おもう)のである。フム。
さて、ガリバーといえば小人(こびと)の国に行ったエピソードばかり知られて(しられて)いるのだが、じつはこの「小人の国」はガリバーの旅行記(りょこうき)の中では、ほんのさわりの部分(ぶぶん)だけである。ガリバーは計(けい)16年と7ヶ月(かげつ)も旅(たび)をし「小人の国」「巨人(きょじん)の国」「空飛ぶ(そらとぶ)島(しま)」「馬(うま)の国」の4カ所(かしょ)も訪れて(おとずれて)いるのである。そして「空飛ぶ島」からは、なんと日本(にほん)に立ち寄り(たちより)長崎(ながさき)の出島(でじま)からオランダ経由(けいゆ)で母国(ぼこく)イギリスへと帰って(かえって)いるのである。
4つの国を訪れたガリバーが出逢う(であう)様々(さまざま)な人々[最後(さいご)は馬であるが・・・]は、人間のイヤな部分(ぶぶん)を思いきり強調(きょうちょう)したような性格(せいかく)の人種(じんしゅ)もいれば、あるいは人間以上(いじょう)のすばらしい知性(ちせい)と品性(ひんかく)を持った(もった)人種もいて、じつにおもしろいのである。最後(さいご)にガリバーが訪れた「馬の国」では、人間によく似た(にた)恐ろしく(おそろしく)野蛮(やばん)な生き物(いきもの)がいるという設定(せってい)も、じつによくできているのである。
子どもだけではなく、おとなも読んで(よんで)いろいろなことを考え(かんがえ)させてくれる「原民喜のガリバー旅行記」。「小人の国」しか知らない(しらない)人は、是非(ぜひ)この一冊(いっさつ)を手にとり、ガリバーとともに不思議(ふしぎ)な旅(たび)を楽しんで(たのしんで)ほしいものである。
「ヒトは宇宙で進化する〜無重力とからだの不思議な関係〜」
(ヒトはうちゅうでしんかする〜むじゅうりょくとからだのふしぎなかんけい〜)
三井いわね(NASAエイムス研究所):著(みついいわね:ちょ)
ポプラ社:発行(ポプラしゃ:はっこう)みんなの大好き(だいすき)な宇宙(うちゅう)に関する(かんする)本である。著者(ちょしゃ)の三井さんは、子供(こども)の頃からずっと宇宙飛行士(うちゅうひこうし)に憧れて(あこがれて)いて、どうしても宇宙にかかわる仕事(しごと)をしたくて、ついにはNASA(ナサ/米国国家航空宇宙局:べいこくこっかこうくううちゅうきょく)のエイムス研究所(けんきゅうじょ)ライフサイエンス部門(ぶもん)の研究員(けんきゅういん)として招かれ(まねかれ)、現在(げんざい)はそこで、宇宙医学(いがく)の研究をしているという経歴(けいれき)を持つ(もつ)なんともすごい人なのである。
この本の中にある、諸君(しょくん)が「面白そう!(おもしろそう)」と思うような見出し(みだし)を載せて(のせて)みようと思うのである。
「宇宙(うちゅう)は自然(しぜん)の毛はえ薬(けはえぐすり)」
「宇宙に行ったら背(せ)が伸びた(のびた)」
「無重力(むじゅうりょく)のおしっこ飛ばし(とばし)」
「宇宙でおならをしてみたら・・・」
「虫歯(むしば)があると死ぬ(しぬ)ほど痛い(いたい)」どうかな?このタイトルを見ただけでも「読んでみたい!」と思った人は多い(おおい)んじゃないかな?
興味(きょうみ)を持った(もった)人はぜひ図書館(としょかん)などで探して(さがして)読んでみてほしいのである。こうした面白いお話から、未来(みらい)に実現(じつげん)するだろう宇宙ホスピタルの話までこの本には宇宙での可能性(かのうせい)を感じさせるお話がいっぱいつまっているのである。そして最後(さいご)には「宇宙は君を待って(まって)いる!」というコーナーで終わる(おわる)のである。この話の展開(てんかい)が素晴らしく(すばらしく)、読み終わった時には「僕(ぼく)も宇宙に行ってみたい!」と思ってしまうのである。そしてその夢を実現するためには、いろいろな道があり、その夢をずっと思い(おもい)続け(つづけ)、努力(どりょく)をすることで必ず(かならず)実現できるということを教えてくれるのである。そう思える勇気(ゆうき)もまたこの本は与えて(あたえて)くれるのである。
○この本を出版(しゅっぱん)しているポプラ社のホームページは
http://www.poplar.co.jp/
「昼と夜」(ひるとよる)
マリア・ゴードン:作(さく)
マイク・ゴードン:絵(え)
にしもとけいすけ:訳(やく)
ひかりのくに:発行(はっこう)どうして昼(ひる)は明るく(あかるく)、夜(よる)は暗い(くらい)の?
どうして夏(なつ)は昼が長く(ながく)、夜が短い(みじかい)の?
そんな当たり前(あたりまえ)なことでも、なぜそうなのかを、わかりやすく答えて(こたえて)くれる絵本(えほん)です。小さい子どもにも簡単(かんたん)にできる実験(じっけん)やヒントも書いて(かいて)あります。
「ふしぎな花時計〜みぢかな花で時間をしろう〜」
(ふしぎなはなどけい〜みじかなはなでじかんをしろう〜)
十亀好雄:著(とうがめよしお:ちょ)
青木書店:発行(あおきしょてん:はっこう)子供(こども)から、大人(おとな)まで家族(かぞく)で楽しめる(たのしめる)自然観察(しぜんかんさつ)の本(ほん)。日本(にほん)にある24時間(じかん)のうちに花(はな)が開いて(ひらいて)、そしてつぼむ37種類(しゅるい)の一日花(いちにちばな)を調べた(しらべた)「ふしぎな花時計」についてや「花ことば」「花のスケッチのしかた」などについて、わかりやすくかかれていて、しかもためになる一冊(さつ)です。
「WHAT TIME IS IT? 時間」(ホワッツタイムイズイット?じかん)
A・G・スミス:著(エー・ジー・スミス:ちょ)
渡会和子:訳(わたらいかずこ:やく)
ほるぷ出版:発行(ほるぷしゅっぱん:はっこう)地球(ちきゅう)や宇宙(うちゅう)・暦(こよみ)・昔(むかし)の時計(とけい)・今(いま)の時計・生物(せいぶつ)時計など広い(ひろい)範囲(はんい)で、時と時間のことを学べる(まなべる)本です。大きな(おおきな)イラストがたくさんはいっていて、それを見るだけでも楽しい(たのしい)よ。
「ポンコツタイムマシン騒動記」(ポンコツタイムマシンそうどうき)
石川英輔:著(いしかわえいすけ:ちょ)
評論社:発行(ひょうろんしゃ:はっこう)電気(でんき)お化け屋敷(おばけやしき)に出前(でまえ)にいった主人公(しゅじんこう)は、ヘンテコな機械(きかい)の中(なか)にむりやり押し込まれ(おしこまれ)てしまう。
出前に持って(もって)いったチャーシューメンとともに、過去(かこ)に行って(いって)しまった主人公はいったいどうなってしまうのか?
「ぼくだってアインシュタイン」(全4巻)
福江純:文(ふくえじゅん:ぶん)
北原菜里子:絵(きたはらなりこ:え)
岩波書店 :発行(いわなみしょてん:はっこう)
アインシュタインが発見(はっけん)した「相対性理論(そうたいせいりろん)」。
大人(おとな)でもなかなか理解(りかい)するのがむずかしいこの理論に何と2人の小学生がチャレンジするという物語(ものがたり)なのである。主人公(しゅじんこう)は、智(さとる)くんと、星子(せいこ)ちゃんという双子(ふたご)の小学生。2人はまず「なぜ月は落ちて(おちて)こないのか」という素朴(そぼく)な疑問(ぎもん)からスタートし、担任(たんとう)の先生に聞いたり、その先生の大学(だいがく)の先輩(せんぱい)を訪ねて(たずねて)いき、次々(つぎつぎ)とわきおこる疑問をひとつずつ解決し、ついにはアインシュタインの相対性理論を学んで(まなんで)しまうのである。さすがに「相対性理論(そうたいせいりろん)」を学ぼうとすると、その前に発見(はっけん)されたニュートンや、ガリレオのことまで一度はさかのぼって説明(せつめい)しなければならず、4冊セットというボリュームであるが、ひとつひとつの理論を説明するのに、身近(みじか)な疑問から入ってくれるのでとてもわかりやすく、また各ページに書かれている解説(かいせつ)のイラストも楽しくて、ついつい読み進んでしまう実に良くできた本なのである。諸君(しょくん)もぜひ図書館(としょかん)などで探して(さがして)読んでみてほしいのである。
各巻(かくかん)のタイトルと内容(ないよう)
1巻:「月とリンゴの法則(ほうそく)」
ニュートンの万有引力(ばんゆういんりょく)の法則と、ガリレオの相対性原理(そうたいせいげんり)についてのお話2巻:「おくれる時計のふしぎ」
アインシュタインの特殊相対性理論(とくしゅそうたいせいりろん)から起こる時間の不思議(ふしぎ)のお話3巻:「なぞのブラックホール」
一般相対性理論(いっぱんそうたいせいりろん)から発見(はっけん)された宇宙(うちゅう)の不思議(ふしぎ)な空間(くうかん)ブラックホールについてのお話4巻:「アインシュタインのゆめ」
科学(かがく)の歴史(れきし)にとって重要(じゅうよう)な発見(はっけん)をしたアインシュタインが一生(いっしょう)をかけて実現(じつげん)しようとしていた夢(ゆめ)のお話○この本を出版(しゅっぱん)している岩波書店(いわなみしょてん)のホームページは
http://www.iwanami.co.jp/
「まわる地球・自転と公転」(まわるちきゅう・じてんとこうてん)
大脇直明:監修(おおわきなおあき:かんしゅう)
中嶋浩一:著(なかじまこういち:ちょ)
ポプラ社:発行(ポプラしゃ:はっこう)地球(ちきゅう)のまわるスピード・昼(ひる)と夜(よる)・時刻(じこく)や季節(きせつ)など地球の自転(じてん)と公転(こうてん)に関係(かんけい)のある、いろいろな話(はなし)をやさしい文(ぶん)でわかりやすく説明(せつめい)しています。
○この本を出版(しゅっぱん)しているポプラ社のホームページは
http://www.poplar.co.jp/
「マンガ アトム博士の相対性理論」(マンガ アトムはかせのそうたいせいりろん)
手塚治虫:マンガ監修(てづかおさむ:マンガかんしゅう)
大塚明郎:内容監修(おおつかあきお:ないようかんしゅう)
東陽出版:発行(とうようしゅっぱん:はっこう)時間(じかん)、空間(くうかん)は、絶対的(ぜったいてき)なものではなく、見る(みる)人(ひと)の立場(たちば)でかわる相対的(そうたいてき)なものだという理論(りろん)をうちたて、証明(しょうめい)した理論物理学者(りろんぶつりがくしゃ)アルベルト・アインシュタインの相対性理論(そうたいせいりろん)を、世界的(せかいてき)にも有名(ゆうめい)なマンガ家の手塚治虫(てづかおさむ)さんが、マンガでわかりやすく教えて(おしえて)くれる本。主人公(しゅじんこう)の二人の兄妹(きょうだい)とアトム博士といっしょに、時のふしぎをおいかける探検旅行(たんけんりょこう)にでかけよう。
「未来いそっぷ」(みらいいそっぷ)
星新一:著(ほししんいち:ちょ)
新潮社:出版(しんちょうしゃ:しゅっぱん)日本(にほん)のSF界(エスエフかい)を代表(だいひょう)するショートショート[非常(ひじょう)に短い(みじかい)小説(しょうせつ)]の第一人者(だいいちにんしゃ)である星新一(ほししんいち)さんの「未来(みらい)いそっぷ」という本である。
星新一さんは、1926年東京(とうきょう)生まれ(うまれ)、1957年に日本で最初(さいしょ)のSF同人誌(どうじんし)「宇宙塵(うちゅうじん)」を創刊(そうかん)し、その中で発表(はっぴょう)した「セキストラ」という作品(さくひん)が推理小説作家(すいりしょうせつさっか)の重鎮(じゅうちん)、江戸川乱歩(えどがわらんぽ)に注目(ちゅうもく)され、「宝石(ほうせき)」に転載(てんさい)されてデビューすることになったんだ。この「宇宙塵」という同人誌からは、前(まえ)に「タイムマシンのつくりかた」で紹介(しょうかい)した広瀬正(ひろせただし)さんをはじめ日本(にほん)のSF小説界を代表(だいひょう)する数多く(かずおおく)の作家(さっか)が生まれているのである。星さんは1000を越す(こす)作品(さくひん)を残し(のこし)、1997年に71歳(さい)でなくなってしまったけれど、今でもその作品は、子供(こども)から大人(おとな)まで多く(おおく)の人たちに愛され(あいされ)続けて(つづけて)いるのだ。
さてちょっと前置き(まえおき)が長く(ながく)なってしまったけれど、今回(こんかい)の「未来(みらい)いそっぷ」の内容(ないよう)をちらっと紹介(しょうかい)したいと思う(おもう)のである。この文庫本(ぶんこぼん)におさめられているショートショートは39篇(ぺん)。その中に「いそっぷ村の繁栄(はんえい)」というタイトルでくくられた「イソップ物語(ものがたり)」をもとにした7篇の作品(さくひん)があるのだが、諸君(しょくん)がよ〜く知って(しって)いる「アリとキリギリス」「北風(きたかぜ)と太陽(たいよう)」「ウサギとカメ」などのイソップ物語の作品が、星新一さんの手によって、じつにおもしろく、なるほどと思わせるような作品に生まれ(うまれ)変わって(かわって)いるのである。ほんの数(すう)ページの作品だが、そこにある発想(はっそう)のユニークさ、違った(ちがった)角度(かくど)でのものの見方(みかた)は、きっと諸君(しょくん)の頭(あたま)をやわらかくしてくれることと思うのである。手に取れば(とれば)終わり(おわり)まで一気(いっき)に読めて(よめて)しまう本なので、是非(ぜひ)とも読んでほしいのである。また文庫本(ぶんこぼん)のシリーズもたくさん出ているので、気に入った人は、その他(ほか)の作品も読んでみることをオススメするのである。
名犬チロリ〜セラピードッグが「奇跡」を起こす〜
(めいけんチロリ〜セラピードッグがきせきをおこす〜)
大木トオル:著(おおきトオル:ちょ)
マガジンハウス:出版(しゅっぱん)セラピードッグとは人の弱った(よわった)心(こころ)と体(からだ)をいやす犬たちのこと、この本は、1匹(ぴき)のセラピードッグ「チロリ」の実話(じつわ)なのである。この本の作者(さくしゃ)は大木(おおき)トオルさん、日本人(にほんじん)のブルースシンガーとして初めて(はじめて)アメリカの労働省(ろうどうしょう)の認可(きょか)を受けて(うけて)、アメリカで活動(かつどう)し、有名(ゆうめい)なブルースミュージシャンと共演(きょうえん)し、数々(かずかず)のレコードをリリースしたというものすごいミュージシャンなのである。
そんな大木さんは、ニューヨークで暮らして(くらして)いる時に、セラピードッグが、病気(びょうき)になった人たちに生きる(いきる)意欲(いよく)を起こさせ(おこさせ)、また犬に触れる(ふれる)ことで、病状(びょうじょう)が良く(よく)なるといった奇跡(きせき)を見て感動(かんどう)し、自分(じぶん)もセラピードッグを広める(ひろめる)活動を始めることにしたのである。アメリカでの活動を始め(はじめ)、日本にも広めようと思って(おもって)いた時にこの本のタイトルとなっている「名犬チロリ」と出会った(であった)のである。
本の表紙(ひょうし)写真(しゃしん)を見ていただけるとわかると思うのだが、諸君(しょくん)の中には、この片耳(かたみみ)がたれた雑種(ざっしゅ)の犬のどこが名犬(めいけん)なの?と思った(おもって)人もいるのではないかな?そう思った人は、この写真の「チロリ」の目をじっと見て欲しい(ほしい)のである。その目に何とも(なんとも)言えない(いえない)優しい(やさしい)光(ひかり)が宿って(やどって)いるのに気づくはずである。この本の中には、その「チロリ」が実際(じっさい)に起こした(おこした)奇跡的(きせきてき)な出来事(できごと)がいくつも載って(のって)いるのである。「チロリ」はもともとは、捨て犬(すていぬ)で、保健所(ほけんじょ)に保護(ほご)されて、もう少し(すこし)で殺されて(ころされて)しまうところを大木(おおき)さんに救われた(すくわれた)のである。捨て犬になる前も、捨て犬になってからも、人間(にんげん)にひどい扱い(あつかい)を受け(うけ)、いじめられたというのに、「チロリ」はその人間たちに、自分(じぶん)の持って(もって)いるすべての力を使って(つかって)、いやしを与えて(あたえて)いるのである。これだけで、我が輩(わがはい)は涙(なみだ)がでてきてしまうのである。それだけ感動(かんどう)のつまった良い(よい)本である。是非(ぜひ)、諸君(しょくん)も読んで(よんで)ほしいのである。
最後(さいご)に、犬は、人間(にんげん)に比べ(くらべ)約(やく)4倍(ばい)のスピードで、歳(とし)をとっていくのである。長く(ながく)生きても(いきても)20年という短い(みじかい)時間(じかん)の中で、セラピードッグだけでなく、犬たちは、その命(いのち)の限り(かぎり)、人々(ひとびと)にいろいろないやしを与えて(あたえて)くれるのである。犬や他(ほか)の動物(どうぶつ)と過ごす(すごす)ことは、その命と向き合う(むきあう)こと。諸君(しょくん)も同じ(おなじ)一つの命についてしっかりと考え(かんがえ)、ともに楽しく(たのしく)かけがえのない時間(じかん)を過ごして(すごして)ほしいのである。
さて、この「名犬(めいけん)チロリ〜セラピードッグが「奇跡(きせき)」を起こす(おこす)〜」を原作(げんさく)した映画(えいが)「犬と歩けば(あるけば) チロリとタムラ」は現在(げんざい)全国(ぜんこく)の映画館(えいがかん)を巡って(まわって)いる最中(さいちゅう)なので、近く(ちかく)に来たら是非(ぜひ)見てほしいのである。※上映館(じょうえいかん)情報(じょうほう)は
→ 「犬と歩けば」公式(こうしき)ホームページ※セラピードッグについて知りたい(しりたい)人は
→ 国際(こくさい)セラピードッグ協会(きょうかい)
「モノづくり日本 江戸大博覧会(モノづくりにっぽん えどだいはくらんかい)」
国立科学博物館:編集(こくりつかがくはくぶつかん:へんしゅう)
毎日新聞社:発行(まいにちしんぶんしゃ:はっこう)2003年の夏に江戸開府(えどかいふ)400年を記念(きねん)して国立科学博物館(こくりつかがくはくぶつかん)で行われた「特別展(とくべつてん) モノづくり日本(にっぽん) 江戸大博覧会(えどだいはくらんかい)」の際(さい)に出版(しゅっぱん)された同タイトルの本である。
江戸時代(えどじだい)、海外(かいがい)の文化(ぶんか)からまったく閉ざされて(とざされて)いた日本が、明治時代(めいじじだい)になり急激(きゅうげき)な発展(はってん)を遂げた(とげた)理由(りゆう)は、江戸時代の技術者(ぎじゅつしゃ)たちのとんでもない技術力の下地(したぢ)があったからなのである。大名(だいみょう)やお金持ち(おかねもち)の商人(しょうにん)が西洋(せいよう)から手に入れた最先端(さいせんたん)の工業製品(こうぎょうせいひん)を、情報(じょうほう)もなく、部品(ぶひん)もない中で職人(しょくにん)たちが、見よう見まねで幾多(いくた)の試行錯誤(しこうさくご)を繰り返し(くりかえし)つくりあげた数々のモノ。この「モノづくり日本 江戸大博覧会」の中には、それらのモノが写真(しゃしん)と詳しい(くわしい)解説(かいせつ)とともに掲載(けいさい)されているのである。
蒸気機関(じょうききかん)の模型(もけい)、カメラ、和時計(わどけい)、地球儀(ちきゅうぎ)、望遠鏡(ぼうえんきょう)、顕微鏡(けんびきょう)、電信機(でんしんき)などなど、当時(とうじ)の職人たちの技術と知恵(ちえ)の結晶(けっしょう)とも言えるそれらのモノの写真を見ているだけで、彼らの気迫(きはく)とか魂(たましい)が伝わって(つたわって)きそうな気がするのである。
つい最近(さいきん)まで「モノづくり王国(おうこく)」と言われていた日本も、生産(せいさん)コストの問題(もんだい)などで、多くの技術が生産コストの安い(やすい)海外(かいがい)へと流出(りゅうしゅつ)しているという現状(げんじょう)である。もう一度(いちど)「モノづくり王国」となり、技術で世界(せかい)をリードしていくためには、今、このホームページを読んで(よんで)くれている諸君(しょくん)が、頑張らねば(がんばらねば)いけないのである。ちょっと高価(こうか)な本なので気軽(きがる)に買う(かう)というわけにはいかないのだが、図書館(としょかん)などで、ぜひこの本を見つけて読み(よみ)、先人(せんじん)たちの魂に触れて(ふれて)ほしいのである。
「モモ」
ミヒャエル・エンデ:著(ちょ)
大島かおり:訳(おおしまかおり:やく)
ミヒャエル・エンデ:絵(え)
岩波書店:発行(いわなみしょてん:はっこう)この本は、ドイツのミュヒャエル・エンデさんが1973年に発表(はっぴょう)した童話(どうわ)で、日本では1976年に大島かおりさんが訳(やく)し、岩波書店(いわなみしょてん)から出版(しゅっぱん)されたのである。
それからじつに、25年以上(いじょう)も多く(おおく)の人たちに読まれて(よまれて)いるのである。表紙(ひょうし)をはじめ、本の中の絵(え)はすべて、ミヒャエル・エンデさんが書いたもの。
なんとも言えぬすてきな絵なのである。
ある日とつぜん、古い(ふるい)壊れた(こわれた)円形劇場(えんけいげきじょう)にあらわれた不思議(ふしぎ)な少女(しょうじょ)モモ。モモは特殊(とくしゅ)な能力(のうりょく)を持っていて、相手がモモに話を聞いて(きいて)もらうだけで、心(こころ)を開き(ひらき)、その心の中にあるものをひきだしてしまうという力を持って(もって)いるのである。町に住む(すむ)人々はそんなモモにひかれ、話にくるようになるんだ。どんなに争って(あらそって)いた人同士(どうし)でも、モモに話を聞いてもらうだけで、心の中にあるわだかまりは消え(きえ)、また仲良く(なかよく)なってしまうのである。大人(おとな)も子供(こども)も、モモがあらわれたことで、とても幸せ(しあわせ)になったのだ。
ところが、人々から時間をうばう灰色(はいいろ)の男たちが現れた(あらわれた)ことによって、町も世界(せかい)もかわってしまうのだ。人々はゆとりをなくし、少しの時間も惜しんで(おしんで)なにかをしていなければ気がすまないようになってまったのである。けれどそれでも、いっこうに人々の生活(せいかつ)や心にも、ゆとりは生まれないのだ。人々が節約(せつやく)した時間はすべて灰色の男たちのエネルギーとなってしまっていたのである。
モモは、とある事件からこの灰色の男たちのたくらみを知る(しる)こととなり、命(いのち)をねらわれるようになってしまうのだ。そんなモモを救った(すくった)のは、世界のすべての時間を動かしているマイスター・ホラである。
マイスター・ホラの家で、時間とは何か?そして時間の持つ(もつ)意味(いみ)を知ったモモは、以前(いぜん)住んでいた円形劇場に戻る(もどる)のである。
その時、すべての人は灰色の人間たちに支配(しはい)されてしまっていたのだ。
誰一人(だれひとり)として味方(みかた)のいないモモは、マイスター・ホラが使い(つかい)として送った(おくった)未来(みらい)を予知(よち)することのできるカメのカシオペイアとともに、人々からうばわれた時間を取り戻す(とりもどす)ために、灰色の男たちと戦う(たたかう)ことになるのだが・・・。
最近(さいきん)の子供たちは、習い事(ならいごと)や塾(じゅく)で大人以上(いじょう)に忙しい(いそがしい)毎日(まいにち)を送って(おくって)いると聞く。そんな子供たちにぜひとも読んで(よんで)ほしい本なのである。また「あれをしなさい、これをしなさい」と子供にいつも言ってしまうお父さん、お母さんにも読んでほしいと思うのである。
時間というものは、使い方(つかいかた)次第(しだい)で、どんなふうにでも使える可能性(かのうせい)いっぱいのものなのである。ただ生活するだけではなく、空想(くうそう)したり、夢(ゆめ)を見たりする時間も人には必要(ひつよう)なのである。しょくんも「モモ」を読んで「自分らしく生きる時間」というものを考えてみてほしいのである。フム。
○この本を出版(しゅっぱん)している岩波書店(いわなみしょてん)のホームページは
http://www.iwanami.co.jp/
やさしい科学/植物シリーズ「アサガオのすいみんじかん」
(やさしいかがく/しょくぶつシリーズ「あさがおのすいみんじかん」)
貝原純子:著(かいはらすみこ:ちょ)
さ・え・ら書房:発行(さえらしょぼう:はっこう)鉢植え(はちうえ)のアサガオがあれば、だれでもできる実験(じっけん)がたくさんのっています。 アサガオがいつ花を開いて(ひらいて)、いつしぼむのか。植物(しょくぶつ)のもっている時間(じかん)をこの本の実験で調べて(しらべて)みよう。
○この本を出版(しゅっぱん)しているさ・え・ら書房(さらえしょぼう)のホームページは
http://www.saela.co.jp/
やさしい科学/動物シリーズ「蚊もとけいをもっている」
(やさしいかがく/しょくぶつシリーズ「かもとけいをもっている」)
千葉善彦:著(ちあよしひこ:ちょ)
さ・え・ら書房:発行(さえらしょぼう:はっこう)いっけん、時間(じかん)など関係(かんけい)なく生きて(いきて)いるような昆虫(こんちゅう)の蚊(か)も、いろいろと調べて(しらべて)みると、じつはとても規則(きそく)正しい(ただしい)生活(せいかつ)をしていた!蚊はどうして時間をしることができるんだろう。
いったいどこに時計(とけい)をもっているんだろう。○この本を出版(しゅっぱん)しているさ・え・ら書房(さらえしょぼう)のホームページは
http://www.saela.co.jp/
「夕ばえ作戦」(ゆうばえさくせん)
光瀬龍:著(こうせりゅう:ちょ)
角川文庫:発行(かどかわぶんこ:はっこう)
ふとしたことで、手(て)にいれたタイムマシーンで、中学生(ちゅうがくせい)の3人ぐみが過去(かこ)の世界(せかい)へ行って(いって)まきおこすドタバタSF(エスエフ)ストーリー。
今(いま)から26年前(まえ)にNHK(エヌエチケイ)でドラマ化(か)され大評判(だいひょうばん)となった。
「雪のひとひら」(ゆきのひとひら)
ポール・ギャリコ:著(ちょ)
矢川澄子:訳(やがわすみこ:やく)
新潮文庫:発行(しんちょうぶんこ:はっこう)このタイトルを聞いて(きいて)「おや?」っと思った(おもった)人がいるんじゃないかな?ふつうは「ひとひらの」と言う(いう)場合(ばあい)は「ひとひらの雪」となるのであるが、この本のタイトルは「雪のひとひら」と逆(ぎゃく)になっているのでなんとなくヘンな感じ(かんじ)がするのである。原題(げんだい)は「Snowflake[スノーフレイク:雪片(ゆきへん)]」、それを「雪のひとひら」と訳して(やくして)いるのである。そして、この「雪のひとひら」はこの物語(ものがたり)の主人公(しゅじんこう)でもあるのだ。
この物語(ものがたり)は、ある寒い(さむい)冬(ふゆ)の日に、空(そら)の上で生まれた(うまれた)雪(ゆき)のひとひらが、地上(ちじょう)に降り(おり)、春(はる)の雪解け(ゆきどけ)と共に(ともに)水になり、川(かわ)を流れ(ながれ)、海(うみ)にたどり着き(つき)、最後(さいご)はまた水蒸気(すいじょうき)となって空(そら)に帰って(かえって)いくという雪の一生(いっしょう)を描いた(えがいた)ものである。その雪の一生を人の一生と重ね合わせ(かさねあわせて)て著者(ちょしゃ)のポール・ギャリコは描いている。人と同じ(おなじ)ように、雪のひとひらは雨(あめ)のしずくという男性(だんせい)と結婚(けっこん)をし、4人の子供(こども)をつくるのである。そして人と同じような喜び(よろこび)や悲しみ(かなしみ)も感じる(かんじる)のである。よく時間(じかん)は川の流れ(ながれ)のようにたとえられるが、雪のひとひらは解ける(とけて)水となり、川の流れのままに人生(じんせい)を過ごして(すごして)いくのである。流れに逆らう(さからう)ことなく、うれしいことも、悲しいことも、どんな運命(うんめい)も受け止めて(うけとめて)行くのである。ひらがなが多く(おおく)、語り(かたり)かけるような優しい(やさしい)文章(ぶんしょう)で、しかも難しい(むずかしい)漢字(かんじ)にはふりがながついているので諸君(しょくん)もきっと読める(よめる)と思う。本屋(ほんや)さんで見つけて、是非(ぜひ)読んで欲しい(ほしい)1冊なのである。
「床下の古い時計」(ゆかしたのふるいとけい)
K・ピアソン:著(ケー・ピアソン:ちょ)
足沢良子:訳(あしさわりょうこ:やく)
金の星社:発行(きんのほししゃ:はっこう)12才(さい)の少女(しゅうじょ)パトリシアは、おばさんの家族(かぞく)とひと夏(なつ)を過ごす(すごす)ことになった湖(みずうみ)のコテージで、床下(ゆかした)にかくされていた、古い(ふるい)懐中時計(かいちゅうどけい)を見つけ(みつけ)ました。時計のネジを巻く(まく)とパトリシアは、35年前(35ねんまえ)のお母さんが12才だった過去(かこ)の世界(せかい)にいる自分(じぶん)を発見(はっけん)しました。・・・・古い金(きん)の懐中時計を軸(じく)にして、過去と現在(げんざい)、そこに潜む(ひそむ)母(はは)と娘(むすめ)の問題(もんだい)や、人間関係(にんげんかんけい)をえがいた物語(ものがたり)です。
「夢ってなんだろう」(ゆめってなんだろう)
村瀬学:文(むらせまなぶ:ぶん)
杉浦範茂:絵(すぎうらのりしげ:え)
福音舘書店:発行(ふくいんかんしょてん:はっこう)人間(にんげん)が寝て(ねて)いる時(とき)だけに見る(みる)ことができる夢(ゆめ)の世界(せかい)。そこでは時間(じかん)も距離(きょり)も科学(かがく)の法則(ほうそく)もメチャクチャになり、現実(げんじつ)では起こり(おこり)えないようなことが、つぎつぎと起こってしまう。
こんなふしぎな夢について小学生(しょうがくせい)向け(むけ)にやさしくお話(はなし)してくれる絵本(えほん)です。
みんなが大好きな(だいすき)タイムマシンの本も紹介(しょうかい)するよ。○この本を出版(しゅっぱん)している福音館書店のホームページは
http://www.fukuinkan.co.jp/
「夜は、なぜあるの?宇宙って、なんだ」(よるは、なぜあるの?うちゅうって、なんだ)
佐治晴夫:文(さじはるお:ぶん)
成瀬政博:絵(なるせまさひろ:え)
日本書籍:発行(にほんしょせき:はっこう)「なぜ夜(よる)が、やってくるのか?」という、子供(こども)ならば誰(だれ)でも一度(いちど)は考える(かんがえる)素朴(そぼく)な疑問(ぎもん)からはじまって、地球(ちきゅう)と太陽(たいよう)の関係(かんけい)、そして宇宙(うちゅう)のふしぎについて、ふたりの子供とおじさんがお話(はなし)をしていくかたちで進んで(すすんで)いく絵本(えほん)です。
「リサと柱時計の魔法」(リサとはしらどけいのまほう)
R・コーディル:著(アール・コーディル:ちょ)
谷口由美子:訳(たにぐちゆみこ:やく)
本庄ひさ子:絵(ほんじょうひさこ:え)
文研出版:発行(ぶんかしゅっぱん:はっこう)孤児院(こじいん)の子供(こども)リサが、1週間(1しゅうかん)、ある家にお泊まり(とまり)することになった。いつも忙し(いそがし)そうな夫人(ふじん)と「ふん、時計(とけい)なんか!」という気持ち(きもち)に余裕(よゆう)のあるおばあちゃんと一緒(いっしょ)にすごすお話。
時間におわれて生きている現代(げんだい)の人たちにとって、生きていく上でどちらがしあわせなのかと考え(かんがえ)させられる本です。
「歴史の陰に時計あり」(れきしのかげにとけいあり)
織田一朗:著(おだいちろう:ちょ)
グリーンアロー社:発行(グリーンアローしゃ:はっこう)歴史(れきし)のさまざまな場面(ばめん)に登場(とうじょう)した時計(とけい)の話(はなし)がぎっしりつまった一冊(さつ)です。日本(にほん)で最初(さいしょ)に時を刻み(きざみ)はじめた時計。はじめてのエベレスト登山(とざん)で注目(ちゅうもく)をあびた防水時計(ぼうすいどけい)など、時計を切り口(きりくち)に歴史を見て(みて)みよう。
「笑うな」(わらうな)
筒井康隆:著(つついやすたか:ちょ)
新潮社:出版(しんちょうしゃ:しゅっぱん)
日本(にほん)を代表(だいひょう)するSF作家(エスエフさっか)の筒井康隆(つついやすたか)さんのショート・ショートを収録(しゅうろく)した本である。筒井康隆さんと言えば最近(さいきん)では「富豪刑事(ふごうデカ)」がテレビドラマ化(か)され、ご自身(じしん)もそのドラマに出演(しゅつえん)されていたので、見た人も多い(おおい)んじゃないかな?
さてこの「笑うな」には多くのショート・ショートが収録されているのであるが、この本のタイトルにもなっている「笑うな」はタイムマシンをテーマにしたショート・ショートである。タイムマシンもののSFショート・ショートは、星新一(ほししんいち)さんの作品(さくひん)を始め(はじめ)、じつに多くの作品が書かれ、多くの傑作(けっさく)が生まれて(うまれて)いるのである。
この「笑うな」も当然(とうぜん)傑作(けっさく)の一つである。物語(ものがたり)は、特許(とっきょ)は持って(もって)いるものの、単なる(たんなる)一人の技術者(ぎじゅつしゃ)である男がある日突然(とつぜん)、タイムマシンを発明(はつめい)してしまう。あまりにもバカバカし過ぎて(すぎて)、信じられない(しんじられない)ような発明(はつめい)をしてしまった彼は、仲(なか)のいい友人(ゆうじん)にその事実(じじつ)を告げよう(つげよう)とするのだが、どうも恥ずかしい(はずかしい)やら、笑われそう(わらわれそう)な気がしてためらってしまうのだ。とりあえず友人を自分(じぶん)の家へ呼び(よび)、タイムマシンを発明したことを告げるのだが、案の定(あんのじょう)、友人は笑いだしてしまうのだ。それにつられて、男も笑い、そのうちに笑いが止まらなく(とまらなく)なってしまうのだ。
さて、そんな二人は、笑いをこらえつつタイムマシンに乗り(のり)、ある場所(ばしょ)へ向かう(むかう)のだが、それはいったいどこなのか・・・・。ページにして、わずか9ページの作品だが「笑うな」と言われても、おもわず読んでいるこちらも笑いだしてしまうという、なんともすごい作品なのである。その他(ほか)にも筒井康隆(つついやすたか)さんのドタバタセンスが溢れる(あふれる)作品(さくひん)がいっぱい入った「笑うな」文庫本(ぶんこぼん)でカンタンに手に入るので、ぜひ買って(かって)読んで(よんで)ほしいのである。頭(あたま)が柔らかく(やわらかく)なること請け合い(うけあい)のおもしろさである。