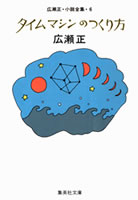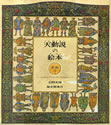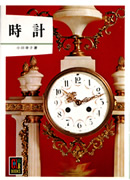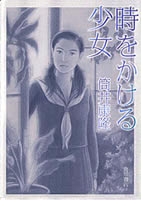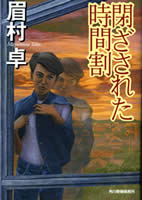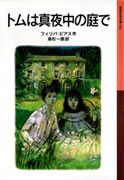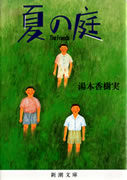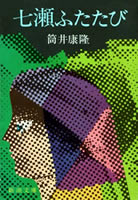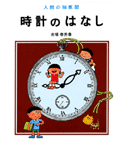(あいうえお順) あ行〜さ行 た行 な行 は行〜ら行
「ダイノザウルス作戦」(ダイノザウルスさくせん)
豊田有恒:著(とよたありつね:ちょ)
徳間文庫:発行(とくまぶんこ:はっこう)人類(じんるい)とは別(べつ)の進化(しんか)をとげた、もう1つの有袋類(ゆうたいるい/カンガルーなどおなかに子そだてのためのふくろをもつどうぶつ)の人類がいた。
お互い( おたがい)の歴史(れきし)を守る(まもる)ため恐竜(きょうりゅう)のいた時代(じだい)を舞台(ぶたい)に、タイムパトロール同士(どうし)のたたかいをえがいた物語り(ものがたり)。
わくわくドキドキのストーリー展開(てんかい)です。
「タイム・パトロール」
ポール・アンダースン:著(ちょ)
大西憲:訳(おおにしけん:やく)
ハヤカワ文庫:発行(はやかわぶんこ:はっこう)ついに開発(かいはつ)された時間航行法(じかんこうこうほう)によって、人類(じんるい)は、すばらしい発展(はってん)をとげた。しかしその一方(いっぽう)で、過去(かこ)にもどって、本来(ほんらい)の歴史(れきし)をかえることで未来(みらい)を違った(ちがった)方向(ほうこう)へかえてしまおうという時間犯罪(じかんはんざい)をうみだすこととなった。
そのために作られた(つくられた)歴史の正しい(ただしい)流れ(ながれ)を監視(かんし)し、守る(まもる)タイムパトロールたちの活躍(かつやく)をえがいた物語り(ものがたり)。
「タイムマシン」
「タイムマシン〜ウェルズSF傑作集1〜」
(タイムマシン〜ウェルズエスエフけっさくしゅう1〜)H・G・ウェルズ:著(エイチ・ジー・ウェルズ:ちょ)
阿部知二:訳(あべともじ:やく)
東京創元社:出版(とうきょうそうげんしゃ:しゅっぱん)「時計と人(とけいとひと)」でとりあげたH・G・ウェルズ(エイチ・ジー・ウェルズ)の「タイムマシン」である。この世(よ)にタイムマシンという空想(くうそう)の乗り物(のりもの)が生まれた(うまれた)記念(きねん)すべき最初(さいしょ)の作品(さくひん)である。物語(ものがたり)は、タイムマシンをつくり西暦(せいれき)802,701年という未来(みらい)の世界(せかい)へ行った(いった)タイムトラベラーの話なのである。西暦802,701年というとみんなはどんな世界を想像(そうぞう)するかな?
この物語(ものがたり)の中で、タイムトラベラーはなんと人類(じんるい)が、地上人(ちじょうじん)と地底人(ちていじん)にわかれた世界(せかい)だったと語って(かたって)いるんだ。彼は、その世界で身(み)も凍る(こおる)ような恐怖(きょうふ)を体験(たいけん)するのだ。命(いのち)からがら、再び(ふたたび)タイムマシンに乗り込み(のりこみ)、さらに未来(みらい)に向かった(むかった)彼は、地球の終わり(おわり)をついに目にすることになる。簡単(かんたん)に言ってしまえば、このようなストーリーなのだが、タイムトラベラーが未来の世界で体験する出来事(できごと)のひとつひとつが、まるで本当(ほんとう)にその世界に行ったかのような細かな(こまかな)描写(びょうしゃ)で書かれて(かかれて)いて、この本が1895年に出版(しゅっぱん)された時に大評判(だいひょうばん)となったのが、わかるような気がするのである。今では、タイムマシンのSF小説(エスエフしょうせつ)はたくさんあるが、当時(とうじ)としては、とんでもなく衝撃的(しょうげきてき)な作品(さくひん)だったはずなのである。この物語の中に登場(とうじょう)するタイムマシンは、人が座席(ざせき)にまたがって乗る(のる)バイクのようなの形(かたち)をしているようだ。タイムマシンはニッケルや真鍮(しんちゅう)象牙(ぞうげ)やなにかの結晶(けっしょう)のかたまりを削って(けずって)できていると書いてある。残念(ざんねん)ながら、どんな原理(げんり)で動く(うごく)のかは詳しく(くわしく)は書かれていないのである。「時計と人(とけいとひと)」には、最初(さいしょ)に映画化(えいがか)された時のタイムマシンのイラストが載って(のって)いるので見てほしいのである。
また、この傑作集(けっさくしゅう)の中には、「塀(へい)についたドア」「奇跡(きせき)をおこせる男」「ダイヤモンド製造家(せいぞうか)」「イーピヨルニスの島(しま)」「水晶(すいしょう)の卵(たまご)」の5つの短編(たんぺん)が収められて(おさめられて)いる。どれもが今のSF小説(エスエフしょうせつ)のお手本(てほん)とも言えるようなとてもおもしろい作品(さくひん)なので、是非(ぜひ)読んで(よんで)みてほしいのである。
「タイムマシン」
H・G・ウエルズ:著(エイチ・ジー・ウエルズ:ちょ)
眉村卓:訳(まゆむらたく:やく)
講談社 :発行(こうだんしゃ:はっこう)1895年に発表(はっぴょう)されたイギリスの小説家(しょうせつか)ハーバード・ジョージ・ウェルズの作品(さくひん)。タイムマシンという言葉(ことば)は、この小説(しょうせつ)で、はじめて使われた(つかわれた)んだ。
時間(じかん)の中(なか)を人はどうして、自由(じゆう)に動き(うごき)まわれないのだろう、というなぞをといた主人公(しゅじんこう)の発明家(はつめいか)が、スクーターのようなタイムマシンに乗り(のり)、80万年後(80まんねんご)の世界(せかい)をのぞいて、地球(ちきゅう)の終わり(おわり)をみてしまうというお話(はなし)だ。タイムマシンのことを知りたい(しりたい)なら、まずこの本から読んで(よんで)みよう。○この本を出版(しゅっぱん)している講談社のホームページは
http://www.kodansha.co.jp/
「タイムマシンのつくり方」広瀬正・小説全集・6
(タイムマシンのつくりかた・ひろせただし・しょうせつぜんしゅう・6
「タイムマシンのつくり方」
広瀬正:著(ひろせただし:ちょ)
集英社:出版(しゅうえいしゃ:しゅっぱん)広瀬正さんは、37歳(さい)という遅い(おそい)作家(さっか)デビュー後(ご)、10年近く(ちかく)世間(せけん)にほとんど認められる(みとめられる)ことがなかったが、1970年に初めて(はじめて)の長編SF小説(ちょうへんエスエフしょうせつ)「マイナス・ゼロ」でようやく認められ、その後3回も連続(れんぞく)で直木賞(なおきしょう)にノミネートされるなど、人気(にんき)作家の道(みち)を歩み始めた(あゆみはじめた)のである。しかし、1972年に突然(とつぜん)の心臓発作(しんぞうほっさ)でこの世を去って(さって)しまったという何とも不運(ふうん)な作家なのである。今回の「タイムマシンのつくり方」はその広瀬正さんの書いた小説を文庫(ぶんこ)にまとめた6冊(さつ)シリーズの中の1冊である。
広瀬正(ひろせただし)さんは「時に憑かれた作家(ときにつかれたさっか)」という異名(いみょう)があるぐらいにタイムマシンもののSF小説(エスエフしょうせつ)を書き続けた(かきつづけた)作家なのである。この「タイムマシンのつくり方」には、タイトル通り(とおり)、そんな広瀬正さんが書いた(かいた)タイムマシンものの短編小説(たんぺんしょうせつ)とショートショートがぎっしりと詰まって(つまって)いるのである。
とくにいちばん最初(さいしょ)に収録(しゅうろく)されている「ザ・タイムマシン」には、タイムマシンという乗り物(のりもの)が持つ(もつ)様々(さまざま)な疑問点(ぎもんてん)、矛盾点(むじゅんてん)が一人のタイムマシンを発明(はつめい)した博士(はかせ)の講演(こうぎ)という形(かたち)で書かれて(かかれて)いるのである。これを読んだ(よんだ)だけで、相当(そうとう)なタイムマシン通(つう)になれること間違い(まちがい)なしである。この後(あと)「Once Upon A Time Machine(ワンス・アポン・ア・タイムマシン)」「化石の街(かせきのまち)」「計画(けいかく)」・・・とタイムマシン、時間(じかん)をテーマにした作品(さくひん)が次々(つぎつぎ)と出てきて、思わず(おもわず)夢中(むちゅう)になって読み(よみ)進んで(すすんで)しまうといったすばらしい1冊(さつ)である。こんな作品を今から30年以上(いじょう)も前に書いていたとは、本当(ほんとう)に驚き(おどろき)である。もし亡くなる(なくなる)ことなく作品を書き続けていたら、どんなに私たちを楽しませて(たのしませて)くれただろうと思うと、残念(ざんねん)でしかたないのである。
タイムマシンは本当にできるの?(タイムマシンはほんとうにできるの?)
〜ふしぎ調査隊 研究レポート(ふしぎちょうさたい けんきゅうレポート)
岡島康治:著(おかじまこうじ:ちょ)
PHP研究所:発行(ピーエイチピーけんきゅうしょ:はっこう)サブタイトルに[〜ふしぎ調査隊 研究レポート(ふしぎちょうさたい けんきゅうレポート)〜]とついているのは、この本が、隊長(たいちょう)、TT(ティーティー)まり隊員(たいいん)、ももや隊員という3人からなるふしぎ調査隊の物語(ものがたり)として書かれているからである。
時間(じかん)とはどんなものから始まって(はじまって)、時間の流れ(ながれ)をとびこえるタイムマシンはつくることができるのかというところまで、隊長と隊員たちがひとつひとつの疑問(ぎもん)を解決(かいけつ)していくという形で書かれているのでとてもわかりやすく読み(よみ)やすい本なのである。さて気になる調査の結果(けっか)は?というと「タイムマシンをつくることはできない」なのだ。けれどこの本では、例えば(たとえば)タイムマシンを使って(つかって)、未来(みらい)のことを知り、そのことによって現代(げんだい)に戻って(もどって)きてお金もうけをしたり、楽(らく)をしたりということで人は幸せ(しあわせ)になるわけではなく、人は考え方(かんがえかた)、生き方(いきかた)で、同じ80年という限られた(かぎられた)時間の中であっても、200年も300年も生きたような充実(じゅうじつ)した幸せな一生(いっしょう)を送る(おくる)ことができると言うのである。じつはこの本、タイトルこそ「タイムマシン」なのだが、内容(ないよう)は時間の大切(たいせつ)さや、毎日(まいにち)を充実して生きることの意味(いみ)を時(とき)や時間の知識(ちしき)とともに教えて(おしえて)くれる本なのである。
諸君(しょくん)も、是非(ぜひ)この本を読んで、発見(はっけん)や驚き(おどろき)がいっぱいの1日を過ごして(すごして)ほしいものである。さらにこの[〜ふしぎ調査隊 研究レポート〜]のシリーズには「おばけは本当にいるの?」という本もあるので、こちらも是非読んでほしいのである。
「太陽系のおいたち」(たいようけいのおいたち)
小森長生:著(こもりながお:ちょ)
岩崎書店:発行(いわさきしょてん:はっこう)私たちの地球(ちきゅう)のある原始太陽系(げんしたいようけい)の誕生(たんじょう)から、太陽系にある星(ほし)のこと、太陽系の未来(みらい)などをきれいな写真(しゃしん)でわかりやすく説明(せつめい)している本です。
「ダック・コール」
稲見一良:著 (いなみいつら:ちょ)
早川書房:出版(はやかわしょぼう:しゅっぱん)一般的(いっぱんてき)なジャンルわけではハードボイルドと呼ばれる(よばれる)ジャンルに入るのであるが、物語(ものがたり)の中にあふれているのは、冷たさ(つめたさ)とか残酷さ(ざんこくさ)ではなく、少年(しょうねん)のような優しい(やさしい)気持ち(きもち)と、自然(しぜん)を愛する(あいする)心である。稲見一良(いなみいつら)さんは、1931年生まれ、記録映画(きろくえいが)のプロデューサーを経て(へて)1989年に作家(さっか)デビュー、1994年に病気(びょうき)でなくなるまでの6年間に、この「ダック・コール」をはじめ、自然や狩猟(しゅりょう)をテーマとしたすばらしい作品(さくひん)をいくつも書き上げたのである。
さて、「ダック・コール」は6篇(ぺん)の短篇小説(たんぺんしょうせつ)が収められて(おさめられて)いるのだが、一環(いっかん)したテーマは「鳥」である。「鳥」を巡る(めぐる)さまざまな人々の物語が、緻密(ちみつ)な観察眼(かんさつがん)によって描かれて(えがかれて)いるのである。その中でも特に諸君(しょくん)に読んで欲しいのが「密猟志願(みつりょうしがん)」という作品(さくひん)である。ガンの手術(しゅじゅつ)を終えた中年男性(ちゅうねんだんせい)と、パチンコや投げ縄(やりなわ)を使う狩猟の名人(めいじん)の少年との心温まる(こころあたたまる)冒険物語(ぼうけんものがたり)である。ふとしたきっかけで出会った二人は、野鳥(やちょう)を自分(じぶん)たちのつくった道具(どうぐ)で捕まえる(つかまえる)「密猟(みつりょう)」を通して(とおして)心をかよわせていくのである。そして、狩猟技術(しゅりょうぎじゅつ)を極めた(きわめた)二人は、近所(きんじょ)でも有名(ゆうめい)な意地(いじ)の悪い(わるい)大金持ち(おおがねもち)が敷地(しきち)で飼って(かって)いる百羽(ひゃっぱ)ちかい鴨(かも)をごっそり盗む(ぬすむ)計画(けいかく)を立てるのである。猟銃(りょうじゅう)を持った(もった)警備員(けいびいん)がいて、要塞(ようさい)のような敷地に、ゴムボードと知恵(ちえ)を絞った(しぼった)わずかな道具(どうぐ)とともに侵入(しんにゅう)し、目的(もくてき)を遂げよう(とげよう)とする二人の描写(びょうが)が、じつにドキドキ、ワクワクと胸(むね)が高鳴る(たかなる)すばらしいものなのである。誰も(だれも)が経験(けいけん)のあるイタズラをする時に感じる(かんじる)ドキドキ感に近いものではないかのう?
人は、誰かの生きている時間(じかん)と重なる(かさなる)ことで、2倍も3倍も楽しい時間を過ごす(すごす)ことができるのである。一度(いちど)は死を覚悟(かくご)し手術(しゅじゅつ)にのぞんだ中年男性(ちゅうねんだんせい)の衰え(おとろえ)に向かっていった時間が、この少年(しょうねん)との出会い(であい)によって再び(ふたたび)、燃えさかる(もえさかる)生命(せいめい)を得て(えて)逆流(ぎゃくりゅう)し始める(しはじめる)。いつしか男性は少年に戻って(もどって)いくのである。このすばらしい物語(ものがたり)をぜひ、諸君(しょくん)も読んで(よんで)ほしいと思う(おもう)のである。
最後(さいご)に、人は一生(しっしょう)のうちに何冊(なんさつ)かの、忘れられない(わすれられない)本に出会う(であう)と思って(おもって)おる。我が輩(わがはい)エルモッチにとっては、この「ダック・コール」がその一冊にあたるのである。諸君(しょくん)もたくさんの本に触れ(ふれ)、そんな本を探し出して(さがしだして)ほしいと常々(つねづね)思っているのである。読書(どくしょ)は、居ながら(いながら)にして諸君の視野(しや)を広げて(ひろげて)くれるすばらしいものである。パソコンも良い(よい)が、たまには本を手に取り(とり)、じっくりと本に向かう(むかう)のもいいのではないかな?
「タンポポ土手のタイムトンネル」(タンポポどてのタイムトンネル)
村野夏生:著(むらのなつき:ちょ)
むかいながまさ:絵(むかいながまさ:え)
新学社:発行(しんがくしゃ:はっこう)SF(エスエフ)好き(ずき)のトシオはある日、タイムトンネルにひきこまれる。
トンネルの向こう(むこう)に広がる(ひろがる)世界(せかい)は江戸時代(えどじだい)。
事件(じけん)のなぞをさぐる。
○この本を出版(しゅっぱん)している新学社のホームページは
http://www.sing.co.jp/
「テクニカラー・タイムマシン」
ハリイ・ハリスン:著(ちょ)
ハヤカワ文庫SF:発行(ハヤカワぶんこエスエフ:はっこう)つぶれかけた映画会社(えいががいしゃ)がタイムマシンを使って(つかって)、現代(げんだい)の映画のロケ隊(たい)を11世紀(11せいき)に送り込み(おくりこみ)、本物(ほんもの)のバイキング[海賊(かいぞく)]を使って、史上空前(しじょうくうぜん)のバイキング映画を撮る(とる)という壮大な計画(けいかく)をたて実行(じっこう)したもののハプニングが続出(ぞくしゅつ)、さてどうなってしまうのか?
冒険(ぼうけん)と笑い(わらい)のユーモアSF小説(しょうせつ)です。
「天動説の絵本」(てんどうせつのえほん)
安野光雄:著(あんのみつお:ちょ)
福音館書店:発行(ふくいんかんしょてん:はっこう)
今の人たちなら誰(だれ)でも「地球(ちきゅう)は丸く(まるく)て、1日に1回転(かいてん)して、太陽(たいよう)のまわりを1年かけて回って(まわって)いる」ということを知っていると思う。
この考え方を「地動説(ちどうせつ)」と言って、1543年にコペルニクスが言いだしたしたものなのである。じつは、コペルニクスが「地動説」を言う前は、「天動説(てんどうせつ)」と言って、太陽をはもちろん全て(すべて)の星は地球のまわりを回っているという考え方が当たり前だのである。今の人からしてみると不思議(ふしぎ)でしょうがないことではあるのだが。
「天動説の絵本〜てんがうごいていたころのはなし〜」には、人々がまだ「天動説」を信じて(しんじて)いた頃の時代(じだい)のお話がとても素敵(すてき)な絵といっしょに書かれておる。その頃の人々が、神様(かみさま)のことをどんなふうに思っていたのか、海の向こう側はどうなっていると思っていたのか、天国(てんごく)のこと、地獄(じごく)のこと、魔法使い(まほうつかい)のことなども含めてである。その時代の人々の心を支配(しはい)していたのは、ほとんどが迷信(めいしん)とか、魔術(まじゅつ)といった非科学的(ひかがくてき)なものだったことがよくわかるのである。
そんな時代の人たちの心の暗闇(くらやみ)を晴らそう(はらそう)とした「地動説」を言いはじめたコペルニクス。「地動説」を多くの人に広めようとして死刑(しけい)になったブルーノ。宗教裁判(しゅうきょうさいばん)にかけられたガリレオたちは、絵本の最後の方に「北の学者(がくしゃ)」とか「かわりもののお坊(ぼう)さん」という呼び方で出てくるのである。結局(けっきょく)、その時代には彼らの思いは果たす(はたす)ことができず、無念(むねん)のうちに死んでいったのだが・・・。
この絵本を書かれた安野さんは、解説(かいせつ)とあとがきで、こんなふうに言っておるのだ。
「ブルーノやガリレオの受けた苦痛(くつう)などを考えると、なんの感動(かんどう)もなしに『地球は丸くて動く』などと軽々(かるがる)しく言ってもらっては困るのです。もう地球儀(ちきゅうぎ)というものを見、地球が丸いことを前もって知ってしまった子どもたちに、いま一度地動説の驚き(おどろき)と悲しみ(かなしみ)を感じてもらいたいと願って書いた(かいた)ものです。」
今の人たちが、当たり前に思っている知識(ちしき)は、多くの先人(せんじん)たちの長く、そして苦しい道のりがあったからこそだということを、われわれは忘れてはいけないのである。フム。
○この本を出版(しゅっぱん)している福音館書店のホームページは
http://www.fukuinkan.co.jp/
「遠い海から来たクー」(とおいうみからきたクー)
著者:景山民夫(ちょしゃ:かげやまたみお)
出版:角川書店(しゅっぱん:かどかわしょてん)この作品(さくひん)は、第(だい)99回(かい)直木賞(なおきしょう)を受賞(じゅしょう)した作品で、アニメ映画(えいが)にもなったので知って(しって)いる人も多い(おおい)のではないかな?
作者(さくしゃ)の景山(かげやま)さんはもともとテレビの放送作家(ほうそうさっか)をしていた人で、ビートたけしさんの番組(ばんぐみ)を始め(はじめ)、じつに多くのお笑い(おわらい)、バラエティ番組を手がけていたのである。その後(ご)、エッセイ、小説(しょうせつ)を書き(かき)はじめ、デビューからわずか数年(すうねん)でこの「遠い海から来たクー」で直木賞を受賞。誰も(だれも)が認める(みとめる)売れっ子(うれっこ)作家となり、数々(かずかず)の作品を残した(のこした)のである。非常(ひじょう)に才能(さいのう)ある人であったのだが、1998年1月27日に不慮(ふりょ)の事故(じこ)で亡くなって(なくなって)しまったのである。
景山さんの作品の特徴(とくちょう)として、胸(むね)がわくわくと踊る(おどる)ような冒険小説(ぼうけんしょうせつ)が多い(おおい)のであるが、この「遠い海から来たクー」も景山さんらしい冒険小説の一つなのである。さて、みんなのうちにはイヌやネコとかペットがいるかな?ペットは、大好き(だいすき)な友だちや家族(かぞく)と同じ(おなじ)ような存在(そんざい)だと思う(おもう)のである。もし、その友だちが、恐竜(きょうりゅう)だったらどうするかな?恐竜好きの人ならもう夢(ゆめ)のような話(はなし)ではないかな?この「遠い海から来たクー」は、6500万年前(まんねんまえ)に地球上(ちきゅうじょう)にいたプレシオザウルスの子どもが、ある男の子の友だちになってしまったというお話なのである。
主人公(しゅじんこう)の徹郎(てつろう)は、海洋学者(かいようがくしゃ)の父親(ちちおや)と一緒(いっしょ)に、ほとんど人間(にんげん)の住んで(すんで)いない南(みなみ)の孤島(こじま)で、偶然(ぐうぜん)出会った(であった)プレシオザウルスの子ども「クー」とともに夢(ゆめ)のような楽しい(たのしい)日々(ひび)をおくっていたのである。ところが、その「クー」を狙って(ねらって)、とんでもない連中(れんちゅう)がやってきて、平和(へいわ)な島(しま)の暮らし(くらし)をめちゃくちゃにしてしまうのである。相手(あいて)は、サブマシンガンを始め(はじめ)暗視(あんし)スコープなど最新(さいしん)の装備(そうび)を身(み)につけた戦闘(せんとう)のプロたちなのである。そんな連中に立ち向かう(たちむかう)徹郎たち、彼ら(かれら)はどうやって「クー」を守る(まもる)のか?読み始めた(よみはじめた)ら、時(とき)の経つ(たつ)のも忘れて(わすれて)、その世界(せかい)にはまり込んで(はまりこんで)しまうドキドキ、ワクワク連続(れんぞく)の冒険小説なのである。
この夏休み(なつやすみ)、諸君(しょくん)も「遠い海から来たクー」を読んで、冒険(ぼうけん)気分(きぶん)を味わって(あじわって)みてはいかがかな?
「時計」カラーブックスシリーズ251
小田幸子:著(おださちこ:ちょ)
保育社:出版(ほいくしゃ:しゅっぱん)
小田さんはセイコー時計資料館(とけいしりょうかん)で、主任研究員(しゅにんけんきゅういん)をつとめていた方で、時計に関する(かんする)知識(ちしき)は日本(にほん)でもトップレベルの方なのである。
またセイコー時計資料館(とけいしりょうかん)は「ときをまなぼう」のホームページづくりでも大変(たいへん)お世話(せわ)になっている場所(ばしょ)なのである。小田さんはこの「時計」の他(ほか)にも日本独自(どくじ)の進化(しんか)をした和時計(わどけい)について調べた(しらべた)「和時計図録(わどけいずろく)」という本にも関わって(かかわって)いるんだよ。
さて、この「時計」は、時計の歴史(れきし)を豊富(ほうふ)なカラー写真(しゃしん)で見ることのできる素晴らしい(すばらしい)本なのである。時計史(とけいし)を知る(しる)上で欠かす(かかす)ことのできない世界中(せかいじゅう)の珍しく(めずらしく)貴重(きちょう)な時計も見ることができるのである。写真だけを見ていても楽しい(たのしい)し、じっくり本を読めば(よめば)、時計についてより詳しく(くわしく)知ることができるのである。その説明(せつめい)も決して(けっして)難しい(むずかしい)文章で書いてあるわけではないので、すぐに理解(りかい)できる時計の資料(しりょう)として本当(ほんとう)に最高(さいこう)の一冊(いっさつ)なのである。残念(ざんねん)ながら、現在(げんざい)この本は手に入れる(いれる)ことが難しくなっているが、図書館(としょかん)や大きな古本屋(ふるほんや)にはカラーブックスシリーズだけをまとめたコーナーがあったり、時計の他にも、コインや電車(でんしゃ)、飛行機(ひこうき)を集めた(あつめた)ものなどたくさんあるので、興味(きょうみ)のあるお友だちは探して(さがして)みてはどうかな?
今回(こんかい)のお話の中で出てきたセイコー時計資料館(とけいしりょうかん)は、セイコーの創業(そうぎょう)100年にあたる昭和(しょうわ)56年[1981年]に開館(かいかん)され、クロック、ウオッチ合わせて(あわせて)17,000点(てん)以上(いじょう)も収集(しゅうしゅう)している、おそらく日本で最大(さいだい)の時計資料館なのである。ここへ行けば時計の歴史(れきし)、日本の時計産業(さんぎょう)の歴史(れきし)を実際(じっさい)に目で見ながら学ぶ(まなぶ)ことができるのである。
保育社 http://www.hoikusha.co.jp/
セイコー時計資料館 http://www.seiko.co.jp/nihongo/horology/
「時をかける少女」(ときをかけるしょうじょ)
「時をかける少女(ときをかけるしょうじょ)」
筒井康隆(つついやすたか)
角川文庫:出版(かどかわぶんこ:しゅっぱん)この作品(さくひん)が書かれた(かかれた)のは1966年。今から40年近く(ちかく)たつというのに、今の時代(じだい)に読んで(よんで)もいっこうに作品としての輝き(かがやき)を失って(うしなって)いないのである。素晴らしい(すばらしい)作品というものは、時代が変わって(かわって)も、変わらない感動(かんどう)を与えて(あたえて)くれるものなのだと、この作品を読み返して(よみかえして)思う(おもう)のである。
さて、「時をかける少女(ときをかけるしょうじょ)」は1972年にNHK(エヌエイチケー)少年(しょうねん)ドラマシリーズの「タイムトラベラー」というタイトルでドラマ化(か)されて、大人気(だいにんき)となり、すぐに「続(ぞく)・タイムトラベラー」がつくられたのである。さらに1983年には原田知世(はらだともよ)さん主演(しゅえん)で映画化(えいがか)。その後(ご)1985年、1994年とドラマ化され、さらに1997年にもまた映画化され、計(けい)6回(かい)も映像化(えいぞうか)されているのだ。諸君(しょくん)のお父さんやお母さんも、きっとテレビドラマや映画で夢中(むちゅう)になって観た(みた)ことがあるんじゃないかな。感想(かんそう)を聞いて(きいて)みてもおもしろいかもしれんのう。また、一つの小説(しょうせつ)でこれだけのドラマや映画がつくられるというのは滅多(めった)にないことなのである。これだけでも、この作品(さくひん)がどんなに人の心(こころ)をひきつける力(ちから)を持って(もって)いるか、おわかりいただけると思う(おもう)のである。
さて前置き(まえおき)がずいぶんと長く(ながく)なってしまったが、カンタンに内容(ないよう)を紹介(しょうかい)しよう。「時をかける少女(ときをかけるしょうじょ)」の物語(ものがたり)が始まる(はじまる)舞台(ぶたい)は、放課後(ほうかご)の理科実験室(りかじっけんしつ)である。そこでラベンダーに似た(にた)香り(かおり)をかぎ、気を失って(うしなって)しまった主人公(しゅじんこう)の和子(かずこ)。その数日後(すうじつご)から和子の身(み)に様々(さまざま)な不思議(ふしぎ)な事件(じけん)が起こる(おこる)のである。そしてそれらの事件には信じられない(しんじられない)ような事実(じじつ)が隠されて(かくされて)いたのである。あとは読んで(よんで)のお楽しみ(たのしみ)なのである。この文庫(ぶんこ)の中にはその他(ほか)にも「悪夢の真相(あくむのしんそう)」「果てしなき多元宇宙(はてしなきたじげんうちゅう)」という少年少女(しょうねんしょうじょ)向け(むけ)のSF小説(エスエフしょうせつ)が収められて(おさめられて)いるので、こちらも合わせて(あわせて)読んでほしいのである。
「時をさまようタック」(ときをさまようタック)
ナタリー・ハビット:著(ちょ)
小野和子:訳(おのかずこ:やく)
評論社:発行(ひょうろんしゃ:はっこう)主人公(しゅじんこう)の少女(しょうじょ)ウィニーと、成長(せいちょう)がとまったまま永久(えいきゅう)に生き(いき)続け(つづけ)なければならないタック一家を組み合わせた(くみあわせた)ミステリアスな物語(ものがたり)です。「人間(にんげん)はいつかは死ぬ(しぬ)運命(うんめい)にある」からこそ、かぎられた時間(じかん)の中(なか)で、人間は毎日(まいにち)の生命(いのち)を力(ちから)いっぱい生きられるのだ、ということを考え(かんがえ)させてくれます。
「時計」(とけい)
小田幸子:著(おださちこ:ちょ)
保育社:発行(ほいくしゃ:はっこう)カラーブックス時計(とけい)の歴史(れきし)にそって、さまざまな時計の写真(しゃしん)と、こまかな解説(かいせつ)がされている本です。ページをめくるたびに出てくるめずらしい時計の写真を見ているだけで楽しく(たのしく)なります。
「時計でさんすう」(とけいでさんすう)
藤沢市算数教育研究会:著(ふじさわしさんすうきょういくけんきょうかい:ちょ)
秋玲二:絵(あきれいじ:え)
太平出版社:発行(たいへいしゅっぱんしゃ:はっこう)この本は、神奈川県藤沢市(かながわけんふじさわし)の算数(さんすう)の教育(きょういく)に熱心(ねっしん)な先生(せんせい)たちが集まって(あつまって)作った(つくった)「藤沢市算数教育研究会(ふじさわしさんすうきょういくけんきゅうかい)」が子どもたちのために、楽しく(たのしく)算数を学べる(まなべる)ようにと書いた(かいた)さんすう文庫(ぶんこ)の中の1冊(1さつ)である。このさんすう文庫のシリーズは、なんと12冊も出ていてどの本も、ほんとうに楽しくさんすうを学ぶことができるのである。さんすうが苦手(にがて)だというお友だちは、図書館(としょかん)で借りて(かりて)、読んで(よんで)みてくれたまえ。きっとさんすうが好きになることまちがいなしなのである。
「時計でさんすう」には、「長い針(ながいはり)と短い針(みじかいはり)」のこと「時間(じかん)」と「時刻(じこく)」のちがいにはじまって、暮らし(くらし)の中の身近(みじか)でわかりやすい例(れい)をあげなから「時間」や「時刻」をどうやってさんすうを使って計算(けいさん)するのかを学ぶことができるのである。
1.数のたんけん(かずのたんけん)
また時計を考える(かんがえる)時には必要(ひつよう)になる角度(かくど)の話(はなし)や、60進法(しんほう)の話も秋玲二(あきれいじ)さんのイラストとともにひじょ〜うにわかりやすく解説(かいせつ)してくれてある。じつはこの本、時の教室(きょうしつ)で「時の算数」を教えているカックル先生も参考(さんこう)にしているのである。その上「時計のはじまり」という章(しょう)では「時計の歴史(れきし)」、そして「地球(ちきゅう)のめもり」という章では、地図(ちず)を読むときに必要(ひつよう)な「緯度(いど)・経度(けいど)」まで学ぶことができるという一冊なのである。
最後(さいご)にさんすう文庫の全冊(ぜんさつ)のタイトルを紹介(しょうかい)しておくので、見てくれたまえ。
2.じゅもんは九九(じゅもんはくく)
3.分数のたべかた(ぶんすうのたべかた)
4.まほうの式(まほうのしき)
5.おかしなおかしな計算(おかしなおかしなけいさん)
6.なんでもはかろう
7.時計でさんすう(とけいでさんすう)
8.はやさのひみつ
9.つみ木であそぼう(つみきであそうぼう)
10.図形がおどる(ずけいがおどる)
11.数のせいくらべ(かずのせいくらべ)
12.さんすうゲーム
算数があまり好きじゃないという人でも、何となく「読んでみようかな?」と思うようなユニークなタイトルがついているのである。もちろん中身(なかみ)にも、算数を楽しく学べる工夫(くふう)がいっぱいなのだ。是非(ぜひ)読んでみてくれたまえ。
「時計にはなぜ誤差が出てくるのか」(とけいにはなぜごさがでてくるのか)
織田一朗:著(おだいちろう:ちょ)
中央書院:発行(ちゅうおうしょいん:はっこう)【時の研究家(ときのけんきゅうか)】として有名(ゆうめい)な織田一朗(おだいちろう)さんの「時計にはなぜ誤差が出てくるのか(とけいになぜごさがでてくるのか)」という本(ほん)である。
ここでちょっと著者(ちょしゃ)の織田一朗(おだいちろう)さんについてお話をしよう。
織田さんは1947年生まれ(うまれ)で、もともとは時計(とけい)のセイコーに勤めて(つとめて)いたのである。セイコーでは営業(えいぎょう)から、宣伝(せんでん)や広報(こうほう)までいろいろな仕事(しごと)をし、その後(のち)独立(どくりつ)して、「時(とき)と時計」についての研究(けんきゅう)に集中(しゅうちゅう)して、今ではじつに多く(おおく)の「時と時計」の本を出したり、テレビに出演(しゅつえん)したり、講演(こうえん)をしたりと、幅広く(はばひろく)活躍(かつやく)されている文字通り(もじどおり)【時の研究家(ときのけんきゅうか)】なのである。織田さんの本でいつも感心(かんしん)させられるのは、まず本のタイトルなのである。みんなが日頃(ひごろ)思って(おもって)いる「時計や時」に関して(かんして)の疑問(ぎもん)をずばっとタイトルに持って(もって)きて、「読みたい(よみたい)!」「読んでみようかな?」と思わせてしまうのである。今回(こんかい)の「時計にはなぜ誤差が出てくるのか」というタイトルも「そう言えば、そうだよなぁ。どうしてなんだろう?」とついついその理由(りゆう)を知りたく(しりたく)なってしまうよね。そのタイトルにつられ、本を開く(ひらく)と、目次(もくじ)にはまた、「どうして?」と思わせる「時計や時」についての不思議(ふしぎ)をとりあげたタイトルがいっぱいあって、その理由を知りたくなって、どんどんと本の中に引き込まれて(ひきこまれて)いってしまうのである。ちょっとその目次からいくつかのタイトルを載せて(のせて)みたので見てほしいのである。
「シンデレラは、11時45分を文字盤(もじばん)で確認(かくにん)できなかった?」
「日時計(ひどけい)はクォーツより正確(せいかく)か?」
「誰(だれ)でもが一発(いっぱつ)で起きられる(おきられる)目覚まし(めざまし)時計はあるか?」
「時計の針(はり)の数(かず)はなぜ増えた(ふえた)のか?」さて、この4つの「?」に諸君(しょくん)もきっと興味(きょうみ)をそそられたのではないかな?
答えはこの本の中にある。
是非(ぜひ)とも実際(じっさい)に読んで、この「?」を解決(かいけつ)してほしいのである。
「閉ざされた時間割」(とざされたじかんわり)
眉村 卓:著(まゆむらたく:ちょ)
角川春樹事務所:出版(かどかわはるきじむしょ:しゅっぱん)眉村卓さんは筒井康隆(つついやすたか)さん、小松左京(こまつさきょう)さんと並ぶ(ならぶ)、日本SF界(にほんエスエフかい)の大御所(おおごしょ)である。今でこそ、SFは一つの文学(ぶんげい)のジャンルとして、日本でも世界(せかい)でも認知(にんち)されているのであるが、日本SFの生まれた当初(とうしょ)は、子どもたちのための空想科学小説(くうそうかがくしょうせつ)というとらえ方をされていたのである。当然(とうぜん)のことながら、SF作家のところに来る注文(ちゅうもん)も、子どもたち向け(むけ)の小説というのが多かったのである。しかし、これが、多くの子ども向けSFの傑作(けっさく)を生みだすきっかけになったのである。眉村さんも、NHK(エヌエイチケー)でドラマ化(か)された「夕映え作戦(ゆうばえさくせん)」、映画化(えいがか)された「狙われた学園(ねらわれたがくえん)」など多くの傑作(けっさく)を残して(のこして)いるのである。この「閉ざされた時間割」もその流れ(ながれ)の作品(さくひん)である。それではちょっとそのあらすじを紹介しよう。
前の日になかなか寝つけず(ねつけず)、ついつい授業中(じゅぎょうちゅう)に眠って(ねむって)しまった良平(りょうへい)が「しまった!」と思い、起きた(おきた)時には、すでにその日の授業は全て(すべて)終わって(おわって)いた。にも関わらず(かかわらず)、ノートは、ていねいすぎるぐらいにとられていた。しかも、その筆跡(ひっせき)は、自分(じぶん)のものではないのである。さらに友人(ゆうじん)に聞いて(きいて)みたところ、先生(せんせい)にあれこれ質問(しつもん)をしていたというのである。そんなことがありえるのか?良平のこの奇妙(きみょう)な体験(たいけん)をきっかけに、次々(つぎつぎ)と学校(がっこう)の中でも奇妙なことが起きてゆく。先生が、友人がまるで何ものかに体をのっとられたような行動(こうどう)を起こす(おこす)のである。じつは地球外(ちきゅうがい)からの借体生物(しゃくたいせいぶつ)[人の体を借りて(かりて)行動(こうどう)する生物]の侵略(しんりゃく)がひそかに進行(しんこう)していたのである。だんだんと大胆(だいたん)な行動をとるようになった借体生物たちは、体をのっとった人々を、廃校(はいこう)の地下(ちか)にある彼らの秘密基地(ひみつきち)に連れこみ(つれこみ)、そこで、彼らの数十万(すうじゅうまん)にも及ぶ(およぶ)仲間(なかま)たちの地球侵略のための準備(じゅんび)をさせるのである。自分の意志(いし)では、どうにもできない借体生物からの支配(しはい)、もはやこれまでか?と思われた時に、良平は彼らの意外(いがい)な弱点(じゃくてん)を発見(はっけん)し、反撃(はんげき)にでるのである。さて、その結果(けっか)は?
難しい(むずかしい)科学知識(かがくちしき)も必要(ひつよう)とせず、空想(くうそう)の世界(せかい)に読者(どくしゃ)を連れていくすばらしいストーリー運び(はこび)。この続き(つづき)はぜひ、本を手にとって読んでほしいのである。「閉ざされた時間割」にはもうひとつ「幻(まぼろし)のペンフレンド」という作品が収録(しゅうろく)されている。こちらもまた傑作(けっさく)なのであわせて読んでほしいのである。
岩波少年文庫「トムは真夜中の庭で」
いわなみしょうねんぶんこ「トムはまよなかのにわで」
フィリバ・ピアス:著(ちょ)
高杉一郎:訳(たかすぎいちろう:やく)
岩波書店:出版(いわなみしょてん:しゅっぱん)【イギリスの作家(さっか)であるフィリバ・ピアスの書いた(かいた)「トムは真夜中の庭で(トムはまよなかのにわで)」という作品(さくひん)である。弟(おとうと)のピーターがはしかになり、夏休み(なつやすみ)をおじさんの家で過ごす(すごす)ことになったトム。退屈(たいくつ)で退屈でしかたない毎日(まいにち)を過ごしていた、ある真夜中。古時計(ふるどけい)がありえないはずの13時を打つ(うつ)音を聞き(きき)、その音に誘われ(さそわれ)、中庭(なかにわ)に続く(つづく)扉(とびら)を開けた(あけた)瞬間(しゅんかん)から不思議(ふしぎ)な体験(たいけん)が始まる(はじまる)のである。
扉(とびら)の向こう(むこう)には、昼間(ひるま)はなかった広々(ひろびろ)とした庭園(ていえん)があり、トムはそこで、ハティという一人の少女(しょうじょ)と出会う(であう)のである。それからというもの、トムは毎晩(まいばん)ベッドを抜け出し(ぬけだし)この庭園へと出かけ、ハティと一緒(いっしょ)に、庭園で木登り(きのぼり)をしたり、小屋(こや)をつくったりと楽しい(たのしい)時を過ごす(すごす)のである。その庭園に何度(なんど)か行くうちにトムは、この庭園に流れる(ながれる)時間(じかん)の不思議(ふしぎ)に気づくのである。トムにとっては1日しかたっていなくとも、庭園では何ヶ月(なんかげつ)も何年も時間が過ぎていて、トムはそのままなのにハティは最初(さいしょ)に会った(あった)時よりも日に日に目に見えて大人(おとな)になっているのである。
そこでトムは「時(とき)」というものが、なんなのかを考え始める(かんがえはじめる)。
自分(じぶん)にとってわずか2〜3週間(しゅうかん)の「時」、そして庭園(ていえん)の10年近く(ちかく)の「時」。どちらが本当(ほんとう)の「時」なんだろう?まったく違った(ちがった)2つの「時」がどうして重なり(かさなり)あうんだろう?おじさんの家を出て、いく日もたった、ある日、トムはその疑問(ぎもん)の答え(こたえ)を出そうと、ある試み(こころみ)をする。その試みは成功(せいこう)したのだが、そのつぎの日、またハティに会う(あう)ため扉(とびら)を開く(ひらく)と、そこには庭園はなかった。
その事実(じじつ)に驚き(おどろき)、悲しむ(かなしむ)トム。もう二度(にど)とハティに会う(あう)ことはできないのか?ところが、トムは意外(いがい)なところでハティに再会(さいかい)することになるのである。2つの時間(じかん)が本当(ほんとう)に重なる(かさなる)奇跡(きせき)・・・。
このエンディングに読んだ(よんだ)人は、きっと感動(かんどう)すること間違い(まちがい)なしである。
ぜひ書店(しょてん)や図書館(としょかん)で探して(さがして)読んで(よんで)ほしい1冊(さつ)である。ちなみに、この物語(ものがたり)に出てくる庭園(ていえん)は、作者(さくしゃ)のフィリバ・ピアスが子供時代(こどもじだい)を過ごし(すごし)、そして今も住んで(すんで)いる自宅(じたく)の庭(にわ)がモデルとなっているとのことである。彼女(かのじょ)の家を訪ねた(たずねた)人の話(はなし)では、本の中にある挿し絵(さしえ)とほとんど同じ(おなじ)庭がそこにあり、トムが登る(のぼる)レンガ塀(べい)についている日時計(ひどけい)もあったそうである。イギリスなのでちょっと行く(いく)というわけにはいかないが、一度(いちど)行ってみたいものである。
「夏への扉」(なつのとびら)
ロバート・A・ハインライン:著(ロバート・エー・ハイライン:ちょ)
ハヤカワ文庫:発行(ハヤカワぶんこ:はっこう)タイムマシンのパラドクスをテーマにした1957年の傑作(けっさく)SF小説(エスエフしょうせつ)。
発明家( はつめいか)の主人公(しゅじんこう)ダニエルが、仲間(なかま)にだまされコールドスリープ[冷凍(れいとう)されて、年をとらないようにして未来(みらい)へいけるシステム]の機械(きかい)にいれられて、30年後(30ねんご)にめざめた未来から、事件(じけん)の真相(しんそう)をときあかし、愛(あい)する恋人(こいびと)と再会(さいかい)するために、タイムマシンにのって過去(かこ)にもどり、さまざまなむずかしい問題(もんだい)を解決(かいけつ)し、そしてまた未来へとまい戻る(もどる)。愛する恋人と彼(かれ)ははたして会う(あう)ことができるのか。
ハラハラドキドキ、まさにエンターテイメントです。
「夏の庭〜The Friends〜」(なつのにわ〜フレンズ)
「夏の庭〜The Friends〜」
(なつのにわ〜フレンズ)新潮文庫(しんちょうぶんこ)
湯本香樹実:著(ゆもとかずみ:ちょ)
新潮社:出版(しんちょうしゃ:しゅっぱん)湯本香樹実(ゆもとかずみ)さんの「夏の庭〜The Friends〜(なつのにわ〜フレンズ)」である。「人間の命(にんげんのいのち)」についてとても考え(かんがえ)させられる、とても素晴らしい(すばらしい)一冊(さつ)なのである。
物語(ものがたり)は、3人の少年(しょうねん)が、町(まち)はずれの古い(ふるい)家(いえ)に住む(すむ)一人暮らし(ひとりぐらし)の老人(ろうじん)を観察(かんさつ)し始め(はじめ)、いつの間(ま)にか友達(ともだち)になり、その老人とともにひと夏(なつ)を過ごす(すごす)というものである。老人を「観察」するとは、ずいぶんヘンな表現だと思った人もいるのではないかな?じつはこの少年たちは「その老人が死ぬ(しぬ)瞬間(しゅんかん)」を見るために文字通り(もじどおり)「観察」を始めたのである。けれども、子供(こども)にとって「死」は、あまりにも遠い(とおい)先(さき)の未来(みらい)のことであり、想像(そうぞう)できないものなのだ。3人は、いたずらやふざけた気持ち(きもち)ではなく、ただ「どんなふうに人は死んでいくんだろう?」という好奇心(こうきしん)から、こんな行動(こうどう)をおこしてしまったのである。
ところが、その老人(ろうじん)は、自分(じぶん)の様子(ようす)を毎日(まいにち)見に来る(みにくる)奇妙(きみょう)な少年(しょうねん)たちのおかげで、なぜか生活(せいかつ)に張り(はり)が生まれ(うまれ)、どんどん元気(げんき)になっていくのである。そして、ある時(とき)からその老人と少年たちは友達(ともだち)になってしまうのだ。一緒(いっしょ)に庭(にわ)の雑草(ざっそう)をとり、縁側(えんがわ)でスイカを食べ(たべ)、庭にコスモスの種(たね)を植え(うえ)、おじいさんが体験(たいけん)した戦争(せんそう)の話(はなし)を聞き(きき)、夜(よる)の河原(かわら)で打ち上げ花火(うちあげはなび)をあげ、子供たちだけでは決して(けっして)体験(たいけん)できないようなステキなひと夏(なつ)を過ごす(すごす)のである。けれど、少年たちが夏のサッカー合宿(がっしゅく)から帰って(かえって)来た(きた)その日、笑顔(えがお)で迎えて(むかえて)くれるはずの老人は・・・。
本(ほん)を読んで(よんで)みると、このひと夏(なつ)の間(あいだ)に、少年(しょうねん)たちが、老人(ろうじん)と出会った(であった)ことによって、心(こころ)が豊か(ゆたか)にたくましく育って(そだって)いくことが感じ(かんじ)られるのである。本を読むということは、その物語(ものがたり)を体験(たいけん)するということである。諸君(しょくん)にも、この物語を是非(ぜひ)読んで、体験し、心をたくましく育ててほしいと願う(ねがう)のである。
「七瀬ふたたび」(ななせふたたび)
筒井康隆:著(つついやすたか:ちょ)
新潮社:出版(しんちょうしゃ:しゅっぱん)著者(ちょしゃ)は、「時をかける少女(ときをかけるしょうじょ)」の筒井康隆(つついやすたか)さんである。この「七瀬ふたたび」は、筒井康隆ファン、SFファンの間(あいだ)では「七瀬三部作(ななせさんぶさく)」[「家族八景(かぞくはっけい)」「七瀬ふたたび」「エディプスの恋人(こいびと)」]と言われ(いわれ)、他人(たにん)の心(こころ)の中を覗く(のぞく)ことができる超能力者(ちょうのうりょくしゃ)、火田七瀬(ひだななせ)が主人公(しゅじんこう)のシリーズものの一つである。もしこの「七瀬ふたたび」を読んで(よんで)おもしろいと思った(おもった)人は、是非(ぜひ)、他(ほか)の2作品(さくひん)も読んでほしいのである。
今回(こんかい)シリーズの1作目(さくめ)ではなく、2作目の「七瀬ふたたび」を取り上げた(とりあげた)のは、この作品がいちばん、諸君(しょくん)が読むのにはとっつきやすい内容(ないよう)だと思ったからである。まずは、登場(とうじょう)する超能力者の数(かず)。「七瀬ふたたび」では、自分(じぶん)の能力(のうりょく)を隠し(かくし)ながら、お手伝い(おてつだい)さんとして、いろいろな家を渡り歩き(わたりあるき)、孤独(こどく)に生きていた七瀬の前に、様々(さまざま)な超能力者が現れる(あらわれる)のである。七瀬と同じく(おなじく)人の心を読む能力[テレパス]を持つ(もつ)少年(しょうねん)、ノリオ、予知能力者(よちのうりょくしゃ)の恒夫(つねお)、念動力者(ねんどうりきしゃ)[テレキネシス]のヘンリー、そして時間遡行(じかんそこう)[タイムトラベル]の藤子(ふじこ)と4人も出てくるのである。さらには、彼女(かのじょ)たちをこの世(よ)から抹殺(まっさつ)しようとする謎(なぞ)の集団(しゅうだん)も登場(とうじょう)するのである。これだけでも、ワクワクドキドキの展開(てんかい)が予想(よそう)できるのではないかな?
さて、諸君(しょくん)の中にも、超能力(ちょうのうりょく)に憧れ(あこがれ「自分(じぶん)にもテレパスや念力(ねんりき)とかあったらいいなぁ」などと夢(ゆめ)見ている人もいるのではないかな?しかしながら、仮(かり)に人の心(こころ)の中が覗けて(のぞけて)しまったら、知りたい(しりたい)ことだけではなく、知りたくないこと、例えば(たとえば)、自分に対する(たいする)イヤな感情(かんじょう)なども見えてしまうのである。また逆(ぎゃく)の立場(たちば)だったら、自分が知られたくないことを、知られてしまったり、そんなことも起きて(おきて)しまうのである。なかなか超能力者というのは、実際(じっさい)にはやっかいな存在(そんざい)なのである。その上、知られたくないことがたくさんある悪い(わるい)人たちが、そんな超能力者の存在を知ったら、どうなるか?当然(とうぜん)、その存在を消して(けして)しまおうと考える(かんがえる)のである。超能力者は彼ら(かれら)にとってはジャマ者(もの)以外(いがい)に過ぎない(すぎない)のである。物語(ものがたり)のクライマックスでは、そんな謎(なぞ)の暗殺集団(あんさつしゅうだん)と七瀬をはじめとする5人の超能力者との想像(そうぞう)を絶するような戦い(たたかい)が始まる(はじまる)のである。はたして七瀬たちの運命(うんめい)は・・・。
「二分間の冒険」(にふんかんのぼうけん)
岡田淳:著(おかだじゅん:ちょ)
太田大八:絵(おおただいはち:え)
偕成社:発行(かいせいしゃ:はっこう)主人公(しゅじんこう)は6年生(ねんせい)の男の子(おとこのこ)。ダレカという黒猫(くろねこ)にさそわれて、とつぜん考え(かんがえ)られないような別世界(べつせかい)にいってしまいます。
その世界でおこる、どきどき、わくわくする「ふしぎな時間(じかん)と空間(くうかん)」の冒険(ぼうけん)物語(ものがたり)です。こちらの世界の生活(せいかつ)では、わずか2分間(2ふんかん)の間(あいだ)のことですが、この別世界の中の時計では、はかりきれない長い(ながい)時間と事件(じけん)がいっぱいです。
「日本に象がいたころ」(にほんにぞうがいたころ)
亀井節夫:著(かめいただお:ちょ)
岩波書店:出版(いわなみしょてん:しゅっぱん)日本(にほん)の地質学(ちしつがく)の権威(けんい)で現在(げんざい)、京都大学名誉教授(きょうとだいがくめいよきょうじゅ)である亀井節夫(かめいただお)さんの「日本に象がいたころ(にほんにぞうがいたころ)」である。
象と言えば、人なつっこく、芸(げい)もでき、動物園(どうぶつえん)でも大人気(だいにんき)の動物であるが、日本では、動物園以外(いがい)では見ることができないのである。ところが2万年前(まんねんまえ)までは、日本人の祖先(そせん)とともに、この日本で象が暮らして(くらして)いたのである。その後(ご)、気候(きしょう)の変化(へんか)で絶滅(ぜつめつ)してしまったために、日本の象は、長い年月(ねんげつ)の間に日本人の記憶(きおく)の中からも消えて(きえて)しまったのである。そのために、わずか200年ほど前までは、化石(かせき)で発見(はっけん)された象の骨(ほね)は、象ではなく竜(りゅう)の骨[竜骨(りゅうこつ)]として珍重(ちんちょう)されていたというのである。竜は想像上(そうぞうじょう)の動物ではあるが、絵(え)などによく描かれて(えがかれて)おり、まったく見たこともない象よりは、より想像しやすい動物だったからなのである。
この本では、そんな勘違い(かんちがい)に始まり(はじまり)、多く(おおく)の発掘(はっくつ)と研究(けんきゅう)によって「日本の象の謎(なぞ)」が解明(かいめい)されていく様子(ようす)が、じつにわかりやすく書かれているのである。まるでタイムマシンに乗って(のって)、象の謎解き(なぞとき)の歴史(れきし)をたどっていくようなわかりやすさと楽しさ(たのしさ)とでも言ったらいいのだろうか?読んで(よんで)いるうちに、日本の象の歴史、世界中(せかいじゅう)の象の歴史、象という動物の特異性(とくいせい)、その進化(しんか)の経過(かてい)など、かなり専門的(せんもんてき)なことまで学ぶ(まなぶ)ことができ、1冊(さつ)を読み終えた(よみおえた)時にはちょっとした「象博士(ぞうはかせ)」になれると言っても過言(かごん)ではないのである。
ちなみに、絶滅以後(ぜつめついご)、日本に初めて(はじめて)象がやってきたのは、1408年。南蛮船(なんばんせん)に載せられて(のせられて)きた象が当時(とうじ)の将軍(しょうぐん)足利義持(あしかがよしもち)に献上(けんじょう)されたという記録(きろく)が残って(のこって)いるのである。その後1574年と1575年に日本に中国(ちゅうごく)の明国(みんこく)から持ち込まれ(もちこまれ)、1602年には、南(みなみ)ベトナムから、徳川家康(とくがわいえやす)に贈られた(おくられた)という記録がある。ヘビのようにくねくねと動く(うごく)長い鼻(はな)を持った(もった)巨大(きょだい)な動物を見た家康はさぞ、驚いた(おどろいた)に違い(ちがい)ないのである。
この本には、多くの人が長い時間(じかん)とたくさんのお金をかけて解明(かいめい)した日本の象の歴史(れきし)と事実(じじつ)がぎっしり詰まって(つまって)いるのである。我々(われわれ)は、そんな貴重(きちょう)な知識(ちしき)を読む(よむ)だけで手に入れることができるのである。なんとぜいたくなことだろう。諸君(しょくん)もぜひ、読書(どくしょ)を習慣(しゅうかん)にし、多くの知識(ちしき)を自分(じぶん)のものにしてほしいのである。
人間の知恵8(にんげんのちえ8)「時計のはなし」(とけいのはなし)
市場泰男:著(いちばやすお:ちょ)
さ・え・ら書房:発行(さらえしょぼう:はっこう)この本は、以前(いぜん)諸君(しょくん)に紹介(しょうかい)した「こよみのはなし」と同じ「人間の知恵(にんげんのちえ)シリーズ」の中の一冊(いっさつ)である。日時計(ひどけい)に始まる(はじまる)「時計の歴史(とけいのれきし)」を順々(じゅんじゅん)に非常(ひじょう)にわかりやすく説明(せつめい)してくれるとてもためになる本なのである。
様々(さまざま)な時計を紹介しながら、その時計がどのように生まれた(うまれた)のか、その仕組み(しくみ)がどのようになっているのか?
そしてそこに秘められた(ひめられた)人間の知恵までもがわかるようになっておる。
本の中は大きく3つにわかれていて「時計のはじまり」「機械式時計の誕生と発展(きかいしきどけいのたんじょうとはってん)」「現在の時計(げんざいのとけい)」となっておる。
中には多くのイラストや写真(しゃしん)が入っていて、それらを見るだけでも楽しい(たのしい)のである。
こうした「時計の歴史(とけいのれきし)」をとりあげた本はたくさんあるが、それらの本を読むたびに思う(おもう)ことは、人間(にんげん)が機械式時計の発明(はつめい)により「人工的な時間(じんこうてきなじかん)」にそって生活(せいかつ)し始めて(はじめて)から、わずか300年ぐらいしかたっていないということなのである。それまでは、太陽(たいよう)とともに暮らす(くらす)「自然の時間(しぜんのじかん)」の中で暮らしていたと言うことである。「時計」ができて便利(べんり)になったことは、多い(おおい)のだが、それによって失って(うしなって)しまったものも多いというのが「時計の歴史」について書く(かく)人たちの共通(きょうつう)した感想(かんそう)なのである。
しょくんも、学校(がっこう)などで時計(とけい)ができて便利(べんり)になったこと。そして時計ができたことによって、人間(にんげん)の暮らし(くらし)がどのようにかわり、それによってなくしてしまったことなどを話し合って(はなしあって)みてはどうだろう?○この本を出版(しゅっぱん)しているさ・え・ら書房のホームページは
http://www.saela.co.jp/
人間の知恵16(にんげんのちえ16) 「こよみのはなし」
小松恒夫:著(こまつつねお:ちょ)
さ・え・ら書房:発行(さらえしょぼう:はっこう)ふだん当たり前(あたりまえ)のように使っているカレンダー。1年は12ヶ月365日で、4年に1度うるう年がある。誰(だれ)もが知っている常識(じょうしき)のようだけれど、この方式(ほうしき)の暦(こよみ)が世界(せかい)で使われるようになってからまだ500年もたっていないのである。しかも日本では、たった130年ぐらい。それじゃぁ、それまではどんな暦が使われていたの?と思う人も多いんじゃないかな?そんなみんなの疑問(ぎもん)に答えてくれるのがこの本なのである。
まず最初(さいしょ)に、この「人間の知恵シリーズ(にんげんのちえシリーズ)」についてお話をしておこう。このシリーズには、われわれの身の回り(みのまわり)のものや、ふだん何気(なにげ)なく使っているものにこめられた「人間の知恵」について色々(いろいろ)なものを取り上げてとてもわかりやすく、そのものがどうしてつくられたのかというようなことからきちんと教えてくれる本なのである。このシリーズに取り上げられているものには「車輪(しゃりん)」「えんぴつ」「鉄(てつ)」「クスリ」「接着剤(せっちゃくざい)」「ガラス」「ロボット」などなんと30種類(しゅるい)!このシリーズを全部(ぜんぶ)読めば、相当(そうとう)な物知り(ものしり)になれること間違い(まちがい)なしなのである。
それでは、今回の「こよみのはなし」に話をもどそう。この本ではまずみんなが大好き(だいすき)なタイムマシンのお話から入って行くのである。タイムマシンで明治(めいじ)5年の12月3日に行ったところ、その日がなくタイムマシンは戻って(もどって)きてしまった!そんなバカな!じつは、明治の旧暦(きゅうれき)から新暦(しんれき)にかわる時に、旧暦の明治5年の12月5日が、いきなり新暦の明治6年1月1日になってしまったということなのである。そんな暦の意外(いがい)な事実(じじつ)から、昔の人たちがどうやって暦をつくっていったのかを、歴史(れきし)にそって、順々(じゅんじゅん)にわかりやすく説明(せつめい)し、その暦についての色々(いろいろ)なおもしろいエピソードもちりばめられていて、あきずに一気(いっき)に読んでしまえるのである。この本を書いた小松恒夫(こまつつねお)さんは最後(さいご)に「こよみを創って(つくって)きた人間の知恵は、その人たちが生きていた時代の生活の知恵だともいえる。たった1まい、あるいは6まい、あるいは12まいの紙がかさねられている、いまのカレンダーは、そんな時代(じだい)の生活の知恵の長い長いつみかさねのおかげだ」と書いている。
そしてわれわれは、この本のおかげで、何千年という暦の歴史をたったの1時間ぐらいで、一気に学ぶことが出来てしまうのである。本というのはすごいものだと、読書(どくしょ)好きの私は、改めて(あらためて)思ってしまったのである。フム。
○この本を出版(しゅっぱん)しているさ・え・ら書房のホームページは
http://www.saela.co.jp/
のんびり森のぞうさん(のんびりもりのぞうさん)
かわきたりょうじ:作(さく)
みやざきひろかず:絵(え)
岩崎書店:発行(いわさきしょてん:はっこう)時計(とけい)は出てこないのだが、時間(じかん)や時(とき)というものをとても考え(かんがえ)させてくれる素晴らしい(すばらしい)1冊(さつ)なのである。
いきなり、この物語(ものがたり)の主人公(しゅじんこう)が住んで(すんで)いる森の名前(なまえ)が「のんびり森」と言うのがなんともいいのである。のんびり森に住む動物(どうぶつ)たちはみ〜んなのんびりしていて、その中でも一番(いちばん)ののんびり屋さんがこのぞうさんなのである。そのぞうさんのおウチにある日、この森に引越して(ひっこして)きたばかりのうさぎさんがやってくるのである。ここでちょっと言っておくと、うさぎというのは「不思議の国のアリス(ふしぎのくにのアリス)」という童話(どうわ)でも、首(くび)から時計をさげて、いつも時間を気にしているという、言ってみればあくせくと生きる(いきる)時間の象徴(しょうちょう)なのである。ここでも、うさぎさんは忙し(いそがし)そうにバタバタと現れる(あらわれる)のである。さて、うさぎさんはぞうさんの赤いおうちを見て郵便屋(ゆうびんや)さんと勘違い(かんちがい)してしまうのである。そして、ぞうさんに引越し祝い(いわい)のパーティーの案内状(あんないじょう)をみんなに配達(はいたつ)してくれるように頼む(たのむ)のである。けれど、のんびり森で一番ののんびり屋さんのぞうさんだから、明日(あす)がパーティーだというのに、最初(さいしょ)の案内状を届けた(とどけた)のが、パーティーの当日(とうじつ)の夜(よる)、それからも1日に1枚ずつ配達をするというのんびりさ!これでは、せっかく招待状を出しても、うさぎさんのところには誰(だれ)も来るわけはないのである。準備(じゅんび)をしてみんなを待って(まって)いたうさぎさんは悲しくて(かなしくて)泣いて(ないて)しまったのである。ところが、次(つぎ)の日、そしてその次の日、その次の次の日と、うさぎさんのおウチには、とても素敵な(すてきな)ことが起きる(おきる)のである。それはいったいどんな出来事(できごと)なのか?この先は、読んで(よんで)のお楽しみ(たのしみ)なのである。
この本は、子供(こども)たちだけでなく、大人(おとな)にも広く(ひろく)読まれているということなのである。時間に追われ(おわれ)忙しく働いて(はたらいて)いる人たちが何となくホッとする世界(せかい)がこの絵本(えほん)の中には描かれて(えがかれて)いるのである。何もかもがスケジュール通り(どおり)にキチンと行われることばかりが良いとは限らない(かぎらない)のである。諸君(しょくん)も是非(ぜひ)、図書館(としょかん)などで探して(さがして)読んでほしいのである。そうそう、この「のんびり森のぞうさん」には「のんびり森のかいすいよく」という続編(ぞくへん)もあるのである。こちらもおすすめなのである。
○この本を出版(しゅっぱん)している岩崎書店のホームページは
http://www.iwasakishoten.co.jp/