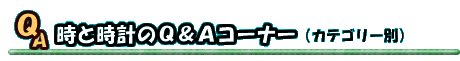1年間(ねんかん)が365日っていうのは、誰(だれ)がいつ、どういうふうに決めた(きめた)の?どうして1日は24時間(じかん)なの?
1年間(ねんかん)が365日の暦(こよみ)が決められ(きめられた)たのは、1582年のこと、地球(ちきゅう)が太陽(たいよう)の周り(まわり)を1周(しゅう)する時間(じかん)を1年とした暦で、太陽暦(たいようれき)と呼ばれる(よばれる)ものなんだよ。太陽暦は、もともと、古代(こだい)エジプトで生まれた(うまれた)暦がローマ時代(じだい)にヨーロッパに渡って(わたって)、広く(ひろく)使われる(つかわれる)ようになったんだ。紀元前(きげんぜん)49年には、見直し(みなおし)が行われて(おこなわれて)、うるう年(どし)が入れられる(いれられる)ようになったんだけど、細かな(こまかな)誤差(ごさ)がつもりにつもって、16世紀(せいき)になった時には、暦と実際(じっさい)の太陽年(たいようねん)との誤差が10日間(かかん)にもなってしまったんだ。そこで1582年に、ローマ法王(ほうおう)グレゴリオ13世(せい)が復活祭(ふっかつさい)の日程(にってい)を正確(せいかく)にすることを目的(もくてき)に、10月4日の翌日(よくじつ)を10月15日として、10日間をいっきに調節(ちょうせい)して、1年を365.2425日にする暦を導入(どうにゅう)したんだ。だからそのローマ法王の名前(なまえ)をとってグレゴリオ暦となったんだ。日本(にほん)では1873年【明治(めいじ)6年】から使われて(つかわれて)いるんだよ。わかったかな。
それともうひとつの質問(しつもん)、こちらはよくもらう質問だけど、やっぱり世の中(よのなか)の単位(たんい)がほとんど、10進法(しんほう)でできているのに、時計(とけい)だけが、12進法という中途半端(ちゅうとはんぱ)な数え方(かぞえかた)になっているのをみんな不思議(ふしぎ)に思う(おもう)のは無理(むり)のないことだよね。そこで、カンタンに説明(せつめい)するから、よく読んで(よんで)理解(りかい)してね。 なぜ12になったかというと、今から4500年ぐらい前に、最初(さいしょ)に暦(こよみ)をつくった古代(こだい)バビロニアの人たちが、12進法という12で繰り上がる(くりあがる)計算方法(けいさんほうほう)を使って(つかって)いたからなんだ。その12進法をもとに、時間(じかん)の単位(たんい)がつくられ、1日は24時間(じかん)。考え方(かんがえかた)としては12×2【12の倍数(ばいすう)】ということになったんだ。今は時計(とけい)の針(はり)は1〜12に統一(とういつ)されているけれど、昔(むかし)のヨーロッパでは1〜24表示(ひょうじ)のものや、1〜6表示のものもあったんだよ。さらにフランス革命(かくめい)の時(とき)には、10進法の時間単位(じかんたんい)がつくられたこともあったんだよ。でも使いにくいのと、その後(ご)ナポレオンが皇帝(こうてい)になったことで、2年もたたずに廃止(はいし)されてしまったんだ。わかってくれたかな? でも4500年も前につくられた数え方が今も使われているなんてすごいことだよね。
正確(せいかく)な時刻(じこく)を合わせたい(あわせたい)のですが、日本標準時(にほんひょうじゅんじ)はネットで調べられない(しらべられない)のでしょうか?
今は、電波修正時計(でんぱしゅうせいどけい)という日本(にほん)の標準時(ひゅうじゅんじ)の電波(でんぱ)を受信(じゅしん)して、自動(じどう)でいつも誤差(ごさ)を補正(ほせい)してくれる便利(べんり)な時計があるけれど、使い慣れた(つかいなれた)自分(じぶん)の時計というのは、なかなか変えられない(かえられない)ものですよね。質問(しつもん)をくれた方もきっと、時計をずっと大切(たいせつ)にしている方なのかな?と思ったり(おもったり)もします。さて、「日本標準時(にほんひょうじゅんじ)」は、ネットで簡単(かんたん)に調べる(しらべる)ことができますよ。この「ときをまなぼう」でも何度(なんど)か紹介(しょうかい)したことのある日本の標準時をつくっている機関(きかん)である、独立行政法人情報通信研究機構(どくりつぎょうせいほうじんじょうほうつうしんけんきゅうきこう)のページにいけば、いつでも日本の標準時が表示(ひょうじ)されているので、このページを見ながら合わせれば(あわせれば)大丈夫(だいじょうぶ)ですよ。独立行政法人情報通信研究機構については、時(とき)の教室(きょうしつ)で見てくださいね
シンデレラに出て(でて)くる、15分(ふん)ごとに鳴る(なる)時計(とけい)。これはどうして15分なのでしょうか?またこのことと、その時代(じだい)の歴史背景(れきしはいけい)や関係(かんけい)はあるのでしょうか?詳しく(くわしく)教えて(おしえて)ください。
この15分(ふん)ごとに鳴る(なる)時計(とけい)というのは、ペローの「シンデレラ」に出てくる時計ですね。ペローの「シンデレラ」が出版(しゅっぱん)されたのは1697年のこと。機械式時計(きかいしきどけい)の父と言われる(いわれる)クリスチャン・ホイヘンスが「ヒゲゼンマイ」のついたテンプ時計をつくったのが1656年、この時計の発明(はつめい)によって分単位(たんい)まで正確(せいかく)に計れる(はかれる)機械式時計ができました。14世紀(せいき)ぐらいから、機械式時計はあったのものの、誤差(ごさ)がありすぎてあまり正確な時刻(じこく)はわかりませんでした。1時間(じかん)ぐらいの誤差があったというから驚き(おどろき)ですよね。しかも時計とは言っても文字盤(もじばん)も針(はり)もなく、鐘(かね)で時刻を知らせる(しらせる)だけの機械だったのです。
さて「シンデレラ」の物語(ものがたり)は、もともと民話(みんわ)から取材(しゅざい)した寓話(ぐうわ)のひとつ。だから、出版(しゅっぱん)された1697年で民話になっているということは、それよりもさらに昔(むかし)の話(はなし)ということになりますね。少なくとも(すくなくとも)この物語の時代設定(じだいせってい)は100年前(ねんまえ)、16世紀ぐらいでしょうか。16世紀には精度的(せいどてき)には劣る(おとる)ものの、機械的に約(やく)15分ごとに鐘を鳴らす(ならす)方式(ほうしき)の時計が多く(おおく)あったようです。時針(じしん)が付き始めた(つきはじめた)のもこの頃(ころ)ですので、おそらくシンデレラの話に出てくるのは15分ごとに鐘を鳴らし(ならし)、時針のある時計ではないかと考えられます(かんがえられます)。それならば、11時45分という時刻を知ることができますね。ここで問題(もんだい)になるのが、シンデレラの見た時計が、塔時計(とうどけい)なのか、室内時計(しつないどけい)というところなのですが、なんとも言えませんね。この時計について研究(けんきゅう)した角山栄(つのやまさかえ)さんの「シンデレラの時計」【ポプラ社(しゃ)】には、修道院(しゅうどういん)などにつけられた塔時計などの大きなものではなく、室内時計だと書いて(かいて)いますし、時(とき)の研究家(けんきゅうか)である織田一朗(おだいちろう)さんの「時計にはなぜ誤差がでてくるのか」【中央書院(ちゅうおうしょいん)】では、時針のついた塔時計だと書いています。角山さんのいう室内時計だったかもしれないし、絵本(えほん)などの挿し絵(さしえ)にある塔時計だったかもしれません。なんとなく月明かり(つきあかり)に照らされる(てらされる)塔時計の方(ほう)がロマンチックな感じ(かんじ)はしますよね。でも、童話(どうわ)の中の描写(びょうしゃ)ですからこれが正しい(ただしい)ということはなく、物語を読む(よむ)人がそれぞれの時計を想像(そうぞう)してもいいのではないでしょうか?
ある資料(しりょう)では、一刻(いっこく)は30分(ふん)で一時(いっとき)が二時間(じかん)。けれど、別(べつ)の資料(しりょう)では一刻が二時間で一時が30分と表記(ひょうき)されてありました。どちらが正しい(ただしい)のでしょう?
これを説明(せつめい)するには、まず、江戸時代(えどじだい)の時刻制度(じこくせいど)の説明(せつめい)をしなくちゃいけないね。江戸の庶民(しょみん)は、日の出(ひので)、日の入り(ひのいり)の時間(じかん)をもとに明け(あけ)6つ、暮れ(くれ)6つを決め(きめ)、これを基点(きてん)として時間を定める(さだめる)不定時法(ふていじほう)を用いて(もちいて)いたんだ。 その6等分(とうぶん)された時間のことを「一刻(いっとき)」と言った(いった)んだよ。おそらく質問(しつもん)のようなまちがいが起きる(おきる)のは「一刻(いっとき)」を「一時(いっとき)」としてしまったために起きて(おきて)いることじゃないかな?「一刻」の長さ(ながさ)は春分(しゅんぶん)、秋分(しゅうぶん)以外(いがい)では、昼(ひる)と夜(よる)で「一刻」の長さが違う(ちがう)ことになり、夏至(げし)、冬至(とうじ)では、その長さが逆転(ぎゃくてん)してしまうので、夏至や冬至の日などは、昼と夜の「一刻」の長さが一時間以上(いじょう)も違って(ちがって)いたんだよ。 だから「一刻」が単純(たんじゅん)に二時間にはならないんだよ。そして、時刻を知らせる(しらせる)ために室町時代(むろまちじだい)後半(こうはん)から鐘(かね)が鳴らされる(ならされる)ようになり、時刻を時鐘(じしょう)の数(かず)で呼ぶ(よぶ)ようになったんだ。時鐘は、昼に9つ打ち(うち)、一刻ごとに1つずつ減らして(へらして)4つの次(つぎ)は深夜(しんや)の9つに戻り(もどり)、また一刻ごとに1つずつ減らして4つの次が昼の9つとなるんだ。昼と夜で同じ(おなじ)数があるので、これらを区別(くべつ)して「暁(あかつき)9つ、8つ、7つ」「明(あけ)6つ」「朝5つ」「朝4つ」「昼9つ」「昼8つ」「昼7つ」「暮れ(くれ)6つ」「夜5つ、4つ」と読んだ(よんだ)んだよ。
時間(じかん)表示(ひょうじ)の件(けん)について質問(しつもん)です。 午前(ごぜん)11時から1時間30分会議(かいぎ)を実施(じっし)。この場合(ばあい)、終了時間(しゅうりょうじかん)表示は午後0時30分か、午後12時30分かどちらでしょうか?
これは、会議(かいぎ)スケジュールなどを書く(かく)時に、まちがえのないように伝える(つたえる)ために重要(じゅうよう)なことだよね。 こういう場合(ばあい)は、まず、12時間(じかん)表記(ひょうき)で書く(かく)のか、24時間表記で書くのかをきちんと決めないと(きめないと)いけないんだよ。 12時間表記の場合は、午前11時から午後0時30という書き方で、 24時間表記の場合は、11時から12時30分という書き方になるんだよ。 午前・午後というのは、12時間表記の考え方(かんがえかた)なので正午(しょうご)を過ぎると(すぎると)午後0時からスタートになるんだよ。 これはみんなけっこうまちがいやすいので注意(ちゅうい)してね。
午後(ごご)1時のことを午後13時のように、24時間(じかん)表記(ひょうき)に午前(ごぜん)・午後をつけるのはまちがいでしょうか?
これは、わりと12時間表記と、24時間表記が、ごっちゃになっているために、よくまちがえてしまう言い方(いいかた)なんだよ。基本的(きほんてき)に午前・午後という考え方(かんがえかた)は、12時間表記で、正午(しょうご)という点(てん)を境(さかい)にして、午前と午後にわけられているんだ。だから午前は0時から始まって(はじまって)11時まで、午後も同じく(おなじく)0時から11時までとなるんだ。つまりここでは、12時間表記では、12時という言い方が存在(そんざい)しないのがわかるかな?12になった途端(とたん)に0にリセットされるからなんだ。24時間表記の場合(ばあい)は、区切る(くぎる)ことなく1日24時間を、順(じゅん)に表記していくやり方だから、午前と午後という考え方がないんだよ。だから24時間表記に午前・午後をつけるのはおかしな話だよね。わかってくれたかな?
1億(おく)数える(かぞえる)のにかかる時間(じかん)を教えて(おしえて)ください
いやいや今回(こんかい)は難問(なんだい)が多い(おおい)なぁ。さてこればかりは、個人差(こじんさ)もあるので、なんとも言えない(いえない)ところなんだ。1億(おく)までの数字(すうじ)を書く(かく)のも大変(たいへん)だけど、1億を数える(かぞえる)というのも大変で、チャレンジした人はいないんじゃないかな?途中(とちゅう)で間違えて(まちがえて)しまいそうだしね。たとえば「1億」というのは口で言えば1秒(びょう)以下(いか)で言えるけど、1億の1つ前の「99、999、999」は「きゅうせんきゅうひゃくきゅうじゅうきゅうまんきゅうせんきゅうひゃくきゅうじゅうきゅう」とたったひとつの数字を数えるだけなのに、5秒もかかってしまうからね。これは時間(じかん)をかけて少しずつ計り(はかり)ながら調べて(しらべて)みるしかないんじゃないかな。ごめんね。
3時12分前(まえ)と、2時48分とでは、時刻(じこく)が早い(はやい)のはどちらか。それとも同じ(おなじ)なのか?
これは、おもしろい質問(しつもん)だね。時刻(じこく)の言い方(いいかた)は、ふつうに何時何分(なんじなんぷん)という他(ほか)に、何時何分過ぎ(すぎ)、何時何分前(まえ)というような言い方もするからね。でも言い方は違っても(ちがっても)、3時12分前と、2時48分とは同じ時刻なんだよ。どこの時を基準(きじゅん)に言うかの違いだけなんだよ。
午前(ごぜん)10時から午後(ごご)12時15分の正味時間数[しょうみじかんすう=実時間数(じつじかんすう)]について
この質問(しつもん)は、非常(ひじょう)に難しい(むずかしい)質問だね。午前(ごぜん)10時から午後(ごご)12時15分[=24時15分]の間(あいだ)に、どんなことをやったのかにもよるからね。それからそれぞれやった内容(ないよう)によってその定義(ていぎ)が変わって(かわって)くるんだよ。なのでここでは「労働(ろうどう)」を例(れい)にしてお話(おはなし)していくね。
「正味労働時間数(しょうみろうどうじかんすう)」あるいは「実労働時間数(じつろうどうじかんすう)」は、働いて(はたらいて)いる人が実際(じっさい)に労働した時間数のこと。休憩時間(きゅうけいじかん)はもちろん除く(のぞく)よ。で、事務所(じむしょ)の就業規則(しゅうぎょうきそく)で定められた(さだめられた)正規(せいき)の始業時刻(しぎょうじかん)を、午前10時、終業時刻(しゅうぎょうじかん)を午後6時とすると、これが「所定内労働時間数(しょていないろうどうじかんすう)」という扱い(あつかい)になるんだ。その間に1時間の昼休み(ひるやすみ)があったとすれば、所定内労働時間数は7時間だよね。
そして、所定内労働時間以降(いこう)の時間は「所定外労働時間数(しょていがいろうどうじかんすう)」となるんだ。つまり残業(ざんぎょう)だね。その「所定外労働時間数」の間に2時間の休憩(きゅうけい)をとったとすれば、5時間15分。で7時間と5時間15分をたして[正味労働時間数=実労働時間数]は12時間15分ということになるんだ。これが正味加工時間数[しょうみかこうじかんすう=実加工時間数(じつかこうじかんすう)]になると計算方法(けいさんほうほう)は違って(ちがって)きて、機械(きかい)の準備(じゅんび)や清掃(せいそう)、機械を動かして(うごかして)いる時間、検査(けんさ)をしたり、手作業(てさぎょう)をしている時間とかを合計(ごうけい)したものになるんだよ。これらの考え方(かんがえかた)は、企業(きぎょう)の生産管理(せいさんかんり)などに使われる(つかわれる)ことが多い(おおい)んだよ。
小一時間(こいちじかん)って何分間(なんぷんかん)ですか? 一時(いっとき)って何時間(なんじかん)ですか?
これはおもしろい質問(しつもん)だね。よく会話(かいわ)の中で使う(つかう)言葉(ことば)だけど、具体的(ぐたいてき)に「何分間(なんぷんかん)?」って聞かれる(きかれる)となんとも返答(へんとう)に困って(こまって)しまうよね。ただ正確(せいかく)に「小一時間(こいちじかん)」が何分かというのは、定義(ていぎ)がなくて「1時間未満(みまん)」というぐらいしか言えない(いえない)んだ。でも「小一時間打ち合わせ(うちあわせ)をしよう」なんて言われた時には、1時間を超えて(こえて)しまうことも多い(おおい)けどね。さて次(つぎ)の「 一時(いっとき)」は「「一時も休む(やすむ)ひまがない」というように「少し(すこし)の間(あいだ)。しばらく」という意味(いみ)に使われる場合(ばあい)と、「一時の勢い(いきおい)がなくなった」というように「ある一時期(いちじき)」と使われる場合があるんだ。その他(ほか)には「昔(むかし)の時間区分(くぶん)」で「一時」は、一昼夜(いっちゅうや)を12等分(とうぶん)する定時法(ていじほう)では一時(いっとき)が今の二時間にあたるんだよ。わかってくれたかな。
なぜ1日は24時間(じかん)なんでしょうか?誰(だれ)が24という数字(すうじ)に決めた(きめた)んでしょうか?何度(なんど)考えても(かんがえても)わかりません!ぜひ教えて(おしえて)ください・・・・・
この質問(しつもん)はよくもらう質問だけど、改めて(あらためて)また答えて(こたえて)おくね。時間(じかん)のことを知る(しる)ためには、知っておかなければいけないことだからね。世の中(よのなか)の単位(たんい)がほとんど、10進法(しんほう)でできているのに、時計(とけい)だけが、12進法という中途半端(ちゅうとはんぱ)な数え方(かぞえかた)になっているのをみんな不思議(ふしぎ)に思う(おもう)のは無理(むり)のないことだよね。なぜ12になったかというと、今から4500年ぐらい前に、最初(さいしょ)に暦(こよみ)をつくった古代(こだい)バビロニアの人たちが、12進法という12で繰り上がる(くりあがる)計算方法(けいさんほうほう)を使って(つかって)いたからなんだ。その12進法をもとに、時間の単位がつくられ、1日は24時間。考え方としては12×2[12の倍数(ばいすう)]ということになったんだ。今は時計の針(はり)は1〜12に統一(とういつ)されているけれど、昔(むかし)のヨーロッパでは1〜24表示(ひょうじ)のものや、1〜6表示のものもあったんだよ。さらにフランス革命(かくめい)の時には、10進法の時間単位がつくられたこともあったんだよ。でも使いにくいのと、その後(ご)ナポレオンが皇帝(こうてい)になったことで、2年もたたずに廃止(はいし)されてしまったんだ。やはり長い間つかわれてきたものはそうそうカンタンに変えられる(かえられる)ものじゃないんだね。
夜中(よなか)の12時は午前(ごぜん)12時というのか午前0時というのかどちらが正しい(ただしい)のですか?お昼(おひる)の12時は午後(ごご)0時というのか午後12時というのかどちらが正しいのですか?また午前や午後をつけない場合(ばあい)は0時ですか?24時ですか?
こちらの質問(しつもん)もよくもらう質問だけど、あらためて説明(せつめい)させてもらうね。夜(よる)の12:00[24:00]あるいはお昼(おひる)の12:00という時刻(じこく)は、正確(せいかく)には午前(ごぜん)、午後(ごご)という分け方(わけかた)はできなくて、午前と午後の中間(ちゅうかん)にある点(てん)なんだよ。その点を境(さかい)にして午前、午後がわかれるんだ。なので、正しく(ただしく)は午前でも、午後でもないんだよ。けれどあえて言う(いう)とすれば、お昼の12時は「午前12時」あるいは「午後0時」。夜の12時は「午後12時」あるいは「午前0時」となるんだ。
24時間法(じかんほう)では、その日の始まり(はじまり)であれば0時、その日の終わり(おわり)であれば24時という言い方(いいかた)になるよね。
みんなからよくもらう質問(しつもん)の中から「楽しい(たのしい)時間(じかん)は短く(みじかく)感じる(かんじる)のに、つまらない時間(じかん)はどうして長く感じるの?」という質問を取り上げて(とりあげて)みたよ。いつも「どうしてかな?」って不思議(ふしぎ)に思って(おもって)いる人は是非(ぜひ)、読んで(よんで)みてね。
この現象(げんしょう)には、おもしろい公式(こうしき)があるんだよ。それは時間の感じ方(かんじかた)=仕事(しごと)の量(りょう)÷力(ちから)というものなんだ。「力」というのは、力を使う(つかう)仕事をするとか、そういうことではなく、仕事に対して(たいして)、どのぐらい集中(しゅうちゅう)するかということなんだよ。つまり、みんなと楽しく(たのしく)遊んで(あそんで)いる時には、みんな遊ぶことに全(ぜん)エネルギーを傾けて(かたむけて)いるよね。そうすると、力が大きくなって、時間は短く感じられる。それとは反対(はんたい)に、例えば(たとえば)、たいくつな授業(じゅぎょう)を聞いて(きいて)いたりする時には、ただ聞いているだけで力を使っていないから、力は小さくなり、時間が長く感じられるということなんだ。おもしろい公式でしょ。みんなも自分の毎日(まいにち)の生活(せいかつ)の中で、どんな時に時間が短く、あるいは長く感じられるかをこの公式に当てはめて(あてはめて)分析(ぶんせき)してみると、さらにおもしろいかも知れない(しれない)ね。
日本(にほん)では、なぜ「サマータイム」をやめてしまったのですか。
サマータイムとは、夏(なつ)の間(あいだ)だけ時計(とけい)の時間(じかん)を1時間(じかん)あるいは2時間進めて(すすめて)、昼(ひる)の明るい(あかるい)時間を有効(ゆうこう)に使おう(つかおう)という制度(せいど)なんだ。欧米(おうべい)では多く(おおく)の国(くに)で実施(じっし)されているけれど、日本では、戦後(せんご)に米軍(べいぐん)の占領政策(せんりょうせいさく)の一環(いっかん)として1948年5月から4年間実施されたけど、反対(はんたい)の声(こえ)が多く廃止(はいし)されてしまったんだ。原因(げんいん)は、日本のさまざまな制度(せいど)が整って(ととのって)おらず、結局(けっきょく)のところ、その分、労働時間(ろうどうじかん)が伸びて(のびて)しまったり悪い(わるい)影響(えいきょう)ばかりが出てしまったからなんだ。なにかすごく日本らしい理由(りゆう)だね。最近(さいきん)は、二酸化炭素(にさんかたんそ)の増加(ぞうか)による温暖化現象(おんだんかげんしょう)やヒートアイランド現象を防ぐ(ふせぐ)ために、再び(ふたたび)導入(どうにゅう)について検討(けんとう)しているみたいだよ。日本の夏はどんどん暑く(あつく)なって過ごし(すごし)にくくなってきているから、みんながおとなになる頃(ころ)には、日本でも普通(ふつう)にサマータイムが実施されているかもしれないね。
どうやって1秒(びょう)の長さ(ながさ)を決めた(きめた)のですか??
1秒という時間(じかん)はどんなふうに決まったのか。カンタンに1秒の歴史(れきし)を振り返って(ふりかえって)みようか。まず1秒という単位(たんい)ができたのは、紀元前(きげんぜん)1900年頃(ごろ)に栄えた(さかえた)古代(こだい)バビロニア文明(ぶんめい)の頃なんだ。当時(とうじ)のバビロニアの人たちは60進法(しんほう)という独自(どくじ)の計算方法(けいさんほうほう)を持って(もって)いて、それから1年(ねん)を12に割り(わり)、1日(にち)を24時間(じかん)、1時間を60分(ぷん)、1分を60秒(びょう)というように細かく(こまかく)割っていくことで「秒」という考え方(かんがえかた)をつくったんだ。
でもこれは太陽(たいよう)の動き(うごき)を基本(きほん)としてつくられたために、冬(ふゆ)と夏(なつ)では、実際(じっさい)の時間が1分もずれてしまうんだ。そこで18世紀(せいき)のヨーロッパで、1平均太陽日(へいきんたいようび)を24等分(とうぶん)した時間を「1平均太陽時(へいきんたいようじ)」とする時間の定義(ていぎ)が広まり(ひろまり)、それによって1平均太陽時の3600分の1が「1秒」となったんだ。でもこの「1秒」にも問題(もんだい)があって、地球(ちきゅう)の自転速度(じてんそくど)は一定(いってい)ではないために、正確さ(せいかくさ)に欠けて(かけて)いたんだ。その後(ご)1956年に、地球の公転周期(こうてんしゅうき)を元(もと)にした1秒の定義として「秒は、暦表示(こよみひょうじ)の1900年当初の太陽年(たいようねん)の1/31,556,925.9747倍(ばい) である」と決めた(きめた)んだよ。
とは言え(いえ)、地球の自転(じてん)、公転周期から割り出す(わりだす)方法(ほうほう)は、観測(かんそく)をしなければならないという問題(もんだい)もあり、1967年に原子時計(げんしどけい)をもととする「1秒」に変更(へんこう)されたんだよ。その定義はちょっと難しい(むずかしい)けど、「セシウム133原子(げんし)の基底状態(きていじょうたい)の2つの超微細準位間(ちょうびさいじゅんいかん)の遷移(せんい)に対応(たいおう)する放射(ほうしゃ)の9,192,631,770周期の継続時間(けいぞくじかん)」となっているんだ。振動(しんどう)する回数(かいすう)から決められた(きめられた)と思って(おもって)もらえればいいかな。この方法(ほうほう)は確かに(たしかに)揺るぎない(ゆるぎない)「1秒」という定義をつくったけれど、地球の自転はだんだんとゆっくりになっているので、この「1秒」の定義で決められた24時間を続けて(つづけて)いくと、実際(じっさい)の生活時間(せいかつじかん)とのずれが出てしまうんだ。それを調整(ちょうせい)するために入れられる(いれられる)のが「うるう秒」なんだ。たかが「1秒」とは言っても(いっても)、それが決まるまでには長い歴史(れきし)と、そしてそれを維持(いじ)していくための工夫(くふう)があるんだよ。
スペースシャトルで宇宙(うちゅう)へ行って(いって)帰って(かえって)きた人の時計(とけい)の時間(じかん)と、地球上(ちきゅうじょう)で、待って(まって)いた人の時計の時間は同じ(おなじ)ですか?
基本的(きほんてき)には、宇宙(うちゅう)に行って(いって)地球(ちきゅう)に帰って(かえって)きた人の時計(とけい)の時間(じかん)と、地球で待って(まって)いた人の時計の時間は同じ(おなじ)進み方(すすみかた)をしているので同じ(おなじ)なんだよ。でも宇宙で作業(さぎょう)をする時には、世界中(せかいじゅう)にあるいろいろな施設(しせつ)とのやりとりをしなければならないために、各国(かっこく)の現地時間(げんちじかん)で指示(しじ)を行うと時差(じさ)の関係(かんけい)で、混乱(こんらん)してしまうよね。そこで、宇宙で作業する場合(ばあい)には、打ち上げ時刻(うちあげじこく)から換算(かんさん)した時間「打ち上げ後時間(うちあげごじかん)」によって、すべてを行うようにしているんだよ。つまり打ち上げ時刻から何時間後(なんじかんご)に、推進(すいしん)ロケットを切り離す(きりはなす)とか、何10時間後に、船外活動(せんがいかつどう)を行うといったようにね。こうすることで、作業にかかわる宇宙船(うちゅうせん)の人も、各国(かっこく)の施設(しせつ)の人も一つの時間体系(じかんたいけい)のなかでスムースに作業を行うことができるんだ。
「時差(じさ)」でたとえば、東京(とうきょう)とニューヨークは「時差が14時間(じかん)ある」または、「-14時間」といいますが、東京が午後の5時の場合は、ニューヨークは午前の4時であり「時差が14時間ではなく、13時間だ」と思う(おもう)のですがどうして「東京とニューヨークは時差が14時間」というのでしょうか?
これは確か(たしか)に不思議(ふしぎ)に思う(おもう)けれど、理由(りゆう)はサマータイムにあるんだよ。ニューヨークではサマータイムが実施(じっし)されているので4月第1日曜日(にちようび)から10月最後(さいご)の日曜日までは、時差(じさ)が 13時間(じかん)でそれ以外(いがい)の期間(きかん)は14時間となるんだよ。 この時差13時間というのは、あくまでも時計(とけい)の文字盤上(もじばんじょう)の話(はなし)であって、実際(じっさい)の時差14時間は変わって(かわって)いないんだよ。
「時間(じかん)の呼び方(よびかた)」で
A.午前(ごぜん)1時とか午後(ごご)1時という呼び方と
B.1時[午前1時]、13時[午後1時]、24時[午後0時]という呼び方[つまり、1〜24時の呼び方]がありますが、
A/Bそれぞれその呼び方・表示法(ひょうじほう)をなんと呼ぶのでしょうか?
Bは「24時間表示(じかんひょうじ)」というんですよ。Aに関して(かんして)は、正式(せいしき)な言い方(いいかた)はないのですが、Bに対比(たいひ)させるならば「12時間表示」ということになりますね。一般的(いっぱんてき)には「12時間表示」という言葉(ことば)は使われない(つかわれない)けれど、時計(とけい)の製作(せいさく)に関わって(かかわって)いる人たちの間では時計の文字盤(もじばん)表示やデジタル表示の時にこのような用語(ようご)を使っているんだよ。
夜って何時(なんじ)からですか?あと深夜(しんや)って何時ですか?午前(ごぜん)で日が高く昇って(のぼって)いるのはだいたい何時頃(なんじごろ)ですか?最後(さいご)に夜明け(よあけ)って何ですか????
すごく、おもしろい質問(しつもん)だね。ふだんなにげなく使っている(つかっている)「夜(よる)」「昼(ひる)」「朝(あさ)」って言葉(ことば)、確か(たしか)に人によって使い方(つかいかた)は曖昧(あいまい)だよね。それじゃぁ、解説(かいせつ)するね。「夜」というのは「日の入り(ひのいり)から日の出(ひので)までの時間(じかん)」のことなんだよ。毎日(まいにち)の新聞(しんぶん)に、その日の「日の出」「日の入り」時刻(じこく)が載って(のって)いるので、それを見て、計算(けいさん)してみれば、その日の夜の時間がわかるよ。「日の出」「日の入り」時刻は毎日変わって(かわって)いくので、その日によって夜の時間は違って(ちがって)くるんだよ。
そして、次の「深夜(しんや)」の定義(ていぎ)についてだよ。「深夜」は「午前0時から日の出時までの時間」のことをいうんだよ。この時間も、日の出の時刻が毎日変わってくるから一定(いってい)ではないんだよ。
次の質問の「午前(ごぜん)で日が高く昇って(のぼって)いるのはだいたい何時頃(なんじごろ)か?」に答える(こたえる)ね。太陽(たいよう)が1日のうちで最も(もっとも)高くなる時を「南中(なんちゅう)」というんだ。日本(にほん)の標準時(ひょうじゅんじ)を決めて(きめている)いる東経(とうけい)135度(ど)の兵庫県明石(ひょうごけんあかし)では、ちょうど正午(しょうご)になるんだけど、各地(かくち)によってズレがあるので、はっきりとは言えないんだよ。しかもこの南中の時刻は、季節(きせつ)によって変化(へんか)するんだ。それは、地球(ちきゅう)の公転速度(こうてんそくど)が変化(へんか)することと、見た目の太陽の動き(うごき)が季節によって変化することが理由(りゆう)なんだよ。
そして最後(さいご)の質問(しつもん)「夜明け(よあけ)」は「日の出」時刻のことなんだよ。「日の出」「日の入り」については、その定義がとても一言(ひとこと)では説明(せつめい)できないので「時の教室(きょうしつ)」の理科(りか)のコーナーにものすごく詳しい(くわしい)解説が載っているので、そちらを読んでみてね。たくさんの質問ありがとね。
なぜ1日は24時間(じかん)なのか?誰(だれ)が決めた(きめた)の?いつから?
この質問(しつもん)は、よくもらう質問だけど、やっぱり世の中(よのなか)の単位(たんい)がほとんど、10進法(しんほう)でできているのに、時計(とけい)だけが、12進法という中途半端(ちゅうとはんぱ)な数え方(かぞえかた)になっているのをみんな不思議(ふしぎ)に思うのは無理(むり)のないことだよね。そこで、カンタンに説明(せつめい)するから、よく読んで(よんで)理解(りかい)してね。 なぜ12になったかというと、今から4500年ぐらい前に、最初(さいしょ)に暦(こよみ)をつくった古代(こだい)バビロニアの人たちが、12進法という12で繰り上がる(くりあがる)計算(けいさん)方法(ほうほう)を使って(つかって)いたからなんだ。その12進法をもとに、時間(じかん)の単位(たんい)がつくられ、1日は24時間。考え方(かんがえかた)としては12×2[12の倍数(ばいすう)]ということになったんだ。今は時計の針(はり)は1〜12に統一(とういつ)されているけれど、昔(むかし)のヨーロッパでは1〜24表示(ひょうじ)のものや、1〜6表示のものもあったんだよ。さらにフランス革命(かくめい)の時には、10進法の時間単位がつくられたこともあったんだよ。でも使いにくいのと、その後(ご)ナポレオンが皇帝(こうてい)になったことで、2年もたたずに廃止(はいし)されてしまったんだ。わかってくれたかな?
教えて(おしえて)いただきたいことがあります。お昼(ひる)の12時16分の表記(ひょうき)として正しい(ただしい)のはどれでしょうか。
1. am12:16
2. pm12:16
3. am 0:16
4. pm 0:16
お昼(ひる)の12:00あるいは夜(よる)の12:00(24:00)という時刻(じこく)は、正確(せいかく)には午前(ごぜん)午後(ごご)という分け方(わけかた)はできなくて、午前と午後の中間(ちゅうかん)にある点(てん)なんだよ。その点を境(さかい)にして午前、午後がわかれるわけなんだ。けれどあえていえば、お昼(ひる)の12時は「午前12時」あるいは「午後0時」。夜の12時は「午後12時」あるいは「午前0時」となるんだ。
ところがデジタル時計(どけい)の12時間(じかん)表示(ひょうじ)では、昼の12時はPM(ピーエム)12:00と表示されて、夜の12時はAM(エーエム)12:00と表示されるんだ。本当(ほんとう)は00:00と表示されれば、つぎの1:00までの間(あいだ)の時刻表示に違和感(いわかん)がないのだけれど、これはデジタル時計ができた時に、そう決まって(きまって)しまったために今もそうなっているんだ。
なので、デジタル表示では、2.の「pm12:16」と表示されるのが普通(ふつう)なんだよ。
時間(じかん)の表し方(あらわしかた)で、数字(すうじ)の右肩(みぎかた)に。3゜12’23”と書く(かく)方(かた)が時々(ときどき)いますが、この表し方(あらわしかた)でよいのですか?
この表現(ひょうげん)は「角度(かくど)や、位置(いち)」を表す(あらわす)ときに使われる(つかわれる)んだ。角度でも「度(ど)」以下(いか)は「分(ふん)」「秒(びょう)」という呼称(こしょう)が使われるので混同(こんどう)しやすいので気をつけてね。時刻(じこく)の表し方は3時12分23秒なら3:12:23と書くのが正しい表記(ひょうき)なんだよ。
25年後(ねんご)には時の概念(がいねん)すらなくなるというのは本当(ほんとう)ですか?
これは初めて(はじめて)聞いた(きいた)話だね。たしかに現代(げんだい)は、いろいろな物事(ものごと)の変化(へんか)するスピードがアップしているし、24時間(じかん)営業(えいぎょう)のお店も増え(ふえ)、夜(よる)になってもずっと人間(にんげん)は動き回って(うごきまわって)いるようになったよね。そういう意味(いみ)では、昔(むかし)よりも時とか時間とかに対する(たいする)考え方(かんがえかた)はどんどん希薄(きはく)になっているんじゃないかな?でも時というものは、この宇宙(うちゅう)が生まれた(うまれた)時からずっと未来(みらい)に向かって(むかって)いるもので、人間(にんげん)が意識(いしき)しようがしまいが、ずっと存在(そんざい)しているものなんだよ。時間の感覚(かんかく)がなくなることはあるかもしれないけれど、時の概念(がいねん)はずっとあり続ける(つづける)んじゃないかな?
どうして時差(じさ)があるの?時差って何?
地球(ちきゅう)は回って(まわって)いて、太陽(たいよう)の方に向いた時が昼(ひる)、太陽と逆側(ぎゃくがわ)になった時が夜になるよね。でも昼と夜とは一瞬(いっしゅん)で切り替わる(きりかわる)んじゃなくて、太陽が東から昇って(のぼって)、西に沈む(しずむ)まで約半日(やくはんにち)の時間(じかん)をかけて変わっていくよね。これは、地球が回っているからなんだよ。世界(せかい)の国の中でわりと小さい国の日本でも、北海道(ほっかいどう)と沖縄(おきなわ)では、日の出(ひので)の時刻(じこく)と日の入り(ひのいり)の時刻には夏では1時間以上(いじょう)もの違い(ちがい)があるんだよ。
さて、これが遠く(とおく)の国だったらどうだろう?日本が朝なのに、その国では真夜中(まよなか)なんてことが起きて(おきて)しまうよね。もし世界中(せかいじゅう)が共通(きょうつう)した同じ(おなじ)時間を使っていたら、不便(ふべん)なことこの上ないよね。そこで、地球を縦(たて)に24にわけて、順番(じゅんばん)に1時間ずつ時間をずらしたのが「時差(じさ)」なんだ。この「時差」があることで、生活時間(せいかつじかん)と日の出、日の入りの時刻がある程度(ていど)一致(いっち)して暮らし(くらし)やすくなるんだよ。でも夏は日の出の時刻が早く、昼の時間が長すぎるために夏の間だけ、さらに1時間早めたサマータイムを生活時間として使っている国も多いんだよ。「ときをまなぼう」の「時の教室(ときのきょうしつ)」にはこうした「時差」の話しとかがいっぱい載って(のって)いるよ。そっちも読んで(よんで)みてね。
【24時間制(じかんせい)】という言葉(ことば)が俗(ぞく)にありますが、
06:00
07:00
|
12:00
13:00
|
22:00
23:00・・・・・
と、きたら つぎは【24:00】が正しい言い回し(いいまわし)なのでしょうか?
【00:00】が正しいのでしょうか?
正確(せいかく)に言えば00:00で振り出し(ふりだし)に戻る(もどる)ということなんだ。そこから新しい1日がまた始まる(はじまる)ということなんだよ。じっさいに24時間(じかん)表示(ひょうじ)のデジタル時計でも23:59のあとは00:00になるからね。でも言葉(ことば)で言ったり書いたりする場合(ばあい)はちょっと事情(じじょう)が違う(ちがう)んだよ。実際(じっさい)に24時15分スタートとか、テレビ番組(ばんぐみ)の時に使われたり(つかわれたり)しているよね。さらにテレビなどの収録(しゅうろく)スタジオでは25時終了(しゅうりょう)なんて表記(ひょうき)も使われているしね。これは人間(にんげん)の生活(せいかつ)サイクルが、1日24時間以上(いじょう)の時間の中で活動(かつどう)するようになったからじゃないかな?
日本(にほん)の旧暦【きゅうれき:太陰太陽暦(たいいんたいようれき)】では閏月(うるうづき)があって、1年が13ヶ月ある年があったそうですね。そこで疑問(ぎもん)です。
1.その閏月はそのころの日本の月の呼び名【睦月(むつき)、水無月(みなづき)など】ではなんと呼ばれて(よばれて)いたのですか?
2.その閏月は1年の13番目の月として12番目の月のあとにあったのでしょうか?月名が数字(すうじ)ならただ12月の後に13月があるだけですが・・・
今の暦(こよみ)に慣れて(なれて)いると確かに(たしかに)不思議(ふしぎ)に思う(おもう)よね。
まず1つ目の質問(しつもん)については、これは閏月(うるうづき)の前の月の名前(なまえ)の前に「閏」を入れ、たとえば「閏五月(うるうごがつ)」「閏如月(うるうきさらぎ)」というような言い方(いいかた)になるんだよ。
2つ目の「閏月の入れ方(いれかた)」は規則(きそく)があって、約(やく)3年に1度(ど)、閏月をつくり1年を13ヶ月としていたんだよ。その閏月は二十四節気(にじゅうしせっき)の「中(ちゅう)」をふくまない月に入れるということになっているんだ。太陰太陽暦(たいいんたいようれき)では月の満ち欠け(みちかけ)を暦の基本(きほん)としているので、新月(しんげつ)から新月まで周期(しゅうき)【29.53日】と二十四節気の「中」がくる周期【約30.44日】のズレがでてくるんだよ。ふつうの月【新月から新月まで】では二十四節気の「気(き)」と「中」がひとつずつ入るんだけれど、このズレによって「中」の入らない月ができてしまうんだ。なので、その月を閏月として暦のズレを調整(ちょうせい)していたんだよ。「中」は月の名前(なまえ)を決める(きめる)という役割(やくわり)も持って(もって)いるので、最初(さいしょ)に1つ目の質問(しつもん)にいったように月の名前もつけられないということなんだよ。
先日(せんじつ)2個(こ)のストップウォッチの測定時間(そくていじかん)がずれているような気がしたので、販売店(はんばいてん)に持って(もって)行って(いって)尋ねた(たずねた)ところ、「電話(でんわ)の時報(じほう)の音に合わせてスタートして、1日後(ご)また時報とのずれを聞けば(きけば)、正確(せいかく)かどうかわかる」と言われました。1/100秒(びょう)の精度(せいど)を聞いて(きいて)いるのに、音を聞いてからスタートスイッチを人が押して(おして)いたのでは正確(せいかく)かどうかわからないのではと尋ねると、「それしか精度を確かめる(たしかめる)方法(ほうほう)はない。SEIKOもそうやって検査(けんさ)している。」と言われました。本当(ほんとう)なのでしょうか?機械(きかい)で測ったり(はかったり)しないのでしょうか?
精度(せいど)は決して(けっして)人がスイッチを押して(おして)確認(かくにん)しているのではなくクォーツテスターという機械(きかい)で検査(けんさ)しているんだよ。
ストップウオッチに限らず(かぎらず)クォーツ時計は回路(かいろ)に組み込まれて(くみこまれて)いるクォーツ【水晶(すいしょう)】の精度によって時計の精度が確定(かくてい)するんだ。一般的(いっぱんてき)な水晶は発振数(はっしんすう)にある程度(ていど)のバラツキがあり、そのバラツキが公差[こうさ:たとえば月差(げっさ)±30秒(びょう)]に入っているかどうかをクォーツテスターで検査しているんだよ。安心(あんしん)してくださいね。
子どもに時間(じかん)を返せ(かえせ)としかられます。その時間は2005年1月18日PM7:00から9:30までです。時間は返せるはずがないのですが、子どもにどうすればいいですか?時間を返せる科学的(かがくてき)な方法(ほうほう)があれば教えて(おしえて)ください。
きっと子どもさんにとってはとても大切(たいせつ)な時間(じかん)だったんですね。でもどんなに科学(かがく)が進歩(しんぽ)しようとも、時間を逆戻り(ぎゃくもどり)させることはできないんですよ。
時間はこの宇宙(うちゅう)が始まった(はじまった)時からずっと、未来(みらい)に向かって(むかって)進んでいるもので、これはどんな人間(にんげん)にも動物(どうぶつ)にも平等(びょうどう)なものなんです。だから、その2時間30分という時間のことを思い悩んで(おもいなやんで)、多くの貴重(きちょう)な時間をムダにするよりも、まだ未来にある手つかずの時間を有意義(ゆういぎ)に使うことの方が大事(だいじ)なのではないでしょうか?お子さんにもそのように説明(せつめい)してあげたらいかがですか?
昼(ひる)の12時は、午前(ごぜん)、午後(ごご)でいうと、午前12時と読み(よみ)ますか?それとも、午後何時(なんじ)というのでしょうか?教えて(おしえて)いただけないでしょうか?
この質問(しつもん)もよくもらう質問(しつもん)なんだ。正確(せいかく)には「お昼(ひる)の12時」は「正午(しょうご)」と言う(いう)んだよ。「正午」は、午前(ごぜん)と午後(ごご)のわかれめで、午前でも午後でもないんだ。午前と午後の間(あいだ)にある線(せん)みたいなものって考えてもらえばいいかな。だから「お昼の12時」の前(まえ)は「午前」。そのあとは「午後」ということなんだ。午前と午後を12時間ずつに区切って(くぎって)言う言い方(いいかた)では、正午を過ぎた時点で 午後0時となるんだよ。つまり11時59分59秒・・・・・のあとは12時ではなく0時になるということ。正午を過ぎた12時30分と言う言い方は24時間で数えているので、そもそも午前と午後という言い方自体(じたい)がないんだよ。わかってくれたかな?
1分はどうしてどうして60秒なのか
この質問(しつもん)はみんなからよくもらう質問(しつもん)だけど、あらためて答える(こたえる)ので、よく読んで(よんで)みてね。
太陽(たいよう)の動き(うごき)を観測(かんそく)すると、その動きは円(えん)を描いて(えがいて)いるよね。古代(こだい)バビロニアの人たちは、すでに、角度(かくど)の1度(ど)は、円周(えんしゅう:えんのまわり)の360分の1(360ぶんの1)という考え方(かんがえかた)を発見(はっけん)していて、秒(びょう)という単位(たんい)を決める(きめる)ときに、円運動(うんどう)をしている太陽の動きを観測してだしたんだ。だから360度という数字が基礎(きそ)になっているんだよ。
円運動をしている太陽が1周(1しゅう)まわると一日、それが約(やく)30回くりかえされると一月、さらにそれが12回続く(つづく)と1年というように観測をすることで、暦の基礎ができていって、今度(こんど)はその逆(ぎゃく)にその一年をどんどん細かく(こまかく)わけていくことで1秒という単位ができたんだ。ちょっと下の計算(けいさん)を見てね。
1年と1日の数え方(かぞえかた)が、12進法(しんほう)で、1時間と1分が60進法で、組み立て(くみたて)られていて、1年=3153万6000秒は、1分60秒×60分×24時間×365日ということに決められたんだ。 だから、なぜ60秒なのかというと、古代バビロニアの人たちが使っていた12進法、60進法がもとになっているからなんだ。
時間(じかん)の始まり(はじまり)はいつですか?
これは、時間(じかん)のことを考えた(かんがえた)時に、誰も(だれも)が不思議(ふしぎ)に思う(おもう)ことだよね。時間は、この宇宙(うちゅう)ができた時から始まって(はじまって)、それからずっと未来(みらい)に向かって(むかって)一方向(いちほうこう)に進んで(すすんで)いるものなんだよ。その時間は、止まる(とまる)ことなく、ずっとずっと続いて(つづいて)いくんだよ。宇宙は、今も広がり(ひろがり)続けているからね。
江戸時代(えどじだい)の人はあまり時間(じかん)を気にしないで生活(せいかつ)していたのに、いつから今のように時間を気にするようになったのですか?
これは、夜(よる)を明るく(あかるく)する照明器具(しょうめいきぐ)が一般(いっぱん)に普及(ふきゅう)するようになってからだろうね。それまでは真っ暗(まっくら)な夜に行動(こうどう)する人たちはいなかったし、極端(きょくたん)に言えば(いえば)、日の出(ひので)とともに起き(おき)、日が沈んで(しずんで)しまえば、あとは寝る(ねる)だけという生活(せいかつ)だったんだよ。けれど、照明器具の普及によって、その気になれば、一晩中(ひとばんじゅう)、明るい中で暮らす(くらす)ことができるようになったんだ。そうなると、きちんと時間(じかん)というものを意識(いしき)しないと、寝る(ねる)時間、起きる時間というのもあやふやになってしまうからね。そうした生活の中に、時計(とけい)という道具(どうぐ)が入り込む(はいりこむ)ようになって、人々(ひとびと)は、時間の過ぎて(すぎて)いく様(さま)を自分(じぶん)の目でつねに確かめられる(たしかめられる)ようになった。そこでも徐々(じょじょ)に、時間への意識(いしき)が高まって、さらには一人一人が時計を身(み)につけて行動(こうどう)するようになり、その時計がどんどんと正確になって、それにつれて、人々はもっともっと時間を意識するようになっていったんじゃないかな?
不定時法(ふていじほう)から定時法(ていじほう)に変更(へんこう)されたことで、政府(せいふ)で働く(はたらく)人や商人(しょうにん)、農民(のうみん)の生活(せいかつ)はどのように変わった(かわった)のですか。
不定時法(ふていじほう)から、定時法(ていじほう)への切り替え(きりかえ)は、明治(めいじ)5年12月3日[=明治6年1月1日]の明治の改暦(かいれき)の時だったんだよ。改暦をすると決まって(きまって)からの間(あいだ)に1ヶ月(かげつ)もないために、告知(こくち)がゆきとどかず、結局(けっきょく)のところ新暦(しんれき)が全国(ぜんこく)に広がるのには50年以上(いじょう)もかかってしまったんだ。不定時法から、定時法へ変わった(かわった)ことによって、まず変わったのは、夏(なつ)や冬(ふゆ)の出勤時間(しゅっきんじかん)だろうね。不定時法は、夏と冬で昼(ひる)の長さ(ながさ)が変わるから、昼の長い夏には長い時間働き(はたらき)、冬には夏よりも短い(みじかい)時間働くという生活が、夏も冬も同じ時間だけキッチリ働くという生活に変わることになったんだ。農家(のうか)の人など畑(はたけ)で、お寺(てら)の鐘(かね)の音(ね)を聞いて(きいて)、時刻(じこく)を知って(しって)いた人たちは、定時法になってからは冬などはずいぶん暗く(くらく)なってから鐘が鳴る(なる)ようになったなぁなんて思って(おもって)いたかも知れない(しれない)ね。
この改暦(かいれき)でいちばん大きな影響(えいきょう)を受けた(うけた)のは、政府(せいふ)で働く人たちなんだ。12月3日が1月1日になってしまったことで、1ヶ月分の給料(きゅうりょう)がもらえなくなってしまったんだからね。明治6年は旧暦(きゅうれき)のうるう年で、13ヶ月ある年だったんだ。財政難(ざいせいなん)の明治政府(めいじせいふ)は、13ヶ月目の給料を払わない(はらわない)ようにするために、強引(ごういん)にこの改暦を行った(おこなった)んだよ。