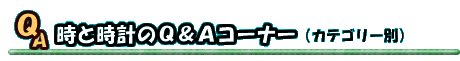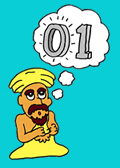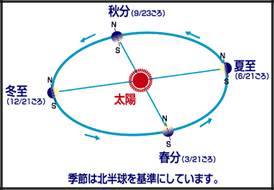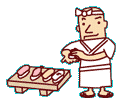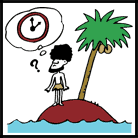4月になるとよくニュースなどで見られる「入社式(にゅうしゃしき)」ですが、外国(がいこく)では、ほとんど「入社式」をすることがないって本当(ほんとう)ですか?
これはおもしろい質問(しつもん)だね。「入社式」と呼ばれる(よばれる)ものは外国にはほとんどないのは本当だよ。日本(にほん)では各企業(かくきぎょう)が大学(だいがく)や高校(こうこう)を卒業(そつぎょう)した人をまとめて採用(さいよう)するので、「入社式」というものをやるけれど、外国では時期(じき)に関わらず(かかわらず)個人(こじん)の仕事(しごと)の実力(じつりょく)や実績(じっせき)から判断(はんだん)して人を採用しているので入社時期(じき)がバラバラなんだ。だから「入社式」をやろうにもやれないというわけなんだ。日本でも、だんだんとそんな風(ふう)になっていくんじゃないかな?
同じ(おなじ)4月生まれ(うまれ)なのに、4月1日に生まれた人と、4月2日に生まれた人が違う(ちがう)学年(がくねん)になってしまうのはなぜですか?
これは、タイムリーな質問(しつもん)だね。たしかに、これは疑問(ぎもん)に思う(おもう)よね。でも、ちゃんとした規則(きそく)に則って(のっとって)決められて(きめられて)いることなんだよ。まず、小学校(しょうがっこう)に入る(はいる)のは「満(まん)6歳(さい)になってから」と決められているんだ。満年齢(まんねんれい)は、生まれた日から計算(けいさん)して誕生日(たんじょうび)の前(まえ)の日に1歳が加えられる(くわえらえる)と法律(ほうりつ)で決まっているんだよ。だから4月1日に生まれた人が、満6歳になるのは3月31日、4月2日に生まれた人は4月1日となって、学年(がくねん)が違って(ちがって)しまうことになるんだよ。よくうるう年の2月29日に生まれた人は4年に1度(ど)しか年をとらないなんていうけれど、この満年齢の決まりによって、ちゃんと28日に、1歳ずつ歳をとっていくんだ。わかってくれたかな?
アメリカの学校(がっこう)の夏休み(なつやすみ)はすごく長い(ながい)と聞きました(ききました)が、いったいどのぐらいの長さなんですか?
夏休み(なつやすみ)は、楽しく(たのしく)遊んで(あそんで)いる間(あいだ)にすぐに終わって(おわって)しまうものだよね。もっと長ければ(ながければ)いいのにって、誰も(だれも)が思う(おもう)よね。日本(にほん)の学校(がっこう)の夏休みはと言うと(いうと)、地域(ちいき)によっても違う(ちがう)けど、だいたい40日ぐらいだよね。期間(きかん)は1学期(がっき)と2学期の間だよね。アメリカの場合(ばあい)は6月から8月までのだいたい3ヶ月(かげつ)ぐらいで、新年度(しんねんど)の新学期(しんがっき)が9月にスタートするんだよ。日本ではつぎの学期に備える(そなえる)ということで、たんまりと夏休みの宿題(しゅくだい)が出るけれど、アメリカの場合はつぎの学年(がくねん)に上がる前なので、宿題はないんだ。というと、とてもうらやましく思う(おもう)かもしれないけど、日本の春休み(はるやすみ)に宿題がないと思えば納得(なっとく)できるかな?でも、長いのは?という疑問(ぎもん)もあるかと思うけど、アメリカは日本と違って(ちがって)祝祭日(しゅくさいじつ)があまりないんだ。日本は少し(すこし)ずつ取る(とる)けれど、アメリカはまとめてどかん!という感じ(かんじ)かな。これも国民性(こくみんせい)からくるものかな?
どうして日本(にほん)の学校(がっこう)は4月に始まる(はじまる)の?
日本(にほん)の学校制度(がっこうせいど)は、イギリスやフランスのものを参考(さんこう)にしているために、もともとは9月から新学期(しんがっき)が始まって(はじまって)いたんだよ。唯一(ゆいいつ)例外(れいがい)で、4月に始まっていたのが、軍(ぐん)の士官学校(しかんがっこう)なんだ。
つまり、8月に卒業(そつぎょう)した学生(がくせい)は、翌年(よくねん)の4月に士官学校に入る(はいる)までに、8ヶ月も間が空いて(あいて)いたんだ。すると、その8ヶ月をムダにしたくないために、優秀(ゆうしゅう)な学生はその上の学校にいってしまうんだ。しかも、大学(だいがく)に進む(すすむ)ことで兵役(へいえき)を免除(めんじょ)されるという特典(とくてん)もあったからね。そうすると、士官学校入学者(にゅうがくしゃ)の質(しつ)がおちてしまうということで、明治時代(めいじじだい)に軍部(ぐんぶ)がすべての学校の始まりを4月に揃えて(そろえて)しまったんだよ。なんとも強引(ごういん)な話だよね。
「今日(きょう)」という漢字(かんじ)の読み仮名(よみがな)は「きょ う」「き よう」なのかどっちですか?
こちらもおもしろい質問(しつもん)だね。「今日(きょう)」と書いて(かいて)「きょう」と読む(よむ)ようになったのは、日本語(にほんご)の歴史(れきし)で言うと(いうと)つい最近(さいきん)のことなんだよ。それまでは「今日」とかいて「けふ」と読んでいたんだよ。「けふ」の「け」は「今朝(けさ)」とかと同じ(おなじ)「け」で「こ:此」の意味なんだ。「ふ」は「ひ:日」の意味だよ。だから無理(むり)にわけるとしたら「きょ う」なんだろうね。
日本(にほん)は日の出ずる国(ひのいずるくに)と言われる(いわれる)のはなぜですか?
これはおもしろい質問(しつもん)だよね。日本(にほん)が「日本は日の出ずる国(ひのいずるくに)」と言われる(いわれる)のは、607年に、当時(とうじ)倭国(わこく)という名前(なまえ)だった日本が、隋(ずい=現在の中国:げんざいのちゅうごく)に、第2回目の遣隋使(けんずいし)を派遣(はけん)した時に聖徳太子(しょうとくたいし)が託した(たくした)「日出ずる処の天子(ひいずるところのてんし)、書を日の没する処の天子に致す(しょをひのぼっするところのてんしにいたす)」という国書(こくしょ)に由来(ゆらい)するんだよ。 この「日 出ずる処」を表す(あらわす)言葉(ことば)として「日ノ本(ひのもと)の国」という言葉になり、今の国名(こくめい)の日本となったと言われているんだ。
さて、中国の大きさから比べたら(くらべたら)日本は、海に浮かぶ(うかぶ)小国(しょうこく)に過ぎなかった(すぎなかった)というのに、聖徳太子はあえて日本を「日出ずる処」、中国を「日の没する処」という表現を使った(つかった)んだよ。それにより、小国とは言え、大国(たいこく)におもねることなく、対等(たいとう)の外交(がいこう)を実現(じつげん)したいという意志(いし)を込めて(こめて)の文章(ぶんしょう)だったんだ。一度(いちど)は隋の皇帝(こうてい)を激怒(げきど)させたものの、その後(ご)隋との対等な外交を行える(おこなえる)ようになったんだ。
みんなからよくもらう質問(しつもん)の中から「学校(がっこう)の時間割(じかんわり)はいつから使われる(つかわれる)ようになったのですか。」という質問を取り上げて(とりあげて)みたよ。いつも「どうしてかな?」って不思議(ふしぎ)に思って(おもって)いる人はぜひ、読んで(よんで)みてね。
毎日(まいにち)、学校(がっこう)に通って(かよって)いて、これはきっとみんなが疑問(ぎもん)に思う(おもう)ことだよね。それじゃ説明(せつめい)するね。日本(にほん)に教育制度(きょういくせいど)の基礎(きそ)ができたのは、明治(めいじ)5年8月のこと。「学制(がくせい)」が公布(こうふ)され、小学校(しょうがっこう)が全国(ぜんこく)につくられ、子どもたちすべてが学校に通い、学べる(まなべる)環境(かんきょう)を整備(せいび)し始めた(しはじめた)んだよ。この時の小学校にはすでに時間割(じかんわり)があったんだよ。というのも、教育制度が整う(ととのう)前の日本には、寺子屋(てらこや)や塾(じゅく)という学校に近い(ちかい)ものがもともとあり、そこでは武士(ぶし)や商人(しょうにん)の子どもたちに「読み(よみ)・書き(かき)・そろばん」などを教えて(おしえて)いたんだよ。そんな寺子屋や塾にも、きちんとした時間割があったんだよ。「学制」を決めた(きめた)明治政府(めいじせいふ)の人たちの中には、この寺子屋や塾出身(しゅっしん)の人たちも多かった(おおかった)から、自然(しぜんと)と似た(にた)時間割を採用(さいよう)したんじゃないかな?でも、さらに昔(むかし)に、フランシスコ・ザビエルなどの宣教師(せんきょうし)が日本にやってきて、布教(ふきょう)のために学校(がっこう)を建てた(たてた)時にも、ちゃんと時間割があったんだよ。けっこう古くからあるんだね。
パソコンとつながる未来(みらい)の時計(とけい)が紹介(しょうかい)されていましたが、その仕組み(しくみ)を教えて(おしえて)ください。いまの時計の仕組み(しくみ)はどのようになっているのですか?(根本育美さん/小学校5年生)
残念(ざんねん)なことに、サイトで紹介(しょうかい)していた「ラピュータ」は、すでに生産終了(せいさんしゅうりょう)になっているんだ。その理由(りゆう)としては、性能(せいのう)のよいコンピュータがどんどん小型化(こがたか)されて、カンタンに持ち歩ける(もちあるける)ようになったので、限られた(かぎられた)機能(きのう)を時計に詰め込む(つめこむ)必要(ひつよう)がなくなってきたことや、携帯電話(けいたいでんわ)の普及(ふきゅう)があげられるんだ。でもね、これからも、パソコンなどのネットワークにつなげて、いろいろなことができる腕時計(うでどけい)とか、テレビ電話(でんわ)ができてしまう腕時計とか出てくるかもしれないよ。
サンタクロースの住所(じゅうしょ)についての続報(ぞくほう)
先月[せんげつ:2004年11月号]あったサンタクロースの住所(じゅうしょ)について、読者(どくしゃ)の方から情報(じょうほう)をもらったよ。サンタクロースの故郷(こきょう)と言われているノルウェーからクリスマスカードが届く(とどく)サービスなど、いろいろなサービスがあるらしいよ。インターネットで、みんなも探して(さがして)みるとおもしろいよ。でも、締切り(しめきり)が12月の最初(さいしょ)の頃(ころ)だから、今年(ことし)のクリスマスにはちょっと間に合わない(まにあわない)かな。
さんたくろうすは、なんでそりのるの?
世界中(せいかいじゅう)すべてのサンタクロースが、トナカイに引かれた(ひかれた)そりに乗って(のって)くるわけじゃないんだよ。南半球(みなみはんきゅう)のオーストラリアでは、クリスマスの時期(じき)は夏(なつ)で、サンタクロースは海(うみ)からサーフボードに乗ってきたり、イルカに乗ってきたりするんだよ。ヨーロッパでも、オランダでは昔(むかし)、ロバに乗ってサンタクロースはやってきたんだよ。世界中のサンタクロースがどんな乗り物(のりもの)に乗ってやってくるのか、調べて(しらべて)みるとおもしろいよね。
サンタさんって、ほんとにいるの!?住所(じゅうしょ)は??返事(へんじ)くれるん???
年末(ねんまつ)になってクリスマスが近づいて(ちかづいて)くると、サンタさん関連(かんれん)の質問(しつもん)がでてくるよね。サンタさんの住んで(すんで)いるところは、グリーンランドであるとか、フィンランドであるとか、いろいろ言われて(いわれて)いるけど、きっとそんな場所(ばしょ)に縛られず(しばられずに)に、世界中(せかいじゅう)の子どもたちの心(こころ)の中に住んで(すんで)いるんじゃないかな?
どうしてイジワルッチがおめでた星(ぼし)にやってきたの?
楽しい(たのしい)質問(しつもん)をありがとね。イジワルッチは、イジワルが大好き(だいすき)な謎(なぞ)の宇宙人(うちゅうじん)。地球(ちきゅう)にやっていたのはたまたま地球の近く(ちかく)にやってきた時にあまりにも地球が青く(あおく)美しく(うつくしく)、そして楽しそうな星に見えたかららしいんだ。ちょっとからかいたくなってしまったんじゃないかな?いつもチョッチイにいろいろなイジワルやイタズラをするけれど、ドジばかりでたいしたことにはならないけどね。
海(うみ)はなぜ波(なみ)がくるの!
波(なみ)は、風(かぜ)と重力(じゅうりょく)によってつくられるんだよ。洗面器(せんめんき)に水を張って(はって)息(いき)を吹いて(ふいて)ごらん。水面(すいめん)にさざ波(なみ)ができるのがわかるよ。それと同じ(おなじ)原理(げんり)なんだよ。強く(つよく)吹けば大きな波が、軽く(かるく)吹けばさざ波ができるということなんだよ。持ち上げ(もちあげ)られた波が重力(じゅうりょく)で押し下げ(おしさげ)られた時、今度(こんど)は周り(まわり)の海水(かいすい)が持ち上げられて、波が繰り返し(くりかえし)発生(はっせい)するんだよ。
飛行機雲(ひこうきぐも)はなぜでるの?
飛行機雲(ひこうきぐも)と言っても(いっても)、雲のでき方(できかた)や種類(しゅるい)はたくさんあるそうなんだよ。高い空を飛ぶ(とぶ)ジェット機(き)のエンジンがつくる飛行機雲について説明(せつめい)するね。ジェット機が飛ぶのは高度(こうど)1万(まん)メートルくらいで、気温(きおん)は大変(たいへん)低くて(ひくくて)なんとマイナス30〜50度(ど)にもなるんだ。飛行機のジェットエンジンからでる高温(こうおん)の排気(はいき)ガスが、大気中(たいきちゅう)の水蒸気(すいじょうき)を急激(きゅうげき)に冷やす(ひやす)と、水蒸気が凝結(ぎょうけつ)して飛行機雲となるんだ。
??なぜ、チョッチイという名(な)?大勢(おおぜい)いるんでしょ???!?
この質問(しつもん)には、おめでた星(ぼし)の作者(さくしゃ)であるひこねのりおさんに直接(ちょくせつ)答えて(こたえて)もらったよ。
『チョッチイは、チョコチョコと動き回る(うごきまわる)小さい(ちいさい)宇宙人(うちゅうじん)で地球(ちきゅう)でいう妖精(ようせい)のようなかんじのものたちです。大勢(おおぜい)いて、組み体操(くみたいそう)の宇宙版(うちゅうばん)のようなもの[どんなものか作者もよくわらないのですが??]をしたり、チョコチョコとかわいい踊り(おどり)を踊る(おどる)という芸(げい)をもっています。好奇心(こうきしん)旺盛(おうせい)でどこにでも『チョコチョコ現れる(あらわれる)チイさい生き物(いきもの)』というわけで『チョッチイ』という名(な)をつけました。(ひこねのりお談)』
どうして夏(なつ)は、暑い(あつい)の?
暑い(あつい)というのは「空気(くうき)の温度(おんど)が高い(たかい)」ということなんだ。それでは、空気はどんなふうに暖められる(あたためられる)んだろう。太陽(たいよう)の光(ひかり)は、空気の中を通って(とおって)きて、地面(じめん)や海(うみ)などを暖めて、その熱(ねつ)が空気に伝わって(つたわって)空気が暖まるんだよ。それだけではなく、太陽の光で暖められた地面や海からは、暖かい間(あいだ)、ずっと赤外線(せきがいせん)が放出(ほうしゅつ)され、空気中(くうきちゅう)の二酸化炭素(にさんかたんそ)や水蒸気(すいじょうき)を暖めるんだ。二酸化炭素には、熱を逃がさない(にがさない)性質(せいしつ)があり、どんどんと熱がたまっていくんだ。地上(ちじょう)に降り注ぐ(ふりそそぐ)太陽の光が最も(もっとも)多い(おおい)のは、夏至(げし)の頃(ころ)、昼(ひる)の時間(じかん)が最も長く(ながく)、太陽の位置(いち)も最も高いからなんだ。その頃からずっと地表(ちひょう)は熱を出し続け(だしつづけ)、夏の7月下旬(げじゅん)や8月下旬がいちばん暑くなるということなんだ。最近(さいきん)では都会(とかい)などで、クーラーなどが出す熱が、気温(きおん)を上げていると問題(もんだい)になっているんだよ。
なぜ、夢(ゆめ)をみるの??
人間(にんげん)は寝て(ねて)いる時(とき)に、浅い(あさい)眠り(ねむり)と深い(ふかい)眠りを繰り返して(くりかえして)いるんだよ。夢はこの2つの眠りのうち、浅い眠りの時に見るんだ。この時には、感覚(かんかく)やひらめきにかかわる右脳(うのう)だけが動いて(うごいて)いるんだよ。その右脳がみんなに、空(そら)を飛んだり(とんだり)、冒険(ぼうけん)をしたりというような夢を見せているんだよ。夢はだいたいが、常識(じょうしき)では考え(かんがえ)られないような不思議(ふしぎ)な出来事(できごと)が多い(おおい)けれど、昼間(ひるま)起きた(おきた)印象的(いんしょうてき)な出来事や、寝る前に見たテレビ番組(ばんぐみ)などの1シーンが姿(すがた)を変えて(かえて)出てくることもあるんだよ。
石(いし)は、なぜいろいろな形(かたち)やいろいろな大きさ(おおきさ)があるの? なーぜーーー?
確か(たしか)に、石(いし)にはいろいろな形(かたち)、色(いろ)、大きさ(おおきさ)のものがあるよね。その石が「どんなふうにしてできたか」でわけてしまうと、あんなにたくさんある石も、すべて3つに分類(ぶんるい)することができるんだよ。
1.「堆積岩(たいせきがん)」石が砕かれて(くだかれて)集まり(あつまり)固まった(かたまった)もの
2.「火成岩(かせいがん)」石が溶けて(とけて)固まったもの
3.「変成岩(へんせいがん)」石が暖められたり(あたためられたり)溶けずに押されたり(おされたり)して固まったものこうしてできた石が、雨(あめ)で流されたり(ながされたり)、またできたものがさらに熱(ねつ)で溶かされたり(とかされたり)、地中(ちちゅう)ですごい圧力(あつりょく)を受けて(うけて)固まって(かたまって)しまったりして、いろいろな形(かたち)、色(いろ)、大きさ(おおきさ)になるんだよ。大きな石も川を長い(ながい)時間(じかん)をかけて転がって(ころがって)流されて(ながされて)いくうちに砕けて(くだけて)、小さくなったり角(かど)が取れて(とれて)しまい、それから、雨によっても石は溶かされたり、表面(ひょうめん)がなめらかになったりするんだ。石の歴史(れきし)はまさに地球(ちきゅう)の歴史(れきし)。調べて(しらべて)みるとおもしろいよ。
なぜサッカーボールは6角形(かっけい)のもようがあるんですか?
サッカーボールは、正五角形(せいごかっけい)12枚(まい)と正六角形(せいろっかっけい)20枚が張り合わされて(はりあわされて)つくられているんだよ。この組み合わせ(くみあわせ)によって完全(かんぜん)な球(きゅう)に近い(ちかい)形(かたち)をつくることができるんだ。最初(さいしょ)の頃(ころ)のサッカーボールは、ブタの膀胱(ぼうこう)に空気(くうき)を入れた(いれた)ものが使われて(つかわれて)いたんだって。それがだんだんと進化(しんか)して、バレーボールのような短冊形(たんざくがた)の布(ぬの)を組み合わせたボールになり、現在(げんざい)はおなじみの形のサッカーボールになったんだよ。発明(はつめい)したのは一説(いっせつ)には日本人(にほんじん)だと言われているけれど、はっきりしたところはわからないんだ。ごめんね。
チョッチイは、猿(さる)??帽子(ぼうし)、かぶってんの?王様(おうさま)は、怒った(おこった)顔(かお)だよ。ヒトデって、★☆星(ほし)が落ちて(おちて)きたやつのこと?
ははは、おめでた星のみんなのことを質問(しつもん)してくれてありがとう。チョッチイは宇宙人(うちゅうじん)で猿(さる)ではないんだよ。帽子(ぼうし)をかぶっているように見えるけど本当(ほんとう)のところはどうなっているのかわからないんだ。王様(おうさま)は怒った(おこった)顔(かお)をしているように見えるけれど、ものすごくやさしい人なんだよ。それからヒトデは、海(うみ)の生き物(いきもの)で、星(ほし)が落ちて(おちて)きたものじゃないんだ。確か(たしか)に形(かたち)は似て(にて)いるけどね。でも英語(えいご)ではstarfish[スターフィッシュ:星(ほし)の魚(さかな)]と呼ぶ(よぶ)んだよ。
1日はどうして24時間(じかん)なんですか?それから、まだ「1日の時間」がわかっていない頃(ころ)の人々(ひとびと)はどうやって1日を生活(せいかつ)してきたんですか?
「1日はどうして24時間(じかん)か?」という質問(しつもん)はこれまでに何度(なんど)か答えて(こたえて)いるので「時(とき)のはてな」の「時間」のコーナーを読んで(よんで)みてね。ではつぎの質問の「【1日の時間】がわかっていない頃(ころ)の人々はどうやって1日を生活(せいかつ)してきたんですか?」について答えるね。その頃の人たちは、自然(しぜん)の移り変わり(うつりかわり)のままに暮らして(くらして)いたんだよ。つまり太陽(たいよう)が出て(でて)明るく(あかるく)なれば、起きて(おきて)狩り(かり)や果物(くだもの)などを採り(とり)に行き(いき)、太陽が沈む(しずむ)前(まえ)に住みか(すみか)へ帰って寝る(ねる)というような暮らしだったんだよ。1日の時間はわからなくても太陽が時計(とけい)がわりで、その太陽の動き(うごき)とともに暮らしていたことになるね。
海(うみ)の水はなぜしょっぱいの?
これは「岩石(がんえん)に含まれる(ふくまれる)ナトリウムが溶けだした(とけだした)から」なんだ。海(うみ)の水には塩(しお)、つまり塩化(えんか)ナトリウム(NaCl)が溶けているんだ。ではどうしてこの塩化ナトリウムができたかというと、地球(ちきゅう)ができたばかりの頃(ころ)、隕石(いんせき)の衝突(しょうとつ)や火山活動(かざんかつどう)で大気(たいき)はとても熱く(あつく)て、空気中(くうきちゅう)には水蒸気(すいじょうき)や二酸化炭素(にさんかたんそ)に塩化水素(えんかすいそ)も含まれて(ふくまれて)いたんだ。そのあと、地球が冷えて(ひえて)くるのにしたがって水蒸気が水となって雨(あめ)として地上(ちじょう)に降り始め(ふりはじめ)、その時、塩化水素が水と混ざって(まざって)塩酸(えんさん)の雨になったんだ。塩酸はいろいろなものを溶かす性質(せいしつ)があって、その雨は、地上の岩石に含まれているナトリウムやマグネシウムを溶かして、それが海に流れ込んで(ながれこんで)塩酸とナトリウムが反応(はんのう)して塩化ナトリウム、つまり塩ができたんだよ。それが長い間(ながいあいだ)繰り返され(くりかえされ)て、たくさんの塩が海の中にできたんだ。
夢(ゆめ)は「寝ている(ねている)時」が思い出せず(おもいだせず)、うっすらとなるのはなぜ?
人間(にんげん)は寝ている(ねている)時に、浅い(あさい)眠り(ねむり)と深い(ふかい)眠りを繰り返して(くりかえして)いるんだよ。夢を見るのは浅い眠りの時だけで、この時には、感覚(かんかく)やひらめきにかかわる右脳(うのう)だけが動いて(うごいて)いるんだよ。だから夢には、空(そら)を飛んだり(とんだり)、冒険(ぼうけん)をしたりという常識(じょうしき)では考え(かんがえ)られないようなものが多い(おおい)んだよ。そうした夢を見ている浅い眠りから深い眠りに移る(うつる)時に、夢の内容(ないよう)が、こんどは理論的(りろんてき)なことを考える左脳(さのう)にうつるんだけど、そのスピードが速過ぎる(はやすぎる)と、バラバラの状態(じょうたい)でしかうつることができず、それを左脳で組み立てる(くみたてる)ことができないために、起きた(おきた)時に夢の内容のほとんどが消えて(きえて)しまうんだよ。だから「思い出せず、うっすらとなる」ということなんだ。わかってくれたかな?
今、理科(りか)の選択(せんたく)の授業(じゅぎょう)で調べて(しらべて)いるのですが、時(とき)や時計(とけい)ってすごく便利(べんり)で社会(しゃかい)の役(やく)にたっていますが、逆(ぎゃく)に人に影響(えいきょう)、害(がい)を与えたり(あたえたり)、不幸(ふこう)にしたり、ということはあるのですか?創造(そうぞう)や架空(かくう)の話(はなし)[本(ほん)、漫画(まんが)など]などを読んで(よんで)いると、「時に縛られる(しばられる)」など、時が関係(かんけい)して不幸になっていったりしますが、本当(ほんとう)にありえることなのでしょうか。時や時計とは関係のあることなのでしょうか?
これはとてもおもしろい質問(しつもん)だね。日本(にほん)を例(れい)にしてみると、今の時刻制度(じこくせいど)[定時法(ていじほう)/1日24時間、1時間の長さ(ながさ)はかわらない]で暮らす(くらす)ようになってからまだ100年ちょっとしかたっていないんだ。その前は不定時法(ふていじほう)と言われる時刻制度のもとで生活(せいかつ)をしていたんだよ。これは昼(ひる)と夜(よる)をそれぞれ6等分(とうぶん)するという時刻制度で、季節(きせつ)によって昼と夜の長さがかわるので、6等分した1刻(こく)と呼ばれる(よばれる)時間の長さもかわるというものだったんだよ。今の時刻制度になれていると不思議(ふしぎ)な感じ(かんじ)がするけど、基本(きほん)は日の出(ひので)とともに起き(おき)、日の入り(ひのいり)とともに寝る(ねる)という自然(しぜん)と調和(ちょうわ)した時刻制度なんだ。どうも「時に縛られる(しばられる)」というように感じられる(かんじられる)ようになったのは、おそらくこうした自然と調和した時刻制度ではなく、今の時刻制度になってからじゃないかな?自然のリズムではなく、時計というリズムによって世の中(よのなか)が動く(うごく)ようになったのかもしれないね。でも「時」を感じるのは人間だから、同じ1時間でも楽しい(たのしい)ことをしている時には短く(みじかく)感じたり、つまらないことをしている時には長く感じられたりってこともあるよね。どんなに悲しい(かなしい)ことがあっても、時がたてば、その悲しみが薄らいだり(うすらいだり)ってことも・・・。それから限られた(かぎられた)時間を活かす(いかす)かムダに過ごす(すごす)かによっても「時」の感じ方(かんじかた)は違ってくるしね。だから大切(たいせつ)なのは、その「時」を感じるその人の心(こころ)の持ちよう(もちよう)だと思うんだ。
蚊(か)に刺される(さされる)とかゆくなるのはなぜですか?
これはきっと「虫(むし)の不思議(ふしぎ)クイズ」からの質問(しつもん)だね。
さて、蚊(か)にさされるとかゆくなるのは、蚊が血(ち)を吸う(すう)時に、だ液(だえき)を人の体(からだ)の中に入れる(いれる)からなんだ。このだ液には血液(けつえき)を固まらせない(かたまらせない)作用(さよう)と、刺された時の痛み(いたみ)をやわらげる作用があるんだ。その唾液の中に毒素(どくそ)が入っていて、それによってアレルギー反応(はんのう)が起こる(おこる)からなんだよ。
なぜ赤ちゃん(あかちゃん)はいっつも、ちちばっかりなんですか?
これは、時間(じかん)とは関係(かんけい)のない質問(しつもん)だけど、答えて(こたえて)みるね。赤ちゃん(あかちゃん)のお口(くち)をよく見て(みて)ごらん。赤ちゃんにはまだ歯(は)がはえていないよね?だから、みんながいつも食べて(たべて)いるような普通(ふつう)のごはんやおかずを噛んで(かんで)食べることがまだできないんだよ。でも、赤ちゃんが大きく(おおきく)なるのにはものすごいエネルギーがいるんだ。おかあさんのおっぱい、母乳(ぼにゅう)には、ふだんみんなが食べているごはんやおかずにかわる大きくなるためのエネルギーのもとが、いっぱいつまっているんだよ。だから、赤ちゃんはいつもお母さん(おかあさん)のおっぱいを飲んで(のんで)いるんだよ。弟(おとうと)さんか妹(いもうと)さんかわからないけど、かわいがってあげてね。
チョッチイは2人(ふたり)??
【おめでた星】のキャラクターをよく見ててくれてうれしいな。じつはチョッチイは2人(ふたり)だけじゃないんだ。「時と人(ときとひと)」のアウグストゥスを見てみてね。チョッチイがたくさん出て(でて)くるよ。
タイはなんでタイ王国(おうこく)なの??
これは世界(せかい)の不思議(ふしぎ)クイズからの質問(しつもん)だね。タイは王様(おうさま)が国の一番上(いちばんうえ)にたって政治(せいじ)や軍隊(ぐんたい)を動かして(うごかして)いるからなんだよ。タイ王国(おうこく)の今の国王(こくおう)は、ラマ9世(せい)で1946年に即位(そくい)しているんだ。とても素晴らしい(すばらしい)王様で、タイの人たちをはじめ、世界の人たちからも尊敬(そんけい)されているんだって。
なぜ涙型(なみだがた)の雨(あめ)なの??
この質問(しつもん)は、気象(きしょう)の不思議(ふしぎ)クイズからだね。涙型(なみだがた)の雨というのは、アニメやマンガの中での話(はなし)で、雨粒(あまつぶ)は落ちて(おちて)くる時に、空気(くうき)の抵抗(ていこう)を受けて(うけて)真ん中(まんなか)がへこんで、ちょうどアンパンのような形(かたち)になるんだよ。速くて(はやくて)小さい(ちいさい)から目で確かめる(たしかめる)ことはで難しい(むずかしい)けどね。
なぜね、おうかんをかぶっているの?
これはハッピーキングに質問(しつもん)をくれたんだね。王冠(おうかん)をかぶっているのはハッピーキングがおめでた星(ぼし)の王様(おうさま)だからだよ。おめでた星では、ずっと昔(むかし)から王様は王冠をかぶることになっているんだよ。この王冠は、ずっとずっと守られて(まもられて)きたおめでた星の宝物(たからもの)でもあるんだよ。
数字(すうじ)は、どうやってできたの?
大昔(おおむかし)、人々(ひとびと)は数(かず)を表す(あらわす)のに、野牛(やぎゅう)3匹(びき)という時は、野牛の絵(え)を3つ描いた(かいた)り、縄(なわ)に結び目(むすびめ)を作った(つくった)り、棒(ぼう)を書いた(かいた)りしていたんだ。[地域(ちいき)によってそれぞれの方法(ほうほう)があった)]
エジプト、バビロニア、ギリシャ、ローマそれぞれの数字(すうじ)があるけど、今、世界中(せかいじゅう)で使って(つかって)いる「アラビア数字」について調べて(しらべて)みるとなんとこれはインドで生れた(うまれた)んだ。千数百年前(せんすうひゃくねんまえ)、アラビアのイスラム帝国(ていこく)は、西(にし)はスペイン、東(ひがし)はインドまでのとても大きな国だったので、いろいろな国の数字があったんだ。その中でアラビア人はインドの数字が一番(いちばん)便利(べんり)だったので、これを選んだ(えらんだ)んだよ。インドで生れた(うまれた)数字は、アラビアへ伝わり(つたわり)、さらにヨーロッパ各地(かくち)へ拡がって(ひろがって)いったんだけど、その間(あいだ)、長い(ながい)年月(ねんげつ)をかけて今のような形(かたち)になったんだ。アラビア数字の優れた(すぐれた)ところは、0123456789の10個(こ)だけで、どんな大きな数でも書けてしまうことなんだよ。
なぜ、時(とき)がたつと、季節(きせつ)の温度(おんど)が変わった(かわった)り、明るさ(あかるさ)が変わるんですか?日本の反対(はんたい)の国(くに)は、午前(ごぜん)と午後(ごご)が違う(ちがう)けど、時間(じかん)は同じ(おなじ)ってほんとですか?
これは「日本(にほん)に四季(しき)があるのはなぜか?」「どうして日本が朝(あさ)の時、アメリカは夕方(ゆうがた)なの?」という質問(しつもん)のところで答えて(こたえて)いるので読んで(よんで)みてね。
人間(にんげん)はなぜ生きて(いきて)いるのか?
これはまさに「時(とき)とは何(なに)か?」とともに、人類(じんるい)最大(さいだい)の永遠(えいえん)のテーマです。人間(にんげん)も動物(どうぶつ)も植物(しょくぶつ)もみんな生き物(いきもの)には寿命(じゅみょう)という限られた(かぎられた)時間があって、その中で生まれて死んで(しんで)いきます。ただ人間がほかの動植物(どうしょくぶつ)とちがうのは、いろいろなことを考える能力(のうりょく)を持って(もって)いることです。この能力のおかげで人間はさまざまな文化(ぶんか)や文明(ぶんめい)を築いて(きずいて)きたんだ。だけど「人間はなぜ生きているのか」というような難しい(むずかしい)問題もかかえることになったんだ。この問題は大昔(たいこ)からたくさんの人々が考えつづけ、その考え方から、さまざまな宗教(しゅうきょう)や哲学(てつがく)が生まれてきたんだよ。でも、この質問へのこたえは1つではなくて、ひとりひとりが自分で考えなければならないものなんだよ。「こどものために」「好き(すき)な人のために」「楽しい(たのしい)ことをするために」など・・・。みんなにとっては、どんなことかな?いろいろと考えてみてね。
なぜ、年越し(としこし)そばを食べる(たべる)の。 除夜の鐘(じょやのかね)ってなあに。
お年玉(おとしだま)って、なぜもらえるの。おせち料理(りょうり)ってなんだろう。
まず、最初(さいしょ)の質問(しつもん)から行く(いく)ね。年越し(としこし)そばを大晦日(おおみそか)に日本人(にほんじん)が食べる(たべる)ようになった理由(りゆう)は、ハッキリとしたことがわかってなくて、よく言われる(いわれる)のは「そばのように細く(ほそく)長く(ながく)生きて(いきて)寿命(じゅみょう)を全う(まっとう)し、家運(かうん)も末永く(すえながく)続く(つづく)ようにとの願い(ねがい)からそばを食べるようになった。」という説(せつ)です。多く(おおく)の人たちが食べるようになったのは、江戸時代(えどじだい)の中頃(なかごろ)だそうです。
次(つぎ)は「除夜の鐘(じょやのかね)」だよ。大晦日に108つの鐘をつく「除夜の鐘」は人間(にんげん)の持って(もって)いる「お金がほしい」「おいしいものが食べたい」といった108つの煩悩[ぼんのう/わかりやすく言えば欲(よく)みたいなもの]を追い払う(おいはらう)という目的(もくてき)があるんだよ。そうすれば、きれいな心(こころ)で新年(しんねん)を迎える(むかえる)ことができるからね。
最後(さいご)の「おせち料理(りょうり)」は、漢字(かんじ)で書く(かく)と「お節料理(おせちりょうり)」になるんだ。みんなもよく知って(しって)いる「節分(せつぶん)」の「節」と同じ(おなじ)で、季節(きせつ)のかわり目のことを表す(あらわす)んだよ。そうした季節のかわり目には、とれたものを神様(かみさま)にお供え(そなえ)していたんだ。そしてそのお供えしたものを使って(つかって)作った(つくった)料理を「節供(せっく)料理」と言っていたんだよ。お正月(しょうがつ)は、その節(せつ)のかわり目の中でも一番(いちばん)大きな時だから、節供の前に「お」がついて「お節供」となって、それが短く(みじかく)なって「お節(おせち)」になり「お節(おせち)料理」と呼ぶようになったそうなんだ。
現代(げんだい)に生きる(いきる)人々(ひとびと)は時間(じかん)が足りない(たりない)と常(つね)に感じて(かんじて)いるようです。私もいろんなことに追われ(おわれ)ながら、日々(ひび)生活(せいかつ)しています。では、こんなに物にあふれていなかった時代(じだい)の人々は、時間についてどのように感じていたのでしょうか。
大昔(おおむかし)の人たちは、朝(あさ)は太陽(たいよう)とともに起き(おき)、畑(はたけ)や猟(りょう)などにでかけ、夕方(ゆうがた)太陽が沈む(しずむ)と家に帰って(かえって)休む(やすむ)という自然(しぜん)の時間の流れ(ながれ)にしたがって暮らし(くらし)ていました。2001年10月号の「時と暮らし(ときとくらし)〜日本人(にほんじん)の時間感覚(じかんかんかく)〜」でもとりあげましたが、今(いま)世界一(せかいいち)セカセカしている日本人でさえ、つい400年ぐらい前のほとんどの人たちはそんな暮らしぶりだったのです。
その頃(ころ)の人たちが時間をどんなふうに感じていたのかを知るにはタイムマシンでもないとむずかしいのですが・・・。けれど、当時(とうじ)の人たちと、現代(げんだい)の人たちの寿命という観点(かんてん)から言えば、今の人の方(ほう)がじつは昔の人たちよりも時間は多く(おおく)もっていることになるんですよ。「人生(じんせい)50年」と言われた昔の人たちとくらべ、今の人たちはほとんどが80才ぐらいまで生きます。単純(たんじゅん)に計算(けいさん)しただけでも30年も多く使える時間を持っているわけです。それなのにみんなが「時間がない、忙しい(いそがしい)」と言っているのは何となくヘンですね。それは今の人があまりにも多くのことをやろうとしているからなのではないでしょうか。またそうした欲求(よっきゅう)を刺激(しげき)するものが、今の世の中(よのなか)には多いのかもしれません。けれど、欲求を作り(つくり)だし大量(たいりょう)消費(しょうひ)をするという構造(こうぞう)の上に今の社会(しゃかい)が成り立っているのですから、仕方(しかた)のないことかもしれませんね。
参考文献「時計の針はなぜ右回りなのか」織田一朗
ガリレオ・ガリレイが発見(はっけん)した「振り子(ふりこ)の等時性(とうじせい)」ってどういう理論(りろん)なんですか。
「振り子(ふりこ)の等時性(とうじせい)」は、カンタンに言えば、振り子が大きくゆれても、小さくゆれても、1往復(おうふく)にかかる時間は同じというものなんだよ。ガリレオは、これを教会(きょうかい)の天井(てんじょう)からつるされたランプが風にゆれる様子(ようす)を見ていて発見(はっけん)したと言われているんだ。
この「振り子の等時性」については、「時の教室(ときのきょうしつ)」の中の「時の理科(りか)」「振り子(ふりこ)の等時性(とうじせい)〜ガリレオ・ガリレイ」を見てもらうともっと詳しい(くわしい)ことがのっているよ。
時間が決まって(きまって)いなかった頃(ころ)の生活(せいかつ)のしかたと時間が決まってからの生活の違い(ちがい)は?昔(むかし)の時間と今の時間との移り(うつり)かわりは?
秒(びょう)の単位(たんい)まで正確(せいかく)に計れる(はかれる)時計が、作られた(つくられた)のが今から約(やく)300年ぐらい前のことなんだ。けれどその正確な時計が発明(はつめい)されたからといって、みんなの生活が正確な時間によって動き(うごき)はじめたというわけではないんだよ。時計はずっと長い(ながい)間(あいだ)、ものすごい高級品(こうきゅうひん)で、ふつうの人たちが家に持ったり(もったり)、一人一人が持って(もって)歩く(あるく)ことなんてとてもできなかったんだ。
そうすると、時計があっても、ほとんどの人は昔(むかし)ながらの自然(しぜん)のリズムで生活をしていたんだよ。朝(あさ)、太陽(たいよう)が昇れば(のぼれば)起きて(おきて)仕事をして、夜(よる)になれば、家に帰って(かえって)寝る(ねる)という生活なんだよ。当然(とうぜん)、季節(きせつ)によって日の出(ひので)と日の入り(ひのいり)時間は違う(ちがう)から、それに合わせた(あわせた)生活をしていたんだよ。
つまり、人もより自然(しぜん)の一部(いちぶ)としての生活をしていたということになるよね。
それが、各(かく)家庭(かてい)に時計が普及(ふきゅう)して、だれもが正確な時間を知る(しる)ことができるようになると、時間に合わせた生活をするようになるんだ。カンタンな例(れい)で言えば、朝、会社が始まる(はじまる)のは夏(なつ)だろうが、冬(ふゆ)だろうが8時、会社が終わる(おわる)のは5時というようにね。
時間によってすべての人が動く生活になったんだ。これは国(くに)単位でもそうで日本のように狭い(せまい)国ならば、国の時間は1つの時間ですむけれど、中国(ちゅうごく)のように東西(とうざい)に広い(ひろい)国で国の時間が1つだとどうなるのか?みんながその時間によって生活しなければいけなくなるので、東(ひがし)の方では、日が昇っている朝8時なのに、西(にし)の方では、まだ真っ暗(まっくら)な朝8時ということになってしまうんだ。
でも働く(はたらく)人は同じ朝8時に会社に行かなければならないという不思議(ふしぎ)な生活になってしまうんだよ。つまり、時間が決まってからの生活というのは、人間(にんげん)が時間によって、動かされる生活ということになるよね。
さて、次(つぎ)の質問(しつもん)の「昔(むかし)の時間と、今の時間の移り(うつり)かわり」は、日本では江戸時代(えどじだい)に使われて(つかわれて)いた「不定時法(ふていじほう)」という時間があって、これは、季節(きせつ)によって、時間の長さ(ながさ)が違って(ちがって)いたんだよ。日の出、日の入りの時間から、その季節ごとの昼の時間と夜の時間をそれぞれ6等分(とうぶん)していたというやり方なんだ。だから昼間(ひるま)の時間の長い夏は昼間の1刻(いっこく)が長く、その逆(ぎゃく)に昼間の時間の短い(みじかい)冬は、昼間の1刻が短いとなるんだ。でも考えてみれば、人間の体が活発(かっぱつ)に動く夏はたくさん働き(はたらき)、活動が鈍る(にぶる)冬は、あまり働かないという生活は、自然(しぜん)な感じがするよね。今は、季節に関係(かんけい)なく、1日は24時間となり、みんなはその中できちんと生活をしているわけなんだ。
------------------------------------------------------------------------
時(とき)と、いうものを決めた(きめた)のは、誰(だれ)ですか?
「時(とき)」というものは誰(だれ)が決めた(きめた)というものではありません。それは宇宙(うちゅう)が生まれた(うまれた)時から止まる(とまる)ことなくずっと未来(みらい)に向かって(むかって)進んで(すすんで)いるものなんだ。大昔(おおむかし)の人たちは、太陽(たいよう)や月(つき)、星(ほし)など天体(てんたい)の決まった動きや、自然のくりかえされる変化(へんか)からこの「時」というものを、長い年月(ねんげつ)の中で知って(しって)いったんだ。でも「時」というものは、さわることも見ることもできないものなので、人間は「時計」という共通(きょうつう)のモノサシを作る(つくる)ことで、誰もが同じ(おなじ)「時」の中で生活(せいかつ)することができるようにしたんだよ。
夕方(ゆうがた)は、だいたい4時ぐらいからって言うけど、本当(ほんとう)は、夕方って何時(なんじ)から何時のことを言う(いう)の?
夕方(ゆうがた)と言う言葉(ことば)を辞書(じしょ)でひいてみても「日(ひ)が暮れ(くれ)はじめて夜(よる)になるまでの間(あいだ)」(三省堂・大辞林第二版)と書いてあって、はっきりと決められて(きめられて)いるわけでないんだよ。季節(きせつ)やそれぞれの人の感じ方(かんじかた)によっても違う(ちがう)しね。
6月10日は「時の記念日(ときのきねんび)」ですが、どうして6月10日なのでしょうか。
どういう由来(ゆらい)があるのですか?「時の記念日」ができたのは、今から80年前。インフレが進む(すすむ)なかで、日々(ひび)の生活(せいかつ)をカンタンにして、合理的(ごうりてき)なものにしようという「生活改善同盟(せいかつかいぜんどうめい)」という団体(だんたい)がつくられて、その団体が一番(いちばん)の目標(もくひょう)にあげていたのが「時間を正確(せいかく)に守る(まもる)こと」だったんだ。
たまたまその頃(ころ)に、文部省(もんぶしょう)も「時間を大切にし、守ること」の考え方(かんがえかた)を広め(ひろめ)ようとしていたんだ。そして文部省が進めていた「時に関する(かんする)展示会(てんじかい)」にいろいろなものを出したり、広めるために手伝い(てつだい)ましょうということで、「時の記念日」を決め(きめ)、宣伝(せんでん)することに決めたんだ。6月10日が「時の記念日」として選ばれた(えらばれた)理由(りゆう)は、日本ではじめて「漏刻(ろうこく)」と呼ばれる水時計を作った(つくった)天智天皇(てんじてんのう)が671年に時刻制度(じこくせいど)をはじめた日だからなんだ。
中国(ちゅうごく)は、3000年前(ねんまえ)にできたと言われていますが、実際(じっさい)は何年前からあるんですか?それから、一番(いちばん)古い(ふるい)国(くに)はどこですか?
中国(ちゅうごく)に文明(ぶんめい)というものができたのは、3000年前よりもっと前の今から8000年前のことなんだ。その文明は黄河文明(こうがぶんめい)と言われているんだよ。ただ国ができたのは3千数百年前の殷王朝(いんおうちょう)だよ。さて、ここで世界史(せかいし)の勉強(べんきょう)を少し(すこし)してみよう。
ちょうど同じ(おなじ)頃(ころ)に、インダス文明、エジプト文明、メソポタミア文明という世界4大文明(せかいよんだいぶんめい)と呼ばれる(よばれる)文明が生まれて(うまれて)いるんだよ。これらの文明は、それぞれが独立(どくりつ)して生まれたわけではなく、最近(さいきん)の研究(けんきゅう)ではいろいろなことでのかかわりがあったのではないかと言われているんだ。そして「一番(いちばん)古い(ふるい)国」は、紀元前(きげんぜん)3100年前にエジプトで、メネス王による2つの南北(なんぼく)2つの王国(おうこく)を統一(とういつ)させた国が人類(じんるい)の歴史上、もっとも古い国の登場(とうじょう)だと言われているんだよ。この国ができたことによって、エジプトの輝かしい(かがやかしい)歴史が始まった(はじまった)んだよ。
もっと詳しく(くわしく)知りたい(しりたい)時には、エジプト大使館(たいしかん)のホームページを見てね。
http://embassy.kcom.ne.jp/egypt/history-j.htm
なぜ、日本(にほん)に四季(しき)があるのはなぜ?ハワイにはないの?
季節(きせつ)は、地球(ちきゅう)と太陽(たいよう)の関係(かんけい)でやってくるんだ。地球は太陽のまわりを右(みぎ)の図(ず)のように回って(まわって)います。
その時の回る道筋(みちすじ)は、ほとんど同じ(おなじ)なのですが、地球の自転軸(じてんじく/地球がまわっているちゅうしんのじく)が23.4度(ど)かたむいたまま、太陽の周り(まわり)を回るために、季節の変化(へんか)があるんだよ。
季節によって、日本が冬(ふゆ)の時(とき)には太陽は南半球(みなみはんきゅう/ちきゅうぎでいうと下はんぶん)の真上(まうえ)から、北半球(きたはんきゅう/ちきゅうぎでいうと上はんぶん)は斜め(ななめ)から光(ひかり)をあてるので、南半球は夏(なつ)に、北半球は冬になるんだよ。その反対(はんたい)に日本が夏の時は南半球は寒く(さむく)、北半球は暑く(あつく)なるんだ。オーストラリアでは、サンタクロースがサーフィンに乗って(のって)くるんだよ。それから春(はる)や秋(あき)はそのまん中にあたり、太陽は真横(まよこ)から照す(てらす)ので、ちょうどいい季節になるんだよ。日本は温帯(おんたい/緯度(いど)でいうと23.5度から66.5度の間)にあるから春夏秋冬(しゅんかしゅうとう)がはっきりしているだけで、常夏(とこなつ)と言われる場所(ばしょ)でも、温度差(おんどさ)は小さいけれど、季節はあるんだよ。
どうして、人間(にんげん)は朝(あさ)、昼(ひる)、晩(ばん)と3回(かい)食事(しょくじ)をとるの?
ふだん、なにげなく食べて(たべて)はいるけれど、よくよく考えて(かんがえて)みると不思議(ふしぎ)に思う(おもう)ことだよね。「食生態学入門(しょくせいたいがくにゅうもん)」という本(ほん)によると、狩り(かり)をしたり、くだものや木の実(きのみ)をとってくらしていた原始社会(げんししゃかい)では、食べものを手に入れた(いれた)時が食事(しょくじ)の時間なので、食べられる時もあれば、食べられない時もとうぜんあったんだ。 
それが、1つの場所に住み(すみ)、農業(のうぎょう)をはじめるようになる原始農耕社会(げんしのうこうしゃかい)では、食べ物をたくわえておくこともできるようになり、1日に夕方(ゆうがた)1回、決まった(きまった)時間に食事がとれるようになったといわれているんだ。それから、社会(しゃかい)のしくみが発達(はったつ)してくるにしたがって、食事をとるゆとりが生まれ(うまれ)、1日2食(しょく)がふつうとなり、昼(ひる)と夕方にとるようになったんだ。
さらに、そのあと、裕福(ゆうふく)な人たちが、2食では満足(まんぞく)しなくなり、朝(あさ)ごはんと晩(ばん)ごはんの間に、間食(かんしょく)をとるようになり、ここではじめて1日3食という習慣(しゅうかん)ができたんだよ。そして、みんなのくらしに余裕(よゆう)ができてくると一般(いっぱん)の人たちの間にも広がって(ひろがって)、今から350年ぐらい前に1日3食がふつうになったといわれているんだよ。
どうしておやつの時間(じかん)は3時(じ)に決まって(きまって)いるの?
3時(じ)のおやつの時間(じかん)は、とっても楽しみ(たのしみ)なもの。
さて、それじゃ、なぜおやつの時間が3時に決まったのか?「おやつ」というのは、広辞苑(こうじえん/辞書:じしょ)によると、その昔(むかし)は「お八(おやつ)」と書いて(かいて)、「八つ時(やつどき)に食べる(たべる)ことから)午後(ごご)の間食[かんしょく/食事と食事の間(あいだ)にたべる軽い(かるい)食事のこと]のこと」となっているんだ。八つ時とは、江戸時代(えどじだい)の時刻制度(じこくせいど)で、今の時間の2時ごろにあたる時間。江戸時代の時刻制度は、不定時法(ふていじほう)と言って(いって)、季節(きせつ)によって、1刻(こく)の時間が違う(ちがう)んだ。だから同じ(おなじ)八つ時でも春分(しゅんぶん)のころには今の午後の2時、秋分(しゅうぶん)のころには今の4時ぐらいになるんだ。明治(めいじ)になって、1日を24時間できっちりとわける定時法(ていじほう)になった時に、間をとって3時と決めたんじゃないかと言われているんだよ。
ちなみに、江戸時代の人々(ひとびと)が「おやつ」の時間に食べていたのは「お寿司(すし)」だったんだ。じつは、その頃(ころ)「おやつ」は子供(こども)たちのためのものではなく、大人(おとな)たちのものでもあったんだ。今の人たちが思っているおやつではなくて、お昼をすぎて、少し(すこし)仕事(しごと)をした後に食べる間食の意味(いみ)が大きかったんだ。
太陽(たいよう)の見えない(みえない)部屋(へや)の中(なか)で、時計(とけい)もなくて暮らし(くらし)たらどうなるの?
このことについては、じつは1965年にドイツのユルゲン・アショフという人が実験(じっけん)を行って(おこなって)いるんだよ。彼(かれ)は太陽(たいよう)の光(ひかり)が入らず(はいらず)、もちろん時計(とけい)もテレビもなにもない地下室(ちかしつ)の中(なか)で人々(ひとびと)を生活(せいかつ)させてデータを集めた(あつめた)んだ。その結果(けっか)は、きちんとしたリズムをたもっていて、そのサイクルは24.7時間〜25.9時間だったんだ。 これによって、人間(にんげん)がもともと持って(もって)いるサイクルは1日が25時間ということがわかったんだ。そして、太陽の光をあびることによって、24時間に近い(ちかい)時間に調節(ちょうせつ)されていることがわかったんだよ。
だから、そんな場所(ばしょ)で暮らし(くらし)たら、25時間サイクルの生活になってしまうんだよ。
時計(とけい)のない国(くに)では、どうやって生活(せいかつ)してるの?
時計(とけい)のない国(くに)では、今(いま)も時間(じかん)を知る(しる)のには、太陽(たいよう)の動き(うごき)を見て(みて)いるんだよ。そうした生活(せいかつ)をしている人たちにとっては、正確(せいかく)な時間というものを知る必要(ひつよう)がないんだ。
朝(あさ)がきて、明るく(あかるく)なれば起きて(おきて)、食べ物(たべもの)を取り(とり)に行った(いった)りして、夜(よる)になって、暗く(くらく)なれば家(いえ)に帰って(かえって)寝る(ねる)という暮らし(くらし)をしているからね。季節(きせつ)によって、昼の時間が長く(ながく)なれば、それにあわせ、短く(みじかく)なれば、それにあわせた生活をする。でも考えてみれば、もっとも人間(にんげん)らしい生き方(いきかた)なのかもしれないよ。
どうして、朝(あさ)とか昼(ひる)とか夜(よる)って決まって(きまって)いるんですか?
朝(あさ)と昼(ひる)と夜(よる)というのは、正確(せいかく)にいうと決まって(きまって)はいないんだよ。ふつうは、お日さまが昇って(のぼって)から11時ぐらいまでが朝で、11時を過ぎて(すぎて)、日がしずむまでが昼。
日がしずんで暗く(くらく)なるっと夜といった感じ(かんじ)かな?もっと細かく(こまかく)わけていくと、日がしずむ前(まえ)の時間を夕方(ゆうがた)というよね。わけ方は、お日さまの動き(うごき)や明るさ(あかるさ)を基準(きじゅん)にして、朝とか、昼とか、夜というような言い方(いいかた)をしているんだよ。
体内時計(たいないどけい)があれば、時計(とけい)なんかいらないんじゃないの?
たしかに、人間(にんげん)にも動物(どうぶつ)にもサーガディアンリズムといわれる体内時計(たいないどけい)はあるよね。でも、このサーガディアンリズムというものは、体内時計というだけあって、体(からだ)の状態(じょうたい)に左右(さゆう)されるんだよ。たとえば、体の調子(ちょうし)がいい時と悪い(わるい)時では、時間の感じ方(かんじかた)がきっと違う(ちがう)と思う(おもう)んだ。人がみんな同じように時間のリズムを感じていれば、サーガディアンリズムだけで、人の社会(しゃかい)も動かすことができるかもしれない。でも、そんなことはありえないから、人間すべてが使える(つかえる)共通(きょうつう)のモノサシである時計を作って(つくって)、同じ時間を共有(きょうゆう)するようになっているんだよ。 遊ぶ(あそぶ)時に、お友だちと、午後(ごご)1時に待ち合わせ(まちあわせ)たとしても、共通の時間を示す(しめす)時計がなかったら、遊ぶことができなくなってしまうよね。
寝て(ねて)いるときに夢(ゆめ)を見る(みる)のはなぜですか?
人は一晩(ひとばん)に5〜6回のサイクルで、深い(ふかい)眠り(ねむり)と浅い(あさい)眠りをくりかえします。この深い眠りから浅い眠りにもどった時に、体(からだ)は眠っているのに脳(のう)は活発(かっぱつ)に働いて(はたらいて)いる状態(じょうたい:これをレム睡眠(すいみん)という)があって、夢はこの状態の時に見ると言われているんだよ。 でも「なぜ、人は夢を見るか?」については、はっきりした理由(りゆう)はまだよくわかっていないんだ。今(いま)、学者(がくしゃ)たちの中(なか)であげられている理由としては、下(した)のようなものがあるんだ。
参考(さんこう)に見ておいてね。●記憶(きおく)するため:「昼間(ひるま)、脳(のう)にはいった情報(じょうほう)を整理(せいり)する」
●忘れる(わすれる)ため:「脳にたまっている不要(ふよう)な情報や古い(ふるい)情報を削除(さくじょ)する」
●「外部(がいぶ)の刺激(しげき)による脳の錯覚(さっかく)である」
●「現実(げんじつ)の生活(せいかつ)の予行演習(よこうえんしゅう)をしている」
どうしてよい子は夜(よる)の9時に寝なくちゃ(ねなくちゃ)いけないの?
この質問(しつもん)は、おもしろい質問だね。
「よい子は夜(よる)の9時に寝る(ねる)」。それじゃあ、起きる(おきる)時間(じかん)から考えて(かんがえて)いこうか。学校(がっこう)が始まる(はじまる)のがだいたい8時30分として、学校に行く前(まえ)に朝食(ちょうしょく)をとったり、したくをしたりで1時間ぐらいは余裕(よゆう)がほしいよね。もし犬(いぬ)なんかを飼って(かって)いたら、朝(あさ)のお散歩(さんぽ)にも連れて(つれて)いかなければならないし、そしたら6時半(はん)か、7時には起きたいよね。それじゃぁ、起きる時間を6時半として、ふうついわれている睡眠時間(すいみんじかん)8時間で計算(けいさん)してみよう。すると、寝る(ねる)時間は、10時〜10時半となるよね。でもお布団(ふとん)に入ってすぐに眠れる(ねむれる)わけじゃないから、眠るまでの時間の30分を見ると、9時半〜10時となる
よね。
とすると、お母さんたちが言う「子供(こども)は、夜の9時に寝なさい」という時間にだいたい近く(ちかく)なるよね。次の日にちゃんとした生活をするためには、子供だったらやっぱり8時間ぐらいは、寝ておきたいよね。「寝る子は育つ(そだつ)」ということわざもあるしね。
とは言っても、科学的(かがくてき)に言うと、人が快適(かいてき)だと思う睡眠時間には、個人差(こじんさ)があって、誰(だれ)もが8時間寝ることがよいというわけではないんだ。
あのナポレオンや発明王(はつめいおう)のエジソンの睡眠時間は6時間ぐらいで、その逆(ぎゃく)に長く寝た人の代表(だいひょう)は、このホームページでもときどき名前(なまえ)がでてくるアインシュタイン。彼(かれ)は9時間以上も寝ていたといわれているんだよ。
自分(じぶん)の言おう(いおう)と思った(おもった)ものを忘れて(わすれて)しまうのはなぜなのですか?
人間(にんげん)の記憶(きおく)には、2種類(しゅるい)の記憶があって、ふだんよく会う(あう)友だちの名前(なまえ)などは、何度(なんど)も何度も自分の口(くち)でその人の名前を言って、そのたびに、自分の脳(のう)の中に記憶されるため脳の中にその情報(じょうほう)がたまっていきます。これを「長期記憶(ちょうききおく)」と言うんだよ。その反対(はんたい)に年に1度ぐらいしか会わない親せき(しんせき)のおじさんの名前とかは、覚えた(おぼえた)あと、ひんぱんにくりかえして言う必要(ひつよう)がないので、すぐ忘れてしまう。これを「短期記憶(たんききおく)」というんだよ。
ものを忘れるというのは、こちらの「短期記憶」の方が多い(おおい)んだ。だから「言おうと思ったことを忘れてしまう」というのは、自分で言おうと思ったことを、思った時に1回は脳の中に記憶されても、その記憶というのが、非常(ひじょう)に弱い(よわい)ものだからなんだ。時間と何か(なにか)関係(かんけい)があるんですか?と言う質問は「長期」の記憶と「短期」の記憶という意味(いみ)で関係あるよね。
どうして世界(せかい)の言葉(ことば)が違う(ちがう)のですか。
これは、みんなが疑問(ぎもん)に思う(おもう)ことだよね。世界中(せかいじゅう)の言葉(ことば)が同じ(おなじ)だったら、どこの国(くに)に行って(いって)も困らない(こまらない)のにね。
言葉というのは、誰(だれ)がつくったものでもなく、長い(ながい)時間(じかん)の中(なか)で、いつのまにかできてしまったものなんだ。自分(じぶん)ひとりで暮らし(くらし)ていたら、人間(にんげん)はしゃべる必要(ひつよう)はないよね。でもある場所(ばしょ)に何人(なんにん)かの人たちが集まって(あつまって)暮らすことになると、その仲間(なかま)の中で、自分の意志(いし)を相手(あいて)に伝えたり(つたえたり)、狩り(かり)をする時など、みんなでいっしょに動く時に、合図(あいず)とかが必要になるよね。その時(とき)に、しゃべるというか、発して(はっして)いた声が言葉の最初(さいしょ)なんだ。だから、人が集まって暮らしていた場所の数(かず)だけ、言葉が生まれて(うまれて)しまった。というわけなんだ。そして、その声(こえ)みたいなものが、文明(ぶんめい)の発達(はったつ)にしたがって、どんどん複雑(ふくざつ)になっていろいろな考えを伝えられる言葉になっていったんだよ。さらに、人間の行動範囲(こうどうはんい)が広がる(ひろがる)ようになると、その同じ言葉を使う人間の数がふえて、国といった広い地域(ちいき)で使われるようになったんだ。
時間も「標準時(ひょうじゅんじ)」というものがきちんと決められるまでは、「地方時(ちほうじ)」といって、その地域の人たちだけの時間が使われていて、たくさんの勝手(かって)な時間がいっぱいあったんだよ。
体(からだ)のサイクルが、くるってしまったらどうするんですか?
体(からだ)のリズムがくるってしまうのには、いろいろな原因(げんいん)があって、たとえば夜(よる)遅く(おそく)まで仕事(しごと)をする生活(せいかつ)が続いたり(つづいたり)、2001年3月号の「時の家庭科(ときのかていか)」でもお話(はなし)した「時差(じさ)ボケ」だったり、あとは精神的(せいしんてき)な病気(びょうき)だったりするんだよ。「夜遅く(おそく)までの仕事」とか「時差ボケ」については太陽(たいよう)の光(ひかり)をきちんとあびる生活(せいかつ)をすることや、食事(しょくじ)を決まった(きまった)時間にきちんと、とることで自然(しぜん)に直って(なおって)いくんだよ。
でも精神的な病気が原因(げんいん)の場合(ばあい)には、お医者(いしゃ)さんに行って(いって)きちんと見てもらわなければいけないよね。
季節(きせつ)によって、夜(よる)が長い(ながい)とか昼(ひる)が長いとか決まる(きまる)のはなぜ?
これは、太陽(たいよう)の動き(うごき)が、季節(きせつ)によってかわるからなんだ。左(ひだり)の図(ず)をみてもらえればわかるとおもうけど、夏(なつ)と冬(ふゆ)では太陽のとおる道(みち)がこんなに違って(ちがって)いるんだよ。
図のおわん型(がた)の下(した)に太陽が入ってしまった時が夜なんだ。だからちょうど春分(しゅんぶん)・秋分(しゅうぶん)の日には、昼(ひる)と夜(よる)の長さ(ながさ)が同じ(おなじ)ぐらいで、夏は昼が長く、冬は夜が長いというようになるんだよ。わかってくれたかな?
どうして夜(よる)は暗く(くらく)て昼(ひる)は明るい(あかるい)の?
カンタンに言えば、夜(よる)が暗い(くらい)のは太陽(たいよう)がでていないから、昼(ひる)が明るい(あかるい)のは太陽がでているからなんだよ。地球(ちきゅう)は自分(じぶん)で回って(まわって)いて、自分が住んで(すんで)いる場所(ばしょ)が太陽の方(ほう)を向いたり(むいたり)、その反対(はんたい)を向いたりをくりかえしているんだよ。
このことを自分でたしかめるのは、地球儀(ちきゅうぎ)と懐中電灯(かいちゅうでんとう)を使って(つかって)イラストのように実験(じっけん)をしてみてね。
「あ・い・う・え・お・・・」と、現在(げんざい)では50音表(50おんひょう)がありますが、昔(むかし)は「い・ろ・は・に‥‥」でしたよね。いつから現在の50音表が使われる(つかわれる)ようになったんですか?
これは時(とき)とは関係(かんけい)ない質問(しつもん)ですが、調べて(しらべて)みたよ。「いろは」というのは、平安時代(へいあんじだい)に多く(おおく)の人たちによって作られた(つくられた)日本独自(にほんどくじ)の音節文字(おんせつもじ)と言われるものなんだ。
でもこれにはもう1つの説(せつ)もあって「いろは」というのは「色(いろ)は匂(にほ)へど(と)、散(ち)りぬるを・・・」という歌(うた)が「いろはにほへと」になっていったというものなんだ。では「あいうえお」の50音表は、いつ作られてたものなのか?現存(げんぞん)するもっとも古い(ふるい)ものは11世紀(せいき)のものなんだ。今(いま)の順序(じゅんじょ)に統一(とういつ)されたのは、江戸時代(えどじだい)の最初(さいしょ)のころなんだよ。もともとのものはカタカナで書かれていて「ン」は入って(はいって)いなかったんだよ。と、これぐらいのところまではわかっているんだけど、どうして「あかさたな・・」の行(ぎょう)の順番(じゅんばん)ができたのかははっきりとしていないんだ。ごめんね。
参考資料:「日本語教育事典(にほんごきょういくじてん)」大修館書店発行
生活(せいかつ)のリズム(体内時計:たいないどけい)がくるってしまったので起きる(おきる)時(とき)、しんどいです。ふとんにねころんでから、前(まえ)までは30分ぐらいで眠れた(ねむれた)のに、今(いま)は1〜2時間(じかん)しないと眠れません。そのぶん、いつもの1時間くらい後(あと)に起きてしまいます。どうしたら体内時計を直せ(なおせ)ますか?教えて(おしえて)ください。
遅く(おそく)まで起きて(おきて)いる生活(せいかつ)をしていると、体内時計(たいないどけい)のリズムがズレてしまうことがあるよね。こんな時(とき)は、いきなりリズムをかえるのは大変(たいへん)だから、少し(すこし)ずつ生活(せいかつ)のリズムをズラしていくのがいいんだよ。春休み(はるやすみ)に寝て(ねて)いた時刻(じこく)よりも30分ぐらいずつ早め(はやめ)に眠るようにして、今まで寝ていた時間まで何日(なんにち)かかけて直していくのがいいんだよ。そうすればだんだんと体のリズムがもとに戻って(もどって)いくからね。
生物(せいぶつ)の「体内時計(たいないどけい)」は何(なに)を基準(きじゅん)にしているの?
時計(とけい)も何(なに)もなかった大昔(おおむかし)の人たちはどうやって時間(じかん)を知った(しった)んだろう?一番(いちばん)わかりやすいのは太陽(たいよう)だよね。太陽が昇って(のぼって)明るく(あかるく)なったら起きて(おきて)、太陽がしずんだら、またほら穴(あな)に帰って(かえって)寝て(ねて)、というように太陽の動き(うごき)を時間として感じて(かんじて)いたんじゃないかな。 たとえば、時計もなにもない無人島(むじんとう)に流された(ながされた)ときに、みんなも大昔の人たちと同じ(おなじ)ように太陽の動きにあわせて生活(せいかつ)するんじゃないかな。それが、時間をはかる最初(さいしょ)のことだと思うんだ。
みんなが、ふだん感じてる「おなかがすいた」「眠く(ねむく)なった」という「体内時計(たいないどけい)」のリズムも、じつは太陽の光(ひかり)に影響(えいきょう)されているんだよ。