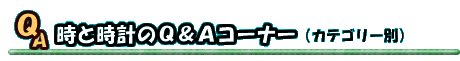5月にある「母の日」は日本(にほん)だけの日なんですか?
今年(ことし)は、5月の第(だい)2日曜日(にちようび)の10日が「母の日」だね。「母の日」は日本だけではなくて、世界中(せかいじゅう)であるんだよ。ちなみに5月の第2日曜日に決めて(きめて)いるのは日本とアメリカで、スペインは5月の第1日曜日、スウェーデンは5月の最終(さいしゅう)日曜日。他(ほか)にもノルウェーは2月、タイは8月、アルゼンチンは10月、インドネシアは12月と、世界中で毎月(まいつき)のように行われて(おこなわれて)いるんだね。日本も戦前(せんぜん)は3月6日に行っていたけれど、戦後(せんご)からはアメリカと同じ(おなじ)ように5月の第2日曜日にしたんだよ。日頃(ひごろ)、みんなのために頑張って(がんばって)くれているお母さんに感謝(かんしゃ)する日、年に1度(ど)だけじゃなくてもっとあってもいいよね。
5月5日は男の子のお祭り(まつり)の日でお休み(やすみ)なのに、なぜ女の子のお祭りの3月3日はお休みじゃないんですか?
これはおもしろい質問(しつもん)だね。たしかに5月5日がお休みで、3月3日が休みじゃないなんて、なんだか男の子だけが特別扱い(とくべつあつかい)されているみたいだよね。でもじつはそうじゃないんだ。その理由(りゆう)について解説(かいせつ)するね。 みんなは、3月3日は「桃(もも)の節句(せっく)【雛祭り(ひなまつり)】」、5月5日は「端午(たんご)の節句」と呼ばれて(よばれて)いるのを知って(しって)いるかな。この「節句」というのは、古くから季節(きせつ)の変わり目(かわりめ)に行われていた日本(にほん)の伝統的(でんとうてき)な行事(ぎょうじ)のことで、じつは江戸時代(えどじだい)までは3月3日も5月5日も祝日(しゅくじつ)だったんだ。でも明治時代(めいじじだい)に入って(はいって)からこの祝日をやめてしまったんだ。それからしばらくして太平洋戦争(たいへいようせんそう)が終わり(おわり)、国民(こくみん)の休日(きゅうじつ)を増やす(ふやす)ことになったんだけど、その時に新しく(あたらしく)加わった(くわわった)のが5月5日の「子どもの日」なんだ。子どもの健やかな(すこやかな)成長(せいちょう)を祝う(いわう)祝日ということで、最初(さいしょ)は、桃の節句の3月3日と端午の節句の5月5日が候補(こうほ)に上がっていたけど、3月だと北海道(ほっかいどう)や東北地方(とうほくちほう)ではまだ寒い(さむい)ということで、全国的(ぜんこくてき)に暖かい(あたたかい)季節(きせつ)の5月5日を「こどもの日」に決めた(きめた)んだ。 だから5月5日は、男の子のお祭りだから休みなんじゃなくて、たまたま同じ(おなじ)日に重なった(かさなった)「子どもの日」だからお休みというわけなんだ。でも、もしこんど休日を増やすことになったら3月3日もお休みにしてほしいよね。
「2月は28日か、うるう年の29日しかありませんが、過去(かこ)に2月30日があったというのは本当(ほんとう)ですか?」
答え(こたえ)は“本当”だよ。みんな知って(しって)いるとおり、一年のうちほとんどの月は30日か31日だけど、2月だけが28日【4年に一度(いちど)のうるう年は29日】だよね。ところが過去に2月30日が存在(そんざい)したときが3回(かい)あったんだ。最初(さいしょ)は1712年にスウェーデンで、その次(つぎ)は1930年と1931年にソビエト連邦(れんぽう:今のロシア)で、2月30日という日があったんだよ。
今の暦(こよみ)は、グレゴリオ暦(れき)といって1582年から使われて(つかわれて)いるもので、それ以前(いぜん)は1600年以上(いじょう)にわたり、ユリウス暦という暦が使われていたんだ。このユリウス暦は、1年、つまり地球(ちきゅう)が太陽(たいよう)の周り(まわり)を回る(まわる)日数(にっすう)を365日とし、4年に一度うるう年を入れて(いれて)366日としていたんだ。でも実際(じっさい)には、日数の数え方(かぞえかた)に微妙(びみょう)なズレがあり、数百年という長い年月(ねんげつ)が経つ(たつ)うちに、ユリウス暦が示す(しめす)暦と実際の季節(きせつ)との間(あいだ)にズレが生じて(しょうじて)きてしまったんだ。そこで、より正確(せいかく)なグレゴリオ暦という新しい(あたらしい)暦を1582年から採用(さいよう)し、このズレを修正(しゅうせい)したということなんだ。
多く(おおく)の国(くに)が、ユリウス暦からこのグレゴリオ暦にいっきに変えた(かえた)んだけど、当時(とうじ)のスウェーデンとソビエト連邦は、しばらく経ってからそれぞれ独自(どくじ)のやり方(やりかた)でグレゴリオ暦に変えていったんだ。その時に、使ったのが2月30日。ふつうの年には存在(そんざい)しない2月30日を追加(ついか)することで暦を調整(ちょうせい)し、少し(すこし)ずつグレゴリオ暦に移行(いこう)させていったんだって。暦の話はちょっと難しい(むずかしい)ので、時間(じかん)があるときに時(とき)と暮らし(くらし)の「今の暦は世界共通(せかいきょうつう)?」も参考(さんこう)にみてね。
お正月(おしょうがつ)といえば1月1日ですが、どうして「旧正月(きゅうしょうがつ)」は、年によって日づけが違う(ちがう)のですか?
これは、旧正月(きゅうしょうがつ)は、旧暦(きゅうれき)によって決められて(きめられて)いるからなんだよ。明治時代(めいじじだい)まで使われて(つかわれて)いた旧暦では、月の満ち欠け(みちかけ)を基準(きじゅん)として1ヶ月(かげつ)の長さを決めていたんだけど、1ヶ月は約(やく)29.5日しかなかったんだ。それを調整(ちょうせい)するために大(だい)の月(30日)と小(しょう)の月(29日)をつくり運用(うんよう)していたんだ。でもこれでいくとすぐに季節(きせつ)と月のずれが出てしまうために、うるう月を入れる(いれる)ことで調整(ちょうせい)していたんだ。ここに1996年から2010年までの旧正月の日づけがあるけれど、2月の時もあれば、1月の時もあるよね。これはうるう月が入るか入らないかによって、すぐに今使われて(つかわれて)いるの暦(こよみ)での月名(つきめい)がずれてしまうからなんだよ。日本(にほん)でも地方(ちほう)によっては、昔(むかし)のなごりで旧正月を盛大(せいだい)に祝う(いわう)ところもあるし、中国(ちゅうごく)やベトナムでは、現在(げんざい)の正月よりも、はるかに旧正月の方が盛り上がる(もりあがる)んだよ。
1996年 2月19日
1997年 2月8日
1998年 1月28日
1999年 2月16日
2000年 2月5日
2001年 1月24日
2002年 2月12日
2003年 2月1日
2004年 1月22日
2005年 2月9日
2006年 1月29日
2007年 2月18日
2008年 2月7日
2009年 1月26日
2010年 2月14日
ヨーロッパのある国(くに)では、クリスマスの終わり(おわり)は新年(しんねん)になってからだと聞きました(ききました)が、これは本当(ほんとう)ですか?
クリスマスはもともとキリスト教(きょう)のお祭り(まつり)なので、カソリック(→カトリック)の影響(えいきょう)が強い(つよい)イタリア、スペイン、フランスなどの国々(くにぐに)では、12月25日に始まって(はじまって)1月6日に終わる(おわる)んだよ。だからクリスマスツリーをかたづけるのもこの日で、子どもたちがプレゼントをもらうのもこの日なんだ。日本では、クリスマスイブが終わると、いっきに世間(せけん)がお正月(しょうがつ)ムードになってしまうけどね。子どもたちにとっては、クリスマスプレゼントをもらって、その後(あと)すぐにお年玉(おとしだま)をもらえるというとてもうれしい時期(じき)だよね。
11月は、30日しかない小(しょう)の月ですが、大(だい)の月と小の月の覚え方(おぼえかた)で「西向く士(にしむくさむらい)」というのがありますが、その他(ほか)の覚え方もあるのでしょうか?
これはおもしろい質問(しつもん)だね。大の月【31日】、小の月【31日未満(みまん)】を覚えるのに「西向く士」、数字(すうじ)で表す(あらわす)と「2 4 6 9 11【士(さむらい)の漢字(かんじ)は十と一からできている】」で、とっても覚えやすいよね。でも外国(がいこく)では、指(ゆび)の関節(かんせつ)を使って(つかって)覚えたりする方法(ほうほう)もあるらしいよ。それじゃ、そのやり方(かた)を説明(せつめい)するね。まず親指(おやゆび)を中に入れた(いれた)グーをつくります。そして、指とすきまを数えて(かぞえて)いきます。人差し指(ひとさしゆび)が1月、人差し指と中指(なかゆび)の間が2月、ちょうどくぼんでいるよね。そして中指が3月、中指と薬指(くすりゆび)の間が4月、薬指が5月、薬指と小指(こゆび)の間が6月、小指が7月、そしたらまた人差し指に戻って(もどって)8月、人差し指と中指の間が9月、中指が10月、中指と薬指の間が11月、薬指が12月。ちゃんと大の月と小の月が覚えられるっていうしくみだよ。これ以外(いがい)にもいろいろあるらしいので、調べて(しらべて)みるとおもしろいかもしれないよ。
10月の呼び名(よびな)を調べて(しらべて)いたら「小春(こはる)」という呼び方(よびかた)が出てきました。季節(きせつ)は秋(あき)なのにどうして「小春」というのでしょうか?教えて(おしえて)ください。
たしかに不思議(ふしぎ)だよね。でも、晩秋(ばんしゅう)から初冬(しょとう)にかけては、穏やか(おだやか)で暖かい(あたたかい)天気(てんき)の日があり、まるで春(はる)のようなことから、このように呼ばれる(よばれる)んだよ。実際(じっさい)は陰暦(いんれき)の10月のことなので、現在(げんざい)の太陽暦(たいようれき)では11月になるんだよ。この頃(ころ)の気候(きこう)のことを英語(えいご)ではインディアン・サマーといって「春」じゃなくて「夏(なつ)」なんだよ。おもしろいよね。
9月1日は「台風(たいふう)がよく来る(くる)日」と言われて(いわれて)いますが、これは本当(ほんとう)ですか?
9月1日は、立春(りっしゅん)から数えて(かぞえて)210日目(にちめ)にあたり、昔(むかし)から、台風(たいふう)がよく来る(くる)日と言われて(いわれて)きたのは本当(ほんとう)のことです。この頃(ころ)は、ちょうど稲(いね)の開花時期(かいかじき)にあたり、台風が来ると稲が全滅(ぜんめつ)してしまう可能性(かのうせい)もあるために、注意(ちゅうい)を促す(うながす)目的(もくてき)もあったと言われています。
たしかに、9月に入って(はいって)からの台風は風(かぜ)も雨(あめ)も強く(つよく)【近年(きんねん)は異常気象(いじょうきしょう)で、そうも言えないけれど】大きな被害(ひがい)をもたらすことが多い(おおい)ので、その日に確実(かくじつ)に来るわけではないけれど、人々(ひとびと)が意識(いしき)することで防災(ぼうさい)につながる効果(こうか)はあったのではないでしょうか?9月1日には風や海(うみ)の神様(かみさま)を鎮める(しずめる)お祭り(まつり)が全国各地(ぜんこくかくち)で行われて(おこなわれて)いるのも、そうした意味(いみ)があるのかもしれませんね。全国的(ぜんこくてき)には9月1日は「防災の日」です。みなさんも非常持ち出し袋(ひじょうもちだしぶくろ)の中身(なかみ)や、非常食(ひじょうしょく)のチェックをしてみてはいかがでしょう。
誕生石(たんじょうせき)ってありますが、誰(だれ)がいつ頃(ごろ)、決めた(きめた)んですか?
たしかに、これは疑問(ぎもん)に思う(おもう)よね。そこで調べて(しらべて)みたよ。この誕生石(たんじょうせき)の誕生(たんじょう)?にはいろいろな説(せつ)があるんだけど、日本(にほん)の場合(ばあい)、各月(かくげつ)の誕生石は、アメリカの宝石商(ほうせきしょう)が20世紀(せいき)の初め(はじめ)に決めた(きめた)ものをもとにして、1958年に全国宝石卸商協同組合(ぜんこくほうせきおろししょうきょうどうくみあい)がアレンジしたものが一いちばん古く、もっとも知られて(しられて)いるものなんだって。下に各月の誕生石を書いて(かいて)あるけど、日本では、サンゴ、ヒスイが追加(ついか)、イギリス、フランスでは水晶(すいしょう)とカーネリアンが追加されているんだよ。
1月の誕生石:ガーネット
2月の誕生石:アメシスト
3月の誕生石:アクアマリン・サンゴ・ブラッドストーン
4月の誕生石:ダイヤモンド・水晶
5月の誕生石:エメラルド・ヒスイ
6月の誕生石:パール・ムーンストーン・アレキサンドライト
7月の誕生石:ルビー・カーネリアン
8月の誕生石:サードニックス・ペリドット
9月の誕生石:ブルーサファイア
10月の誕生石:オパール・トルマリン
11月の誕生石:トパーズ・シトリン
12月の誕生石:ターコイズ・ラピスラズリ・ブルートパーズ・ジルコニア・タンザナイト
宝石(ほうせき)は、昔(むかし)から魔よけ(まよけ)の力(ちから)があるといわれたり、おまじないなどにも使われて(つかわれて)いたので、神秘的(しんぴてき)に感じる(かんじる)けれど、この「誕生石」が決まったきっかけは、宝石をたくさん売る(うる)ためのプロモーションのひとつだったみたいだね。
「6月は梅雨(つゆ)で、雨がいっぱい降って(ふって)水はたくさんあるのに、どうして「水無月(みなづき)」というの?」
これは、旧暦(きゅうれき)の6月のことなので、今の6月とはちょっと季節(きせつ)がずれているからなんだよ。ただ、この「水無月」については、いろいろな説(せつ)があって、一般的(いっぱんてき)にいわれるのが「梅雨が終わって(おわって)、水がなくなる月」というものだけど、その他(ほか)に「田んぼに水を張る(はる)月」の「水張り月」「水月」が変化(へんか)したものという説もあるんだよ。ただいえるのは、旧暦で6月は、もう梅雨が終わっている時期(じき)だということだね。
「鯉(こい)のぼりを6月にあげるところがあると聞いた(きいた)のですが本当(ほんとう)ですか?」
これは本当(ほんとう)なんだよ。日本(にほん)の伝統行事(でんとうぎょうじ)は、もともとは旧暦(きゅうれき)で行われて(おこなわれて)いたために、お雛祭り(おひなまつり)も、端午(たんご)の節句(せっく)も、七夕(たなばた)も地方(ちほう)によってはまだ旧暦で行われているところがあるんだよ。ほぼ1ヶ月(かげつ)うしろにずれていると思って(おもって)もらえば大丈夫(だいじょうぶ)だよ。ちなみに日本でいちばん有名(ゆうめい)な仙台(せんだい)の七夕祭り(たなばたまつり)も、新暦(しんれき)の7月ではなく旧暦の7月にあたる8月に行われているんだよ。
「春(はる)」はどうして「春」というんですか?
これはおもしろい質問(しつもん)だね。たしかに、どうしてこの「春」という呼び方(よびかた)がついたのかは気になるよね。そこで、調べて(しらべて)みたよ。「春」の語源(ごげん)については、いくつかあるけれど「草木(くさき)の芽(め)が張る【はる:ふくらむ、膨張(ぼうちょう)する】時だから」という説(せつ)がもっとも一般的(いっぱんてき)なんだ。そういわれてみると、春の草花(くさばな)のつぼみや芽は、パンパンに膨らんで(ふくらんで)今にも弾けそうな(はじけそうな)勢い(いきおい)を感じる(かんじる)よね。ちなみに、英語(えいご)で「春」は「spring(スプリング)」だけど、「spring」も「急に(きゅうに)動く(うごく)、飛び出る(とびでる)、水がわき出る」というような意味(いみ)なんだ。人が、季節(きせつ)に感じる(かんじる)印象(いんしょう)は、世界中(せかいじゅう)、わりと似通って(にかよって)いるんだね。
今年(ことし)はうるう年。うるう年は4年に1回(かい)必ず(かならず)やってくるものなのですか?
2月になると必ず(かならず)「うるう年」についての質問(しつもん)がくるよね。そもそも「うるう年」が生まれた(うまれた)理由(りゆう)から説明(せつめい)するね。太陽(たいよう)が春分点(しゅんぶんてん)を出発(しゅっぱつ)して黄道(こうどう)を一周(いっしゅう)し再び(ふたたび)春分点に戻って(もどって)くるまでの時間(じかん)、つまり地球(ちきゅう)が太陽の周り(まわり)を一周する時間【太陽年(たいようねん)と呼ぶ(よぶ)】の長さ(ながさ)は365.2422日。時間に置き換える(おきかえる)と、365日 5時間48分(ふん)46秒(びょう)となるんだ。暦(こよみ)の365日よりも、「5時間48分46秒」も実際(じっさい)の1年は長いんだよ。だから、この誤差(ごさ)が、昔(むかし)からの人類(じんるい)の「暦」に不都合(ふつごう)を生じ(しょうじ)させ悩ませて(なやませて)いたんだ。ほおっておくと、長い間(あいだ)に季節(きさつ)と暦に少し(すこし)づつ狂い(くるい)が生じ、生活(せいかつ)してゆく上でさまざまな問題(もんだい)が生じてしまうんだよ。そこで、この時間のずれを補正(ほせい)するよう配慮(はいりょ)されたものが「うるう年」なんだ。わかってくれたかな?それでは、質問(しつもん)に答える(こたえる)ね。結論(けつろん)は、「必ずしも4年に1回やってくるわけではない」ということなんだ。これは、今、世界的(せかいてき)に使われて(つかわれて)いるグレゴリオ暦(れき)にきちんと決められて(きめられて)いるんだよ。下の説明(せつめい)を読んで(よんで)ね。
1)西暦年(せいれきねん)が4で割り切れる(わりきれる)年はうるう年とする。
2)西暦年が4で割り切れる年でも、100で割り切れる年はうるう年としない。 西暦1700年、1800年、1900年は、4で割り切れるけど、100でも割り切れるので、うるう年ではなかったんだ。 だから、2100年、2200年、2300年もうるう年ではなくなるよね。
3)西暦年が4で割り切れ、100でも割り切れる年でも400で割り切れる年はうるう年とする。 今から8年前の2000年は、4で割り切れるけど、100でも割り切れ、さらに400で割り切れるので、うるう年になったんだよ。 次は、2400年になるよね。
素朴(そぼく)な疑問(ぎもん)です。1月のことをなぜ「お正月(しょうがつ)」というのですか?
確かに(たしかに)、これは不思議(ふしぎ)だよね。「正」という字(じ)には「ただしくする、改める(あらためる)、きちんとする、ちょうど」というような意味(いみ)があるんだ。つまり「正月」とは「改める月」という意味で、「魂(たましい)が若返り(わかがえり)、新しく(あたらしく)なる月」ということなんだ。ちなみに、今は、誕生日(たんじょうび)に歳(とし)をとるけれど、昭和(しょうわ)20年頃(ごろ)までの日本(にほん)では、元旦(がんたん)に歳をとることになっていたんだ。だから、元旦には家族全員(かぞくぜんいん)が一緒(いっしょ)に歳をとったことを祝った(いわった)んだよ。バースデーケーキはないけれど、みんなで一緒に歳をとるっていうのもなにか幸せ(しあわせ)でいいよね。
イタリアやフランスのクリスマスは日本(にほん)とはちょっと違う(ちがう)と聞いた(きいた)ことがあるのですが、どんなふうに違うんでしょうか?
日本(にほん)では、クリスマスといえば、12月24日のイブがいちばん盛り上がって(もりあがって)、25日になるとなんか急(きゅう)にしぼんでしまって、ケーキの投げ売り(なげうり)が始まったり(はじまったり)するよね。そして26日になれば、テレビでは、すぐにお正月(しょうがつ)のCM(シーエム)が始まったりして、いやが上にでもお正月気分(きぶん)にさせられちゃうよね。でも、もともと、クリスマスはカソリックのお祭り(まつり)なので、カソリックの影響(えいきょう)が強い(つよい)イタリアやフランスでは、クリスマスは12月25日に始まって1月6日に終わる(おわる)んだよ。つまり年をまたいでのお祭りということなんだ。クリスマスプレゼントをもらうのは25日じゃなくて、クリスマスの終わりの日である1月6日なんだよ。なんか遅い(おそい)お年玉(おとしだま)みたいだね。
11月3日の文化(ぶんか)の日は、晴れ(はれ)になる確率(かくりつ)の高い「特異日(とくいび)」だという話を聞きました(ききました)が、この「特異日」ってどんな日なのですか?
おもしろい質問(しつもん)をありがとう。「特異日」というのは、気象学的(きしょうがくてき)な理由(りゆう)はないけれど、統計(とうけい)をとると毎年(まいとし)、その日には、特定(とくてい)の天気【てんき:晴れ(はれ)/雨(あめ)/雪(ゆき)】が現れる(あらわれる)傾向(けいこう)のある日のことをいうんだよ。これは日本(にほん)だけではなく、海外(かいがい)でもあるんだよ。ここでいくつか、特異日の例(れい)をあげてみるね。
1月16日:晴れの特異日
3月14日:晴れの特異日
3月30日:雨の特異日
6月1日:晴れの特異日
6月28日:雨の特異日
8月18日:猛暑(もうしょ)の特異日
9月17日:台風(たいふう)襲来(しゅうらい)の特異日
10月10日:晴れの特異日
とくに10月10日は晴れの特異日として有名(ゆうめい)で、東京(とうきょう)オリンピックの開会日(かいかいび)に選ばれた(えらばれた)のも、それが理由(りゆう)なんだよ。科学的(かがくてき)な根拠(こんきょ)はないのに不思議(ふしぎ)だよね。
9月は英語(えいご)で書く(かく)と「September」ですが、「Sept」という文字(もじ)には「数字(すうじ)の7」という意味(いみ)があると聞き(きき)ました。9月なら「数字の9」に当たる(あたる)文字をつけるのが普通(ふつう)だと思い(おもい)ますが、どうしてですか?
これはおもしろいところに気がついたね。確かに(たしかに)「Sept」は「7」で、「September」は「7番目(ばんめ)の月(つき)」という意味(いみ)なんだよ。でも暦(こよみ)では「9月」だよね。ついでに言って(いって)おくと10月は「October」で「Oct」は「8」を意味する言葉(ことば)なんだよ。こうしてみると暦と月の名前(なまえ)には2ヶ月(かげつ)のズレがあることがわかるよね。つまり、もともとは、「September」は「7月」、「October」は「8月」だった時代(じだい)があったということなんだ。今から2000年以上(いじょう)も前(まえ)の古代(こだい)ローマ時代には、3月が1年の始まり(はじまり)の月で、それで数えて(かぞえて)いくとちゃんと合う(あう)よね。しかも、3月が1年の始まりだったので、春(はる)、夏(なつ)、秋(あき)、冬(ふゆ)という季節(きせつ)の流れ(ながれ)ともピッタリとあっていたんだよ。それを変えて(かえて)しまったのがローマ帝国初代皇帝(ていこくしょだいこうてい)のユリウス・シーザーだ。これにつては「時(とき)と人」のコーナーに詳しく(くわしく)書いてあるから読んで(よんで)みてね。
夏至(げし)の日は、北半球(きたはんきゅう)ではいちばん昼(ひる)の時間(じかん)が長く(ながく)なると聞き(きき)ました。昼の時間が長いということは、いちばん日照時間(にっしょうじかん)が長いということで、そうなると夏至の日【6/22】がいちばん暑く(あつく)なると思う(おもう)のですが、夏至よりも日照時間が少ない(すくない)8月とかの方(ほう)が暑いのはなぜですか?
確かに(たしかに)そう思う(おもう)よね。地球(ちきゅう)が太陽(たいよう)の熱(ねつ)に暖められて(あたためられて)いる時間(じかん)が長ければ(ながければ)、気温(きおん)は上がって(あがって)いくはずだよね。でも日本(にほん)でいえば、夏至(げし)の頃(ころ)は、ちょうど梅雨(つゆ)の真っ最中(まっただなか)で、しとしとと雨が降り続いて(ふりつづいて)、冬よりも日照時間(にっしょうじかん)が少ない(すくない)日もあったりするんだよ。そうすると雲(くも)にさえぎられて太陽の熱は届かず(とどかず)気温が上がらないということになるんだ。それに、気温は地球の地表温度(ちひょうおんど)とも関連(かんれん)があって、地表温度というのは、短い(みじかい)時間に大量(たいりょう)の熱を与えても(あたえても)すぐに上がるわけじゃなくて、少しずつ熱が蓄えられて(たくわえられて)温度が上がっていくんだよ。だから、暑い日がずっと続く(つづく)ことで、どんどんと地表温度が上がっていって、それにともなって気温も上昇(じょうしょう)し、8月の頃(ころ)には暑さがピークになっているということなんだよ。わかったかな?
6月は「ジューンブライド」とか「6月の花嫁(はなよめ)は幸せ(しあわせ)になれる」とか言われて(いわれて)結婚式(けっこんしき)の多い(おおい)季節(きせつ)だそうですが、6月は梅雨入り(つゆいり)もあって、天気(てんき)もあまりよくなく、せっかくおめかしして結婚式にでかけても、雨でびしょびしょになってしまったりと、結婚式をするのには、あまりふさわしい月ではないと思う(おもう)のですが、どうしてなんですか?
ははは、おもしろい質問(しつもん)だね。たしかにその通り(とおり)だよね。「ジューンブライド」は「6月に結婚式(けっこんしき)を挙げた(あげた)花嫁(はなよめ)は幸せ(しあわせ)になれる」とかいう言い伝え(いいつたえ)なんだけど、名前(なまえ)からもわかるように日本(にほん)の言葉(ことば)ではないんだ。「6月の花嫁が幸せになれる」という言い伝えは、もともとヨーロッパから来た(きた)もので、それをそのまま日本にあてはめてしまったから、こんな事態(じたい)になっているんだよ。ヨーロッパの6月は、日本と違って(ちがって)とっても天気(てんき)がよく1年でもっとも雨の少ない(すくない)月なんだ。 そして6月はキリスト教(きょう)のお祭り(おまつり)が行われる(おこなわれる)時期(じき)でもあるんだ。天気は良く、街行く(まちゆく)人々(ひとびと)もお祝い(おいわい)の気分(きぶん)がいっぱい、そんな中で結婚式を挙げたら、それは幸せになれそうな気がするよね。
「五月雨(さみだれ)」という言葉(ことば)がありますが、5月は比較的(ひかくてき)お天気(てんき)の良い(よい)日が多く、雨は少ない(すくない)と思います(おもいます)。なのに、どうして5月に降る(ふる)雨をわざわざこんなふうに言う(いう)ようになったんですか?
これはなかなかおもしろい質問(しつもん)だね。確かに(たしかに)今の5月は、ニュースなどでも「五月晴れ(さつきばれ)の良い(よい)1日でした」というように爽やか(さわやか)に晴れた日が多くて(おおくて)「五月雨(さみだれ)」なんて言葉(ことば)は似合わない(にあわない)よね。でもこれは新暦(しんれき)だからこそ、旧暦(きゅうれき)では5月は梅雨(つゆ)の真っ只中(まっただなか)、だから「五月雨(さみだれ)」というのは梅雨のことなんだよ。「五月雨式(さみだれしき)に」と形容(けいよう)されるのは、梅雨の雨のようにだらだらと長く続く(つづく)という意味(いみ)なんだ。旧暦から新暦に変わった(かわった)ことで、昔(むかし)から使われて(つかわれて)きている言葉(ことば)にもズレが出てしまっているんだ。そんなこともあり、最近(さいきん)では「五月晴れ」のことを「さつきばれ」と言わず(いわず)に「ごがつばれ」とあえて読み方(よみかた)を変えて5月の天気の良い日のことを表現(ひょうげん)する人もいるんだよ。こういうのを見ていると「言葉(ことば)が生き物(いきもの)だ」と言われる理由(りゆう)がわかるよね。
カレンダーの「大(だい)の月(つき)」と「小(しょう)の月」がよく覚えられ(おぼえられ)ません。よく、今月(こんげつ)は何日だっけ?なんて考えて(かんがえて)しまうことがあります。なにかいい覚え方(おぼえかた)ってないですか?
昔(むかし)から使われて(つかわれて)いる「小(しょう)の月(つき)」の覚え方(おぼえかた)を紹介(しょうかい)するね。それは「西(にし)向く(むく)侍(さむらい)」。「西向く侍」は「に[2月]し[4月]む[6月]く[9月]さむらい[11月]」となっていて、最後(さいご)の侍は「武士(ぶし)の士」。「士」を分解(ぶんかい)すると「十と一」になるんだ。誰(だれ)が考えた(かんがえた)のか知らない(しらない)けれど、おもしろい覚え方だよね。おじいちゃんやおばあちゃんに聞いて(きいて)みたらきっと知っていると思う(おもう)から、機会(きかい)があったら聞いて(きいて)みるといいよ。
4年に1回(かい)しかないうるう年の2月29日に生まれた(うまれた)人は4年に1回しか年をとらないんですか?
これを説明(せつめい)するにはまず、「年齢計算(ねんれいけいさん)に関する(かんする)法律(ほうりつ)」について説明する必要(ひつよう)があるんだ。この法律によると年齢の数え方(かぞえかた)は「誕生日(たんじょうび)の前日(ぜんじつ)に満年齢(まんねんれい)に達する(たっする)」という決まり(きまり)になっていて、2月29日生まれの人でも、2月28日になった時点(じてん)で、ちゃんと年を一つとるということになるんだよ。この「年齢計算に関する法律」は、学校(がっこう)の入学年(にゅうがくねん)を決めるのにも使われて(つかわれて)いて、同学年(どうがくねん)になるのはその年の4月2日が誕生日の人から翌年(よくねん)の4月1日までの人ということになるんだよ。つまり誕生日の前日(ぜんじつ)で満年齢になるからなんだ。わかってくれたかな?
1000年後(ご)の地球(ちきゅう)は、どうなっているのですか
これはとても難しい(むずかしい)質問(しつもん)だね。それではまず、今から1000年前のことを考えて(かんがえて)みよう。2007年の1000年前(まえ)といえば、11世紀(せいき)だよね。日本(にほん)はちょうど平安時代(へいあんじだい)、1010年に書かれた(かかれた)「源氏物語(げんじものがたり)」の世界(せかい)だと思って(おもって)くれればよいかな。さて、その当時(とうじ)の人たちが、1000年後の世界を想像(そうぞう)できたかな?たぶん、まったく想像できながったんじゃないかな?極端(きょくたん)にいえば、私たちのおじいさんやおばあさんが、子どもの頃(ころ)に、2007年の今の世界を想像できたかといえば、これも無理(むり)だったんじゃないかな?科学(かがく)の発展(はってん)はめざましく、次々(つぎつぎ)と新しい(あたらしい)技術(ぎじゅつ)が開発(かいはつ)されて、世の中(よのなか)は変わって(かわって)いってしまうんだ。1000年後の世界はきっと、今の人たちが想像もつかない世界になっているんじゃないかな。はっきりとした答え(こたえ)じゃなくてごめんね。
よく「旧正月(きゅうしょうがつ)」という言葉(ことば)を聞きます(ききます)が、お正月に「新旧(しんきゅう)」があるんですか?
日本(にほん)で現在(げんざい)使われて(つかわれて)いる暦(こよみ)は、世界中(せかいじゅう)で標準(ひゅうじゅん)の暦として使われている太陽暦(たいようれき)なんだけど、明治(めいじ)の改暦(かいれき)をする前は、月の満ち欠け(みちかけ)を基本(きほん)に太陽暦の要素(ようそ)を加えて(くわえて)つくられた太陽太陰暦[(たいようたいいんれき:旧暦(きゅうれき)]が使われていたんだ。だから、旧正月というのは、旧暦で数えた時の正月ということになるんだ。今の暦よりもっずっと長い間使われていた旧暦は、お祭り(おまつり)などの開催日(かいさいび)を旧暦でやるなど、今もなごりが残って(のこって)いるんだよ。でも、旧暦の場合(ばあい)は毎年(まいとし)、元旦(がんたん)の日が変わる(かわる)んだ。2007年は今の暦でいうと2月18日が元旦(がんたん)となり、その日から旧正月となるんだよ。
1年の終わり(おわり)は何時(なんじ)何分(なんぷん)何秒(なんびょう)ですか?
年末(ねんまつ)になるとやっぱり、こういうことが気になるよね。でもね、これはハッキリと言えない(いえない)んだよ。2006年12月31日23時59分59秒の1秒後(ご)には確かに(たしかに)、2007年1月1日の0時0分0秒がやってくるけれど、その最後(さいご)の1秒というのは限りなく(かぎりなく)細かく(こまかく)できるんだ。ミリ秒、マイクロ秒、ナノ秒、ピコ秒、フェトム秒、アト秒、ゼプト秒、ヨクト秒というようにね。つまり2006年12月31日23時59分59.999999999999999999999999999999999・・・・・秒と単位(たんい)がないところまで理論上(りろんじょう)は、時刻(じこく)は存在(そんざい)していることになって、でもその終わりがないうちに、いつの間にか、2007年1月1日の0時0分0秒が来てしまうんだよ。不思議(ふしぎ)でしょ。
10月は、昔(むかし)「神無月(かんなづき)」と言われて(いわれて)いたのはなぜ?
「神無月」と書いて(かいて)、「かんなづき」と読む(よむ)んだけど、これは10月になると、日本中(にほんじゅう)の神様(かみさま)が、出雲(いずも)の国(くに)【現在(げんざい)の島根県(しまねけん)】に集まり(あつまり)会議(かいぎ)を開く(ひらく)ため、出雲以外(いがい)の国には神様がいなくなってしまうことからそう呼ばれて(よばれて) きたんだよ。おもしろいことに、神様の集まる出雲の国では反対(はんたい)に10月は神在月(かみありづき)と呼ばれているんだよ。
もともとこの会議が行われる(おこなわれる)ようになったのは、日本の国土(こくど)をつくった大国主神(おおくにぬしのかみ)が、自分(じぶん)の息子(むすこ)や娘(むすめ)を各国(かっこく)に配置(はいち)し、その地(ち)を管理(かんり)させたからなんだ。つまりは、子どもたちが一斉(いっせい)に里帰り(さとがえり)をするということなんだよ。そのうちに、大国主神系以外(おおくにぬしのかみけいいがい)の天照大神系(あまてらすおおみかみけい)の神様も出雲にくるようになり、日本中の神様が、やってくることになったんだ。
さて、この神様たちの会議は旧暦(きゅうれき)の10月11日から17日までの間(あいだ)、出雲大社で開かれて、その後(ご)は、佐太神社(さだじんじゃ)に移動(いどう)し26日まで会議の続き(つづき)を行う(おこなう)んだよ。ちょうどその期間(きかん)には、出雲大社と佐太神社で神在祭(かみありさい)が行われるんだ。なかなかおもしろい話だよね。
どうして、5月の連休(れんきゅう)の時のことをゴールデンウィークって言う(いう)の?
これはおもしろい質問(しつもん)だね。これにはいくつかの説(せつ)があるんだよ。「ゴールデンウィーク」というのは和製英語(わせいえいご)で、もちろんアメリカにはないものなんだ。まず、昭和(しょうわ)26年に、日本の映画関係者(えいがかんけいしゃ)が5月の連休期間(れんきゅうきかん)を「黄金週間(おうごんしゅうかん)」と決めた(きめた)のが始まり(はじまり)ということなんだ。この連休期間中は映画館(えいがかん)にたくさんの観客(かんきゃく)がつめかけて、映画業界(えいがぎょうかい)はものすごく儲かった(もうかった)から、映画関係者にすれば、まさに「黄金週間」だよね。ただこの「黄金週間」という言葉(ことば)では、インパクトがないということで「ゴールデンウィーク」としたらしいんだ。この他(ほか)にもアメリカのゴールドラッシュが由来(ゆらい)になっているという説があるけれど、アメリカでGolden weekと言う言葉がないので、この映画業界からの説が有力(ゆうりょく)なんだよ。おもしろいことに、NHK(エヌエイチケー)のニュースでは「ゴールデンウィーク」と言わずに「大型連休(おおがたれんきゅう)」と言い続けて(いいつづけて)いるらしいよ。
2月の日数(にっすう)がほかの月より少なめ(すくなめ)なのは、なぜですか??
これは誰(だれ)もが一度(いちど)は疑問(ぎもん)に思う(おもう)ことだよね。この質問(さいしょ)に答える(こたえる)には、まずは今使って(つかって)いる暦(こよみ)の成り立ち(なりたち)から説明(せつめい)しないといけないんだ。今、私たちが使っている暦を「グレゴリオ暦(れき)」というのは知って(しって)いるかな?この暦は1582年に当時(とうじ)のローマ法王(ほうおう)のグレゴリオ13世(せい)が決めた(きめた)ものなんだよ。その暦のもとになったのが紀元(きげん)49年にユリウス・シーザー[ジュリアス・シーザー]がつくったユリウス暦というもので、当時(とうじ)すでに、1年は365日と1/4日というのがわかっていて、この日数(にっすう)を暦にする時に12分割(ぶんかつ)して、それぞれの月に割り当てた(わりあてた)んだ。ユリウス暦の場合(ばあい)はキチンと大(だい)の月[31日]、小(しょう)の月[30日]というようにわかれていて、わかりやすかったんだけど、シーザーの後(あと)にローマ皇帝(こうてい)になった、アウグストゥスが、自分(じぶん)の名前(なまえ)のついた8月が小の月[30日]とはけしからんということで、2月[うるう年には30日で小の月になる]を29日から28日に減らして(へらして)、8月を31日に無理矢理(むりやり)変更(へんこう)してしまったんだ。つまりは、2月が他(ほか)の月よりも少ない(すくない)のは、アウグストゥスのわがままで勝手(かって)に決めて(きめて)しまったということなんだ。 その暦が今もずーっと使われているんだよ。
みんなからよくもらう質問(しつもん)の中から「カレンダーは1月から始まって(はじまって)12月に終わる(おわる)けど、学校(がっこう)は4月から始まって3月に終わるのはなぜですか?」という質問を取り上げて(とりあげて)みたよ。いつも「どうしてかな?」って不思議(ふしぎ)に思って(おもって)いる人はぜひ、読んで(よんで)みてね。
これは年の始め(はじめ)に、みんな不思議(ふしぎ)に思う(おもう)ことだよね。年賀状(ねんがじょう)にも「新春(しんしゅん)」って書いて(かいて)あるのに、季節(きせつ)は真冬(まふゆ)だもんね。それでは、まずカレンダーの話からしよう。西洋(せいよう)では「春分(しゅんぶん):現在(げんざい)の3月21日ごろ」の日を1年の始め(はじめ)とする国が多く(おおく)、暦(こよみ)と季節(きせつ)は一致(いっち)していたんだよ。このままの暦であれば、新学期(しんがっき)の始まりも1年の始まりも同じ(おなじ)だから問題(もんだい)はないよね。ところが、紀元前(きげんぜん)46年、ローマ帝国(ていこく)初代皇帝(しょだいこうてい)のジュリアス・シーザーが政治(せいじ)の年度(ねんど)の始まりの月を1年の始まり、つまり1月にしてしまったんだ。現在(げんざい)、使われて(つかわれて)いる暦は、このシーザーの暦がもとになっているので、季節と暦はそれ以来(いらい)ずっとズレたままなんだ。
さて、それでは、次(つぎ)は学校(がっこう)の新学期(しんがっき)の話をしよう。日本(にほん)の教育制度(きょういくせいど)の基本(きほん)は明治時代(めいじじだい)に決められて(きめられて)、その時に参考(さんこう)にしたのが、アメリカとフランスの教育制度だったんだ。どちらの国(くに)も新学期は9月から始まる(はじまる)んだ。もちろん日本もそれにならって、小学(しょうがく)・中学(ちゅうがく)・大学(がいがく)の新学期が9月からで、士官学校(しかんがっこう)などの軍関係(ぐんかんけい)の学校だけは翌年(よくねん)4月からとなっていたんだ。ところが、当時(とうじ)、大学生は軍隊(ぐんたい)に行かなくて(いかなくても)も良い(よい)という特典(とくてん)があって、優秀(ゆうしゅう)な学生(がくせい)のほとんどが9月から始まる普通(ふつう)の学校に入学(にゅうがく)し、翌年の4月に入学する士官学校などの学生の質(しつ)が落ちて(おちて)しまったんだ。そこで困った(こまった)軍部(ぐんぶ)が、圧力(あつりょく)をかけ、新学期の始まりを9月から4月に変更(へんこう)したんだ。西洋(せいよう)で9月に学校が始まるようになったのは、昔(むかし)の子どもたちは春から夏の間(あいだ)は農作業(のうさぎょう)などを手伝い(てつだい)、秋から冬にかけて学校に通った(かよった)ことからきているらしいよ。日本も西洋も、けっこうおとなや社会(しゃかい)の都合(つごう)によって決められた(きめられて)みたいだね。
なんで、一年は、365日か366日と決まって(きまって)いるんですか?
1年が365日[うるう年は366日]の暦(こよみ)は「太陽暦(たいようれき)[グレゴリオ暦]」と言われていて、1582年から世界(せかい)で使われ(つかわれ)始める(はじめる)ようになったんだよ。
もともとは古代(こだい)エジプトで生まれ(うまれ)ローマ時代(じだい)にほぼヨーロッパ全体(ぜんたい)に広がった(ひろがった)んだよ。でもその時はまだ1年は365日で、うるう年という考え方(かんがえかた)はなかったんだよ。うるう年の考え方が暦に加えられた(くわえられた)のが紀元前(きげんぜん)49年、1年を365.25日となったんだ。これがユリウス暦という暦で、そのまま1582年まで使われていたんだよ。でも、実際(じっさい)の太陽年(たいようねん)とのズレがあって、16世紀(せいき)になった時には、なんと10日も暦がズレてしまったんだよ。そこで1582年に、1年を365.2425日とする「太陽暦[グレゴリオ暦]」が採用(さいよう)されて、それが世界の暦の標準(ひょうじゅん)となって、今も使われているんだよ。でも、世界(せかい)には1年が365日ではない暦を宗教(しゅうきょう)などの行事(ぎょうじ)に限って(かぎって)使っている国もあるんだよ。イスラム暦は1年が354日、マヤ暦は364日なんだよ。
セシウムが1967年にうんぬんと書かれて(かかれて)いて、1秒(びょう)に決まり(きまり)ました。とありますが、この1967年はかなり最近(さいきん)のような気がするのですが、この年度(ねんど)はあっていますか?
実際(じっさい)に、セシウムの振動回数(しんどうかいすう)による1秒(びょう)の定義(ていぎ)が決まった(きまった)のは1967年に間違い(まちがい)ないんだ。たしかに、歴史的(れきしてき)に見ると、ずいぶんと新しい(あたらしい)気がするよね。もう少し(すこし)詳しく(くわしく)言うと、国際原子時(こくさいげんしじ)が定められた(さだめられた)のが1958年の1月1日。それから国際度量衡総会(こくさいどりょうこうそうかい)で正式(せいしき)に秒の定義を天文時(てんもんじ)から原子時(げんしじ)へ変更(へんこう)する1967年までの10年間は、原子時[原子時計(げんしどけい)で測る(はかる)時間]と天文時[地球(ちきゅう)の自転(じてん)を基準(きじゅん)に測る時間]の比較(ひかく)がずっと続けられて(つづけられて)いたんだよ。その結果(けっか)を受けて(うけて)、原子時へと変更することが決められた(きめられた)んだよ。さらに、1972年には、国際原子時をもとに地球の自転の変化分をうるう秒の挿入(そうにゅう)によって補正(ほせい)する新たな(あらたな)協定世界時(きょうていせかいじ)が定められた(さだめられた)んだよ。
4月1日生まれ(うまれ)の人はなぜ、年(とし)が一つ下がる(さがる)んですか?????
確か(たしか)に不思議(ふしぎ)に思う(おもう)よね。じつは年齢(ねんれい)の計算方法(けいさんほうしき)を定めた(さだめた)法律(ほうりつ)というのがあって、そこで、年齢の数え方(かぞえかた)は、誕生日(たんじょうび)の前日(ぜんじつ)を持って(もって)、満年齢(まんねんれい)に達する(たっする)という決まり(きまり)になっているんだ。だから4月1日が誕生日(たんじょうび)の人は、前日の3月31日に満年齢になるので、小学校(しょうがっこう)などの入学年(にゅうがくねん)が1学年(がくねん)前(まえ)へ繰り上がる(くりあがる)ことになるんだよ。この計算のしかたがあるので、うるう年の2月29日生まれの人も、前日の2月28日に満年齢になるので、きちんと年が数えられていくんだよ。わかってくれたかな?
4年(ねん)に1回(かい)しかない2月29日に生まれた(うまれた)人は誕生日(たんじょうび)はそのままなのですか?つまり4年ごとに歳(とし)をとるってことですか?それとも誕生日が1日ずれるのですか?
確か(たしか)に2月29日は4年(ねん)に1度(ど)しかないよね。でも安心(あんしん)してね。じつは「年齢(ねんれい)計算(けいさん)に関する(かんする)法律(ほうりつ)」があって、年齢(ねんれい)の数え方(かぞえかた)は「誕生日(たんじょうび)の前日(ぜんじつ)に満年齢(まんねんれい)に達する(たっする)」と言う(いう)きまりになっているんだよ。だから2月29日生まれ(うまれ)の人でも、前日の2月28日になった時点(じてん)で歳(とし)が1つ増える(ふえる)んだよ。ちなみにうるう年の2月29日に生まれた有名人(ゆうめいじん)には、推理小説家(すいりしょうせつか)の赤川次郎(あかがわじろう)さん、タレントの飯島直子(いいじまなおこ)さん、俳優(はいゆう)の原田芳雄(はらだよしお)さんがいるんだよ。
カレンダーは1月から始まって(はじまって)12月に終わる(おわる)けど、学校(がっこう)は4月から始まって3月に終わるのはなぜですか?
これはなかなか気づかないけれど、いい質問(しつもん)だね。まずカレンダー[暦(こよみ)]の話からしよう。西洋(せいよう)では「春分(しゅんぶん):現在(げんざい)の3月21日ごろ」の日を1年の始め(はじめ)とする国(くに)が多く(おおく)、暦と季節(きせつ)は一致(いっち)していたんだよ。このままの暦であれば、新学期(しんがっき)の始まりも1年の始まりも同じ(おなじ)だから問題(もんだい)はないよね。ところが、紀元前(きげんぜん)46年、ローマ帝国(ていこく)初代皇帝(しょだいこうてい)のジュリアス・シーザーが政治(せいじ)の年度(ねんど)の始まりの月を1年の始まり。つまり1月にするということをしてしまったんだ。現在、使われて(つかわれて)いる暦は、このシーザーの暦がもとになっているので、季節と暦はそれ以来(いらい)ずっとズレたままなんだ。
さて、それでは、次(つぎ)は学校(がっこう)の新学期(しんがっき)の話(はなし)をしよう。日本(にほん)の教育制度(きょういくせいど)の基本(きほん)は明治時代(めいじじだい)に決められて(きめられて)、その時(とき)に参考(さんこう)にしたのが、アメリカとフランスの教育制度だったんだ。どちらの国も新学期は9月から始まる(はじまる)んだ。もちろん日本もそれにならって、小学(しょうがく)・中学(ちゅうがく)・大学(だいがく)の新学期が9月からで、士官学校(しかんがっこう)などの軍関係(ぐんかんけい)の学校だけは翌年(よくねん)4月からとなっていたんだ。ところが、当時(とうじ)、大学生(だいがくせい)は軍隊(ぐんたい)に行かなくて(いかなくても)もいいという特典(とくてん)があって、優秀(ゆうしゅう)な学生(がくせい)のほとんどが9月から始まる普通(ふつう)の学校に入学(にゅうがく)し、翌年の4月に入学する士官学校などの学生の質(しつ)が落ちて(おちて)しまったんだ。そこで困った(こまった)軍部(ぐんぶ)が、圧力(あつりょく)をかけ、新学期の始まりを9月から4月に変更(へんこう)したんだ。西洋(せいよう)で9月に学校が始まるようになったのは、昔(むかし)の子供(こども)たちは春(はる)から夏(なつ)の間(あいだ)は農作業(のうさぎょう)などを手伝い(てつだい)、秋(あき)から冬(ふゆ)にかけて学校に通った(かよった)ことから来て(きて)いるらしいよ。
なぜ十二支(12し)は年になるんですか?
十二支というのは、十干十二支(じっかんじゅうにし)と言って、下にある十干と十二支を組合わせ(くみあわせた)暦(こよみ)で、中国(ちゅうごく)の前漢(ぜんかん)の時代(じだい)に始まった(はじまった)ものなんだ。日本に入ってきたのは6世紀(せいき)ごろで、十干と十二支を「甲子(きのえね)」「丙午(ひのえうま)」というように組合わせて年、月、日にあてて使った(つかった)んだ。この組合わせが60通り(とおり)あって、60年で1周(しゅう)するわけなんだ。それが今も使われていて、午年(うまどし)や未年(ひつじどし)という言い方をするんだよ。でも同じ午年でも「庚午(かのえうま)」「壬午(みずのえうま)」「甲午(きのえうま)」「丙午(ひのえうま)」「戊午(つちのえうま)」と5つあるんだよ。今年は「壬午(みずのえうま)」の年なんだ。
●十干(じっかん)
甲(きのえ)乙(きのと)丙(ひのえ)丁(ひのと)戊(つちのえ)己(つちのと)庚(かのえ)
辛(かのと)壬(みずのえ)癸(みずのと)
●十二支(じゅうにし)
子(ね)丑(うし)寅(とら)卯(う)辰(たつ)巳(み)午(うま)未(ひつじ)申(さる)
戌(いぬ)亥(い)酉(とり)
子
(ね/ネズミ)丑
(うし/ウシ)寅
(とら/トラ)卯
(う/ウザギ)辰
(たつ/竜)巳
(み/ヘビ)午
(うま/ウマ)未
(ひつじ/ヒツジ)申
(さる/サル)酉
(とり/ニワトリ)戌
(いぬ/イヌ)亥
(い/イノシシ)
1ヶ月の日数(にっすう)は28日だったり、31日あったりとその月によって違う(ちがう)のは何故(なぜ)ですか。どうやって、1月〜12月までの月の日数を決めた(きめた)のですか。教えて(おしえて)ください。
今、私たちが使って(つかって)いる暦(こよみ)を「グレゴリオ暦(れき)」と言うのは知って(しって)いるかな?この暦は1582年に当時(とうじ)のローマ法王(ほうおう)のグレゴリオ13世(せい)が決めた(きめた)ものなんだ。その暦のもとになったのが紀元(きげん)49年にユリウス・シーザー(=ジュリアス・シーザー)がつくったユリウス暦なんだ。その当時すでに、1年は365日と1/4日というのがわかっていて、この日数(にっすう)を暦にする時に12分割(ぶんかつ)して、それぞれの月に割り当て(わりあて)たんだ。だからユリウス暦はキチンと大の月(だいのつき:31日)、小の月(しょうのつき:30日)というようにわかれていて、わかりやすかったんだけど、シーザーの後にローマ皇帝(こうてい)になった、アウグストゥスによって、自分(じぶん)の名前(なまえ)のついた8月が小の月とはけしからんということで、2月を28日に減らし(へらし)、8月を31日に無理矢理(むりやり)変更(へんこう)してしまったんだ。それぞれの月の表(ひょう)を見てね。つまりは、その月によって日数が違う(ちがう)のも月の日数を決めたのも、人が勝手(かって)に決めてしまったということになるね。
■ユリウス暦
1月 31日
2月 29日(うるう年には30日)
3月 31日
4月 30日
5月 31日
6月 30日
7月 31日
8月 30日
9月 31日
10月 30日
11月 31日
12月 30日■グレゴリオ暦
1月 31日
2月 28日(うるう年には29日)
3月 31日
4月 30日
5月 31日
6月 30日
7月 31日
8月 31日
9月 30日
10月 31日
11月 30日
12月 31日
どうして2月(がつ)は、28日(にち)までしかないのですか?
この質問(しつもん)は、2月号(がつごう)の「時と暮らし(ときとくらし)」でバッチリ書いて(かいて)あるので、読んで(よんで)みてね。
今(いま)は、西暦(せいれき)2001年だけど、2001年前(まえ)は、どう言うふうに、西暦が作られた(つくられた)の?
西暦(せいれき)を考え出したのは、今から1500年ぐらい前の数学(すうがく)と天文学(てんもんがく)に詳しい(くわしい)ローマの修道院長(しゅうどういんちょう)ディオニュシウス・エクシグウスという人なんだ。西暦はイエス・キリストの誕生(たんじょう)の年(とし)を西暦0年としたものなんだよ。採用(さいよう)されたのが西暦500年ぐらいだから、そこからイエス・キリストの誕生までさかのぼって、数えた(かぞえた)ことになるよね。それまでは、統一(とういつ)された暦(こよみ)というものはなくて、民族(みんぞく)や宗教(しゅうきょう)によって様々(さまざま)な暦を使って(つかって)いたんだよ。この暦のお話(はなし)は、2001年6月の「時と暮らし(ときとくらし)」に詳しく(くわしく)のっているから読んで(よんで)みてね。
6月10日の「時の記念日(ときのきねんび)」はいつ、誰(だれ)が、なぜつくったの?
「時の記念日(ときのきねんび)」がつくられた理由(りゆう)は、今(いま)から80年前(80ねんまえ)、インフレが進む(すすむ)中で、日々(ひび)の生活(せいかつ)をカンタンにして、合理的(ごうりてき)なものにしようという「生活改善同盟(せいかつかいぜんどうめい)」という団体(だんたい)がつくられて、その団体がいちばんの目標(もくひょう)にあげていたのが「時間を正確(せいかく)に守る(まもる)こと」だったんだ。
たまたまそのころに、文部省(もんぶしょう)も「時間を大切(たいせつ)にし、守ること」の考え方(かんがえかた)を広め(ひろめ)ようとしていたんだ。そして文部省が進めていた「時に関する展示会(てんじかい)」にいろいろなものをだしたり、手伝い(てつだい)ましょうということで、「時の記念日」を決め(きめ)宣伝(せんでん)することに決めたんだ。6月10日が「時の記念日」として選ばれた(えらばれた)理由は、日本(にほん)ではじめて「漏刻(ろうこく)」と呼ばれる(よばれる)水時計(みずどけい)を作った(つくった)天智天皇(てんじてんのう)が671年に時刻制度(じこくせいど)をはじめた日だからなんだ。
うるう年(どし)はどうしてあるの?
カンタンに言うと、1日が24時間というのは太陽(たいよう)の動き(うごき)をもとに決められた(きめられた)ものなんだ。でも、そのせいで、暦(こよみ)に「うるう年」というのをいれなければならなくなってしまったんだ。みんなも知って(しって)いるように太陽は、きっちりと24時間で動いているわけではないんだ。
暦では、1年は24時間×365日となんだけど、太陽が春分点[しゅんぶんてん/春分の日に太陽が通る道(とおるみち)]を通過(つうか)してまた春分点に戻って(もどって)くるまでの時間、つまり1太陽年(いちたいようねん)は正確(せいかく)に言うと、365日と0.242日(約4分の1日:やく4ぶんの1にち)なんだ。
だから、暦では、4年で約1日分たりなくなってしまうんだ。
そこで、4年に一度「うるう年」を入れることで、そのずれを直して(なおして)いるんだよ。
どうして1年は365日なの?
1年を365日にするようになったのは、太陰太陽暦(たいいんたいようれき)とよばれる暦(こよみ)を採用(さいよう)した時(とき)からなんだ。この太陰太陽暦は月(つき)の満ち欠け(みちかけ)で日を数え(かぞえ)、ひと月は29日か30日というもの、そのために月にズレが出てしまうんだ。だから、ズレを調整(ちょうせい)するために、「うるう月」とよばれるものを使って(つかって)いたんだ。だからうるう月が入る(はいる)年は、1年が13ヶ月になるんだ。日本(にほん)の旧暦(きゅうれき)は、この太陰太陽暦にあたるんだ。 その後(ご)、みんながよく知っている太陽暦(たいようれき:グレゴリオ暦)になるんだ。
これは、地球(ちきゅう)が太陽の周り(まわり)を1周(1しゅう)する時間を1年とした暦で、正確(せいかく)にはかった1太陽年=365.2422日をもとにしていて、1582年から世界(せかい)で使われているんだ。この太陽暦は、もともと古代(こだい)エジプトで生まれ(うまれ)、ローマ時代(じだい)にほぼ現在(げんざい)の形(かたち)に整理(せいり)されてヨーロッパ全体(ぜんたい)に広がった(ひろがった)のよ。
この時は、まだ1年は365日。その後に、ローマのユリウス・カエサルが、エジプトのアレキサンドリアの数学者(すうがくしゃ)ソシゲネスに助言(じょげん)されて、1年を365.25日とするユリウス暦による暦法(こよみほう)の改革(かいかく)を行ったのが紀元前(きげんぜん)49年のこと。
このユリウス暦にも、うるう年はあって、4年に1度入れることで、ズレを調整(ちょうせい)をしていたのんだ。でも実際(じっさい)の太陽年が11分14秒短かった(みじかかった)ために、100年で18時間、1000年で8日もカレンダーがズレてしまって、16世紀(せいき)になった時には3月21日の春分の日(しゅんぶんのひ)が、3月11日になってしまったんだ。チリもつもれば何(なん)とやら。ホントだよね。
そこで、1582年、ローマ法王(ほうおう)グレゴリオ13世(せい)が復活祭(ふっかつさい)の日程(にってい)を正確にすることを目的(もくてき)に、10月4日の翌日(よくじつ)を10月15日とし、10日間をいっきに調節(ちょうせつ)して、1年を365.2425日にする暦を導入(どうにゅう)したんだ。
だからそのローマ法王の名前(なまえ)をとってグレゴリオ暦となったんだ。
明々後日(しあさって)のつぎはなんて言うのですか。
これはおもしろい質問(しつもん)だね。いっしょに見てみようか。
- 明日
- あす
- 明後日
- 明日(あす)の次(つぎ)の日
- あさって(あさての促音化:そくおんか)
- 明明後日
- 明日(あす)の次の次の日
- 明後日(あさって)の次の日
- しあさって
でもそれ以降(いこう)となると、標準語(ひょうじゅんご)ではないけれど、弥の明後日(やのあさって/またはやなあさって)と言う言葉(ことば)があって、これは東京(とうきょう)では、昔(むかし)は明明後日の次の日という意味(いみ)だったんだ。東京生まれ(うまれ)のおじいちゃん、おばあちゃんなら知って(しって)いるかもしれないね。
もし、他(ほか)にも言い方(いいかた)があったら教えて(おしえて)ね。参考資料「広辞苑(こうじえん)」
昨日(きのう)の前(まえ)はおととい。じゃあ、おとといの前は?
「おととい」の前(まえ)は「さきおととい」または「いっさくさくじつ」となるんだよ。漢字(かんじ)で書く(かく)と「一昨昨日」となるんだ。「おととい」は漢字で書くと「一昨日」で「いっさくじつ」と読む(よむ)んだよ。わかってくれたかな?
太陰暦(たいいんれき)ってどんな暦(こよみ)なのですか?太陰暦でも1日は24時間なのですか?
太陰暦(たいいんれき)というのは、月(つき)の満ち欠け(みちかけ)を観察(かんさつ)してつくられた暦なんだ。新月(しんげつ)から次(つぎ)の新月までのサイクルはだいたい29日半(はん)でこれが12回続く(つづく)と、1年になるという考え方(かんがえかた)をもとにしているんだ。
この太陰暦を、いちばん最初(さいしょ)に決めた(きめた)のは、イスラム教(きょう)をはじめたモハメットなんだ。彼(かれ)は、奇数(きすう)の月を30日、偶数(ぐうすう)の月を29日に決めて、1年の12(12ヵ月:かげつ)でわると、29.5日になるように暦をつくったんだ。けれど、月の動き(うごき)は、29.5日よりちょっと長いことがわかり、それを調節(ちょうせつ)するために、30年のうち11年は偶数の月である12月を30日としたんだよ。
この暦では、1年が354日か、355日になるんだ。時刻(じこく)については、1日と言う考え方が太陽(たいよう)の動きをもとにつくられていたので、1日24時間というのは、太陽暦とかわることはないんだよ。