|
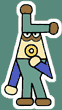 だれがなんというおうと、トニカク、わたくしがカックルです。 だれがなんというおうと、トニカク、わたくしがカックルです。
さて今回(こんかい)は、「時のはてな星(ときのはてなぼし)」によせられた質問(しつもん)の中から古川第1小学校2年(ふるかわだい1しょうがこう2ねん)の谷地森駿さんの「1週間はどうして7日ですか?(1しゅうかんはどうして7かですか)」に答えて(こたえて)いくぞ。
カックン。
1週間という考え方(かんがえかた)がはじまったのは、今(いま)から3000年ぐらい前(まえ)の、古代(こだい)バビロニアで生まれた(うまれた)といわれているんだぞ。
そのころの人たちは、地球(ちきゅう)に一番(いちばん)近い(ちかい)月(つき)が、地球や人に強い(つよい)影響(えいきょう)を与える(あたえる)ことから、それよりも遠い(とおい)星(ほし)はもっと強い力(ちから)をもっていると考えていたんだぞ。カックン。
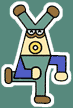 そして、太陽(たいよう)をはじめとする7つの星(土星[どせい]木星[もくせい]火星[かせい]太陽[たいよう]金星[きんせい]水星[すいせい]月[つき])が、時間(じかん)というものを動かして(うごかして)いると考えていたんだ。
そして、太陽(たいよう)をはじめとする7つの星(土星[どせい]木星[もくせい]火星[かせい]太陽[たいよう]金星[きんせい]水星[すいせい]月[つき])が、時間(じかん)というものを動かして(うごかして)いると考えていたんだ。
そのころは、まだ天王星(てんおうせい)海王星(かいおうせい)や冥王星(めいおうせい)は、発見(はっけん)されてなかったんだ。この星たちが、地球のまわりを1周(しゅう)するのに7日かかると考えた古代バビロニアの人たちが、1週間を7日と決めた(きめた)といわれているんだぞ。
太陽は曜日(ようび)の、日(ひ)をあらわすんだぞ。
で、それぞれの曜日にどうやって、星の名前(なまえ)がわりふられていったのかを、続いて(つづいて)説明(せつめい)するぞ。それは、今から2200年ぐらい前の古代エジプトの人たちが、今度(こんど)は、さっき説明した7つの星が
地球から遠い土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月の順番(じゅんばん)で時間を動かしていると考えたんだぞ。
そうしてその力の強いじゅんに、1時からはじめて24時間をわりふっていったんだぞ。
下にある図(ず)をみてほしいぞ。
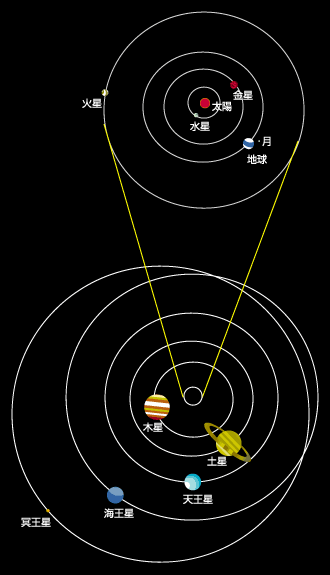
1日目
1時/土星 2時/木星 3時/火星 4時/太陽 5時/金星 6時/水星 7時/月
8時/土星 9時/木星 10時/火星 11時/太陽 12時/金星 13時/水星 14時/月
15時/土星 16時/木星 17時/火星 18時/太陽 19時/金星 20時/水星 21時/月
22時/土星 23時/木星 24時/火星
2日目
1時/太陽 2時/金星 3時/水星 4時/月〜
3日目
1時/月
4日目
1時/火星
5日目
1時/水星
6日目
1時/木星
7日目
1時/金星
というように、わりあてていった1時にくる星が土、日、月、火、水、木、金のじゅんになって、それを曜日にしたんだぞ。このころ、週(しゅう)のはじまりは、地球(ちきゅう)からもっとも、遠く力のある星の土星(どせい)である土曜日(どようび)だったんだぞ。カックン。
それが、現在(げんざい)使われている1週間七日制(ななにちせい)になったのは、ユダヤの人たちからはじまったんだぞ。諸君(しょくん)は、旧約聖書(きゅうやくせいしょ)を知って(しって)いるかな?
その旧約聖書の中に、神(かみ)が天地万物(てんちばんぶつ/このよのすべてのもの)を6日で創り(つくり)、7日めに休んだ(やすんだ)とかかれているんだぞ。
その7日めが安息日(あんそくにち/ユダヤきょうで、金曜日におひさまがしずんでから、土曜日にまたおひさまがしずむまで、仕事(しごと)などをせずに休む日)としたんだ。
ここで、土曜日が1週間の始まりの日から、終わり(おわり)の日になったんだぞ。カックン。
さらに、ローマ帝国(ていこく)の皇帝(こうてい)コンスタンティヌス1世(せい)が、321年に日曜日をすべての仕事を休み、神とともに過ごす(すごす)日と決め(きめ)、休みの日となったんだぞ。
この時はまだ、日曜日が週の始まりの日だった。けれども、働く(はたらく)人たちにとっては、「働く前(まえ)に休む」よりも「働いてから休む」ほうが、なんとなく気分的(きぶんてき)によいために、だんだんと休みの日は、週の終わりの日になっていったんだ。
そのうちに週休2日制(しゅうきゅうふつかせい/週に2日休む決まり)になって、週の始まりが月曜日になっていったんだぞ。あー、カックン、カックン。
さて今回は「時の算数(さんすう)」といいながらも、歴史(れしき)やら、星のはなしなど、いろいろと勉強してしまったな。トニカク今回はここまで、次回(じかい)もよろしくだぞ。カックン。
参考文献
永田久『暦と占いの科学』新潮選書
2000年8月号
|