|
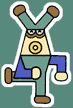 トニカク、わたくしがカックルです。 トニカク、わたくしがカックルです。
さて、時間(じかん)をあらわすには、〜時(じ)、〜分(ふん)、〜秒(びょう)というのはみんな知って(しって)いるよね。でもその一番(いちばん)小さい(ちいさい)単位(たんい)の「びょう」というものはどうやって決められた(きめられた)のかは知らないんじゃないかな。
「びょう」というものは、1200年前(まえ)から天文学者(てんもんがくしゃ/星(ほし)や宇宙(うちゅう)のことを調べる(しらべる)人(ひと)たち)の間(あいだ)では使われて(つかわれて)いたもので、それを世界中(せかいじゅう)で使いましょうとなったのが、今から約(やく)200年前のことなんだぞ。カックン。
それじゃ、その「びょう」ってどのぐらいの長さ(ながさ)なのかというと、これがすごいことになってくるんだ。
最初(さいしょ)、1年間のおひさまの動き(うごき)を観測(かんそく)して、そこから計算(けいさん)してだした1日を8万(まん)6400でわったものが、1秒といわれていたんだぞ。
60(秒:1分)×60(分:1時間)×24(時間:1日)=8万6400(秒)
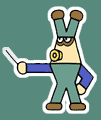
「秒」で1日をあらわすと、8万6400秒になるのがわかるだろ。
でも、この計算、じつは大きな問題(もんだい)が1つあったんだ。それは、地球(ちきゅう)がいつも同じ(おなじ)スピードで回って(まわって)いるという考え(かんがえ)をもとにしていたからなんだ。1956年、今から44年前に地球がいつも同じスピードでまわっていないことがわかって、1秒の長さがかわることになった。これは大変(たいへん)だ、カックン。
それで、その長さというのが、1899年の12月31日の夜(よる)9時の時(とき)の地球のまわっているスピードから出した1年を3155万6925.9747でわった長さにするというもの。
前の「びょう」が1日から出されていたんだけど、今度(こんど)は1年から出すようになったんだ。
さっきみたいな計算をしてみよう。計算機(けいさんき)を使ってもいいぞ。
60(秒:1分)×60(分:1時間)×24(時間:1日)×365(日:1年)=3153万6000
1年のところに、うるう年(どし)は計算してないので、ちょっと違う(ちがう)けど、だいたいのことはわかってもらえるよね、ふーっ。ここで、終わり(おわり)かと思った(おもった)ら)星の動きを調べて(しらべて)出した「びょう」(これを天文秒[てんもんびょう]という)ではまだまだ正確(せいかく)じゃないということで、1967年、今(いま)から33年前(まえ)に、「セシウム原子(げんし)が約(やく)92億回(おくかい)!!ぶるぶるっとふるえる時間を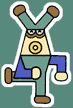 1秒(びょう)」としたんだぞ。(これを原子秒という) 1秒(びょう)」としたんだぞ。(これを原子秒という)
ここまでくるともう先生もお手あげに近い(ちかい)ぞ。
そのセシウム原子といわれるものが、ふるえるようすだって、もちろん目で見ることもできないし。
でも今、世界中で使われている「秒」は、この「原子秒」をもとにして全て(すべて)が決められているんだぞ。
この「原子秒」をもとにした時間を「原子時(げんしじ)」というんだぞ。
トニカク今回はここまで。次回(じかい)もよろしくだぞ、カックン。
2000年6月号
|