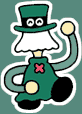 わがはいのページへようこそ。今回(こんかい)の「時計の歴史(ときのれきし)」は、振り子(ふりこ)とならぶ大発明(だいはつめい)となるゼンマイについてお話(はなし)をしていこうかのう。
わがはいのページへようこそ。今回(こんかい)の「時計の歴史(ときのれきし)」は、振り子(ふりこ)とならぶ大発明(だいはつめい)となるゼンマイについてお話(はなし)をしていこうかのう。
前回(ぜんかい)学んだ「機械式時計(きかいしきどけい)」は、ゼンマイが発明されるまでは、冠型脱進機(かんむりがただっしんき)のようにおもりを使って(つかって)動かして(うごかして)いたのじゃ。
だから、大きく重い(おもい)ものが多く(おおく)、持ち運ぶ(もちはこぶ)ことなんて、とてもできなかったのじゃ。
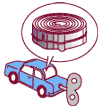 おっと、ここでゼンマイについて知らない(しらない)人がいると困る(こまる)ので、ちょっと説明(せつめい)しておこうかのう。
おっと、ここでゼンマイについて知らない(しらない)人がいると困る(こまる)ので、ちょっと説明(せつめい)しておこうかのう。
ゼンマイというのは、うずまきになった長い(ながい)板(いた)バネのことなんじゃ。
このゼンマイは、むりにうずまきの形(かたち)にまかれているので、つねにまっすぐになろうという力が働いて(はたらいて)いるんじゃ。その力を利用(りよう)して、いろいろなものを動かす動力(どうりょく)として使えるわけじゃな。
今(いま)は数(かず)が少なく(すくなく)なってしまったが、きみたちのお父さんが子供(こども)のころは、自動車(じどうしゃ)などのおもちゃを動かすのはみんなゼンマイを使っていたんじゃぞ。そうそう、今のおもちゃで言えばチョロQ(チョロキュー)の中にもゼンマイは入っているんじゃぞ。
 さて、ゼンマイのことはわかってくれたかのう?それでは、話を時計にもどすとしよう。
さて、ゼンマイのことはわかってくれたかのう?それでは、話を時計にもどすとしよう。
時計の動力(どうりょく)としてゼンマイを発明したのは、1500年ごろ、ドイツのニュールンベルグで時計師(とけいし)として働いて(はたらいて)いたペーター・ヘンラインという人なんじゃ。
ちなみにこのころの時計は、ものすごくねだんが高く(たかく)て、工芸品(こうげいひん)や宝石(ほうせき)のようなあつかいをされていたのじゃ。
ゼンマイが発明されてから、時計はしだいに小さくなって、1600年ごろには、持って(もって)歩ける(あるける)ぐらいの小さなものが作られるようになったんじゃ。
しかしながら、最初のころの動力としてのゼンマイは、いっぱいまいた時は力(ちから)が強く(つよく)、ほどけるにしたがって力が弱まって(よわまって)しまうのじゃ。だから時計の動きが一定(いってい)にならず、どうしても遅れたり(おくれたり)するので、正確さ(せいかくさ)をもとめられる時計にはあいかわらず、おもりをつかって動かしていたんじゃ。
では、ゼンマイを動力としてつかって、さらに時計を正確に動かすには、どうしたのか。
そこで登場するのが「ヒゲ・ゼンマイ」なんじゃ。
ヒゲ・ゼンマイは、振り子と同じ(おなじ)ように、時計の動きを一定にするための働き(はたらき)をするものなんじゃ。時計のアンクル型脱進機(アンクルがただっしんき)を発明した科学者(かがくしゃ)のフックにより「フックの法則(ほうそく)」を利用(りよう)して、下の図(ず)にあるような調速機(ちょうそくき/そくどをちょうせいするきかい)が作られたのじゃ。このヒゲ・ゼンマイの発明によって、動力として使っているゼンマイの力が強い時でも、弱くなった時でも、一定の速度(そくど)をたもてるようになったのじゃぞ。
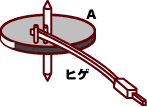 |
この棒(ぼう)の形(かたち)をしたのが、「ヒゲ・ゼンマイ」なんじゃ。
ヒゲ・ゼンマイは、ピンによって左右(さゆう)の動きは制限(せいげん)されていて、動いた分と同じ分だけまた戻る(もどる)ような仕組み(しくみ)になっているんじゃ。だからAの部品の動きがちょうど振り子と同じようになって、いつも一定の速度がたもたれるというわけなのじゃ。わかったかな。
|
このヒゲ・ゼンマイが作られたことで、持ち運び(もちはこび)に便利(べんり)で、その上、正確な小型(こがた)の時計を作ることができるようになったのじゃ。
さらに、このヒゲ・ゼンマイは、1675年に「機械式時計の父」とよばれるクリスチャン・ホイヘンスが、ヒゲを下の図にあるようなうずまき型に改良(かいりょう)したのじゃ。
この形ならば小型の時計に入れるのには、場所もとらずに都合(つごう)がいいのお。
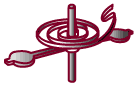
ここまで来るとかなり今の時計に近づいて(ちかづいて)きたのう。さて、次回(じかい)はなにが出てくるか。
みんな楽しみにまっててくれたまえ。
2000年10月号