|
 さて、今回(こんかい)は「有名人が残した時の言葉(ゆうめいじんがのこしたときのことば」第4回(だい4かい)である。これまでに「日本人初(にほんじん)のノーベル賞(しょう)受賞者(じゅしょうしゃ)湯川秀樹博士(ゆかわひできはかせ)」「アメリカ合衆国(がっしゅうこく)初代(しょだい)大統領(だいとうりょう)リンカーン」「アウトドアライフの先駆者(せんくしゃ)H・D・ソロー(エイチ・ディー・ソロー)」ととりあげてきたのだが、諸君(しょくん)は読んで(よんで)くれたかな? さて、今回(こんかい)は「有名人が残した時の言葉(ゆうめいじんがのこしたときのことば」第4回(だい4かい)である。これまでに「日本人初(にほんじん)のノーベル賞(しょう)受賞者(じゅしょうしゃ)湯川秀樹博士(ゆかわひできはかせ)」「アメリカ合衆国(がっしゅうこく)初代(しょだい)大統領(だいとうりょう)リンカーン」「アウトドアライフの先駆者(せんくしゃ)H・D・ソロー(エイチ・ディー・ソロー)」ととりあげてきたのだが、諸君(しょくん)は読んで(よんで)くれたかな?
偉大(いだい)な人が残した(のこした)「時にまつわる言葉」には、その人の人生(じんせい)や考え方(かんがえかた)がにじみ出ていて、とてもためになるものなのである。その言葉にふれることで、諸君もこれから生きて(いきて)ゆく上で何か(なにか)を見つけてもらえばと思う(おもう)のである。
それでは始め(はじめ)よう。コホン。
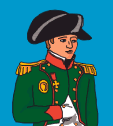 今回紹介(しょうかい)するのは、ナポレオン・ボナパルトである。 今回紹介(しょうかい)するのは、ナポレオン・ボナパルトである。
まずはナポレオンの生涯(しょうがい)をたどってみることにしよう。
1769年8月15日、地中海(ちちゅうかい)のコルシカ島[コルシカとう:現在(げんざい)のフランス]に生まれ(うまれた)たのである。母レティツィアはナポレオンの生涯(しょうがい)にものすごく影響(えいきょう)を与えた(あたえた)人で、ものすごくしっかりとした女性(じょせい)で、夫はもちろん戦闘(せんとう)に弱気(よわき)な男たちを怒鳴り(どなり)つけるというぐらいの人だったのである。皇帝(こうてい)になった時のエピソードに、あまりにもナポレオンに対して(たいして)小言(こごと)を言うので、皇帝は「余(よ)はフランス皇帝なるぞ!」と言えば、母は「私はその皇帝の母なるぞ!」と言いかえした。というのだから諸君(しょくん)もその気の強さ(つよさ)というのがわかってもらえるかな?
さて子供時代(こどもじだい)のナポレオンは、友だちと戦争(せんそう)ごっこをしたり、食事(しょくじ)に出た(でた)白い(しろい)パンを半分(はんぶん)だけ食べ(たべ)、半分をフランス軍(ぐん)の兵士(へいし)に頼み(たのみ)軍隊(ぐんたい)で配られて(くばられて)いたまずく堅い(かたい)黒(くろ)パンにわざわざ換えて(かえて)もらったというのである。9才になると陸軍(りくぐん)の幼年学校(ようねん)に入学(にゅうがく)するが、フランス語(ご)がうまく話せず(はなせず)、また貧乏(びんぼう)だったために周囲(しゅうい)にとけこめず、一人(ひとり)読書(どくしょ)をして知識(ちしき)を高める(たかめる)という学校生活を送って(おくって)いたのだ。しかしながらそんな中でも、ナポレオンの将来(しょうらい)を予感(よかん)させるような出来事(できごと)があったらしい。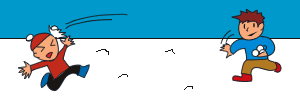 それは、学校で雪合戦(ゆきがっせん)をした時のこと、ナポレオンのチームは彼の見事(みごと)な作戦(さくせん)と指揮(しき)で圧勝(あっしょう)し、その時に彼が考えた(かんがえた)陣地(じんち)があまりにも立派(りっぱ)だったので町のみんなで見に来た(きた)というのである。 それは、学校で雪合戦(ゆきがっせん)をした時のこと、ナポレオンのチームは彼の見事(みごと)な作戦(さくせん)と指揮(しき)で圧勝(あっしょう)し、その時に彼が考えた(かんがえた)陣地(じんち)があまりにも立派(りっぱ)だったので町のみんなで見に来た(きた)というのである。
ナポレオンはその後(ご)、パリの士官学校(しかんがっこう)に進み(すすみ)、16才で卒業(そつぎょう)する。希望(きぼう)は海軍(かいぐん)であったのだが、母親(ははおや)の反対(はんたい)にあい陸軍(りくぐん)だったのだ。さて、ここからの活躍(かつやく)は年表(ねんぴょう)で説明(せつめい)しよう。
|
1795年
|
「ヴァンデミエール13日の乱(らん)」の鎮圧(せいあつ)に成功(せいこう)。 |
|
1796年
|
イタリア遠征(えんせい)(〜1797) |
|
1798年
|
エジプト遠征(〜1799) |
|
1799年
|
ナポレオンを中心(ちゅうしん)としたクーデターが成功。統領政府(とうりょうせいふ)をつくる。 |
|
1804年
|
「フランス民法典(フランスみんぽうてん)」をつくる。初代(しょだい)フランス皇帝(こうてい)に。 |
|
1805年
|
トラファルガー海戦(かいせん)vsイギリス(敗北:はいぼく)
三定会戦(さんていかいせん)vsロシア・オーストリア(勝利:しょうり) |
|
1806年
|
ライン連邦(れんぽう)成立(せりりつ)・神聖ローマ帝国(しんせいローマていこく)消滅(しょうめつ)
ベルリン入城(にゅうじょう)・大陸封鎖令(たいりくふうされい) |
|
1808年
|
スペイン占領(せんりょう) |
|
1810年
|
最初(さいしょ)の妻(つま)ジョセフィーヌと離婚(りこん)・オーストリア皇女(こうじょ)と結婚(けっこん) |
|
1812年
|
ロシア遠征(失敗:しっぱい) |
|
1813年
|
諸国民解放戦争(しょこくみんかいほうせんそう)(〜1814 フランス軍敗北) |
|
1814年
|
エルバ島(エルバとう)流刑(りゅうけい) |
|
1815年
|
00日天下(てんか)・セントヘレナ島流刑。1821年5月5日没(ぼつ) |
|
(参考文献)世界史人物事典/水村光男著(かんき出版)
|

フランス皇帝(こうてい)にまで登り(のぼり)つめたナポレオンだったのだが、2度(2ど)の島流し(しまながし)にあい、最後(さいご)はセントヘレナ島でさびしく死んで(しんで)いったのである。
1815年の「100日天下(てんか)」というのはエルバ島から逃げ出し(にげだし)パリに戻り(もどり)、再び(ふたたび)皇帝の座(ざ)についたのだが、それがたったの100日ぐらいしか続かな(つづかな)かったことから、この呼び方(よびかた)をされるようになったのである。
さてそんな激動(げきどう)の生涯(しょうがい)を歩んだ(あゆんだ)ナポレオンの残した(のこした)時(とき)に関する(かんする)言葉(ことば)を紹介(しょうかい)しよう。
まずは
「愚か者(おろかもの)は過去(かこ)を語り(かたり)、賢者(けんじゃ)は現在(げんざい)を語り、強者(きょうじゃ)は未来(みらい)を語る」
この言葉の中にある強者というのは、もちろんナポレオンのこと。多く(おおく)の戦い(たたかい)を勝ち(かち)抜いて(ぬいて)きたナポレオンだからこそ言えた(いえた)言葉なのである。
かんたんに言えば、過去ばかりふりかえっていては何の(なんの)進歩(しんぽ)もない、未来のことを考えられるような人間(にんげん)でなければ、強く(つよく)生き(いき)残って(のこって)いくことはできない。という意味(いみ)なのである。
次(つぎ)の言葉は
「世界(せかい)ができるのに6日かかったことを忘れて(わすれて)はいけない。欲しい(ほしい)ものはみんなやろう。時(とき)以外(いがい)は」
神(かみ)がこの世(よ)をつくるのに6日[7日目(7かめ)は休み(やすみ)のためにナポレオンはこう言ったのだろう]かかった、自分(じぶん)も同じ(おなじ)ように、大きな(おおきな)帝国(ていこく)をつくるのには、時間(じかん)がかかった。今(いま)、自分はあらゆるものを手(て)に入れた(いれた)が「時」だけはどうにもならない。という意味なのである。
ナポレオンの残した(のこした)言葉として最も(もっとも)有名(ゆうめい)な言葉は
「余(よ)の辞書(じしょ)には不可能(ふかのう)の文字(もじ)はない」
こうしてみるとやはり絶頂(ぜっちょう)の時にあった人間(にんげん)はどこかしら、自分(じぶん)はすごいと思い(おもい)こみ日本語(にほんご)で言うところの「天狗(てんぐ)になっている」ような気がしてならないのである。
さて、最後(さいご)にナポレオンのマメ知識(ちしき)。
諸君(しょくん)がよく知って(しって)いる缶詰(かんづめ)は、ナポレオンが戦争(せんそう)に行く時の保存食(ほぞんしょく)の製造(せいぞう)方法(ほうほう)を国民(こくみん)に応募(おうぼ)させ、その中で採用(さいよう)されたアイディアなのである。なかなか面白い(おもしろい)のである。
ということで、今回(こんかい)はここまで。
次回(じかい)、またここでお会い(あい)しよう。
きりつ!れい!フム。
(参考文献)時と時計の百科事典/織田一朗著(グリーンアロー出版社)
世界不思議物語(リーダーズダイジェスト) |
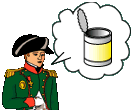 |
2002年1月号
|