|
 さて、毎日(まいにち)暑い(あつい)日が続いて(つづいて)おるが、しょくん、冷たい(つめたい)ものを飲み(のみ)すぎたりして、お腹(おなか)などこわしたりしていないか? さて、毎日(まいにち)暑い(あつい)日が続いて(つづいて)おるが、しょくん、冷たい(つめたい)ものを飲み(のみ)すぎたりして、お腹(おなか)などこわしたりしていないか?
夏休み(なつやすみ)の宿題(しゅくだい)はきちんとやっているか?
今回(こんかい)もまた、しつこく言わせて(いわせて)もらうが「時(とき)」や「時間(じかん)」についてのことわざや、昔(むかし)から言い伝え(いいつたえ)られてきた言葉(ことば)には、先人(せんじん)つまりわたくしたちよりも前(まえ)に生きて(いきて)いた人たちのちえがいっぱいつまっておる。フム。
こころして読んで(よんで)ほしいのである。
まあ、前(まえ)おきはこのぐらいにして、さっそくはじめよう。
今回は「よいことはいそげ」ということを言っている言葉をしょくんと学んで(まなんで)いこう。
まずは、「善は急げ(ぜんはいそげ)」である。
これは「善(ぜん)つまり、よいことは、時間をおかずにいそいでやるほうがよい」という意味(いみ)である。
非常(ひじょう)にわかりやすいな。フム。
たとえば、いいアイデアを思い(おもい)ついた時など、すぐにそれをかたちにするとか、そのアイデアを実現(じつげん)するために、すぐに行動(こうどう)しなさいというような言葉である。あとまわし、あとまわしにしていると、いつの間(ま)にかものごとというものは、うまくいかなくなるものなのである。フム。
しかしながら、人間(にんげん)というものは、よほどなまけものらしく、この「よいことはいそげ」という意味の言葉は、世界中(せかいじゅう)にたくさんあるのである。こうした言葉を自分自身(じぶんじしん)にいい聞かせる(きかせる)ことによって、いましてめているのであるな。フム。
で、つぎは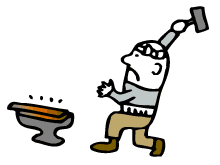 「鉄は熱いうちに打て(てつはあついうちにうて)」である。 「鉄は熱いうちに打て(てつはあついうちにうて)」である。
この言葉は、日本だけでなくイギリス、フランス、ドイツ、デンマーク、オランダ、イタリア、スペイン、ポルトガル、ロシア、中国(ちゅうごく)とまさに世界中で使われて(つかわれて)いるのである。
この言葉の意味(いみ)は「鉄をうまく加工(かこう)するには、熱く(あつく)なって鉄がやわらかいうちに打つ(うつ)のがコツである。ものごとにとりかかるのも、それにふさわしいタイミングでやらなくてはいけないということをいっているのである。またこれには、もう1つの意味があって、「鉄は熱くなってやわらかいときに打つのがいいように、人もまだ頭(あたま)が固く(かたく)ならず、じゅうなんな考え方(かんがえかた)をもっている若い(わかい)うちに、いろいろなことを学んだり、おぼえたりするのがいい」というもの。
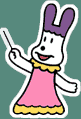 ならいごとも、小さな(ちいさな)ころからはじめると、おぼえるのが早い(はやい)ものなのである。最近(さいきん)よくいわれる「絶対音感(ぜったいおんかん)」というのも、4さいぐらいまででないと、身(み)につかないといわれておる。 ならいごとも、小さな(ちいさな)ころからはじめると、おぼえるのが早い(はやい)ものなのである。最近(さいきん)よくいわれる「絶対音感(ぜったいおんかん)」というのも、4さいぐらいまででないと、身(み)につかないといわれておる。
わがはいも、小さなころから、ピアノでもならっておれば、マーリンリン先生(せんせい)のように音楽(おんがく)の先生になっていたかもしれないのである。コホン。
では、つぎにいこう。「早起きは三文の得(はやおきはさんもんのとく)」
これは、しょくんもお父さん、お母さんからきいたことがあるだろう。
この言葉は「早起き(はやおき)して、仕事(しごと)にはげむと、いいことがある」簡単(かんたん)にいえば、こういう意味である。わがはいも、ついつい夜(よる)おそくまで、本(ほん)を読むのに夢中(むちゅう)になって寝坊(ねぼう)をしてしまうことがあるのだが、本当はあらためないといけないのである。フム。
これに似た(にた)意味の言葉で「早い時間は、金の時間(はやいじかんは、きんのじかん)」という言葉もある。
「金(きん)」とは、きちょうで、価値(かち)のあるもののたとえである。
うまいいいかたをするものである。フムフム。
 さて、今回の言葉からしょくんは、なにを感じて(かん)じてくれたかな。 さて、今回の言葉からしょくんは、なにを感じて(かん)じてくれたかな。
教室(きょうしつ)のみんなや先生、お父さん、お母さんとも話してみてくれたまえ。
今回はちょっとわがはいのことをしゃべりすぎてしまったようなきもしないではないが、まあよしとしよう。コホン。
それでは、次回(じかい)、またここで、お会い(おあい)しよう。きりつ!れい!フム。
2000年8月号
|